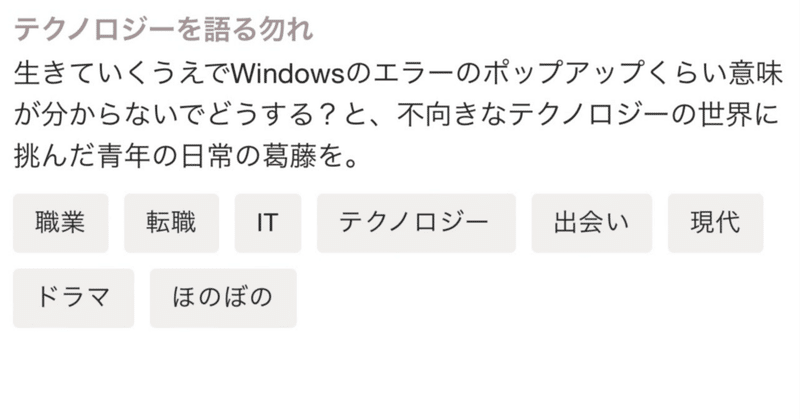
【小説】テクノロジーを語る勿れ【第49話】
いわゆるサービスの範疇で一通りのことを寸でところまで手際良く済ませたユカは、広木の手を引いて身を起こさせながら、今度は自分がベッドの上に仰向けに横たわった。次は上から自分の方にも愛撫を寄越して欲しいと、その気になったユカから促されているのだと見て取る。体も既に十分に反応した状態となっている広木も、もはやこの状況でそれを拒んでいる場合ではないと、それまでのもったい付けたようなリアクションを無かったかのように、ユカの体に上から覆い被さろうとした時、ユカが口を開いた。
「…挿れて良いよ」
「仕事中にしちゃったら怒られるんじゃないの?」
「いちいち監視されている訳でもないから、言わなきゃバレないし。別にバレても別に良い」
「どうしたの?いつもと雰囲気違うんだけど」
「分からない。でもそうして欲しいの」
「そう言われてもな。こちらも悪い気はしないけれど」
「今日もう広木くんが最後だし、後の事考えずにそうしちゃいたい」
知り合ってほどなくして、店の外でそのような逢瀬に至ることを楽しみにユカと時間を作るようになっていた。何度かに一度はユカが、「毎回SEXしてしまうとお店に来てくれなくなるといけないから(笑)」と言ってそれを拒んだが、ユカにとってはそれはただの予定調和のようなものだったのだろう。一方で広木にとっては、今日な何としてもという時に肩透かしを食わされたような状態に陥り、当てにならないことに内心腹を立てながら、そうであれば最初から期待せずにいられるストリートでの新たな出会いを追い求めた方が健全ではないかと、徐々に連絡の頻度を落とした。
ユカの方からこのように打診されることはこれまでになかった。広木はあっけに取られながらも、目の前の美人にそう言われて嫌な気がするはずもなく、動揺を隠しながらも言われるように応じようと体を起した。
ユカの体に垂直になるように体を合わせ奥の方へと密着させると、ユカが両手を広木の方へ伸ばしながら手前へ寄るように強く求めた。背中に回した腕の力の強さからやはりユカの様子が普段とは違うことに気付かされる。広木がいつものように前のめりで無いこともあったかも知れないが、そうであれば、やはり押してばかりでは駄目なのだということを改めて体現出来ているのかも知れない。だがそれだけではないようにも思えた。
体位を変えようとする広木をユカは静止した。代わりに、そのままの体制でもっと強くして欲しいのだと簡潔に告げられ、そのように応じることにした。枕の端を両手で掴んで声を掻き消そうと口元を結ぶ表情はまるで苦痛に悶えるようで、広木の中の何かを擽られたような気がした。
体の動きを早めながら広木が更に力を込める。それまでとは裏腹に、ユカが暴れ狂うように悲鳴にも似た声を上げて脚先ピンと伸ばしたところで広木は果てた。暫く止めずにゆっくりと同じ動作を続けながらユカの表情を窺うと、失った声を取り戻すように静かに呼吸を整えていた。視線は虚ろなまま天井を見上げている。何と声を掛けて良いか分からない広木は、とりあえずはユカの横に並んで横たわり、一緒に天井を眺めていた。
十分に呼吸を整え終えたユカが体を起して、広木の方へ体を預けながら口を開いた。
「来てくれてありがとう。嬉しい」
「あんなに大きな声出して良いの?」
「たまに余所の部屋の子の声聞こえるし良いでしょ(笑)」
「いつもと雰囲気違うじゃん。びっくりするんだけど」
「久々に会えてうれしかったのと、今日仕事入ってからお店の人とケンカしちゃって、クビになっても良いからせっかく来てくれた広木くんと良いことしちゃおうと思って」
「投げやりなのは良くないなぁ」
「大丈夫。誘ったのは私だから気にしないで」
シャワーを浴びながらあと何日地元で過ごすのかとユカに問われた。半月くらいのものだろうとふんわりした返事をすると、機会を作って映画か食事にも行こうとユカから誘いを受けながら、プライベートの携帯電話の連絡先を教えられた。今までのはどういう用途の連絡先だったのだとも思ったが、ここに来てユカの方から距離を縮めようとする言動についてもそう嫌な気はしなかった。
帰りの車も行きと同じく広木がハンドルを握った。行きの道中の、その後の展開に対して半信半疑で臨もうとしていた時と打って変わり、何もかもことが上手く運んだような手応えのあった広木は、日付が変わろうとしている時間帯にも関わらずすっかりと気が晴れたような爽快な気分だった。限られた期間の猶予しかないが、ユカとの楽しみが出来たことは、ある意味では新しい彼女が出来た時のように気持ちをふわふわとさせた。
それを聞いた恋愛依存気質なマサが自分に置き換えて想像を膨らませるように発狂するように、広木と同じようにハイテンションになっていた。単純と言うべきか感受性豊かと言うべきかそういうマサの一面も広木は好きだった。その展開にジローも関心したように会話に応じながらも、出掛け際に宣言していたように助手席を思い切り倒し、西広島バイパスを乗る頃にはすっかり寝入っていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
