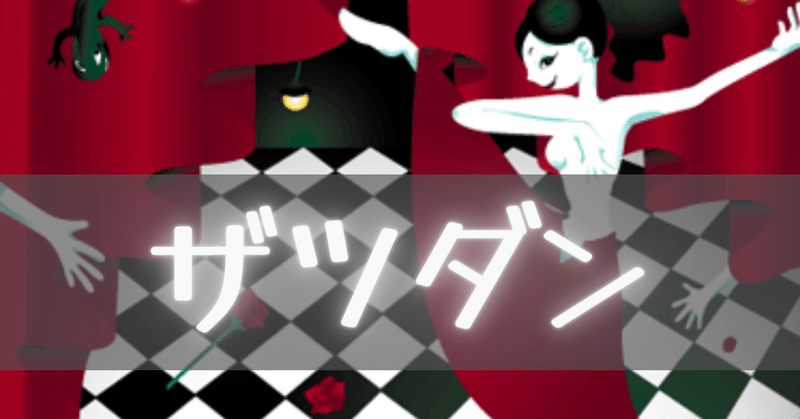
【Zatsu】世の中をひっくり返すもの6
まじめな話。
このシリーズまだやるの? ええ、まだやります😅
Another Me ってご存知でしょうか。
自分の分身をデジタル空間に解き放ち、本来ならあきらめざるを得なかった可能性を実現可能にするものです(自分なりの解釈)。
たとえば、こんなイメージです。
仕事の依頼がたくさん舞い込んできてうれしいんだけれど、手が足りなくてとても対応しきれない。こんな時もう一人自分がいればなぁ。
ケガで入院することになった。医者からは絶対安静といわれている。でも、これまで準備してきた企画の発表が数日後にせまっている。どうしよう。
そんなときに助けてくれるのがAnother Me(もうひとりの私)。
やあやあ、たいへんそうだね。手伝うよ。なにしろ私は、見た目も能力もキミと同じだ。デジタル上の存在だから肉体はないけれど、今の時代、肉体の有無はたいした違いじゃない。存在はあいまいになるけれど、仕事上で他人とやり取りする場合も、ほとんどネット上で完結するんだ。コミュニケーションをとる上で、何ら支障はない。それこそ、あちら側もAnother Meかもしれないしね。
パーマンのコピーロボットってあるじゃない? あれのデジタル版。
だれだって、たいてい体はひとつしかないし、手は二本までしかない。1日だって最大24時間しかないし、自由に使える時間となればさらに限られる。
その一方で、やりたいことは山ほどある。
処理できる量 🟰 処理能力 ✖ 費やす時間
じゃあどうするか。上の数式を踏まえると解決策は次の3つしかない。
1. やりたいことを減らす
2. 処理スピード(能力)を上げる
3. 使える時間を増やす
1.はもっとも簡単な方法。高望みせずにあきらめる。でもこれで納得できるならいいけれど、たいてい不満やストレスが残るよね。
2.は自分のスキルを磨いたり、スペックの高い機械に変更したり。努力や投資が必要で、一定の効果は望めるけれど、同時に伸びしろに限界もある。
3.は神様にお願いして1日48時間くらいにしてもらう? もしくは、会社に相談して締め切りを伸ばしてもらうとか。いや、ちょっとまてよ、べつに1人でやる必要はない。1日24時間しかなくても2人でやれば48時間になる。これも、一種の「使える時間を増やす」方法だ。
ものすごく乱暴に言えば、Another Me はこの2、3番目と親和性が高い。で、このAnother Me をテーマにしたワークショップが開催されていて、そこでは「Another Me は人か否か(独立した人格とみなすか)」という例の議論がやはり発生している(最後にリンク張っておきます)。
Another Me は自己のコピー、つまり自分の機能拡張にすぎないんだから、いってみれば3本目の腕が生えてきたのと変わらないわけで、独立した人格なんてあるはずない。そう考えることもできる。
ただ、一方でAnother Me は本体とは別に行動し、自身の判断で活動する。常時監視下、制御下にある二本の腕とは異なり、彼/彼女は個別の意思決定プロセスを経て行動している。そして本体とは別行動をとるなかで、それぞれ本体とは異なった経験や知識を獲得することになる。一卵性双生児は最初はひとつの卵子だけれど、母親の胎内で分化する。出生前の時点でそれぞれ別の人格を持つということに異論の余地はないだろう。一方のAnother Me は出生後に分化するわけだけれど、生まれる前か後かの違いだけで本質的には同じともいえる。双子が別人格ならAnother Me にも別人格がそなわっていなければ辻褄が合わないだろう。そう考えることもできる。
この問題は現時点ですぐに答えが出ないと思うので、議論継続でいいけれど、おなじワークショップで話題になっていた「自分の死後もAnother Me を残したいか(遺族や後世の人のために)」というテーマは、慎重な議論が必要だなと感じたね。
もちろん悪用云々の話もあるんだけれど、そういう運用面の各論以前に、自分がいちばん気になったのは、人の成長機会を奪うことになりやしないか、ということ。
人であってもペットであっても、身近な存在が亡くなれば悲しいけれど、その悲しみを乗り越えることで人間的に成長し、次のステージに移るわけじゃない? 形見や想い出の写真もあるけれど、人間的成長を阻害するほどのものではない。それは相手への自身の愛情を投影する役割にすぎないんだ。いってみれば、故人は天国からそっと見守っていてくれるからこそ(一方通行だからこそ)、こちらも成長できると思うのよ。
それが、死後もあいかわらず目の前に存在してあれこれリアクションされたり口出しされたら、どうだろうね。Another Me によって存在があいまいになるということは、裏返せば死そのものの意味もあいまいになるんだ。
命に対するありがたみも薄れる、それは生命を奪うという行為に対する抵抗感も同時に引き下げることになる。
死はその圧倒的な存在感ゆえに哲学や文学のテーマになってきたけれど、それも衰退するね。だって、実質的に死なない(少なくとも周囲にとっては生前のコピーが本人の死を打ち消してくれる)んだから、テーマとしての魅力も半減するし。
社会の新陳代謝も進まなくなる。よく「老害」といわれる人たち。どんなに絶大な権力を持っている人でも、いずれ「死」によってピリオドが打たれ、社会の主役は次世代へ移るというのが、現在の世の中の在り方。アダムがリンゴを食べたことによって神様が我々に与えてくれたプレゼントだな。
それがなくなる。我が意思を後世まで残したいという老害がどんどん増殖していく世界。やってられません。
死の克服(永遠の命)というのは古くから為政者、権力者が夢見てきたもので、医学の進歩によって「永遠」とまではいかなくても、長寿化は実現された。ただこのふたつは根本的に異質なもので、長寿化をどんなに推し進めていっても、限りなく長寿化が進むだけで、「永遠の命」にたどり着くことはないと思う。
もしこの世で永遠の命が実現するとしたら、Another Me のような科学技術によるものかもね(その場合、なにをもって「命」とするかの再定義が必要になるが)。
ただ、どちらにせよ、永遠の命が価値を持つのは本人にとってだけであって、周囲にしてみたら迷惑なことこの上ないでしょ。偉大な死があるからこそ、偉大な生として評価される。死を惜しまれることは、生に対する最大の賛辞じゃないのかな。
ワークショップで交わされた応答
「自分の死後もAnother Me を残したいか?」
「愛する人やパートナーのためにAnother Meを残したい」
本当に相手のことを思うなら、慎重に考えたほうがいいね。自分のコピーが残り続ける。それって、長い目で見たとき本当に相手を幸せにするのかな。
