
色彩検定に挑戦した話
お久しぶりです。
しおたです。
今回は僕が先日受検した色彩検定についての記事です。
色彩検定とは?
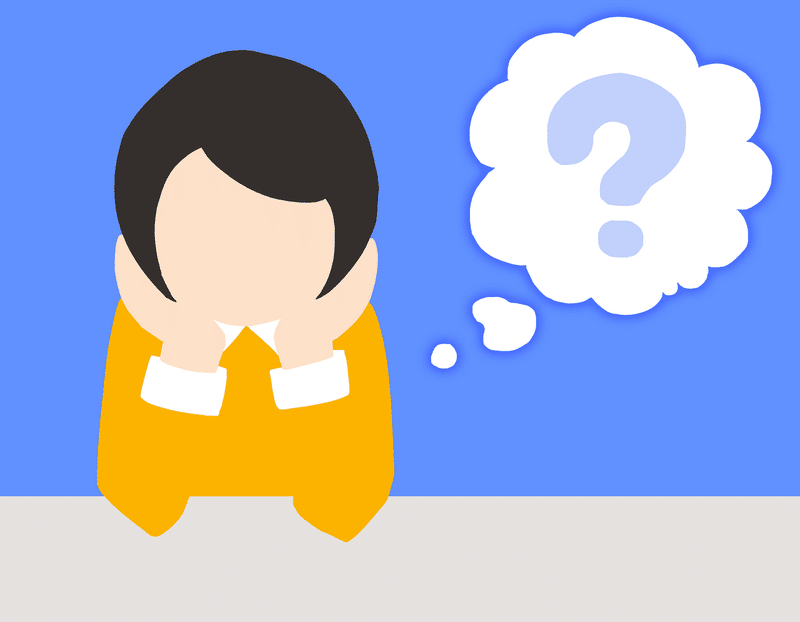
公式サイトには以下のように記載されています。
「色」は世の中のあらゆるものに使われ、私達は常にその影響を受けています。
にもかかわらず、一般的な学習課程で色について理論的・体系的な知識を得られる機会はあまりありません。専門的な教育を受けない限り、色についての知識や利用は個人の感覚や経験則に頼らざるを得ないのです。
色彩検定では色の基礎から、配色技法(色の組み合わせ方)、専門分野における利用などを幅広く学習します。「色彩検定」の学習によって感性や経験によらない、理論の土台を身に付けることができます。また、ご自身の現在の知識や目指すレベルに合わせて1、2、3級、UC級 のどの級からでもご受検いただけます。色についての知識が無く基礎からしっかり学びたい方や、現在色を扱った仕事をしているが知識を整理したい方、さらなるスキルアップを目指したい方など、様々な方に受検していただけます。
要するに、色についての知識を習得できる検定ということですね。
色って身近なところにいっぱいあるもので、それらがどういうルールで配色されているのか検定で学習をすることでわかるようになるっぽいです。
どうして検定を受けようと思ったか?
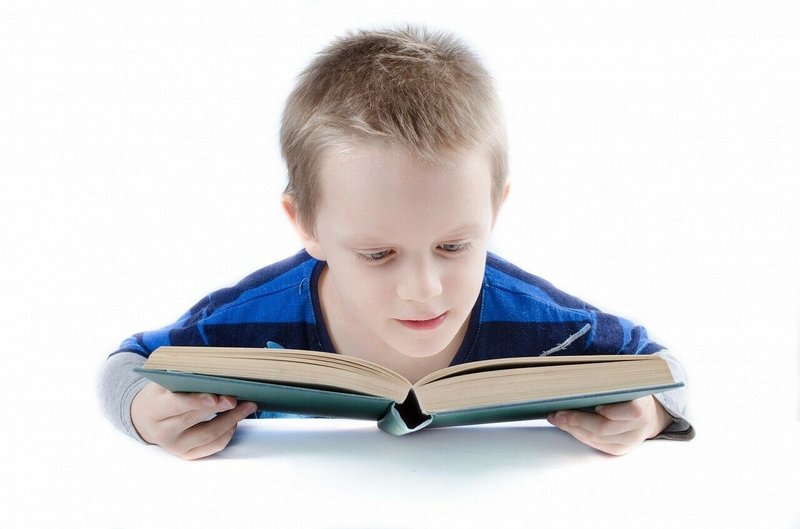
ちなみに僕の仕事はソフトウェア開発なので全く関係ないかと言われるとそうでもないですが、仕事が理由ではありません。
僕ソフトウェア開発も好きですが、叔母がデザイナーということもあるのかデザインも好きなんです。
ただ、自分で絵書いたりするのは得意ではないので作れるものと言ったらWebデザインが多いんですけどね。
仕事ではあんまりデザイン好きをアピールする機会がないのでプライベートのほうで発散しております。
そして、僕超理系の論理的思考主義なので、なんでもかんでも理由がないとモヤモヤしちゃうんですよね。
でもデザインってセンスというか考えずに感じるものみたいな感じじゃないですか?(個人的偏見)
だけど論理的思考主義なのでデザインも論理的に考えたくなって勉強しようと思ったのがきっかけです。
とりあえず色かなと。
色が分かればなんとなく理解できるかなと思いました。
検定を受けてみての感想

僕が受検したのは3級だったので、3級の話をすると、内容としてはそんなに難しく無かったです。
なんでかというと、例えば皆さん、白の服と黒の服ってどっちが膨張して見えるか分かりますか?
分かりますよね?
こんな感じで普通に考えればわかるような内容がちらほら出てくるので新しく覚える知識がそんなにないっていうのが理由です。
あとは、この色と同じ明るさの色はどれ?みたいな問題とか同じ濃さの色はどれ?みたいな問題は色を感覚的に色を見分けることができればノー勉でもいけるっていうのもありますね。
女性は男性より色を識別する能力が高いって言いますので向いているかも知れませんね。
実際試験会場の8~9割は女性でしたし。
ちなみに毎年合格率は70%台後半っぽいので難易度はそんなに難しくないです。
実際デザインに活かせそう?

まだ3級なので基礎的な知識の勉強だけでしたが、複雑なことでなければ活かせると思います!
例えば、服選びのときに全体的にまとまりのある感じにしたいとかあるデザインをこの雰囲気にしたいときに色を選ぶとしたら何が良いかとかその対象物の印象を全体的に揃えるってときは活かせると思います。
ほんと単純に揃えるって感じですね。
明るい!って感じにしたかったら明るい!って感じにはできるけど、明るさの中にちょっとしたスパイスを加えて…とかは3級レベルでは出来ないと思います。
上手く伝わりますかね…?(笑)
なので僕もまだ単純なことしかわからないのでまだまだ勉強してみたいなと思っております。
まとめ

今回色彩検定を受けてみて、自分がデザインについて論理的に理解できるようになれたかどうかと言われるとまだ不明確なことがいっぱいあると思いますのでもうちょっと色については勉強してみたいと思います。
結局自分が満足できればいいと思ってますので無理せず自分のペースで進めていきたいです。
ちなみに色彩検定の結果についてはまだ発表されておりません(2021年12月13日合格者発表予定)が、自己採点的には合格ラインは超してたので大丈夫だと思います!
結果が公表されたらこの記事に追記でもしようとかと思っておりますので皆さんお楽しみに。
2021/12/21 追記
本日合格証書が届きました!
無事合格です!
ご一読ありがとうございます。お読みいただいた記事がもし無料、あるいは価格以上の価値があると思ったら、フォローならびに、サポートいただけますと幸いです。
