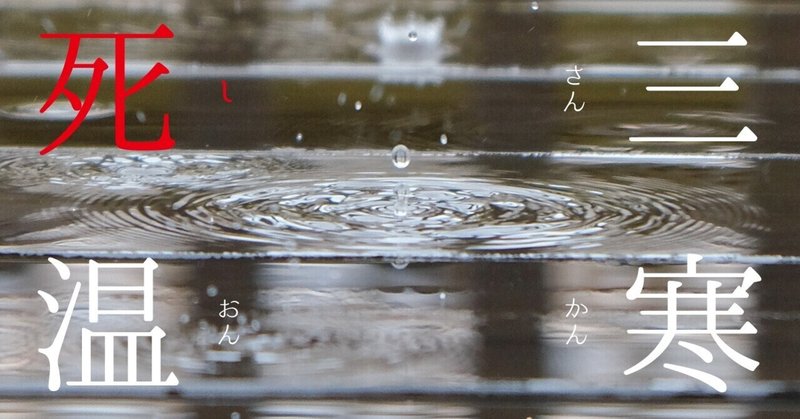
長編小説【三寒死温】Vol.19
第三話 型破りな中学校教師
【第四章】質問に質問で返す教師
彼女が死んでから、しばらくの間はみんな大人しくしていた。
しかし、大人しくはあるものの、そこには以前とは全く違う空気が漂っていた。どこか妙にそわそわしていて、久しぶりに復活したアイドルが出演したネットテレビの話をしていても、誰も目を合わせようとはしなかった。
クラスメイトは誰も彼女のことを話題にしなかったし、教師もまた、誰も彼女のことを話題にしなかった。
目に見える唯一の変化といえば、担任が変わったことだけ。
それは夏休みの登校日だった。
朝から蝉の声が耳鳴りのように反響する教室に学年主任が現れ、「少しの間、副担任が代行します。」とだけ言って去って行った。
でも、それが少しの間だけではないということを、クラス全員が分かっていた。あの若い女性教師が再び教壇に立つことはもう二度とないということを、クラス全員が分かっていた。
責任を取らされたのか、自らの意思なのかは分からないけれど。
このまま、本当に何もなかったのだということで話が進んでいってしまうのだろうか。人ひとりがその存在をこの世から完全に消し去ったというのに、それが、近所の住民が使用する以外はほとんど人通りのない丁字路に人知れず立つ一時停止の標識のように、完全スルーされていいものなのだろうか。
少しだけ焦りにも似た気持ちをあたしが感じ始めた頃、第二の生贄探しがひっそりと、しかし確実に、その産声を上げた。
正確に言えば、それは生贄探しではない。
首謀者たちからすれば、わざわざ探す必要など初手からどこにもない。
ターゲットは予め決められていたからだ。
最初に気がついたのは、音楽の授業が終わって教室に戻ってきた時だった。
トイレに行こうと思って通学鞄に入れてあったポーチを手に取ると、やけに薄くなっていた。トイレの個室に入ってポーチを開けてみると、生理用ナプキンが空になっていた。
実際のところ、それで不便を被ったわけではない。まだ生理までには数日あったから。でも反対に、あたし以外の誰かが抜き取ったのだということも、はっきりした。
だって、知らないうちに使い切ってしまったということはないし、入れ忘れてきたということもない。
ことナプキンに関しては、先月から手を付けていないのだから。
だからと言って、特に驚くようなこともなかった。
当然と言えば当然。次はあたし。普通に考えればそうなるよね。
数日後、事態は本格化した。
生理用ナプキンに続いて、あたしの私物は次から次へとなくなっていった。
階段を歩いていると、クラスメイトがわざとその後ろからはしゃいだ声を出してじゃれ合いながら、ぶつかってきた。女子同士だから暴力はないと勘違いしている大人も多いが、そんなことはない。合唱の練習の合間にも体育の授業で整列している合間にも、よろけるふりをして多くのクラスメイトがあたしの足を踏みつけていった。
男の子の前ではやらないというだけだ。
クラスのグループLINEでは、あたしの投稿に誰も返信をつけなくなった。ならばあたしを除いた新しいグループを作ればいいものを、なぜかそうはしない。あたしをいないものとして扱うのではなく、いないものとして扱っていることをあたしにアピールしているわけだ。
そんないわゆる無視が、ネットから現実の世界へと移行するのに、大して時間は掛らなかった。
◆
いい歳をした大人たちが、最近のいじめについてあれやこれやとあげつらう場面を、ここのところよく目にする。
やり口が陰湿になっただの、巧妙で大人が気づき難いだの。
彼らは、ことさらにその特異性を強調し、煽り立てている。でも、その度に首を傾げずにはいられない。
何をピントのずれたことを言っているんだろうと。
昔のいじめって、陰湿じゃなかったのかしら?
陰湿じゃないいじめなんて、この世の中に存在するの?
あるなら見せて欲しいくらいだ。
陰で行わずに堂々と面と向かってお互いに罵り合い、殴り合ったら、それはすでに喧嘩ではないか。
そんなところまで「あの頃は良かった」ことにしなければ、自分たちが生きた時代に自信が持てないのかしら?
そもそも、所詮は子どもがやることだ。
本気で大人が探そうと思ったら、その痕跡はいくらでも見つかる。
あたしたちが設定しているスマホのロックナンバーなんて、あなたたちが思っているよりもよっぽど単純なものよ。ほとんどが誕生日か名前を数字に置き換えたものばかり。ちょっと凝っている子でも、友だちと誕生日を交換してお互いに設定したり、好きな男の子やアイドルの誕生日(もしくは名前の語呂合わせ)にしたりする程度。
あたしたち子どもをよく観察している親なら、たいてい察しがつく番号に他ならない。例え一発で正解しなくても、いくつか候補を挙げれば必ず入ってくるだろう。もっと言えば、あたしみたいにロックを掛けていない場合だって、意外なほど多い。
何事もそうだけれど、見つける気のない人間には何も見つけることなんてできない。親の財布から盗ませたお金ならすぐに気がつくけれど、援交で稼がせたお金は気がつき難い? 冗談でしょう?
いじめなんて見つけたくない。それが本音のくせに。
◆ ◆ ◆
「ね、ごくありきたりな理由でしょ?」
そう言ってあたしは、今、自分にできる一番の作り笑いをして見せた。
自分が遭っているいじめの数々をこのおじさんに話しているうちに、つい気持ちが高ぶってしまった。我慢しないと涙が零れ落ちてきそうなのを、悟られたくなかった。最初は冷静に話をできていたと思うのだけれど、進むに連れて、感情を抑えることができなくなっていった。
どういうことなのか、自分でもわけが分からなかった。
いじめを受けている時だって、ここまで悔しいと感じたこともなかったし、ここまで情けないと感じたこともなかった。あくまでもあたしの想像を逸脱しない彼女たちの言動に、苦笑いしながら冷静に受け流していた。
それが今になって、こんな見ず知らずの自称教師のおじさんに話をしているだけで、どうしてここまで感情が溢れ出してくるのだろう。
あたしの声にひとしきり耳を傾けていたおじさんは、三本目の煙草を同じように校舎の屋上から放り投げた。
そして、ふんと鼻を鳴らしながら
「確かにキミが言う通り、どこにでもよくある普通のいじめだな。」
と言った。
どうやらおじさんは、何か策があった上で、あえてあたしのことを挑発しているのではないようだ。
たしかにおじさんから見れば、こんなのそこら中に星の数ほど溢れているありきたりないじめの一つに過ぎないのだろう。教師を名乗るくらいだから、見慣れてもいるはずだ。
それでも、さすがに涙を流しそうな女の子の姿を見れば、どんな大人だって慰め態勢に入るんじゃない? そういうものでしょう?
それがこの言い草だもの。ただ単に、ひねくれ者なだけなのだ。
アウトローを気取っている格好つけた中年男。
あたしの担任だったら面白いと感じなくはないけれど、人間としてはかなり疑問符が付く。
「ただ、本当にそんなことで死ぬのか?」
あれ、ちょっと待って。やっぱり止めるの?
「そりゃ大人からしたら、たかがいじめで死ぬなんてって、思うかもね。」
ちょっと、おじさん、そういう作戦だったのね。悪ぶって見えたところは、やっぱり演技だったのかしら。
これからきっと、怒涛の引き留め工作が発動されることだろう。
あたしは、もう少しだけ付き合ってみるのも悪くないかなと思った。
「大人になれば、楽しいこと、たくさんあるんでしょ?」
「どうかな? そう感じたことはないけど。」
「生きてさえいれば、いつかいいこと、あるんじゃないの?」
「それは大人の詭弁だな。そんな根拠のない可能性なんぞに騙されるな。」
あれ? どういうこと? 想定と違う。
畳みかけるような大人賛辞が続くものとばかり思っていたあたしは、面食らって言葉に詰まってしまった。
「いじめなんて、大人になってからでもいくらでもあるぞ。
俺たちの仕事でもな、仲のいいやつが困っている時は言われなくても手伝うくせに、嫌いなやつの場合はトラブってたって見て見ぬふり、そんな連中ばっかりだ。それどころか、気づかれない程度に手を抜いておいたり、咎められない程度に間違えておいたり、そんなことは誰でもやってる。
子どもたちから『先生』なんて呼ばれている教師ですら、だぞ。」
「何それ。夢も希望もないじゃん。」
「俺はいまだに、高校時代に戻りたくて仕方がない。正直、あの頃が一番、楽しかった。勉強も嫌いだったし、親も鬱陶しかったし、友だち付き合いも煩わしかった。イヤなことは山ほどあったけど、今に比べればずっとマシだ。」
おじさんはどうやら心の底からそう思っているようで、苦々しく顔を歪めながら、唾でも吐きそうな勢いで一気にまくし立てた。
やっぱり何の策略でもなかったようだ。
もしかしたら本当に、あたしを止めるつもりはないのかも知れない。
何よ、という気もしないでもないが、大してこちらの話を聞きもしないで説教染みた説得をされるよりは、数段まともだ。それに、これなら特に取り繕う必要もないなと、少し気が晴れたのも事実だった。
「それじゃ、頑張って耐えて大人になっても、あんまり意味ないね。」
「それは分からない。キミから見れば俺は大人だけれど、爺さん婆さんから見ればまだまだ子どもだ。この先にどんな未来が自分を待っているか、俺だって知らない。」
「知りたいの? これから先のこと。自分の未来。」
おじさんは、また斜め掛けしたショルダーバッグから煙草を一本取り出して、火を点けた。さっきからひっきりなしに、何本吸っているのだろう。三本目までは数えていたのだけれど。
明日から赴任する学校の生徒の前で、よくもまあ、ここまで吸えるものだ。
「なかなか鋭いな。そう聞かれると、思わず答えに詰まっちまう。
でも、まだどこかで自分に期待しているのかもな。諦めようって気には、不思議とならない。何かできることがまだある。
そうそう、『諦めたらそこで試合終了ですよ』って名言、知らないか?」
名言?
名言と言うほど、特殊な意味を持つ言葉には聞こえなかった。
それどころか、それはごく普通の言葉のように思えた。
あたしの周りでも、同じような言葉はごく普通に使われている。
部活でも、教室でも、どこでも。
「昔、読んだ漫画の台詞だ。今の子には当たり前すぎて響かないか。まあ、気にするな。」
きょとんとしているあたしを尻目にそうぶつぶつと呟きながら、おじさんは美味しそうに煙草を一口吸った。おじさんの口から吐き出された半透明の煙が、朝日を浴びて少しだけ輝いて見えた。
「やっぱり、あたしが死んだら負け犬かな?」
「目的によるな。」
「あたしが屍を晒せば、あいつら、少しは変わるかな?」
「どう思う?」
質問に質問で返さないでよ。
そう思ったけれど、あたしは何も答えることができなかった。
そう、一度では変わらなかった。
一人が死んだだけでは、変わらなかった。
二人ならどうだ? という淡い期待はあるけれど、本心では、難しいって分かっている。
「子どもは、良くも悪くも、その瞬間だけを生きている。その瞬間だけで生きている。それは、生まれてからずっと誰かに守られているからだ。本当の意味で、自分の言動に責任を負ったことがないからだ。
だから、守られている以上、根本的には変わらない。謝りさえすれば、変わらなくても生きていけるんだ。変わる必要なんてないだろう?
周りにいる大人が守るのをやめない限り。それはいつまでも続く。」
おじさんはふっと息を吐いてから、煙草を一口吸った。
「でも、そんな大人たちが子どもを突き放すことはない。できないんだ。
それは子どものためなんかじゃない。自分のためだ。自分は子どもを突き放すような大人ではないという、大人側の自己満足だ。『子どものため』っていう言葉ほど、大人にとって都合のいいものはないんだよ。」
とうとうおじさんは、校舎の屋上から唾を吐いた。
「いじめたやつらを見返す手段としてなら、自殺したところで大して意味はない。そこで反省できる感性の持主なら、初めからいじめになんて加担していないからな。それこそネットに個人名でも流出すれば、一時的なダメージは受けるかも知れない。それでもすぐに、周りの大人が囲っちまうだろう。
でも、いじめから逃げたくて自殺するやつには何も言えない。止めたところで、何も責任なんて取ってやれないからな。」
おじさんの言っていることは、きっと本気の言葉なのだろうと思った。
そこには、目の前で校舎から飛び降りようとしているあたしを止める目的のような、作為的な意図は感じられなかった。
それどころか「お前はどっちなんだ?」という問いかけにさえ聞こえる。
どっちでもあるようで、どっちでもない。何とも答えようがない。
ところでさ。そう言っておじさんは、あたしが最も聞かれたくないことを聞いてきた。
「親や担任には、話したのか?」
再び、あたしの心臓が大きく高く飛び跳ねた。ゲートに押し込められて前脚と後脚を交互にばたつかせるレース直前のサラブレッドのように、鼓動が激しく波打つのが手に取るように分かる。
そう、親にも担任にも言っていない。
いじめを受けていることなんて、周りの大人には一言も口にしていない。
岬の時には、あんなにも懸命に訴えていたのに、いざ自分の事となったら、何一つ話をすることはできないでいた。
口ごもったままでいるあたしの横顔をちらりと見やったおじさんは、苦笑いを浮かべながら言った。
「愚問だったな。大人なんて、誰も信用できないもんな。」
ずっと我慢し続けていたあたしの涙腺が、おじさんのその一言を皮切りに、崩壊した。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
