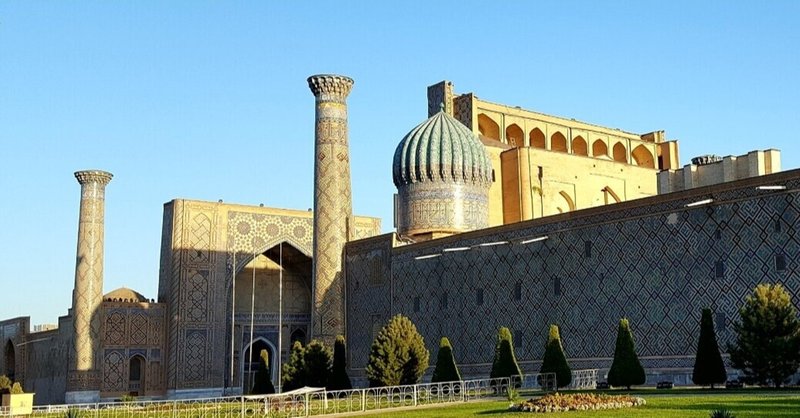
合気柔術とは(中)
武士は元服から隠居まで武術をやらなければならない。徳川時代は35歳になると齢(よわい)老骨と称し、40歳になればはや、翁と自称している。これは、東洋医学では青年の成長は24歳までとなっているからである。老骨にむち打って体力・気力の必要な第一線のための柔術を続けることは難しかったであろう。さて、大東流の合気柔術は合気を知るために柔術を知る技でもある。合気だけでは武術ではないからである。柔術は極め技、合気は気合外しであり捌きである。古流剣術に「合気に注意」せよ(合気を外せ)との極意の言葉がある。
合気柔術の代表的な技として袖取技法がある。両袖を持った相手(気合)の両指先をからめ極めて(痛くない)これを捌くのが合気である。技として投げれば呼吸投げとなる。合気投ではない、なぜなら相手の掴む力を利用した技ではないからである。
昭和62年の第3週は、この両袖取から始まる合気柔術の説明をした。
合気柔術といわれる技法には2系統ある。すなわち中級武士用の鍛錬用技法群と上級武士用のものである。上級武士は稽古量の差があり中級武士に実力で勝てない。そのため合気を最初から教え次元の違う技法で対応できるよう英才教育するのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
