2つの「憲法」の碑
132年前の今日(1889年2月11日)は大日本帝国憲法が公布された日です。
私が住んでいる横浜市金沢区には2つの憲法の碑があります。
「憲法草創之處」碑(横浜市金沢区洲崎町)と「日本国憲法起草之地」碑(横浜市金沢区富岡)です。
「憲法草創之處」碑は、伊藤博文らが大日本帝国憲法草案を執筆するためにこもった旅館の跡地付近に立てられています。
「日本国憲法起草之地」碑は、敗戦後の吉田茂内閣で憲法担当大臣として日本国憲法制定に深く関わった金森徳次郎が憲法草案を練った実業家の別荘の跡地に立っています。
ご覧の通り、伊藤博文らの「憲法草創之處」碑に比べて、「日本国憲法起草之地」碑の小さいことに驚かされます。
1945年9月2日のアジア太平洋戦争敗戦まで、この国が明治憲法体制下にあったのが56年。一方、日本国憲法公布(1946年11月3日)から現在までが75年。
この2つの碑の落差が、日本人の「近代150年」に対する歴史認識を象徴するように思えます。


以下、長文になりますが、作家の徐京植さんの「憲法九条は被害民族への国際公約である」とする論考を全文引用します。
【憲法九条、その先へ ──「朝鮮病」患者の独白】
(※『徐京植評論集Ⅲ 日本リベラル派の頽落』より引用)
憲法九条が風前の灯である。本年(二〇一六年)七月に予定されている参議院選挙の結果次第では、安倍政権は改憲への道に踏み出すだろう。かりに今回の選挙で改憲発議ラインである衆参両院三分の二以上の議席獲得に成功しなかったとしても、安倍政権は引き続き高い支持率を維持しているので、改憲の危機が去るわけではない。「緊急事態条項」という、ある意味では九条改廃よりさらに危険な独裁制への道も開かれようとしている。
この時期に当たって、私のような者も何かひとこと言わないではいられない。
「私のような者」というのは、簡単にいうと日本に生まれ育ち、日本社会の動向に直接の影響をこうむる立場でありながら参政権すらない在日朝鮮人ということ、つまり日本社会から「周縁化された者」という意味である。
「朝鮮病」患者
振り返れば、憲法九条が現在のような改廃の危機に瀕するまでに、いくつかの曲がり角があった。その一つは一九九九年八月一三日の「日の丸・君が代」法制化(国旗国歌法)であったと、私は思っている。
私はどの国のものであれ国旗や国歌には基本的に反対だが、とくに日本のそれは、第二次世界大戦の敗戦国、「三国防共協定」を結んでいたドイツ・イタリア・日本のうち、日本のものだけが戦争以前のままであるという理由ひとつだけでも、とても受け入れることはできないと考える。しかし、そのことよりもさらに、この法律が制定される過程の浅薄さが耐え難い。当時の文部大臣はオリンピックなどの国際競技で日本の選手が他国の国歌国旗に「無礼な態度をとった」ことを法制定を必要とする理由に挙げた。しかし、他国とくに日本の戦争被害国がそのような「無礼」を非難したことは耳にしたことがない。むしろ、かつての侵略戦争の旗幟を再び公然と掲げることのほうが他国の反発を買うと考えるのが道理であろう。しかし、元東大教授である文部大臣が、このような幼稚で見え透いた虚言を弄し、マスコミを含む日本国民多数もそれに同調した。
小渕首相(当時)は衆議院本会議で、「政府といたしましては、国旗・国歌の法制化に当たり、国旗の掲揚に関し義務づけなどを行なうことは考えておりません」と答弁した。昨今のいわゆる安保法制をめぐる政府の国会答弁をみるにつけ、私は強い既視感に襲われる。人間の尊厳と生命、基本的人権を左右する重大事がこんなやり方で決められてきたのである。二〇一五年六月、文科省は国立大学での国旗掲揚と国歌斉唱を要請した。文科大臣は「これは強制ではない、要請だ」と、耳に馴れた台詞を付け加えた。その場かぎりの子供じみた理屈づけとあからさまな虚言。それに同調して自粛する人々。昨日今日に始まったことではない。
二〇〇〇年の三月一一日、東京で行なわれた「日の丸・君が代」に反対するある集会に私はメッセージを寄せた。その要旨を以下に再録する。
*
ああ、せめて
あの空に
窓でも開けられぬものか。
息がつまる……
一九二〇年代の植民地朝鮮で、ひとりの詩人がこう謳い、その詩にみずから「朝鮮病」と題した。病いのほんとうの原因は日本の支配にある。それなのに日本人たちはみな、何喰わぬ顔、どこ吹く風。朝鮮人ばかりが確実に窒息していく。だから、「朝鮮病」なのである。(中略)
西暦二〇〇〇年の日本──
戦争に次ぐ戦争であれほど他民族を殺したというのに、日本人自身もあれほど多く死んだのに、あっという間の君が代・日の丸法制化。次に待つのは九条改悪。
小国寡民、東洋のスイスなどと、真面目くさって理想を説いていたのに、
教え子を戦場に送るなと、たとえ一時でも心から叫んだはずなのに、
自己否定とか、わが解体とか、格好よかったし、
近頃は多文化主義とか、多民族共生なんて、耳障りのよい言葉をまき散らしていたのに、
その時その時は、まんざら嘘八百でもなかっただろうに、
だからいつでも、あやうく信じてしまいそうになったのに、
それなのに、
見わたせば、いつの間にかまた、誰もかれも何喰わぬ顔、どこ吹く風だ。
これじゃあ「病気」にだって罹るわけがない。「日本病」なんてあり得ない。
無病息災、不老不死、千代に八千代に、日本人よ永遠なれ。
ああ、息がつまる……
俺たちは、昔もいまも「朝鮮病」だ。
*
このメッセージの冒頭に引用した詩句は、「奪われた野にも春は来るか」を歌った李相和の詩「朝鮮病」の一部である。一九二〇年代の朝鮮、日本による植民地支配を受けて一五年が過ぎ、一九一九年の三・一独立運動も大弾圧によって敗北、総督府は欺瞞的な「文化政策」を行なう一方で農村の収奪を強め、農民たちは飢えて土地から引き剥がされ流民となっていく。その状況の窒息感を「朝鮮病」と題して歌ったものだ。李相和の時代からおよそ一〇〇年後を生きる私も、相変わらず「朝鮮病」患者である。
私のこのメッセージは「中心部日本国民」に向けられたものだ。戦後憲法体制から周縁化され、疎外された在日朝鮮人の私が、戦後憲法の価値を理解しないまま特権だけを享受して来た「中心部日本国民」に向けて憲法を守れと訴える、そのことの皮肉を痛感する。しかし、日本国憲法の中に平和主義と民主主義という普遍的な価値が存在している。その普遍的な価値は、「中心部日本国民」が自ら闘い取ったものではないが、そのことが憲法に盛り込まれたのは、無数のアジア人を戦争の犠牲者にした上でのことなのだ。アジア人たちが殺されたからこそ、日本国に民主的憲法が「押し付け」られ、「中心部日本国民」は戦後民主主義を享受したのである。だから私たち「周縁化された者たち」は、その空洞化を許すことができない。そう主張する資格が充分にあるのである。
憲法九条は被害民族への国際公約である
まず、現行の日本国憲法に対する私の考えをかいつまんで述べておく。
第九条(交戦権の放棄)は必ず守られなければならない。このことを大前提としたうえで、さらに述べておくと、現在の憲法を理想化して、それをそのまま守るべきだ、という議論には私は同意することができない。
「平和憲法のおかげで戦後の平和と繁栄が守られた」とか、「戦後七〇年間、憲法九条のおかげで一滴も血を流さないですんだ」といった言い方には、私は自己中心主義と欺瞞の匂いを嗅いでしまう。
私が憲法九条を守るべきだと主張する理由は、それが「日本国民」の平和を守ってきたから、ではない。それが、日本による侵略戦争の無数の犠牲者(連合国兵士や自国民のみならず、それに数倍する被侵略民族の人々)の血と涙で贖われたものだからだ。
日本国民の多くは、米国を中心とする連合国の強大な軍事力に日本は敗北したという誤った観念を植え付けられ、いまも保持している。しかし、それは事実の一面でしかない。実際には、中国人民をはじめとする侵略される側のたゆまざる抵抗が、日本の侵略を打ち負かしたのである。
したがって、憲法九条はいわば、戦後の再出発に当たっての「再び侵略しません」という国際公約ともいえる。その約束を、相談も了解もなく放棄することは許されないのである。九条という歯止めのない日本という国家を、アジアの被侵略民族の側から想像してみれば、それがどれほど不安な存在であるかがわかるだろう。九条の改廃は、謝罪、補償、歴史教育などを通じた被害民族との信頼関係構築の上で初めて主題化できることなのだ。そうでなければ、そのような試みはつねに新たな脅威としか受け止められないのである。
私が九条を守れと主張するもうひとつの理由は、そこに(「日本国民」だけではなく)人類全体の未来がかかっているからである。日本国民にはその厳粛な普遍的意義を改めて自覚していただきたい。
私はことし三月、講演等のためコスタリカを訪ねた。コスタリカは小さな国だが、現在では世界で唯一、軍隊を持たない国である。日本も同じように憲法上武力を持たないことを宣言している国だが、その規定は現行憲法公布後数年にして形骸化した。しかし、たとえタテマエに過ぎないとしても、そのタテマエすらかなぐり捨てた後に何が続いているのか。その不安と恐怖が、形骸であれ、平和主義を維持させてきたのである。ところが昨今、自衛隊が憲法違反だというのなら憲法の方を変えて正式な軍隊にしようという主張が、首相自身をはじめ主要政治家の口から公然と飛び出すようになった。
コスタリカで出会った教授や学生たちに「いまでは世界で非武装国家は名実ともこの国のみになりますね」と、私が話しかけてみると、彼の地の人々は明るい表情で、自分たちはこれからも何があろうと非武装の原則を守り通していくと答えてくれた。全世界で軍事主義と排外主義が高潮していく中、コスタリカの人々は、いつまでこの原則を守っていけるだろうか。こんな現代に、武装せずに平和に暮らす人々の国が、地球上にたったひとつでも存在することの大切さを想像してみる。希少動物の絶滅が生態系の破滅的破壊を予告するように、この小国がその理想と平和を守り通していけるかどうか、そこに人類全体の未来がかかっているとすら私は思う。日本国民は憲法九条を守って、コスタリカの人々に連帯し、ひいては全世界に平和主義を普及させていくべきだ。それは日本国民が自国の戦争によるすべての被害者と死者たちに負っている債務であり、重い使命なのである。
自国民中心主義
私がもろ手を挙げて現行憲法を丸ごと擁護できない理由を以下に述べる。
戦前、日本内地(ほぼ現在の日本領に該当)に住む朝鮮人・台湾人などには、限定的ながら参政権が認められており、朝鮮人議員も存在した。日本政府は敗戦後、旧植民地出身者の日本国籍は講和条約発効まで引き続き有効であるとの立場をとったが、それと同時に一九四五年末の衆議院議員選挙法改正によって旧植民地出身者の参政権を剥奪した。翌一九四六年に戦後最初の選挙が行なわれ、初めて選挙権を認められた女性も多くが参加した。男女同権を謳う戦後民主主義の輝かしい出発と称された。しかし、あらかじめ参政権を奪われていた旧植民地出身者は、この選挙に参加できなかった。そして、この選挙で選ばれた議員たちによる議会が承認したことによって、現在の憲法が発効したのである。なお、沖縄は米軍の直接占領下に置かれたため、選挙は行なわれなかった。つまり、現行憲法はその出発時において、旧植民地出身者と沖縄住民を周到に排除した上でつくられたものなのである。
現行憲法(日本語)第三章「国民の権利および義務」第一〇条は、「日本国民たる要件は法律でこれを定める」、第一一条「国民は全て基本的人権の享受を妨げられない。この憲法が国民に保証する基本的人権は、侵すことの出来ない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。(以下省略)」と記している。
ここでの権利の主体は「国民」という言葉であらわされており、基本的人権が「国民」にだけ保障される特権と解釈されうるように書かれている。日本国が植民地支配した結果として日本国に住むことになり、一九五二年のサンフランシスコ講和条約までは日本国籍を持たされていた存在である在日朝鮮人・台湾人など旧植民地出身者(私もその一員)は、「国民」ではないために憲法上の基本的人権が保障されない存在にされたのである。つまり、植民地支配によって「臣民」の枠に引き入れられ、敗戦によって「国民」の枠外に追放されたのだ。すでにこの時点で一つの特権化が作動している。「国民」として特権化された人々が、普遍的であるべき民主主義的諸権利の、その普遍性を理解することのないまま、戦後憲法を定めた。だから彼ら中心部日本国民は、憲法に内包されている普遍的価値を自らの経験を通じて理解することができないのである。
憲法の英文に目をやると、第一一条には「The people shall not be prevented from enjoyingany of the fundamental human rights.」と書いてある。これはいわゆる「マッカーサー草案」をもとにして作られている英文テクストである。その日本語版は「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」である。
「国民」という言葉がもともと「people」という言葉だったことがわかる。「The people」というのは、一般には「人民」と訳すべき言葉である。そして、憲法第一〇条の英文を見ると、「Theconditions necessary for being a Japanese national shall be determined by law.」となっている。「a Japanese national」というのは「日本国籍保有者」ということだ。したがって、ここで分かることは、第一〇条と一一条が指している「国民」という言葉は、日本文では同じ「国民」と訳されているが、英文原文では違う言葉だということである。「a national」と「people」という異なる概念に同じ「国民」という訳語を当て、「国民の権利及び義務」という同じ章にくくった。そのために日本国籍を持っているものが「国民」であり、その「国民」が基本的人権を享受する、逆にいうと、日本国籍を持ってないものは基本的人権を認められなくても仕方ない、そういう解釈がまかり通ってきた。
これは、基本的人権の原理にそもそも反する。基本的人権は人間でありさえすれば誰にでも保障されるべき権利であって、国籍のあるなしは関係ない。しかし、現在の憲法にはそれを自国民だけに排他的に保障された特権であるかのように誤って解釈させる余地がある。そのような誤った考えが長い間まかり通り、「日本国民という言葉は日本国籍保有者という意味に限定的に解釈されるべき」であるという法解釈によって、過去には国民年金訴訟で在日朝鮮人が敗訴した例もある。
日本が国連難民条約に加入し批准した一九八二年以降、ようやく少しずつ、在日外国人の公務員任用とか国民年金法の手直しに着手し始めたが、その進捗は遅々としており、まだまだ不十分である。このことから私が言いたいことは、在日外国人に対する差別という点だけではない。むしろ、こうした経過によって、「基本的人権」という普遍的な理念を自国民の特権としてしか解釈できない中心部日本国民の意識が形成されたということである。それが翻って、在日朝鮮人など「国民」でない他者が人間として当然な基本的権利を要求した際に、それを「在日特権」などと称して攻撃する歪んだ心性が蔓延することになった。
そうした傾向を根本的に克服するためには、憲法そのものを反人権的(自国民中心主義的)解釈の入り込む余地のないものへ改めなければならない。「People」の訳語である「国民」を「住民」に改めることがその具体案の一つである。
憲法一条をどうするのか
敗戦を前後する時期、当時の日本政府は「国体護持」すなわち天皇制の維持を最大の課題としていた。明治憲法の君主主権制をすすんで変える気はなかった。そこで、GHQの側からマッカーサー草案という形で、現在の日本国憲法のもとになるものを提示することになる。マッカーサー草案の三つの骨子は、第一に象徴天皇制として天皇制を残し、天皇を通じた間接支配を行なうことだった。ことが長引くとソ連や中国など他の連合国から、天皇制を徹底的に廃止する形での新憲法という要求が出てくるかも知れないということで、アメリカは東アジアの戦後国際秩序における自国の覇権戦略を貫くため、そういう内容の憲法草案を作ったのだ。マッカーサー草案の第二の柱は、日本国の武装解除ということ。これが憲法九条である。そして、第三の柱は、民主主義的権利の保障ということだ。天皇制の護持という極めて否定的な側面と平和主義、民主主義という肯定的側面とがない混ぜになった形で、戦後憲法の構想が提示された。
憲法第一条は「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」と記している。この規定こそまさに、天皇制と天皇個人の戦争責任(および植民地支配責任)を不問に付しつつ、米国の戦略的利益を追求するためにひねり出されたものであるといえる。それはまた「国体護持」に固執する日本保守層の思惑とも合致した。それが日米安保条約である。戦後天皇制と安保条約はコインの裏表ともいえる関係であり、沖縄はその犠牲に供された。
この第一条がある限り、私は現在の日本国憲法を支持することはできない。自分が植民地支配を受けた朝鮮民族の一員だからそう考えるという面ももちろん否定しない。植民地朝鮮は天皇に「直隷」する朝鮮総督によって軍事占領された。朝鮮独立の試みは「国体変革」を禁じる治安維持法によって無慈悲に弾圧された。治安維持法犠牲者の数は、朝鮮人のほうが日本人よりはるかに多い。朝鮮植民地支配の究極的責任が天皇にあることは明らかである。
しかし、言うまでもなく、天皇制の犠牲者は朝鮮民族だけではない。日本国民たちも多くが天皇制の被害を受けた。大逆罪や治安維持法によって残虐な刑罰を受けた抵抗者たち、広島・長崎の原爆被害者、東京・名古屋・大阪などの空襲被害者、その他無数の非戦闘員被害者はもちろん、心ならずも戦地に送られて戦死か餓死を強いられ、あるいは無辜の現地人を殺戮する役割を演じた兵士たちにいたるまで、その責任の軽重に差があるとはいえ、おしなべて天皇制の被害者であった。日本国民たちは明治以来続いた対外膨張と侵略の歴史、それを可能にした制度と心性を根本的に克服すべきである。一九四五年の敗戦は、日本国民自身がこの「君主制のくびき」(あるいは「呪縛」)から脱する好機だったはずだ。
上記の憲法第一条の条文中、天皇の地位を日本国民の総意に基づくものとしていることは、ポツダム宣言受諾の前提として日本政府が意図した「国体護持」の意向確認に対するアメリカ合衆国からの「日本の政体は日本国民が自由に表明する意思のもとに決定される」との声明とも関連する。つまり、憲法第一条は「日本国民の自由な意思」によって変更可能なのである。いつまで時代錯誤的な君主制を護持し続けるのか。いつまで、みずからすすんで臣民であることをよしとするのか。自発的臣民としてこれからも他者と自国民の弱者を傷つけ続けるか、それとも、真の主権者となって、世界平和と人権という普遍的価値のために生きるか、そのことが日本国民に問われているはずだ。
だが、いまでは、そのような問いそのものを耳にすることもきわめて稀になった。戦後詩人に限っていえば、私自身の不明のせいかもしれないが、ストレートな天皇制批判として心に浮かぶのは茨木のり子の「四海波静」「倚りかからず」くらいである。詩人のみなさんには、槇村浩、中野重治、小熊秀雄ら、日本にも決して少なくない抵抗詩の命脈を失ってほしくない。
一滴の血も?
本稿冒頭で私は「戦後七〇年間、憲法九条のおかげで一滴も血を流さないですんだ」という常套句への違和感を表明しておいた。まず、これは事実に反する。朝鮮戦争では日本は米軍の兵站基地となり、おおいに朝鮮人と中国人の血を流すことに加担したが、秘密裏に掃海作業に派遣された日本人の血も流された。連合国軍の要請を受け、海上保安官や民間船員などの「特別掃海隊」を国連軍の作戦に参加させ、多数が命を落としたとされる。吉田茂首相の承認の下に行なわれたこの掃海活動は、戦後の日本にとって初めての参戦となった。
朝鮮戦争のみならず、ベトナム戦争でも湾岸戦争、イラク戦争でも、日本はおおいに他者の血を流すことに加担した。ベトナム戦争では日本で製造されたナパーム弾が嘉手納基地を飛び立ったB51爆撃機によってベトナム民衆の頭上にまき散らされた。そして朝鮮戦争でもベトナム戦争でも、日本社会は「特需景気」に沸いたのである。
国連決議もないままに他国に侵攻したイラク戦争に大義はなかったということは、現在では世界の常識となっている。この大義なき戦争の結果、ひとつの国家が根底から破壊され、数十万人が殺害され、その地域はいまではさまざまな武装勢力が割拠する無法地帯になってしまった。しかし、アメリカ合衆国ジョージ・W・ブッシュ大統領(当時)はもちろん、戦争に加担した各国の為政者は誰も責任を問われていない。日本の小泉純一郎首相(当時)も責任ある者の一人だ。
流されたのが「日本人の血」でさえなければよいというのか?(前述したようにそれも虚言であるが)ここには自分さえ安穏であればという自己本位な心性が現れていないか? 他人の血を流すことを漫然と黙認していると、やがて自分たちの血も流すことになる。それが歴史の教訓であるにもかかわらず、現在の日本社会に蔓延する自己中心主義とシニシズム(冷笑)に心が痛む。人間が「平和」とか「人道」とか「人権」とかいった、崇高な目的のために活動するということそのものを冷笑するシニカルな精神、そのシニカルな「国民」世論に、政府や政治家が積極的に迎合しマスコミもこれをむしろ煽るという傾向。それが恐ろしい。しかも、その一方で、為政者がきわめて浅薄に、ご都合主義的に、「理想」や「人道」という言葉をもてあそぶ。本来、崇高なはずの言葉が、これぐらい汚され、卑しめられた社会は、かつてないのではないか。
その最たるものが、イラクに自衛隊を派遣する際に小泉首相が行なった記者会見であった。そこで彼は憲法の前文を読んだ。憲法九条に触れなかったことが、一定の批判を受けた。しかし、それよりも重要なことだと私が思ったのは、憲法前文の精神そのものを捻じ曲げ、歪めて利用したということだ。憲法前文は「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を維持しようと決意した」と、平和主義の理念を強調している。その憲法前文を借りて、平和でも人道でもない戦争への加担を正当化したのである。
そのことを「国民」多数も承知していた。だが、憲法前文の理想を汚すなという声が澎湃と湧き起こるという事態は、ついに起きなかった。「国民」は後になって「騙された」ということは言えない。なぜなら、アメリカの盟友である英国ですらイラク戦争参戦の正当性についてきびしい検証を行なったのに、日本ではいまだに検証すら行なわれないままであり、「国民」の間からもそれを求める声がほとんど聞かれないからである。
ここまで書いてきた理由により、私は、日本国民が自律的に憲法九条を守ることができるかどうか、深く危惧している。そして、それでもなお、九条を守ろうとする日本国民に声援を送る。憲法九条は、先に述べたように、他民族の戦争被害者たちの血と涙によって贖われ付託されたものであり、現在を生きている日本国民だけの独占物ではないからである。
日本国民に切に望む。現在の憲法を理想化する地点に立ち止まり満足すべきではない。九条擁護のその先へ、日本国憲法にすら潜んでいる自己中心主義を脱し、真に普遍的な価値を実現する方向を目指して踏み出すべきである。そのためには、侵略と植民地支配の過去を真摯に見つめ、国外と国内の被害者たちと連帯すべきである、と。
-----------------------
初出:『詩人会議』二〇一六年八月 第五四巻第八号 詩人会議発行
二〇一五年に「安保法制」(戦争法)を成立させた安倍内閣は、二〇一六年になると憲法改定の意図をあらわにし始めた。同年七月の参議院選挙の結果、改憲勢力があわせて改憲発議ラインである議席数の三分の二を占めることになると、いよいよ改憲の動きが具体化することが見込まれた。本稿はその参議院選挙を前にした時点で書かれたものである。
-----------------------
【参考文献】
■中塚明著『日本人の明治観をただす』
■徐京植・高橋哲哉編著『奪われた野にも春は来るか』
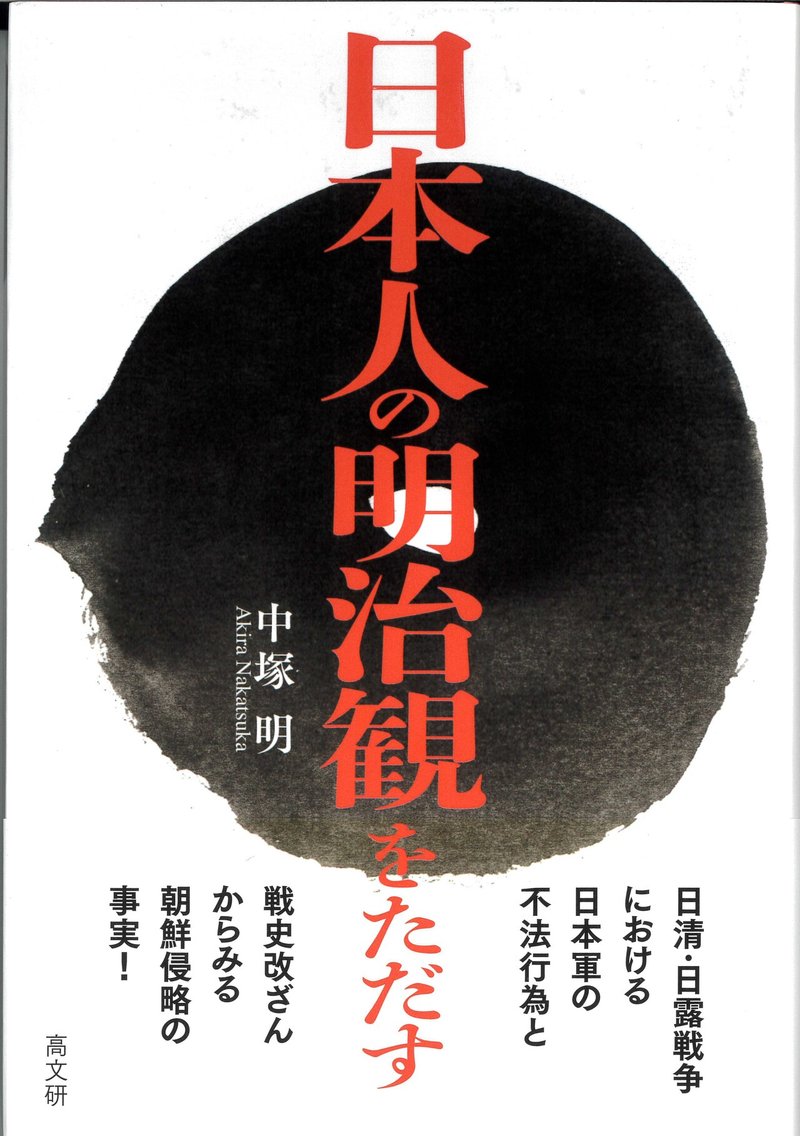
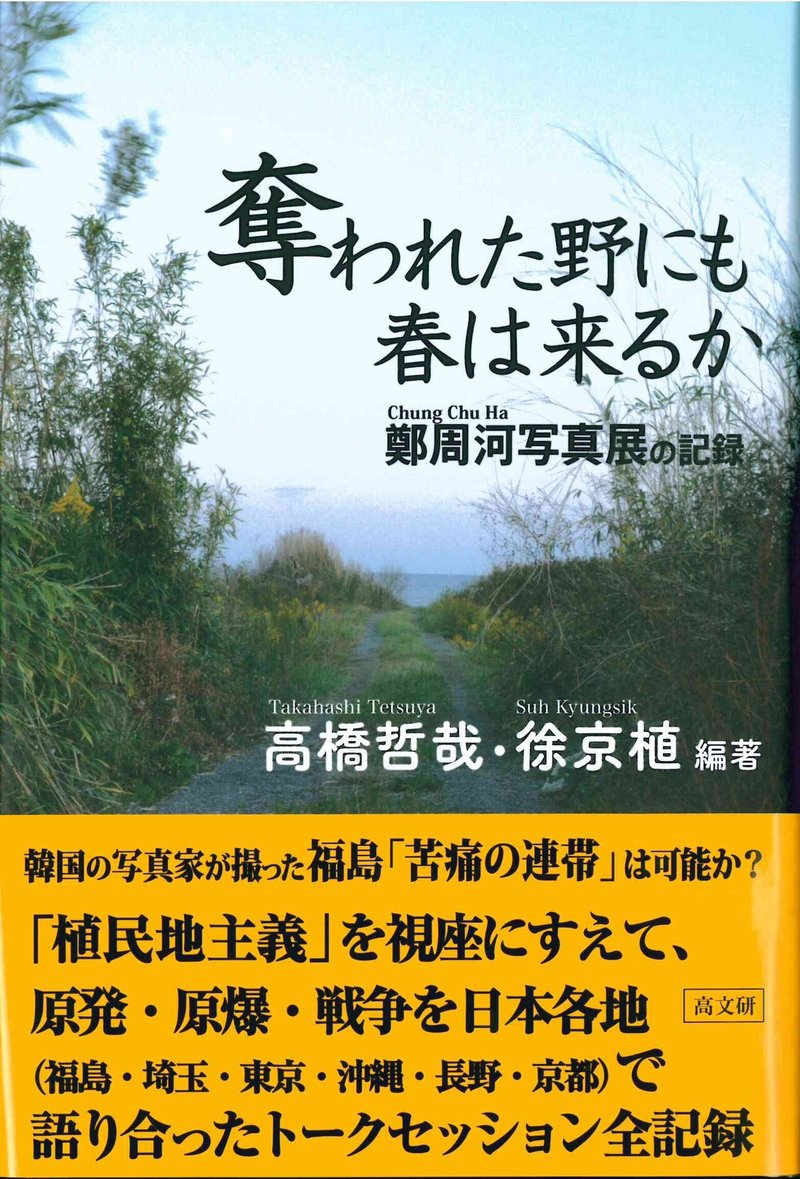
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
