「慰安婦」にされた人たちのことを「生身の人間」として受けとめるために
2021年1月8日、韓国・ソウル中央地裁は、韓国人の「慰安婦」被害者12人が日本政府を相手に損害賠償を求めていた裁判で、日本政府に1人当たり1億ウォン(約950万円)を賠償するよう命じる判決を言い渡した。
菅首相は「我が国としては、このような判決が出されることは、断じて受け入れることはできない」と断言している。安倍政権からの対韓国強硬路線は継承されているようだ。
「慰安婦」にされた人たちのことを「生身の人間」として受けとめるための参考文献。
川田文子著『イアンフとよばれた戦場の少女』

川田文子著『新版 赤瓦の家─朝鮮からきた従軍慰安婦』
l
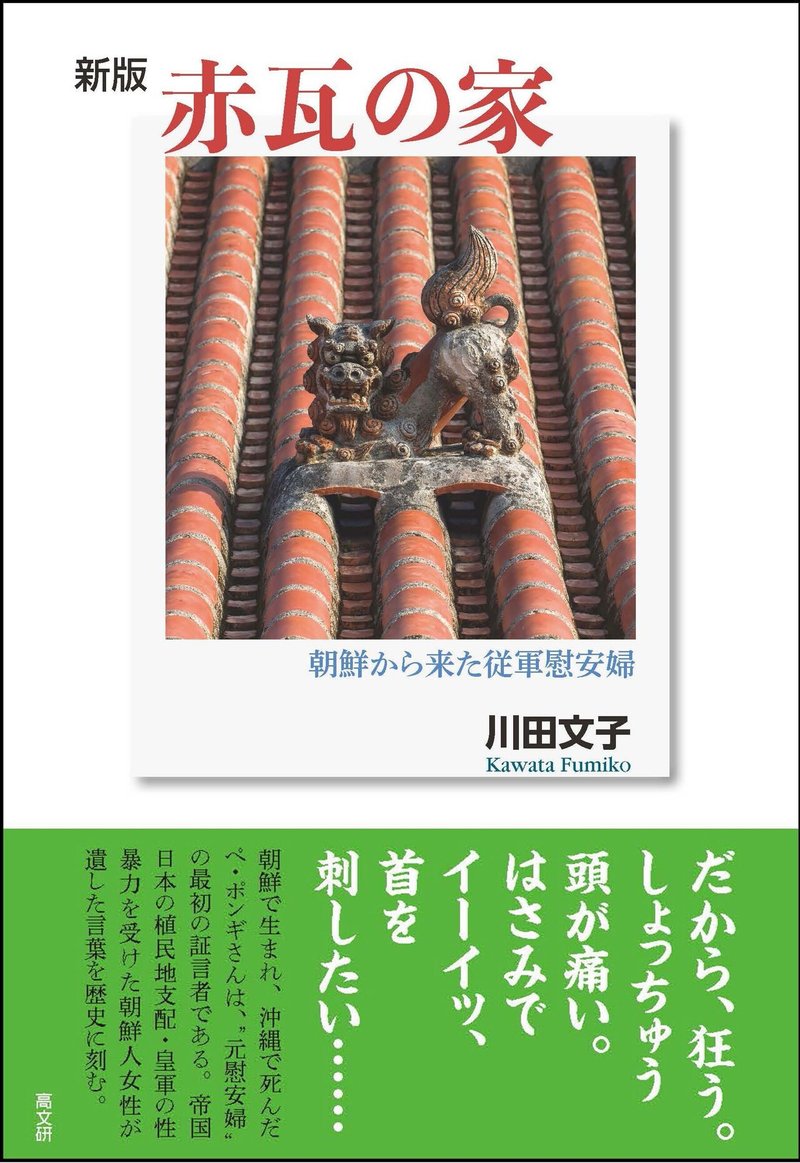
平井美津子著『「慰安婦」問題を子どもにどう教えるか』

以下に、徐京植「母を辱めるな」(『日本リベラル派の頽落』所収。初出:『ナショナル・ヒストリーを超えて』〈東京大学出版会、1998年〉)を全文掲載する。
母を辱めるな
彼は侮られ、人に捨てられ、悲しみの人で、病を知っていた。また顔を覆って忌み嫌われるもののように彼は侮られた。我々も彼を尊ばなかった。誠に彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。しかるに我々は思った。彼は打たれ、神にたたかれ、苦しめられたのだと。しかし、彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷により我々は癒されたのだ。(略)彼は暴虐な裁きによって取り去られた。その世の人のうち誰が思ったであろうか。彼はわが民の咎のために打たれて、生けるものの地から絶たれたのだと。
――旧約聖書「イザヤ書」五十三章
私の母がこの世を去る時、息子(私にとっては兄)が二人、政治犯として韓国の監獄に囚われていた。独裁者の死によってかすかに芽生えた釈放の期待は、別の独裁者の登場によって摘み取られた。光州に戒厳軍が投入され、多数の市民を虐殺したのが一九八〇年五月十八日。子宮癌による大量出血のため、母が京都市内の病院で息を引き取ったのが二日後の五月二十日未明である。「朝までの辛抱やで。朝になったら楽になるよ!」という私の気休めに、「朝まで? まだまだやないか……」と応じたのが最期の言葉だった〈註1〉。
「慰安婦」とか「朝鮮ピー」とかいう言葉を生前の母から聞いた記憶はない。だが、母はきっとその言葉の意味を知っていただろう。日帝時代〈註2〉の末期、朝鮮では若い娘が「挺身隊」という名目で狩りだされ日本軍の慰みものにされているという噂が広く流れ、未婚の娘をもつ朝鮮人家庭にパニックが広がった。その当時、母はすでに日本に住んでいたが、社交家で親分肌だったという祖父をたよって故郷の同胞がわが家に頻繁に出入りしていたというから、このまがまがしい噂は母の耳にも入っていたはずだ。
それに、あれは一九六〇年頃だっただろうか、わが家は小さな町工場を営んでいたが、工員のなかに一人、兵隊あがりの日本人がいた。日頃は温厚寡黙なその人が食事時など一杯はいると、中国の戦場で「便衣隊」をどんなふうに殺したか、銃剣が人体に深く刺さっていく感触まで描写しながら上機嫌に語っていたことを私は憶えている。まだ小学生の私かそんな話を耳にするのを、母はひどく嫌っていた。いまになって想像するのだが、あの兵隊あがりはきっと、「朝鮮ピー」をどんなふうに抱いたかなどということも話していたのではないだろうか。
一九六五年に刊行された朴慶植氏の名著『朝鮮人強制連行の記録』を、私は高校生の時に読んだ。だが、同書にある「慰安婦」に関するこんな記述は、つい最近まで私の記憶から消えていたのだ。恥ずかしいことである。
軍属として動員され片脚切断の重傷を負った玉致守さんという在日一世からの聞き取りである。
「玉致守氏の乗った船で南方に連行された朝鮮女性だけでも二千数百名にも上る。これらの女性は故郷にいるときには戦争への協力を強制され、軍需工場、被服廠で働くのだといわれて狩りだされた一七―二○歳のうら若い娘たちであった。しかし実際はこうして輸送船に乗せられて南方各地の戦線に送られ軍隊の慰安婦としてもてあそばれた。(略)玉氏が三回目に沈められた船にも一五〇余名の同胞の女性がのっていた。途中沖縄の宮古島に下船させたので海のもくずとはならなかったが、彼女らの運命はどうなったかわからない。」〈註3〉
解放後(日本敗戦後)も在日朝鮮人の間で、「慰安婦」をめぐる記憶が語り伝えられていたことがわかる。わが家に出入りした同胞たちの話題にもなったことだろう。ただ低い声で語り伝えられるだけの、姿も形もない「慰安婦」。――彼女らの運命に私の母がどれくらいわが身を重ね合わせていたかは、ただ想像してみるほかない。
すでに昨(一九九六)年六月、ある新聞記事〈註4〉を目にした時から、私の胸のなかで、ゴツゴツしたかたまりが限界近くまで膨らんでいた。板垣正参議院議員が、韓国から来日した元「慰安婦」の金相喜さんに対して、「カネはもらっていないのか」と何度も問い詰め、「強制的に連れていったという客観的証拠はあるのか」と言い放ったのだ。同じ紙面には、「明るい日本・国会議員連盟」の会長に就任した奥野誠亮元法相が「慰安婦は商行為」と述べたという記事も出ている。
板垣議員は朝鮮軍司令官も務めた戦犯の家族であり、日本遺族会顧問でもある。奥野元法相は内務官僚出身で、終戦時には米軍の押収をまぬがれるため公文書を焼却して証拠湮滅を行なったと自ら語っている人物だ〈註5〉。植民地支配の当事者ともいえる彼らが過去の罪を認めようとしないことには、いまさら驚きはしない。しかし、その記事を見たときには、何ともいえない嫌悪感がこみ上げてきた。とうとう決定的な一線が超えられたと感じた。この恥を知らぬ人々は最低限の慎みすらかなぐり捨て、面と向かって直接に、被害者を辱めるという行為に踏み出したのだ。
同年夏から「自由主義史観研究会」の藤岡信勝という東大教授が恥を知らぬ人々の合唱に加わり、九七年度採用予定の中学校歴史教科書から「慰安婦」に関する記述を削除するよう要求する動きを始めた。この東大教授や、西尾幹二、小林よしのり、坂本多加雄などといった人々が発起人となり、同年十二月二日には「新しい歴史教科書をつくる会」が発足した。それからしばらくたったある日、歯医者の待合室で雑誌の頁を開いたとき、私の中のゴツゴツとしたかたまりが破裂したのだ。「新しい歴史教科書をつくる会」の発起人のひとり山本夏彦が、元「慰安婦」が「今ごろ騒ぎだしたのは『金ほしさ』のためだといえばこれも誰もうなずく」と書いていたのである〈註6〉。
「金ほしさ」だって? 元「慰安婦」たちは、差別と貧困の中で刻々と年老いている。七十五歳になる宋神道さんにしても、異国日本で周囲の無理解と差別にさらされながら、身寄りもなく、生活保護だけをたよりに暮らしているのだ。どんなに心細いことだろうか。喉から手が出るほど金がほしいのは、当たり前だ。それに、彼女たちには補償金を要求する正当な権利がある。「金がほしい」としても、だからといって侮辱されなければならない理由などない。
宋神道さんは一九九三年四月五日、在日の元「慰安婦」としては初めて、日本政府の謝罪と補償を求める訴訟を東京地裁に提起した。宋さんは最初から弁護団や支援者に言っている。「おれは謝ってもらいてえ。謝ってもらえればそれでいいんだ。金目当てじゃないってことを分かってもらいてえ」〈註7〉。法廷での本人尋問の際にも、「いらない、金。謝れば一番いいんだ。謝って二度と戦争をしないこと」と、はっきりと答えている。このような原告の意向を受け、提訴の際は金銭的補償の要求(金員請求)をせず、謝罪文の交付と国会における公式謝罪のみを請求した。原告の受けた被害はとうてい金銭に換算できるものではないという点に加えて、「差別のある日本社会のもとでは、原告に危害が加わる恐れがあること」も、金員請求をしなかった理由のひとつに挙げられている〈註8〉。しかし、裁判開始後、日本の法律では謝罪請求だけでは訴訟が成り立たないという裁判官の意見によって金員請求を追加したのである。
「俺たちの税金で生活保護を受けて食ってるくせに、なんで裁判始めるんだ。文句があるなら韓国へ帰れ」「金が欲しくて裁判始めたんだろ。もう金はもらったか」――宋さんは地域の人々にそんな陰口をたたかれているという〈註9〉。提訴当初の原告側の危惧は、まさに板垣正、奥野誠亮、藤岡信勝、小林よしのり、山本夏彦らの言動によって裏付けられた。新聞、雑誌、漫画、講演などを通じて公然と行なわれる被害者への侮辱に、かなりの数の日本人が腹のなかでうなずいているのだろう。これがあからさまな「危害」でなくて何だろうか。
「私の母を辱めるな。」――この時から私は、日本軍の性奴隷にされたすべての元「慰安婦」たちを「母」と呼ぶことに決めたのだ〈註10〉。これは単なる感傷的な比喩ではない。
昨日(一九九七年十月二十四日)、私は宋神道さんに初めてお会いした。というより、そっと宋さんの姿を見るつもりである集会に出かけたら、紹介されてしまったのだ。元「慰安婦」は「私の母だ」と、あちこちで書いたり言ったりしてきたのに、私は実際に彼女たちの姿を見たことも、声を聞いたこともなかったのである。現実の宋さんを前にすると、「私はあなたを母だと思っています」などと、とても言いにくかった。おれはこんな息子をもった憶えねえよ、長い間、見向きもしなかったくせに、都合のいいときだけ気やすく「母」なんて呼ぶんじやねえ――そういって叱られそうな気がした。無理もない。宋さんが困難な訴訟を始めて四年以上になるのに、私はただ気を揉んでいただけで、一度だって傍聴にも行っていなかったのだから。申し訳なさがこみ上げて、ただ、すみません、すみません、と詫びていたら、おめえ何をそんなに謝る、泥棒したわけじゃあんめえ――そう言われてしまった。
宋神道さんは一九二二年の生まれである。私の母は戸籍上は一九二〇年生まれとなっているがこれはいい加減なもので、本人は常々、戊年(一九二二年)生まれだと言っていた。宋さんの出身地は現在の韓国の忠清南道論山郡。私の母の生まれ故郷である公州郡とは隣どうしだ。私の母と宋さんは、同郷の同年生まれなのである。母の生前に二人が知り合っていたら、ほんとうの姉妹のように親しくなっていたかもしれない。
解放後日本から引き揚げた祖父(母の父)は、論山で百姓をして暮らしていた。三十年ばかり前、高校一年生のとき、私は祖父を訪ねてその土地に行ったことがある。
べったりと広がる田圃、あばらが透けるほど痩せた飴色の牛、荷役に酷使されて背中が赤く禿げた朝鮮馬、誰もが充血した目をした農民たち、椀で飲む一杯の濁酒とやけっぱちな哄笑……そんな風景の中に、かつては日本人地主のものだったという屋敷が不似合いに立派な姿で残っていた。祖父のところも決して豊かではなかったが、それでも、そこには下働きの女性がいた。決して私と目を合わそうとしなかった彼女が朝から晩まで追い立てられるように働いて得る代償は、収穫後の米一叺だということだった。それが一年分の労働の報酬のすべてだと聞いて、絶句してしまったことを思い出す。あれから二、三年後、祖父は胃癌で死に、わずかな田畑は人手に渡った。あの女性はどうなったのだろうか。
今ではずいぶん様子が変わったが、私が訪ねた頃はまだ、あの土地にも日帝時代の朝鮮農村の貧しさの片鱗が残っていたのだろう。いや、日帝時代の貧しさは到底あんなものではすまなかったはずだ。当時の朝鮮農村では朝鮮総督府による「産米増殖計画」(一九二〇―三四年)が強行されており、朝鮮での米の生産量は約二割増加したが、朝鮮人一人あたりの米消費量は約四割も減少した。朝鮮人農民の多くは米を作りながら自分ではその米を食うことができず、土地を手放して没落していった。その救いのない植民地の貧しさのただ中に、私の母も、宋さんも、産み落とされたのだ。
宋神道さんは十二歳の時、父親を病気で亡くした。母親と妹の三人だけがとり残されたのだ。疲弊の極にあった当時の農村で、一家に唯一の働き手を失うことが何を意味していたかは想像に難くない。
宋さんは数え年十六歳のとき嫁に出されたが、これは「口べらし」だったのだろう。当時はめずらしいことではなかったはずだ。だが、宋さんは結婚初日に婚家から逃げ出したのだという。実家に逃げ帰ったものの母親に追い出された宋さんは、子守りや洗濯などの下働きをして、「まんまもらって食ったり」したというが、それがどんなに惨めな暮らしだったか、私はかつて祖父の家でみた、あの色黒で無口な女性の姿を重ね合わせてみる。
私の母も宋さんと同じく、貧しい朝鮮人農民の娘だった。
「今はうっすら夢みたいに憶えてますけどね、家の前に川があったりして、山裾の一軒家ですけどね、……ものすごく貧乏でね。食べるだけが精一杯。憶えてるけど、私のお母さんのお父さんは、占い師と言うんですか……。手先が器用で、ザルを編んだり、百姓ちょっとしたりしてたんですけど、ものすごいケチンボで、おばあさんが正月に餅をついて子供らに食べさせるいうたら、杵に粉が付くので勿体ないからやめとけ言うて、喧嘩したことがあるらしいですよ。それだけ貧乏やったいうことですね。」
宋さんの父親は亡くなったが、私の母の父は日本に渡った。一九二〇年代を通じて、窮乏化した何十万という朝鮮農民が生きる途を求めて、あるいは「満州」の間島へ、あるいは日本へと流れて行ったが、私の祖父もその一員だったわけである。
「酷いところへ行かされる前に(日本に)来た方がまだマシやというのでね、日本に『募集』があったさかいね。……(お父さんは)勤労奉仕させられてる時、途中でね、あの掘るもの(ツルハシ)を、どうせ行くんなら嫁さんのところの庭に放り込んでおけと思って、パーッと垣根越しに放り込んでね、それで家族にも誰にも言わんと日本に来たらしいんです。……私の母にも黙って、ね。(お父さんが)日本にきてから後で、心配してたら日本へ行ったという報せがあったらしいんです。」
「産米増殖計画」の過程で水利事業や道路建設などの労働に農民が駆り出されたが、「勤労奉仕」というのはそのことを指しているのだろう。とにかく、祖父は家族にも告げないままいなくなってしまったのだ。あとになって日本から連絡があるまで、残された家族はどんなに不安だっただろうか。何らかの事情で、そのまま祖父がいなくなっていたら……。たとえば、自暴自棄になって家族を捨てる、労働現場で怪我をする、関東大震災のときのような虐殺にあう、――そういうことはみな、いくらでもありえたことだ。もしもそうなっていたら、宋さんと同じように、私の母も、一家に唯一の働き手を失うことになっていたのである。
ともあれ、祖父は京都市郊外の農家の下働きとなり、故郷に残した家族を呼び寄せた。母が玄界灘を渡って下関に着いたのは満六歳のとき、一九二八年のことだ。ここで私の母と宋神道さんの運命が分岐したのである。
もっとも、日本に渡って来たからといって、母が安楽な生活を送ったわけではない。それどころか、母はわずか八歳から子守奉公に出なければならなかった。それに加えて、露骨な民族差別にさらされた。ある大工の家庭に雇われたときには、母だけが土間の床几で食事をするよう命じられたという。しかも、おかずはいつもタクアンだけだった。
「普通に遊んでいてもね、朝鮮人やからというだけで、もう一ペんに(態度が)変わってね、『あァ、ニンニク臭いし遊ばんとこ』と、こうなる。……『チョーセン』てなんで悪いのやろなァ、と自分で小さい時考えてました。私は学校も行ってへんし、着る物もええのを着せてくれへんし汚いからやろか、と思ったりしてましたけどね。……私もおかしなところがあるのか、(奉公先で)慣れて大事にされて、『お前はな、うちで真面目にようやってくれたら、箪笥、長もち買うてな、お嫁さんに行かしてあげるしな……』と言われるとね、何か不安になってくるんですね。…………なんでかと言うとね、私は朝鮮人やのに、ウッカリしたら日本人になるのと違うやろか、……何かそんな気持ちが起きたんですね。」
そうやって母は、日本人の子どもたちが学校に通うのを横目で見ながら、幼い頃から奉公暮らしに明け暮れ、のちには「織り子」とよばれる西陣織の女工になった。同世代の在日朝鮮人女性のほとんどがそうであるように、母は小学校の門すらくぐったことがなく、晩年まで文字が読めなかった。父と一緒になり、太平洋戦争が始まってからは、父が徴用にとられるのを免れるため、京都府下の周山という村で小作農になったが、高率の小作料に加えて供出が強いられたため、筆舌に尽くしがたい極貧生活を嘗めた。
「畔道ひとつ歩いてても、『うちの畔道、チョーセンが歩いてる』と、こうなりますやろ。それで、山ひとつ自由に行けしません。『チョーセンが山行って荒らす』とか言うさかいに……。昔は木を焚くさかいに枯木でも拾いに行きますやろ。そんな辛いときがありました。」
朝鮮憲兵隊司令部作成の『朝鮮同胞に対する内地人反省資録』(一九三三年)という文書がある〈註11〉。そこに挙げられている七十八項目の事例をみれば、当時どれほどの民族差別が日常のこととして行なわれていたか、その一端をうかがい知ることができるだろう。以下はその一部である。「火事と聞いて駆け付けたが朝鮮の人の家と判って皆引き返す」「『鮮人〈註12〉の腐れ頭を刈る器械はない』と散髪を断り追い返す」「停車場の待合室で待合中席を譲れと靴で足を蹴る」「商品券で物を買った鮮人客に『何処で拾ってきたか』と侮辱す」「落穂を拾った鮮女を泥棒と罵り足蹴にしたために流産す」「『ヨボ臭い豆腐は貰っても喰はれぬ』と侮辱した奥さん」「『ヨボ〈註13〉は豚小屋の様な家ばかり』と敷地の貸与をはねつける」「『今日は日本に負けた日だ』と鮮童を罵る小学生」……
母は常々、あの日々を「死にもの狂い」で乗り越えてきたと語っていた。日帝時代の朝鮮人の暮らしは、朝鮮半島ではもとより、宗主国日本の国内にあっても、このように「奴隷なみ」といっても大げさではない。けれども、母と同郷で同い年の宋神道さんは、あの日々、文字どおり「奴隷」の暮らしを強いられていたのである。何かの偶然で運命の歯車がわずかに狂っていたら、それは私の母の体験でもありえたのだ。
宋神道さんは大田で子守をしていたとき、見知らぬ中年女性に騙され、新義州で「コウ」という朝鮮人の男に売り飛ばされた。中国の天津までは鉄道で、そこからは「大きな汽船」に乗って、連れてこられたところが武昌だった。一九三八年、宋さんが十六歳のときのことだ。日本軍は、その前年七月七日の盧溝橋事件をきっかけに本格的な中国侵略戦争を開始し、前年末に南京で大強姦と大虐殺を起こしていた。三十万人の大兵力を動員した武漢作戦によって、日本軍が武昌を制圧したのがこの年十月二十七日、宋さんが武昌に到着したのは「寒いときだった」というから、十一月か十二月だっただろう。武昌への途中でも、到着してからも、宋さんはたくさんの死体を目にしたというが、硝煙と血の匂いが立ちこめる最前線に送り込まれたのだから無理もない。
朝鮮からいっしょに連れられて来た七、八人の女性とともに、宋神道さんが放りこまれた広い建物は、「世界館」という日本軍専用「慰安所」だった。そこが何をするところかも分からず、初潮すらまだだった十六歳の宋さんは、しかし、すぐにむごい現実を思い知らされなければならなかった。
最初に「軍医の橋本少尉」が「下の検査」をした。検査が終わった晩、その軍医が部屋にきた。
「遊びにきたの。……顔見たらやっぱり検査のとき見た顔だから、いや、この男、いったい何をするんだべなって、おっかなかったの。……こっちへ来いって、それ引っ張ってもだめだって、ういういと泣いたの。……半分は怖いし、半分は悲しいし、言葉は分からないし、大変だったよ。」
夢中で抵抗したところ軍医はあきらめて立ち去ったが、「帳場のサイ」や「コウ」に手荒く折檻された。「髪をひっぱって殴ったり、蹴っとばしたり、鼻血が出るくらい殴ったりしたの。……お前は借金背負ってきたんだから、借金払っていけだとかさ」。
宋神道さんは、そうやって「慰安婦」という名の日本軍性奴隷にされたのだ。
「入れ替わり立ち替わりにね。……言うことをきけだとか何とか言って、またいじめるんじゃないかと思って、気持ちが半分おっかなかったの。……とにかく言葉が通じないから、もう大変だったよ。とにかく嫌なら嫌と今ならばしゃべられるけど、俺は無学でしょう。学校も出ていないから。だから字も読めないし、言葉も通じないし、……情けのない軍人は刀抜いて暴れまくったり、これで殺すと言ったり、いろんな軍人がいました。……裸なれだの、へのこなめろだのさ、いろんな軍人がいました。そういうやつらが一杯いました。……入れ替わり立ち替わりね。表のほう蹴っとばしたり、早くやれだの何だのかんだのって、外でせんずりかいてるやつもいるし、様々な人間がいました。
帳場には殴られる。軍人たちには殴られる。本当に殴られ通しだよ。だから気持ちも荒くなるの、今は無理もないの。
朝の七時から夕方の五時まで兵隊時間だから。それから五時から八時までが下士官、士官。それから八時から一二時までが将校の時間。……飯食う時間がないんだってば。若いからいい。普通の人間だったらもう死んじまったよ。七〇人くらいとさせられたこともあるんですよ。――生理があろうが、肺病がたかろうが、マラリアであろうが、兵隊を相手にすることがきまっているの。」
逃げ出そうにも地理も分からず、文字が読めず、中国語はおろか日本語も満足にしゃべれず、まったくの無力で、誰一人として庇護者もいなかった。強いられる行為を拒めば容赦なく殴打され、自暴自棄になって暴れる日本軍人の刀で傷つけられた。その後遺症で宋さんの片耳は聴こえないし、右脇腹と脚の付け根には刀傷が残っている。
宋さんは武昌での三年間ののち、漢口の海軍慰安所を経て、岳州、安陸、宜昌、沙市、応山、咸寧、長安、蒲圻などの慰安所を点々と連れまわされた。これらの都市はいずれも日本軍の作戦区域内であり、司令部や主要部隊が置かれた重要拠点である、その点で宋さんの記憶は正確であり歴史の事実にも整合すると、歴史学者の藤原彰氏は証言している〈註14〉。日本軍による中国人の惨殺場面を強制的に見せられたこと、山の斜面に掘った人がひとり入れるくらいの穴で「慰安」を強いられたことなど、いまだに公開の場所で言葉にすることができない過酷な経験もあったという〈註15〉。そんな性奴隷の生活を日本敗戦まで七年もの間、続けさせられたのだ。
こうして宋神道さんの法廷陳述を拾い書きしているだけで、胸が詰まってくる。しかも、ここに語られていることは、宋さんが実際に経験した地獄の何百分の一に過ぎないのである。宋さんはその記憶を封印することによって、ようやく生き延びてくることができた。忘れてしまいたかった、思い出したくなかった、それでも勇気をふるって法廷に立ち、ここまで語ってくれたのである。それを「金ほしさ」に騒ぎだしたのだと罵る者がおり、その野卑な罵声にうなずいている多くの者がいる。これは、いかなる世界であろうか。
憤り、悔しさ、悲しさ、申し訳なさ、それらすべての入り混じった思いに胸が詰まる。――十六歳の少女に加えられた凄まじい暴虐に。国家意志によって、組織的に、何千、何万という女性たちに対して、こうした暴虐が加えられたことに。それが当たり前だと考えていた植民地支配者の民族差別と性差別に。それ以上に、現在なお、それを当たり前だと考えて疑わない人々がこんなにも多くいることに。「慰安婦」の存在を知識としては知っていながら、こんなにも長い間、具体的なことは何もしてこなかった私自身の罪深さに。そして、日本の国家犯罪の「手先」となって同胞の少女を売買し、殴打し、搾り取り、寄生虫として私腹を肥やした「サイ」や「コウ」、その他多数の朝鮮人犯罪者にも。
朝鮮人の「手先」がいたからといって、「元締め」である日本国家の責任はいささかも減免されない。「『慰安婦』を連行した業者の中には『朝鮮人』もいた」などという、民族差別意識につけこんだ責任のがれは許されてはならない。同時に、いかに「元締め」の罪が大きかろうと、「手先」には「手先」なりの罪がある。「元締め」の罪を追及するためにも、これら朝鮮人内部の犯罪者の追及は私たち朝鮮人自身の手でやりとげなければならない。
日本敗戦時、宋神道さんたち「慰安婦」は戦地に捨てられた。映画『ナヌムの家』(ビョン・ヨンジュ監督)には、当時捨てられたままいまも中国で暮らす朝鮮人元「慰安婦」が、たどたどしくなってしまった朝鮮語で故郷の歌をうたうシーンがある。
宋さんは現地除隊した元日本兵の誘うままに結婚し、この元日本兵に連れられて日本へ渡ってきた。しかし、博多港にたどり着いたとたん、元日本兵は宋さんを捨てたのだ。元日本兵は戦犯として処罰されることを恐れ、民間人を偽装するため宋さんを利用したものとみられる。見知らぬ異国日本にただ一人放り出された宋さんが、さらにどれほどの苦難を嘗めなければならなかったか、それをここに詳述することはできない。自殺をこころみて死にきれなかった宋さんは、ある在日朝鮮人男性に救われ、その男性とともに東北地方の一地方で戦後日本を生きてきたのである。
宋さん自身は元「慰安婦」であることを固く秘密にしてきた。「やっぱり格好悪いわ。風呂さ行ったりすると。……それで自分の縫い物の針でとろうと思ってつついたんだけど、なかなかとれてこないもの。……大きい絆創膏はってれば見えないべちゃ。……そういうふうに隠れ隠れして、それで風呂入ったの。」宋さんは武昌の慰安所で金子という名前を付けられ、その名を左腕に刺青されていたのである。
「引揚げ手当て」をもらおうと役場を訪れ、役人になぜ戦地に行ったのかと問われても「慰安婦」だったと答えることはできなかった。しかも、その手当ては日本国籍のない者には交付されないものだったのだが、宋さんには、そんなことは知るすべもなかった。
「あんまり男とやりすぎてお前のべべ(性器)にはタコがよってるんだべ」「お前の穴はバケツみたいに大きいんだってな」〈註16〉――そんな、毒を塗ったトゲのような言葉が浴びせられた。慰安所体験をもつ中国戦線帰りの元兵士が推測をつけ、いつしか、宋さんは元「慰安婦」だという噂が地域に広まったのだ。
「町会議員の平山」に「朝鮮さ、帰れ、帰れ」と言われ、宋さんは悔しさのあまりに殴りかかったこともあるという。
「朝鮮、帰れ」――ああ、何と聞き慣れた台詞だろう。
私自身も幼い頃、子どもどうしのケンカになると最後にはかならず「チョーセン、チョーセン、帰れ、帰れ」とはやされた。「チョーセン、チョーセン、パカ、スルナ、オナチメシクテ、トコチガウ(朝鮮、朝鮮と馬鹿にするな、同じ飯を食ってどこが違う)」と、近所や学級の子どもたちが大声で歌いはやした。大人たちが教えなくて、どうして子どもがそんな台詞を知っているだろう?
「チョーセン」とは何のことか、なぜ「チョーセン」である自分がこの日本にいるのか、どこに帰れというのか、何もわからないまま、泣くまいとして口をへの字にまげて帰宅すると、何も言わないうちに母はすべてを見通して、無条件に、ただ無条件に私を抱き締めたものだ。ことの経緯を聞くでもなく、ケンカの理由を問うでもなく、理由の如何にかかわらずケンカはいけないなどと退屈な市民道徳を諭すこともなく、ただ無条件に私を抱き締め、母は低い声で私の耳に何度も何度も繰り返した。「チョーセン、悪いことない、ちょっとも悪いことないのやで」。
その母の力で、私はまた、真っすぐに立つことができたのである。
どうして母は、あれほど揺るぎのない態度で「チョーセン、悪いことない」と言い切ることができたのだろうか? 自分自身も幼いときに日本に渡ってきて、差別と侮蔑にさらされ、学校にも行けず、朝鮮民族の文化や歴史を知らず、文字すらも読めなかった母が。
その上、母は後年、息子ふたりを韓国の監獄にとられることになって、再び何度も息子たちを抱き締めなければならなかった。「ペルゲンイ(アカ)、悪いことない」と。
母に守られ、母のあらゆる犠牲の上で、いわば母の肉を喰らって、私は学校へ通い、文字を覚え、「知識」なんか身につけ、いつの間にか小ざっぱりした中産階級のなりをして、きいたふうな口をきいている。
母が世を去った二年後、まだ獄中にあった兄のひとり(徐俊植)が母の夢をみたと手紙に書いてよこしたことがある。夢の中の母はバスの停留所でひとり立っていた。嬉しくて駆け寄ってみると、母は鼻を赤くして泣いていた。
「お前たちがみんな立派な人になってくれるようにと大学に入れてみたら、大学で難しい勉強をしてきては、みんなこの母さんを無学だと言って蔑むではないか。お前たちは学のない母さんを恥に思っているのではないか。だから私独りでどこか遠いところへ行って暮らすつもりだ。」〈註17〉
兄は夢の中で泣き、夢から覚めて「イザヤ書」五十三章を思い出したと書いていた。
宋神道さんを思うとき、私は母を思う。母を思うとき、宋神道さんや多くの元「慰安婦」を思う。侮られ、人に捨てられた人。顔を覆って忌み嫌われる人。私たちの病を負い、私たちの悲しみを担った人。この人を、私たちも尊ばなかった。植民地支配と戦後日本の差別社会の中で、民族分断体制と反民主強権政治の下で、つねに踏みつけにされ、軽んじられ、小突きまわされるように生きてきた人。富も地位も権力も知識も持たなかった人。だからこそ、まさにその故に、「自分たちは何も悪くない」と、一点の曇りもなく信じていることができたのだ。母たちは、その打たれた傷によって私たちを癒したのである。
いつの間にか母のことなど忘れかけていたこの身勝手な息子が、今度は、無条件に母を抱き締めるべき時なのだ。ことの経緯など問わず、「狭義の強制連行」があったかどうかなどと詮索することなく、ただ無条件に。日本による朝鮮「併合」そのものが「強制」だった。あの時、すべての朝鮮人が大日本帝国の臣民へと「強制連行」されたのだ。それ以上、どんな詮索が必要だろうか。母に向かって投げ付けられる石つぶてをこの身で受けとめながら、「正史」が黙殺し隠蔽してきた母たちの歴史のために、母たちとともに、また母たちに代わって、息子である私が声を発さなければならないのである。文字なんか覚え、知らず知らず心身を「知識」に侵されてしまったこの息子は、もはや母たちのようにひたすらに無垢であることはできないが、せめてその文字と「知識」を振り絞って、母たちを抱き締める力に変えたいと思う。
そして、私は知っている。こうして力んでみたところで、実際には私が母たちのために証言しているのではなく、今でも母たちが身をさらして私たちのために証言しているのだということを。宋神道さんがそうであるように。
【註】
〈1〉呉己順さん追悼文集刊行委員会編『朝を見ることなく――徐兄弟の母 呉己順さんの生涯』(社会思想社現代教養文庫、一九八一年)。以下、呉己順の言葉の引用は同書による。
〈2〉日本帝国主義が朝鮮を植民地支配していた時代を指す、朝鮮語の慣用的な表現。
〈3〉朴慶植『朝鮮人強制連行の記録』(未来社、一九六五年)一二二頁
〈4〉「朝日新聞」 一九九六年六月五日
〈5〉自治大学校史料編集室作成『山崎内務大臣を語る座談会』(一九六〇年)
〈6〉「週刊新潮」 一九九六年十二月十九日号
〈7〉在日の「慰安婦」裁判を支える会発行の冊子『宋さんといっしょに――よくわかる在日の元「慰安婦」裁判』一九九七年五月十六日。以下、本文中に引用した宋神道さんの言葉は同冊子による。
〈8〉「在日の慰安婦裁判を支える会会報」創刊号、一九九三年五月二十八日
〈9〉川田文子「陳述書」(一九九七年十月十五日、東京地裁に提出)
〈10〉徐京植「もはや黙っているべきではない」『分断を生きる――「在日」を超えて』(影書房、一九九七年)所収。この文章は「『自由主義史観』『新しい歴史教科書をつくる会』等の動きを憂慮する在日朝鮮人のアピール」(一九九七年一月二十日)への賛同を呼びかけたもの。同アピールには「朝鮮人」一一八四名、それ以外九百名が賛同した。
〈11〉宮田節子氏のご教示による。
〈12〉朝鮮人に対する蔑称。
〈13〉同上。日本語の「もしもし」や「おい」にあたる、朝鮮語の呼びかけが転じたもの。
〈14〉藤原彰「鑑定意見書」(一九九七年十月四日、東京地裁に提出)
〈15〉川田・前掲「陳述書」
〈16〉同上
〈17〉『徐俊植 全獄中書簡』(西村誠訳、柏書房、一九九二年)二二〇頁
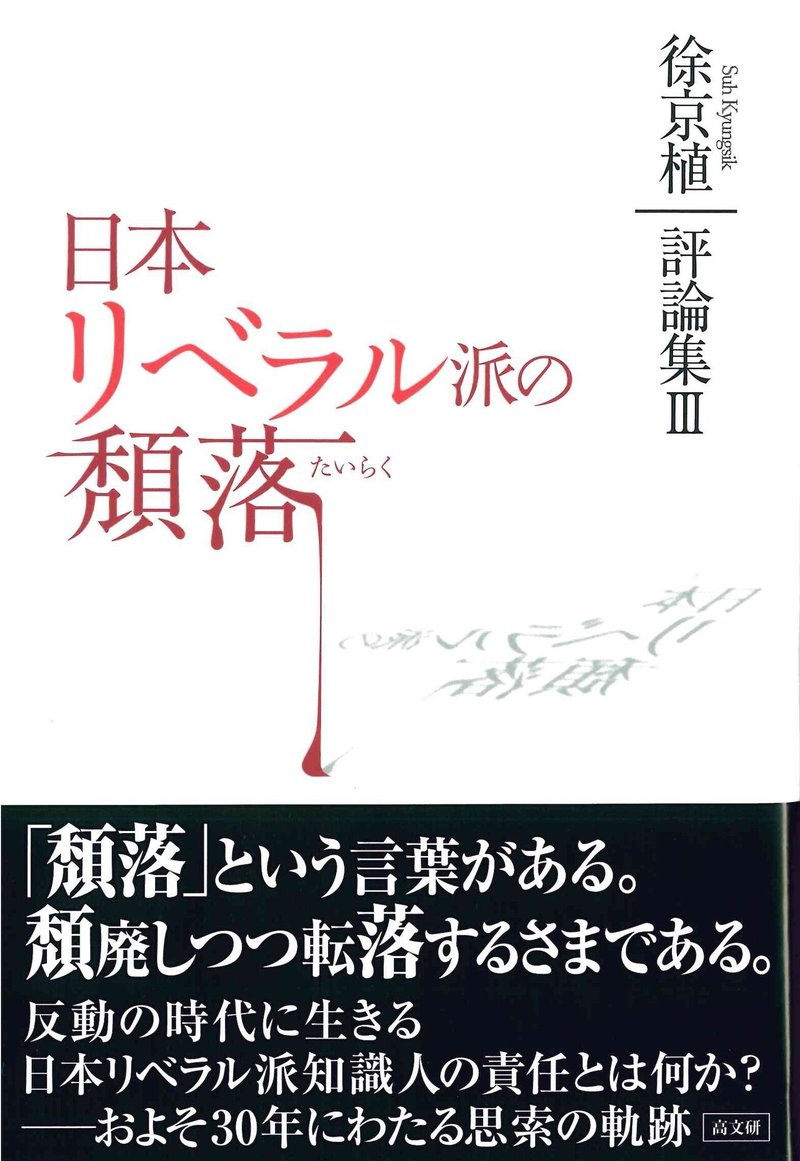
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
