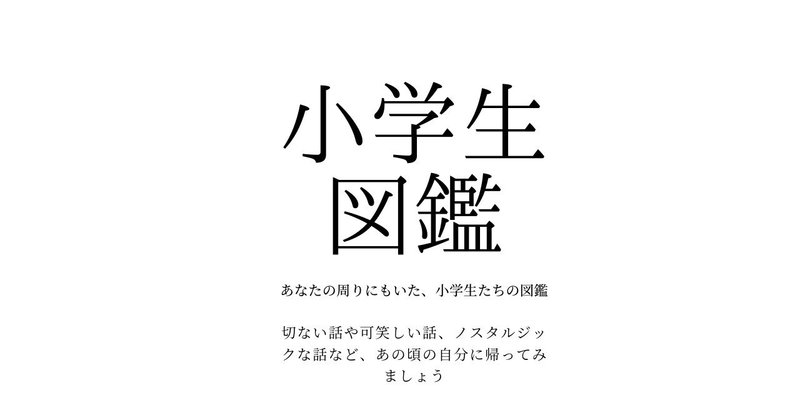
長ズボン
キタガキは、絶対に半ズボンを履かないやつだった。どんなに暑い日でも、体育の時間であっても、長ズボンで通した。誰もそのことについて何も訊かなかった。ただ、キタガキは半ズボンを履かないやつなんだな、というだけのことだった。それがカッコいいことだとも思わなかったし、カッコ悪いことだとも思わなかった。無関心というのではなく、地球が自転しているのを意識しないのと同じように、当たり前のこととして特別な意識をしていなかった。
運動会が近づくと各競技に向けた練習が始まった。団体競技のひとつに、みんなで同じ体操着を着て、行進をしたり輪を作ったりする、マスゲームのようなものがあり、この練習の時に、小さな事件が起きた。先生が、ひとりだけ違うと目立ってしまうから次からは必ず半ズボンを履いてきなさい、とキタガキに注意したのだ。キタガキは、嫌だと言った。先生は何故嫌なのだ、と訊いた。キタガキは、半ズボンを履きたくないからだ、と言った。先生は、あなたひとりが長ズボンを履いていると、輪を乱すことになるのだ、絶対に半ズボンを履いてきなさい、と叱った。
次の練習の時、キタガキは半ズボンを履いてきた。半ズボンを履いたキタガキは、キタガキっぽくなかった。キタガキのようでキタガキではないようだった。嘘っぽい二本の白い脚が却ってキタガキを目立たせ、クラスをザワつかせ、落ち着きのないものにした。
先生は、ひとりだけ違うと目立って輪を乱すのだ、と言った。誰から目立ってしまう、ということだったのだろう。運動会を観にくる生徒の家族から、ということだったのだろうか。そうだとすれば、運動会とは、誰のものなのだろう。競技をしている生徒にとっては、キタガキが長ズボンを履いていることで何も支障はなく、キタガキ自身にも、もちろん支障などなかった。寧ろ半ズボンを履くことの方が支障があった。
輪を乱す、という言葉が使われる時、画一的でなければいけない、みんなと同じでなければいけない、という、他者の目を勝手に意識して忖度した、自分目線だけの思い込みはないだろうか。個性を潰すことによって、その個性があってこそ均衡が保たれていたものを破壊してしまうことがあることを、小学生のぼくらは、その時漠然と学んだ。
とある夏休みに学校のプールに行くと、監視のために登校していた先生が半ズボンを履いていた。それは滅多に見ることのない先生のプライベートな姿であったが、太ももとスネをあらわにした姿に、キタガキに感じたのとは別の違和感を感じざるを得ず、多様性だと割り切って受け入れられるほどの、大人の感受性はぼくにはまだなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
