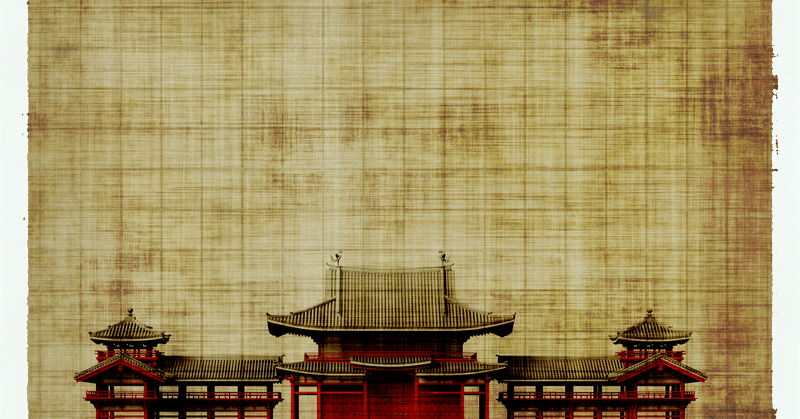
真・幼帝再臨抄 中華ノ皇帝、現代デ美少女トナリテ Ⅰ-2~5
Ⅰ-2 歴史と邂逅
かつては長安などと呼ばれ繁栄を極めた都市・西安(シーアン)。
その地に建設された巨大な歴史再現テーマパーク『SERICA(セリカ)』。
拡張現実と呼ばれる技術を使い、中国四千年の生きた歴史の姿を驚異的な再現度で体験できるのが売りなんだそうだ。
なんの因果だろうか今ぼくはこの施設の中で過ごしている。
いや――取り憑いている、とでもいうべきか。
「驚いたな……」
『魏晋(ぎしん)南北朝』
後世そう呼びならわされる、中華を二分する動乱の中――『宋(そう)』最後の皇帝として世を去っておよそ千五百年。
その後の世界の歴史を読み漁らせてもらったけど……
いかにあの時代がメチャクチャだったのか、ということを再認識することとなった。
あの時代は中国四千年と言われる歴史全体を眺めても、とりわけ狂っていたという結論に至らざるを得ない。
二二〇年に献帝が曹丕(そう・ひ)に王位を譲り、長きにわたり皇統を伝えた『漢』(後漢)が滅んだ。『三国志』時代の幕開けである。
一時は北部『魏』の有力家臣・司馬氏の『晋』が中華を統一したもののすぐに瓦解。中華は再び小国が乱立し互いに争う大混乱の時代となる。
長い時代を経て各国家の統合が進み、北部の『魏』(北魏)と南部の『晋』(東晋)の二大国が並び立つ『南北朝時代』が成立。
その『晋』を、漢王朝開祖・劉邦の弟の末裔を自称した我らが『宋』の開祖・劉裕(りゅう・ゆう)が滅ぼして以来、南北ともに短期間に国が変わり続ける異常事態が常となった。
それはぼくの生きた『宋』も例外ではない。
というよりは、その凄惨を極めた時代の中でも、特に後継者争いが熾烈を極めた時期であったらしい。
やっぱりな、という感じである。
あんな時代が正常であってたまるか。
ともあれこうした一連の混乱は、楊堅(よう・けん)の『隋(ずい)』が中国を統一するまで、宋滅亡から百年あまり――漢滅亡から数えて三百六十年以上続いたというのだから、いかに混乱が根深いものだったかを窺い知ることができるだろう。
『宋』末期に権力を握り、ぼくを暗殺し皇帝となった蕭道成(しょう・どうせい)将軍の興した『斉(せい)』も我らが一族にも劣らぬ醜い内部争いを繰り返したそうじゃないか。
とんだ笑い話だよ。なんのためにぼくは殺されたというのだろう。
まったくの無駄死にじゃないか。
――にしても、だ。
今この『トショカン』とかいう書蔵院にて、共に読書にふける女性。
ふだんその大部分が覆われている前髪は髪留めで分けられ、慎み深く柔和なその双眸を今ははっきりと見上げることができる。
凡河内結(おおこうち・ゆう)。
彼女があの、ぼくが接見した『倭(わ)』の人間であったとは。
ぼくはたった2年しか皇位に就いてはいなかったが、その間に特筆すべき外交成果があった。それが、ワカタケル大王――倭王武(雄略天皇とされている)が派遣した使節団の受け入れだ。
こちらは味方の確保のため、あちら側にとっては王の権威付けのため。
ぼくの名前で倭王武に新たな称号を与えたことは覚えている。
倭は時に新羅(シルラ)や百済(ペクチェ)を攻めるなどし、当時としても珍物の多い、豊かな国々の連合体だったと伝え聞く。
そんな彼らの国がやがて『日本』となり、世界史の中でも独自の発展をみせたことも、ある種納得はできようものだが……
しかしまさか一八九四年、中華王朝が日本に負けてしまうなんて。
いやそれもそうだが、それよりも。
ぼくの時代も北部を取られてはいたが──後世ついには異民族(モンゴル・女真)に全土を掌握されてしまったということにも衝撃を覚えた。
長きに渡る時の流れで、ぼくなんかじゃ考えもしなかったように変わってるのだなと、隔世の感に堪えない。
正倉院というらしい歴史的建造物をモチーフにしたというこの、人の息づかいすら響くほどの落ち着いた雰囲気の『トショカン』にしてもそう。
すべての蔵書がデータベース? とやらに収められ、室内であればどこでもまったく何もないハズの空間に文字を映し出すことができる。
仕組みは想像さえつかないが、実際にそうなんだから仕方がない。
……おそらく、このぼく自身の存在もデータベースとやらの産物なんだろう。
何もないところから生まれ、またこの『トショカン』も含めた作り物の世界『SERICA』内でしか生きられない。
穏やかに、されど確かに聞こえる息吹。
ぼくと彼女は一緒にいるようであっても、絶対に交わることのない関係にある。ぼくがどんなに彼女に惹かれようとも、触れることすらできない。
「……もし何かお聞きしたいことがありましたらちょっと出ますか?」
少し表情を強張らせてしまっただろうか。ぼくを案じるように彼女が顔をのぞき込む。気を遣わせてしまったか。
「……そうだね。ここじゃなるべく話をしないようにってことだったよね」
トショカンは私語は基本ダメ。
だけど激しい義務感に駆られてこうして未来を調べるにつれ、どうしても、何にもならぬ思いを叫びつくしてしまいたくなるんだ。
ここはお言葉に甘えて、少し外の風にでも当たりながら、気を鎮めたい。
……いやまあ、あくまでも現実に風を感じたりはできないんだけどね。
ぼくのような仮想上の存在だけが感じることができるように組まれたプログラム? だっけ?
それを通してなら五感もちゃんとあるんだけど、自然にあるものからはなんの感覚も得られないというのは、まったく難儀な被造物だ。
木製の椅子から立ち上がる結の所作をなぞるようにして『トショカン』を後にしようとしたその矢先、まったく意図せず呼び止められた。
「劉氏宋王朝の劉準、だね?」
見るとぼくの少し上程度の歳だろうか、小柄な少女。
洋服と呼ばれるスタイルで揃えているものの、この少女も――?
『トショカン』は戦闘厳禁のはずだが、不測の事態に備え身構える。
それを見て少女は両手を上げ表情を崩す。
「大丈夫ですよ、戦闘の意思はありません。わたしは楊侗 (よう・とう)。『隋』最後の皇帝です。もっとも、正式な皇帝とは見なされてはいませんが……」
……『隋』。混迷の時代を終わらせた、あの……?
この人、信用できるのか……?
傍らの結の様子を窺う。結もすぐに察してくれたようで、ぼくの欲しかった情報をくれる。
「隋の二代目・世祖(せいそ)楊広(よう・こう)が暗殺されてから、傀儡として立てられた皇帝ですね」
……なるほど、経歴は確かに。
それにつけてもこの才女。それが専門とはいえ、よくスラスラと出てくるものだ。
向かいの少女はなおのこと驚嘆していた。
「驚きました……我が祖父を『煬帝(ようだい)』と呼ばない方に初めてお目にかかります。人並みでない知見をお持ちです」
「恐れいります。『世祖』の諡号を贈られたのは貴君でございますから」
「……なんとそこまで……! 暴君としての評価が固まって久しい祖父帝も、さぞや天でお喜びのことでしょう……!」
楊侗はすっかり気を良くしたようだった。
彼女が結の言うとおりぼくと同じような運命を辿った皇帝だったとすれば――気持ちはとてもよくわかる。
家臣どもはいかに自分を利用し、帝位を奪おうか考えているような人物ばかり。ありのままのぼくら自身と向き合ってくれる、信頼に足る人物はいなかった。いたとしても裏切られた。
そんな人生を送ってきたぼくたちに寄り添い肯定してくれる。そんな人を、心の底から渇望しているんだ。
楊侗は何かを確信したのか、幾度となく小さく頷く。
「……わたしの勘は間違ってなかった。貴女と劉準に頼みがあります」
楊侗は覚悟を決めた面持ちだった。
「わたしを、奪ってください」
Ⅰ-3 死を与える
う、奪ってください……⁉
いきなりそんなことを言われても何が何やらさっぱりだ。今はじめて会ったばかりなのに、いったい何を奪うというのだろう。
ふと結(ゆう)の反応を窺う。楊侗(よう・とう)の悲痛な覚悟のようなものを汲み取ったのか、彼女は非常に沈痛な面持ちだった。
「……やはり、場所を移しましょう。ここは戦闘の心配はないとはいえ、図書館ですからね」
そう言って、唇に右の人差し指を重ねる。
なるほど、私語は慎めと。楊侗はこれを承けて深く恥じ入っていた。
とはいえ。この施設から一歩でも外へ出れば、再びいつ戦闘が始められてもおかしくはないし、それに――
大丈夫だとは思うが、この少女を信用していいのかという点。
仮に楊侗に敵対の意思はないとしても、彼女を裏で利用しようと暗躍している人間がいないとも限らない。
『トショカン』だから表立って手を出して来ないだけで、一歩出たら敵が大挙して待ち構えてる、なんてことも考えられるのだ。
そういう駆け引きは、嫌と言うほど見てきた。それはおそらく、楊侗もそうだろう。
「……大丈夫なの? 結」
「おそらく大丈夫。刺客が潜んでるようなデータは見られないわ」
……データ、か。
ぼくや楊侗、そしておそらくはほかの元皇帝やその軍勢。結のような内部プログラムを解析できるような人間にとっては、それらはすべて拡張現実上でしか動作しない文字情報の集まりでしかないのだろう。
やはりぼくと結には、高くそびえる長城のように乗り越えられない壁が存在している。
ぼくたちは少し歩いて、大きな池の見える広場に腰を落ち着けた。
……まあ本来こうして座り込む場所じゃないし実際に歩いた座ったと言えるのは結だけかもしれないけど。
「皇帝自らお独りで来られたのにはそれだけ深い覚悟がおありなのでしょうが……陛下は本当に、それでよろしいのですか?」
「構いませんよ。わたしはやり直しなんて求めてない。生まれ変わっても王家なんかに生まれないようにと言ったのに」
……生まれ変わっても二度と王家なんかに、か……
この人も、ぼくと似たような思いだったんだな。
「みんな皇帝としてのわたしの地位がほしかっただけで、誰からもわたしの命なんか望まれてなかった。そんなわたしの命でも、誰かの糧になれるのなら。それが、わたしなりに考えた末での結論なんです」
「……そうですか。わかりました、ならば何も言いません。『生命の結義』を執り行いましょう」
悲痛な面持ちでふたり勝手に話を進めていく。いやいや、状況がまったく見えてこないんですけど……!?
しかも何だよ、生命(いのち)の――なに?
ぼくの聞き間違いじゃなければ――『結義』という語句は、『三国志』の劉備が関羽張飛と共に悠久の絆を誓い合ったという時のようなものを指すはずだ。
もっとも『三国志演義』でつい最近読んだだけなんだけど。
初めて会ったばかりの者に、しかもロクな説明もなしに、そんな大それた誓いをしようというのか!?
「ちょちょちょっと、『生命の結義』ってなんだよ!」
それには流石にぼくも待ったをかけたい。
結はああそうかといった表情でこちらへ向き直る。
「説明してませんでしたね。失礼しました。それには、まずは前提となるお話も説明しなければならないでしょう。思い出してください、あなたが最初に一族の方に襲われた時のことを。その時あなたに力をもたらしたものがなんであったかを」
そう言って結は右手首を軽く掲げ、ぼくへ装身具の注目を促す。
赤黒く光を反射する小さな宝石が嵌め込まれた、小さな腕輪。
この石からいきなり力が湧いてきて――でもそれと何の関係が……
「それは古風そうな装身具ですが、見た目に反して数値データが埋め込まれています。その埋め込まれた数字のぶんだけその宝具は、あなたに力を与えてくれるのです」
「いまいち要領を得ないが……やっぱりこれが以前爆発的な力を引き出した原因だということで間違いはなさそうだね」
「はい。その数値は明確な計算のうえではじき出されたものです」
結の説明はこうだ。
国が存続した年数から、亡くなった時の年齢と通算皇帝在位年数とを引いた数値が、装備者が引き出すことのできる力となるという。
だとすると僕の場合、宋王朝が命脈を保った59年から、僕の年齢である10、そこから在位年数2も引いて47。というのが秘められた力の総数、ということになる。
なお隋(ずい)王朝最後の皇帝・楊侗の場合37から生年14、在位のおよそ1年を引き22。
つまり、年齢上は楊侗と比べるとぼくのほうが下だが、潜在的な力は倍以上ある計算となる。なるほど、彼女が大きく出られないわけだ……
だが実際のところこの数値、高いものなのかどうか、よくわからないというのが率直な感想だった。もっと数値の高い人がいっぱいいそう。
それに。そもそもだ。
原理はともかく、いったいそんなものをそれぞれの王に身につけさせていったい何をするつもりだ……?
確かめるように自らの宝具に目をやると、すぐに異変に気がついた。
「……!? 少ない……!?」
計算上47というのがぼくの持つ力の数値であるはずだが、宝石が映しだした数字はそこから1少ない。言ってたかだか1程度だ、誤差の範囲とも取れなくはないが……!?
その疑問すらも想定内という様子の結。うつむき加減で、バツが悪そうだった。
「……それは、劉義符との戦いの時に力を発動させたからです。力を発動させればそのたびに数値は減ってしまいます」
あの時はすごく悩んだがそうしなければ最初から負けていた。緊急とはいえごめんなさい、と深々と頭を下げる結。
「いやいや、顔を上げてよ。結は命の恩人。今だってこうして教えてもらわなきゃぼくは何も知らなかった。いくら感謝しても足りないくらいさ」
これは心の底からの、素直な気持ちだった。
この施設の中でしか生きられない拡張現実のプログラム体でしかないぼくに命なんてものがあるのかどうかは別として、ね。
とはいえ、これまでの説明でどうしても気になる点はいくつか出てきた。そのいくつかを結にぶつける。たまに言葉に詰まらせながらも、彼女は初学者に論語を教授するかのごとく、やさしく説明してくれた。
「たとえばこの数字の力を、全部使い切ったら……?」
「……消え去ります」
……やっぱり。消える、か。ぼくは別にそれでもいいけどね。
「でもそれじゃ、劉義符のような者が襲ってくるたびに力を使わなきゃいけないハメになるんでしょ? いくら刺客を撃退したとしてもすぐに力尽きてしまうんじゃ?」
「そうでしょうね。なので、この争いに参加している者たちはみな、『禅譲(ぜんじょう)』と『放伐(ほうばつ)』で、ほかの皇帝たちから力を奪うことに躍起になってるのです」
「力を……奪う」
そんなことができるのか。
……そういえば、劉子業があの時ポイントがどうこう言ってたのは……!?
「そうか。あいつらがぼくを襲ったのは……」
「そうです。劉準様はこの世界に『転生』したばかりでまだ力の使い方も知らなかった。その状態の劉準様を降す――『放伐』できれば、力をまるまる強奪できる。彼らからすれば非常に美味しい標的だったというわけです」
……早い話が、カモにされたというわけだ。
しかも劉子業はぼくの奇襲に失敗した劉義符を抹殺し、彼の力をせしめたというわけだ。深い溜息を出さずにはいられなかった。
何も変わっていない。何も。
千年以上もの時を経たというのに劉宋の一族というのはつくづく身内争いが好きだな……血で血で洗う内訌(ないこう)を繰り返した結果、それで身を滅ぼしたというのに!
「自らがはじめから持つ力だけではいずれ頭打ち。ほかの皇帝の力をなんとしても手に入れなければいけない。その方法は、劉義符らが行ったような、力づくで倒して奪い取ろうとする『放伐』。このほかにもう一つ、力を譲ってもらう『禅譲』があります。……聡明な劉準様なら、もうおわかりでしょう」
「禅譲……」
なるほどね……
結局、それか。
『禅譲』というのは、世の為を考え、皇帝が自分より優れている者に位を譲ることをいう。それが本当に皇帝自ら納得した上での決断だったら、どんなに美しい理念だろうとは思う。
だけど現実は権力奪取を目論む者たちに、
「自分は前の皇帝から任されて国を建てるんであって、決して無理やり支配者になったわけじゃない」
――という自己正当化の方便として使われた、というのが実態。
古くは三国志時代の献帝――そして蕭道成将軍に『禅譲』したぼくも。
皇帝なんて望んでなったものじゃないとは思っていたけれども……どうしてあわよくば自分を引きずり下ろそうとする者に帝位を譲りたいなんて思うだろうか。
自らすすんで、まったくの他人に皇帝の座を譲ろうなどと考える人は――
……待てよ。いるじゃないか、すぐ側に。
「お察しいただけたみたいですね。『生命の結義』とは、本来の意味での『禅譲』。ここにおられます楊陛下は、ご自身に宿る力のすべてをあなたに捧げることをお望みなのです」
開いた口が塞がらなかった。
すべて、って……
「で、でも! そんなことをしたら、彼女は――」
これまで押し黙っていた楊侗が、すうっと割って入る。どうして、どうして……そんなに穏やかな顔をしていられるんだ。
「いいんです。未練なんて。それにどうせ大した力も持たないわたしなんかは、どのみち誰かの格好の餌食です。誰とも知らぬ欲深い輩に命を奪われるくらいなら、君のような、かつて同じように泣いた者に託したいのです」
「か、勝手に決めないでよ……! ぼくは……」
「……確かに。これはわたしの身勝手かもしれない。ですが、劉宋の末裔。あなたには正しく導いてくれる人がいる。彼女とあなたらば、このバカバカしい戦いに、終止符を打ってくれる気がするんです」
「……戦い?」
「そうです。わたしたちは争わされているのです。かつて不幸のうちに帝位を追われた皇帝たち同士で、この広大な、かつての都を模した施設の支配権をめぐって、ね」
彼女のその言葉にハッとさせられた。そうか。そういうことか……!
やっと、おぼろげながらもこの世界のことが見えてきた。
ぼくら劉宋の一族や楊侗を『転生』させて、このような強力な力を秘めたものを持たせる。現代の人間どもは、ぼくたちを互いに争わせて、値踏みしているんだ。ぼくたちが真に皇帝としての資質があるのかどうかを――
「悪趣味だ……」
「そうですね。まったく、そのとおり」
「……君たち現代人はぼくたちを見世物にしてるの、結?」
「……否定はしません。ですが、私は終わらせたい。敵対ではなく手を取り合うような手段はあるはずなんです。これもあなたからすれば身勝手に聞こえるでしょう。でも」
「……」
「強制はしません。ですが……私のことを少しでも信頼してくださっているのなら、どうか、力を貸してほしいんです」
ぼくの心は揺れていた。
正直なところ、皇帝位だの施設支配権をめぐる争いだのは興味がない。
どうぞご勝手にという感じだ。
でも、ぼくの先祖一族が襲ってきたこと、そして幼くして運命に翻弄された同士との対面。いくら無関係を装いたくてもほぼ間違いなく、今後もこうした事件に巻き込まれていくのだろう。
ぼくだって、誰かに託したいよ。これほど明らかな面倒事に首を突っ込みたくはない。もうこりごりなんだ。
という気持ちも強くある一方で。
この女性と離れたくない――
という気持ちも、奥底から湧いてきて止めることができないんだ。
戸惑う気持ちはあるけれど、ぼくはこの出逢いを無駄にしたくない。
「ぼくは――」
意を決して自らの新たな運命を受け入れようとした、その時だった――
「助けてくれェェーーーーーー!!」
鬼気迫る表情でこちらに向かってくる、成人した男性。その出で立ちは現代人とは明らかに異なっている。明らかに『こちら側』だ。何者かに狙われているのか!? 身構え、追手に備える。
この男を見た時、結はこう呟いたのだった。
「この男――『元凶劭』……!」
Ⅰ-4 元凶の顕現
「元凶(げんきょう)劭(しょう)……?」
気づけばぼくは結(ゆう)の発した言葉をそのまま復唱していた。
その名前もまた、劉子業(りゅう・しぎょう)などのように生前から悪い評価で聞き及んでいた。
劉義符(りゅう・ぎふ)亡き後王位を継いだ第三代皇帝・文帝こと劉義隆(りゅう・ぎりゅう)は三十年に及ぶ長期間王位に就き、劉宋王朝の全盛期を築いた。
だがその末期には平和ゆえのほころびが生じはじめる。
軍人たちの強い反対を押し切って北半分を治める魏(北魏)を攻めたが、案の定平和ボケした軍隊では太刀打ちできず、かえって大敗を喫し、宋は大いに衰退した。
混乱に乗じて文帝を暗殺したのが、実の息子である皇太子劉劭(りゅう・しょう)その人である。
親殺しという大罪を犯し代わりに皇帝となった劉劭であったが、みずからも実の弟によりほどなく殺され、さらし首にされたという。歴史書でも国を乱した『元凶』とされ、正式な皇帝とは認められていない。
……まったく呆れるほど劉宋らしい挿話じゃないか。
その『元凶』がこうしてぼくたちにすがりついてきたのである。警戒するなというほうが無理な相談というものであろう。
「なあ、あんた運営の人間だろ……? 助けてくれよ……! おれはまた中途半端に死にたくはないんだよ……!」
やはりというべきだろうか、疑念を捨てきれずにいるらしい。彼を見下ろす結の表情は身震いするほどに冷ややかだった。
「運営……ですか。まったく……子業といい、あなた方一族は、どこでそのような言葉を覚えられたのでしょうかね?」
すぐに廃されたとはいえ、一時的にでも中華の南半分を統べた者とは思えぬいやしさで結の足下でへりくだる男。一族の恥を見せつけられているようで、ぼくはいたたまれない気持ちに襲われる。
そんなぼくたちの厳しい視線など構う余裕すらないのか、劉劭は必死にまくし立ててくる。
「そんなことどうでもいいだろ! お願いだよ……! おれは今追われているんだよ。そいつを助けてやったんだろ? だったらおれもいいじゃないかよ……!」
「……この子はルールを知らなかった。特別な措置です」
「じゃあ今は!? あんた、こいつに不必要に肩入れしてるじゃねぇか!」
「この少女は非常に不公平な立ち位置にいます。公正な戦いを望む観測者であるならば、彼女を守らなければいけないのです――外の世界の情報を漏らしているような何者か、からね」
「……おれを疑っているのかよ!? そんなに言うなら教えてやるよ、情報を漏らしているやつの正体を……それなら、信じてくれるだろ?」
「――!?」
結の眉が一瞬、大きく動く。彼女の表情の変化を、『元凶』と名付けられた男は見逃すことはなかった。
「そうだよなあ、お前らがいちばん欲しい情報だものなあ! 教えてやるよ、あいつらとつながっているのは――」
ヒュッと、風を切り向かってくる何かの気配。同じ感覚を味わったのはこれで2度め。そう、あれは――
「――危ない!」
両手を前に突き出して気を発する楊侗(よう・とう)。
ふたつの短刀が目の前でカランと音を立てて落下する。
……彼女が助けてくれたおかげで、すんでのところでぼくたちに向けられた殺意を防ぐことができた。
ぼくたちは人体には直接影響を及ぼすことはできないがモノに関しては触ったりすることができる。だから実体のないはずのぼくも図書館で本を読むような芸当もこなせたのである。
なんでも拡張現実上の座標軸を調整して現実のモノを動かしているそうだが、そんな原理今はどうだっていいだろう。
楊侗がいなければぼくも――そしておそらくは、結も……。
だが、劉劭を守る余裕まではなかった。
彼の背中には短刀が突き刺さっていた。
気付けばさっきまでぼくたちに媚を売っていた男は、無残に地面を舐める形で絶命していたのだった。
ほどなくして、ぼくたちの前に見知った男が姿を現す。
「まったく……これだから裏切りが染み付いたヤツは信用できねェ」
やっぱりか……劉子業!
「計画がちょっとばかし狂っちまったが……まァいい。こいつらを『放伐』するのは、予定通りだからなァ」
心底面倒くさい、といった態度で身体のあちこちを無造作にかきながら現れたその男を、結はキッと睨みつける。ぼくや楊侗に向ける穏やかなそれとあまりに正反対で、少し肝が冷える。
「……またあなたですか。ここまで身内を執拗に狙う理由はなんですか?」
二度目の闖入者は、結の鋭利な言葉を軽くいなしてみせる。
「身内、だからだよ。それがわからねェ嬢ちゃんじゃねェだろ。両雄並び立たず。劉宋の皇帝は一人で充分なんだよォ……!」
「……話し合いの余地はなさそうですね」
「はッ。話し合い。そんなのは暇な儒学者にでもやらせとけばいいんだよ。結局ものをいうのは力。圧倒的な力! そう思うだろ……末帝よォ!?」
突如としてぼくへと水を向けられる。
それについて返す言葉を持ち合わせていなかったけれど。
それでも何かは言わなきゃと、ぼ、ぼくは――とまごつかせる。
そんなぼくを見かねてか、彼女が割り込む。
「……匹夫の勇、ですね。弱い犬ほどよく吠える」
ぼくたちに尊大な態度をとる劉子業は、彼女のこの言葉にあからさまなイラつきを隠さなかった。
「テメェには聞いてねェんだよクソアマ……死にてェらしいなァ?」
結はといえば、劉子業の挑発に取り合うのも疲れたといった調子だった。
「……やれやれ。仕方ありませんね。できればこの手は使いたくなかったのですけど……天知る、地知る、我知る、人知る――孝を範に糾えし者よ、顕れたまえ!」
前の呪文とは違う――!?
「――!? なにもないところから……人が、出てきただと……!?」
「さて前廃帝こと劉子業。学があまりなさそうなあなたに歴史のお勉強です。孝献皇帝――さて、どなたのことだと思いますか?」
多くの粛清を行うとともに著しく礼を欠いたため側近に殺害されたという劉子業。そのような傍若無人な男であっても、その名前を耳にした瞬間、顔面蒼白となっていた。それもそうだ。その名前の意味するところは、ただごとではない。
姓は劉、名は協。字(あざな)は伯和(はくわ)。
彼については小説でも読んだし、生前に史書で知るところだった。
曹操(そう・そう)の傀儡として生き、その息子である曹丕(そう・ひ)に位を奪われた悲劇の皇帝。
そう、『献帝』という呼び方でもっとも知られている皇帝である。
落ち着き払いつつもすべてを諦めたと言わんばかりに厭世観ただよう、憔悴した初老のような姿。
彼もまた心底「再び転生などしたくはなかった」とその目で訴えかけているように、ぼくには映った。
そんな老いさらばえた廃帝、劉子業ならば身のこなしひとつで容易く縊(くび)り倒せるはずだ。
……にも関わらず、どうしてその男性の素性を知るやいなや顔色を変えたのか。それはひとえ背負っている「歴史」の重みが、あまりにも違いすぎるからだろう。
「漢帝国は前漢の214年と後漢の195年。合わせて409。そして献帝54歳の在位31年。それらを引いて計算――するまでもありませんね?」
「……な、なんだよそれ……!? 勝てるわけねェじゃねェか……!」
「そうですよ。あなた達が束になっても勝てるわけがないんです。だからこそ、あなたたちが不正した時のために、観測者たる私と行動を共にしてもらっているのです」
「そ、そんなこと聞いてねェ……話が違うじゃねェかよォォ……!」
劉子業はひどく取り乱す。だけどこれまでの経緯を考えれば、まったく同情の余地もない。
「劉子業、あなたもまた捨て駒だったということです」
「な……んだと……!? このオレが……捨て駒……!?」
「たかだか劉宋の皇帝たちを降したくらいでは到底敵うわけがない。最初から、私の力を消費させるためだけにけしかけられた。あるいは私の注意をひくためか……大方そんなところでしょう」
彼女の話を聞き終えた劉子業はスクリーンに映し出された偽りの虚空を見上げ、狂ったように高笑いをはじめる。
「……はッ。ははは、ふはははは」
「……何がおかしいの?」
「確かに? オレたちのようなポッと出の劉氏なんかじゃない血筋。大変なお力があることでしょうなァ!?」
劉子業は再び短刀を投げる。
「……ムダなことを!」
苦し紛れの抵抗だろうか。
けれど、まとわりつくような不吉な予兆を感じざるを得なかった。
どんな時でも命を狙われていた廃帝ゆえの本能なのかもしれない。
劉子業は、ニタリと粘っこく笑った。
「オレたち廃帝はテメェら生きるものに直接危害を加えることはできねェ。だがなァ!」
敵の投げた短刀は、先程楊侗がさばいて地面に転がり落ちていた短刀に当たり、双方大きく宙に打ち上がる。
「――!?」
きりもみ回転する短刀。それはいつの間にか結の背後を捉えていた。
「ひとたび術者の力が離れれば、その限りじゃねェんだぜ!?」
なんてことだ! このままじゃ――!
「結さん!」
「――っと、させねェよ!」
ぼくと楊侗が彼女を守ろうと動き出そうとしたところで、凄まじい気の流れと共に顕れた巨大な何者かが襲い掛かってくるのだった。
「くそっ、足止めか……! 結ぃっ!」
猪の顔と人の姿が混じった巨躯の獣。その猛攻を受けているその間。
激しく回転していた短刀はピタリと静止したと思えば加速度的に急降下、結の背後を脅かす。これは先程召喚された献帝が、巨大な腕の形となった強大な気によって双方弾き返す。
ほっとしたのも束の間だった。
本当の劉子業の狙いは、もう一方に落ちていた方で――彼女の華奢な身体は目にも留まらぬ速さで射抜かれ、力なく倒れるのが――信じられないほどに明瞭に、ぼくの眼前に映し出されたのだ。
鮮血が目の前で噴き出し、ポタポタとこぼれ落ちる。
「――結ぃぃぃーーーーーーーっ!」
気付けば涙を流し叫んでいた。
動揺のあまり、「いけない! 劉準君!」という楊侗の声が呼び戻してくれるまで、ぼくは自らの置かれた状況を見失ってしまっていたのだ。
「――はッ!?」
目の前には、肥えた『猪王(ちょおう)』。
獲物を仕留める獣が、太い腕を振り下ろさんとしていた。
ダメだ、間に合わない――やられる。
でも、ぼくは結を守ることができなかった。彼女を守りたいと誓ったばかりなのに。それなら、もう、今ここで終わってしまっても――
「――!? ぐふっ!?」
腹部に風で押しつぶされたような圧迫を感じたと思えば、ぼくの身体は大きく吹き飛ばされた。
悲鳴のような音を立てるほどの地面との激しい摩擦と、腹部を襲った衝撃に、むせ返る。
でも、生きている。
楊侗のやつか……ずいぶんと強引な手で目覚めさせてくれる。
でもおかげでスッキリしたよ。そうだ、ぼくは生きなければ。
生きて、このロクでもない見世物を終わらせなければならないんだ。痛みに耐え、立ち上がろうと、膝を上げた時だった。
「……ぁあぐっ!? ああぁぁああぁあぁ!!」
とてつもなく大きな……御しきれないほどの気が、身体中を駆け巡っている――!?
く、苦し……破裂しそうだ……!
「劉準君っ!?」
楊侗があわてて駆け寄ろうとしているらしかったが、意識が混濁してはっきりとは見ることができない。
まどろみの中、頭の中に直接語りかけてくるような声が聞こえてきたのだった。
「聞け、小童よ。吾(われ)の姓は曹、字は孟徳(もうとく)。汝の身体、しばし借りるぞ」
Ⅰ-5 乱世の奸雄
曹操――字(あざな)は孟徳。
もちろん知っている。
献帝を担いで後漢最後の実質的支配者となっていた男。
治世の能臣、乱世の奸雄──その曹操が……ぼくの頭の中に……直接……!?
「あぁあああぁぁあ……があああぁあぁぁあぁーーーーッ!!!」
再び大きな力がぼくの身体を駆け巡る。
ぼくの身体をかろうじてつなぎとめているかりそめの肉体が四散しそうなほどの負荷だ……! 幼虫のように身体を丸め身悶えることしかできない。
「劉準(りゅう・じゅん)君! しっかりして!」
ぼくの身を案じる楊侗(よう・とう)と、それを勝ち誇るように見下ろす劉子業(りゅう・しぎょう)。
「……支えを失って錯乱したか。まあ、テメェら廃帝にはふさわしい運命なんじゃねェの?」
「……劉子業……! あなた、これほどの規約違反を堂々と……!」
「あーーーッ敗者の負け惜しみがこんなに気持ちいいなんてなァ! そりゃあ権力の簒奪なんてやめられねェわなァ。歴史はどんな形であろうが、のし上がったもの勝ちなんだよ。勝てば官軍。不正なんてものは一時的な価値観の産物であって、勝者になればいくらでも変えられるんだよ。それを最も知っているのはオレたちだろォ!?」
「……外道!」
「はッ。雑魚だと思って捨て置いてやったのに、よほど『放伐』されたいみたいだな。いいぜ、まずはテメェから――」
「――!?」
「――うぎゃあああああッ!? お、オレの腕がアアアアアアァァァッッ!!」
「……劉……準君、なの!? いや……あなたは――」
「……ぐぅぅぅッ……! テメェ……劉準じゃねェ、献帝なのか、それとも!」
「劉準君!? き、消え……!?」
「神足、影さえ捉えること能わず。故に、絶影」
「――その名は……!? 劉準君、あなたまさか――」
「テメェ……! いい気になるなよォ! どうせここで勝てば桁違いの力が手に入るんだ。もう出し惜しみしねェ! 行けよ、猪王(ちょおう)!」
「――な、この気……危な――」
「なっ……んだとォ……!!? た、たった一撃……」
ぼく自身、何をしたのか、わかっていなかった。ただ確実に言えたのは、ぼくはぼくでない大きな力によって突き動かされていた、ということ──
「……ちくしょう……畜生がああああァァァァ!!!」
己の全能力を乗せた起死回生の召喚術も破られた哀れな元皇帝は、膝をつけて嗚咽をあげる。ぼくの眼前には、すべての力を使い果たし出涸らしとなった劉子業を、手刀で貫き降す――その光景だけが映し出されるばかりだった。
「……劉準君」
「……くぉ、くおああああああああッ!?」
目の前の敵を降したと思えば、再び身体じゅうを龍が這っているかのような痛み。
くそっ……なんだっていうんだ……!
ぼくは一刻も早く結を助けたいのに……!
ぼくができないのなら、彼女に……
「……ううっ……楊侗……」
「劉準君! 劉準君なんですね! よかった……」
「……ぼくのことは、いい……それよりも、結を……ッ……!」
「わかりました。すぐに助けを。あなたも気をしっかり持って」
再び縮こまって痛みに耐えるしかできない。そんなぼくを楊侗は心配そうにちらりと見たあと、すぐにその場を後にする。
……さて。ぼくはぼくに巣食う龍と、対峙しなければ……!
――曹、孟徳!
「……ほう。汝、意外と見どころがあるな。この状況で、吾(われ)を呼び捨てとは」
ぼくの内部から反響するような声。
「……ぼくを殺したり完全に乗っ取る気なら初めからそうしている。それをあえてしないということはあなた自身にも弱みがあるということ……違いますか?」
ぼくの話を聞き終えた曹操はケタケタと、やおら豪快に笑いだした。
「――劉という姓には何かと縁がある。皇帝、劉季玉に劉玄徳――そして汝劉準。ふはは、おもしろき宿縁よ。汝もあの時代を生きていれば、存外群雄となり吾を苦しめていたやも知れぬな」
「……それは、どうも。でも……ぼくは器には不十分ですよ」
この男一人乗りこなせない身体、ではね――
「そうとは限らんぞ。確かに汝は何事もなしえぬまま生涯を終えたやも知れぬ。が、それは裏を返せば今後次第で何物にもなり得るということだ。名君にも、暗君にもなり得る可能性が、今の汝にはある」
「……」
曹操が話を進める。
「漢王朝の長大さと、吾という力。単純な攻撃力にかけては敵なしといえよう。だが……いかんせんそれを支えるだけの器を、劉伯和は持っていない」
ぼくの目の前には、老体の献帝の姿も映る。
目の前にたたずむ老人は、悲しさと無念さをにじませたような表情をたたえていた。彼の意思を代弁するように、曹操は続ける。
「帝位を追われた皇帝としては珍しく天寿をまっとうできたことが逆に災いして、強大すぎる力は老体に荷が重すぎてな。みだりに力を使いすぎると、吾も献帝も自壊してしまうのだ」
「それで、ぼくの身体に一時的に憑依したと……?」
僕の意識下に映る曹操は首肯する。
「これは歴史的事実として話すが。吾が息子たちが皇帝陛下を廃位させて興した魏は孫権の呉よりも短命に終わった。口惜しいが、吾の天寿よりも短い年数だ。それゆえ、吾は曹一族の祖としてはこの世界に根を下ろすことができないのだ」
今ぼくと対峙している曹操という男は献帝という存在に依存し寄生しなければ存在することができない不安定な存在、ということになるのだろうか。
なるほど、ある意味で生前と立場が逆転している。
「……現実的な問題として、吾々はこの『SERICA』の支配権をめぐる戦いには初めから勝ち目がなかった。それゆえ吾々は、この世界を調停する役割に回ることを選んだのだ」
ぼくの下へ姿を晒した曹操その人は、天下の大部分を私(わたくし)した豪傑には思えぬほど、ひどく小さく感じられた。
少なくとも純粋な体格においては成り上がりの軍人である蕭道成――ぼくを殺したあの大男のほうが、はるかに壮健だったように思い起こされる。
「……かつては覇道を望んだ男が、小さく収まっているものだと笑うか?」
ぼくの生きた時代からすでに伝説的存在だった男の、意外なほど人間的な一面に触れた気がした。
この曹操という男のほんとうを、献帝と、ぼくだけが知っている。
それが、ひどく特別なことのように思えて嬉しくもあり残念でもあったが――ぼくはそんな老人を、嗤うことはできない。
「……まさか。そんなことを言うなら、ぼくにはそもそも野望さえもない。ぼくには、何もないんだ」
ただひたすらにここから逃げ出したい。皇族なんかに生まれたくなかったと、後ろ向きに生きることしかできなかったぼくには……
「そうかな? 汝が今もっとも望んでいること。それは……何だ?」
……ぼくが、ぼくが……今もっとも望んでいること……?
そんなの、ひとつ――いや、一人しかいない。
結。
「――力が欲しい。大切な人を――結を護ることのできる、圧倒的な力が」
老人は、満足気に微笑む。
「決まり――だな。皇帝陛下。この者と『生命の結義』を執り行いませい」
曹操に促され、献帝が進み出る。
「……献帝……いえ、劉伯和さん」
「……案ずることはない。そうは見えぬかもしれないが……今私は心晴れやかな気持ちなのだ」
「……どうして、ですか?」
「禅譲というのは神話上にしかありえぬものだと思っていた。だがここに、本来の正しいあり方で執り行うことができる。心から信じられると思えた者に後事を託すことができたと思えば――我が生命がここに転生したことにも意味があったというものだ」
献帝による呪文の詠唱が、ゆっくりとはじまる。
「――ああ爾(なんじ)舜(しゅん)よ、天の巡る運命は爾が身にあり。まことにほどよき中ほどを守れ。四海は苦しめり。天の恵みの永久に続かんことを――さあ。ここから先は、君が詠唱する番だ。この続きは……君もよく知っているはずだ」
ぼくはあまりにも悲しくて、首を横に振った。
「……こんなの……こんなのって……こんなのってないですよ……!」
「言うんだ、皇帝。君は、真の天子になるんだ」
ぼくは、詠唱をしている間、涙を止めることができなかった。
「……皇帝の臣下準、はっきりと偉大なる上帝に申し上げます」
これは『論語』を下敷きにした『禅譲』の定型文なのだ。そう、ぼくはこれから続く言葉によって帝位を追われた。
そしてそれは、この歴史上の先輩も同様なのだ。
つまりかつて味わったであろう屈辱を、再びこの人に上塗りしなければならないということ。
その残酷さと趣味の悪さに。
この規則を創った現代を生きる者たちに、そして、その規則に添ってしか存在することができないみずからの歯がゆさに。深い憤りを抱かずにはいられなかった。
「天は大佑(たいゆう)を顕し、天命を下す。天下は兆民の望むままに、ここに真の天子に託された――!」
「そうだ。それでよい。では劉準――汝にこの世界を、結を、任せたぞ」
「曹……孟徳さん……!」
ぼくはそれ以上言葉にすることができなかった。
抵抗するかのように身体を這いずり回っていた龍のような気が、ぼくの気脈に沿うように吸い込まれていき、鎮まる。目覚めたときとは比較にならない力が宿っていくのが、ありありとわかった。
長大なる漢王朝の歴史が、ぼくの生命に刻まれ息づいていく――そんな風に思えた。
先程までぼくの目の前に立ち並んでいた曹操も、献帝も。もういない。
あの二人を飲み込んだのだ。ぼくが、ぼくごときが……この手で。
これが禅譲――『生命の結義』。
ただただ理不尽な暴力の前に順うことしかできなかった無力な皇帝だったぼくが。
今回の戦いで差し引かれた分を考えても、332加算されて369。
当初のぼく自身の生命力である47から、いきなり、およそ8倍もの力を手にすることになったのだ。
この日を境に、歴史上ありふれた幼帝の一人にすぎなかったぼくの運命は一変してしまうのだった。
次の話はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
