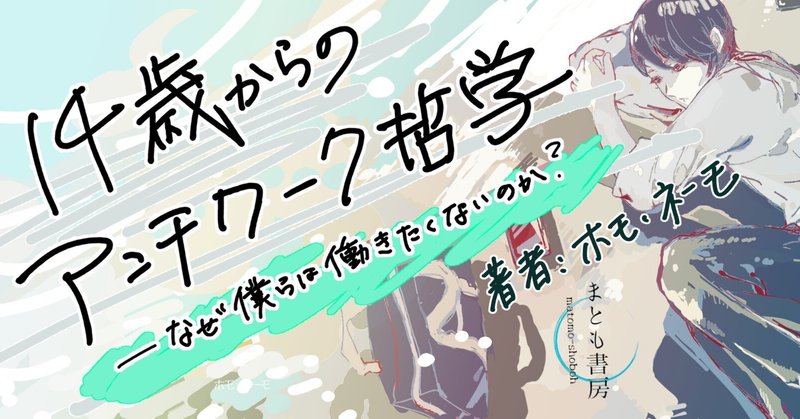
5章 人間が欲望するもの【14歳からのアンチワーク哲学】
※2024年6月発売予定の新刊を1章ずつ無料公開します。
【前の章】
雨は加速し、風が吹き抜ける。まるで嵐だ。でも、あまり気にならない。僕たちの議論も同じ速度で進んでいるようだ。
嫌なことをやめて、好きなことをやる。欲望のままに生きる。それはダメなことだと思い込んでいたけど、ニケは逆に欲望のまま生きるべきだと言う。本当にそうなのだろうか。一を理解すれば十の疑問が浮かんでくる。
もし、ニケが言うように、人間が欲望に従って勝手に貢献する生き物だったのなら、どうしてこの世界にはお金があって、支配があって、労働があるのだろうか? 自由になった人間は本当に、水道や電気、家、スーパーマケット、美味しいレストラン、温かいベッド、漫画、ゲーム機を自発的に提供してくれるのだろうか? それは趣味のように素人レベルの仕事にとどまり、途中で投げ出されるのではないだろうか?
穴の空いたボートから水をかき出すように、僕は次から次へと疑問をニケに投げ捨てなければならない。そうしなければ、思考の海に溺れてしまいそうだ。一つ一つ、議論をしていこう。
本当にお金のため?
「どや? ベーシックインカムで環境問題も、犯罪も、いじめも、パワハラも、企業の不祥事も、消える。こんなにポテンシャルのある解決策を試さへんなんて、あほらしくないか? 他のやり方で散々いままで失敗してきてるのに」
「でもさ、ベーシックインカムのメリットをいくら並べても、誰かが必要最低限は働かないと絵に描いた餅だよね?」
「ん? どういうことや?」
「もし誰も働かなくなって食べ物がなくなるのなら、さっきまでのメリットも意味なくなるよね?」
「あぁ、せやな」
「お金が配られてもみんなが必要な仕事をするなんて、やっぱり信じられないよ。みんなお金のために働いているわけなんだし、お金が配られればずっと家でゲームしたり、海外ドラマを観たり、コタツでみかんを食べてたりするんじゃない?」
「あんな、そういうところが中二病やねん」
「どういうこと?」
「人間は怠惰で利己的でワガママやと決めつけるのがカッコいいって思ってるやろ?」
「いや、別にそういうわけじゃ・・・」
「斜に構えといたら、なんとなく頭良さそうに見えるもんな?」
「いや・・・」
「はっきり言うで。そういうのはもうダサい」
「え?」
「おまけにキモい」
「は?」
なにもそこまで言わなくても・・・。僕は少しムッとなって、ニケに言い返した。
「平日の昼間から中学生相手に公園で説教垂れてるニートの方がダサくてキモくない?」
「せやな。少年、痛いところ突くなぁ」
ニケは笑いながらあっさりと認める。僕は拍子抜けして笑ってしまった。どうやらニケにはプライドってものがなく、誰がなにを言おうが気にしないらしい。まぁ、そうでなければ五十歳になるまでニートができるわけがないのだけれど。
「冗談や。それに仕方ないねん。この世の中では中二病が蔓延してるからな」
「え? そうなの」
「せや。人間が怠惰で利己的でワガママっていう考え方が蔓延ってる。有名人が環境問題解決のために活動してたら、みんなどう反応する?」
「どうだろう?」
環境保護に熱心な有名人は定期的に見かける。なんだか説教くさいし、嘘くさいし、どこかお金の匂いがすると、僕はいつも感じている。
「褒める人もいるだろうけど、『本当に環境のため? お金のためなんじゃないの?』と勘繰る人も多そうだね」
「そう。でも想像して欲しいねん。その有名人が『実はお金のためでした』って発表したらどうなる?」
「なかなかない状況だけど、言ったとすれば叩かれるだろうね」
「せやな。でもな『本当にお金のため?』と疑う人はおらんのちゃうか?」
「そりゃそうでしょ。実際にそうなんだろうし」
「でも不思議じゃないか? なんで『本当にお金のためか? なにか裏があるんじゃないか?』と勘繰る人はおらんねやろな?」
「それは・・・どうしてだろうね?」
「まるで金儲けのために環境保護活動することが正しいことって言われてるみたいやないか?」
「そう・・・かな?」
「せや。でも、そもそも『真の理由はなにか?』という質問が間違ってるねん」
「え?」
「『真の理由』っていうのはそもそも存在せん」
またニケは身も蓋もないことを言う。
「出たよ。ニケお得意の、質問そのものを台無しにするパターンじゃん」
「必殺技みたいやろ? でも、哲学者ってこういう仕事なんやで」
「自称哲学者のくせに」
「まぁええがな。ところで、さっき少年は飢えた子どもがいたらお菓子を分けるって言ったな?」
「うん」
「それはなんのためや?」
なんのため? 理由を聞かれると答えるのはむずかしい。
「うーん、かわいそうと思ったからだし、冷たい奴と思われたくないからでもあるかな」
「じゃあ、その子が大きくなって金持ちになったときに見返りをもらうためではないんか?」
「いやぁそんな風には考えないだろうけど・・・」
「どうやって証明する?」
「そう言われたら、ちょっとくらい期待していたような気もするなぁ」
「その理由って、いま俺に言われて思いついたやろ?」
「え?」
「俺が質問するまで、少年の中に理由なんて存在してたか?」
そう言われれば、いちいち理由なんて考えていなかった。子どもが飢えているなら、お菓子を与えたいと思った。それ以上でも以下でもない。
「わかったやろ。理由なんて曖昧で、適当で、後付けなんや。『真の理由』なんか、言ったもん勝ちやねん」
「なるほどね。で、それが中二病の話とどう関係があるの?」
「俺はな、なんでもかんでも金を『真の理由』だと認定する考えを中二病と呼ぶわけや。それに対して、アンチワーク哲学は行為の理由を別の角度から説明する」
「別の角度?」
「そう。『人間はなぜ行為するのか?』という問題についてもっと根本的な説明をするんや」
「なにそれ? いま『理由なんてない』ってニケが言ったばっかりじゃん」
「まぁ焦るな。哲学っていうのは結論を急がずに、一歩一歩積み上げていくもんやねん。まず、考えなあかんのは・・・そもそも行為ってなんやと思う?」
「行為・・・」
知っているつもりだけれど、言われてみれば説明がむずかしい。
「まぁ、考えたこともないやろから、さっさと進めるで。行為とは『変化を起こすこと』や。人間は変化を起こすことを欲望するんや」
トイレに行くと決めたのは?
どうやら、哲学っぽい抽象的な話題に突入したらしい。ちょっと休憩したい気持ちもあるけれど、頑張ってニケについていってみよう。
「行為とは、変化?」
「そう。考えてみ? なんの変化ももたらさない行為なんかあるか?」
「それは・・・あるんじゃないの? 僕が瞬きしてもなにも変化しないよ?」
「少年が瞬きしたらまぶたが動くやろ?」
「あ、そうか。じゃあ呼吸は?」
「呼吸すれば息が出てくるやろ?」
「んー、じゃあ頭の中でなにかを妄想するとか?」
「ほう、なにを妄想するんや少年は?」
「別に、関係ないでしょ」
「まぁそれを行為と呼ぶかは微妙なところやけど、それでも頭の中でイメージが湧き上がって変化していくやろ」
「たしかにそうだね」
「逆に言えばな、人間以外・・・正確に言えば生物以外の物質は、なんの変化も起こさへん」
「どういうこと? 石は転がるし、雲は動いているよ」
「それは単に物理法則に則って反応してるだけや。石が自発的に行為して結果を変えることはできへんやろ? 反応と行為は別もんや」
反応と行為は別。ニケは哲学者っぽく話すが、簡単に納得はできない。
「それを言うなら人間も反応してるだけじゃない? 僕がなにかをするとしても、それは周りに影響を受けてやっているわけで、完全な僕の意志ではないよね」
「でもな、影響を受けてるからといって百パーセント決定されてるとは限らんやろ」
「どういうこと?」
「一パーセントでも周りから影響を受けたら、意志がないことになるんか?」
「それは・・・」
「そもそもなんの影響も受けずに自分の意志だけで行動できるんやとすれば、それは神様かなんかや。人間は地球の上で重力を受けてるし、生まれた親からの影響は避けられへん」
「じゃあやっぱり、ぜんぶはじめから決定されてるんじゃ・・・」
「その立場は、いわゆる決定論ってやつやな。まぁ俺の経験上、決定論は正しいと思う」
「経験上?」
「でもな、アンチワーク哲学では『決定されてるか? されてないか?』という議論に深入りはせん。あくまで人間が『決定されてない』って感じていることに注目するんや」
「どういうこと? 決定論を信じる人は、決定されてるって感じてるんじゃないの?」
「決定論を信じる人もトイレ行くやろ?」
「そりゃあ、行くんじゃないの」
「なんでや?」
「なんでって・・・行かないと漏らすからじゃない?」
「せや。トイレに行かなかったら漏らすけど、行ったら漏らさずに済む。決定論者は、その二つの選択肢を前にしてトイレに行くことを選択しているわけや。決定されてると思ってたら、こんなことはせんやろ?」
複雑な話で頭がこんがらがってきたので、僕は少し間を置いて考えなおしてみた。人間はトイレに行くことを選択している。本当にそうだろうか?
「でもさ、気づいていないだけで『トイレに行こうと選択すること』も事前に決定されていたのかもしれないよ」
「仮にそうやとしても、決定論者がトイレに行くと決めたときは、『自分がトイレに行くと決めた』と感じてることは疑いようがないやろ」
「それは・・・そうだね」
「議論の場では決定論を振りかざす頭のカタイ哲学者も、普段の生活で決定論を信じて生きているわけやない。人間は自分の意志でなんらかの変化を起こしていると感じながら生きているわけや」
あれもこれも欲望
行為とは自分の意志で変化を起こすこと。仮にすべて事前に決定されているのだとしても、少なくとも本人は「自分の意志で変化を起こした」と感じている。ここまでは理解できた。でも、この話が「ベーシックインカムが配られても人が働くのか?」という僕の質問とどう関係するのだろうか?
「『それがどんな関係があるの?』って顔しとるな」
バレた。ニケはまるで少し先の未来を見ているようだ。
「うん」
「まぁ焦るなや。アンチワーク哲学では行為とは『自分の意志で変化を引き起こすこと』と定義する。で、意志とは欲望とも言い換えられる。貢献欲は欲望の一つや」
「貢献も変化を引き起こすの?」
「そう。人に貢献することも変化を起こすやろ。ご飯をつくってあげれば、相手はお腹がいっぱいになるし、喜ぶ。それに、自分のことを好きになってくれるかも知らん」
「たしかにそうだね」
「逆に食べることもお腹が膨らみ、満腹感を味わうという変化が起きる。それは食欲と呼ばれる欲望が突き動かしてるわけや」
つまり、行為とは自分の欲望で変化を起こすこと。むずかしいが、ここまでは理解できた・・・気がする。
「で、欲望は大きいものから小さいものまでさまざまや。パンツが食い込んでるからなおしたいと思うのも欲望やし、パンを食べたい気持ちも欲望、第二次世界大戦を引き起こしたい気持ちも欲望やな」
第二次世界大戦を引き起こしたい人って、そんな人いるのだろうか?
「つまり、欲望の種類は人間の行動の種類だけ存在するってことや。人間はパンツをなおすし、パンを食べるし、第二次世界大戦を引き起こす。ここで言いたいことは、それを引き起こしているのは食欲や睡眠欲、金銭欲といった限られた欲望だけではなく、『パンツをなおす欲』『第二次世界大戦を引き起こす欲』みたいな多様な欲望があるってことや」
「でも、食欲は存在しないって最初に言ったよね?」
「せや。現実に存在するわけではない。でも、存在すると仮定して考えると便利っちゅうことや。虚数って聞いたことあるか?」
キョスウ? 初耳だ。
「えーっと」
「まぁええ。高校の数学で習うから、そのときに思い出せ。つまり、実際には存在しないけど、思考の過程において存在すると仮定した方が都合のいい概念っていうのはある」
「そういうものなの?」
「まぁこの辺は余談や。とにかく人間は多種多様な欲望を持つ。ここまではええな?」
「うん」
「人は食べることを欲望するし、誰かに料理を振る舞うことも欲望する。それぞれの欲望は事実として平等に観察すべきなんや」
「どういうこと?」
「食欲や性欲、睡眠欲、あるいは名誉欲や金銭欲という言葉はすでに存在する。でも、貢献欲という言葉は存在していない。だから、あたかも名前のついた欲望だけが真の欲望であって、それ以外を人が欲する場合は『真の欲望』を取り繕っているだけかのような印象を与えてしまう。だから中二病的な勘違いが蔓延してるんやけど、これは宗教みたいなもんや」
「どういうこと? 貢献欲の方が、宗教っぽいけど?」
「逆や。あらゆる行動の理由を欲望だと解釈するのは、事実を平等に評価しているやろ? でもあらゆる行動の原因を食欲や金銭欲みたいなもので説明しようとするのは、『すべては神の御業』って説明するのと同じちゃうか?」
言われてみれば、そうかもしれない。
「でも人間は食欲の方が大きいのは事実じゃない? だからお金を配られたら食べる人ばっかりで、つくる人がいなくなる」
そういえば最初の方にもこんな話をした気がする。話題がループしているようだ。
「じゃあこう考えてみたらどうや? 少年はお正月に孫がやってくるのを楽しみにしているおばあちゃんやとしよう」
「また『たとえば』の話?」
「ええから聞いてくれや。ほんでな、おばあちゃんは孫のためにおせち料理を用意するとしよう」
「うん」
「でも孫がやってきて『僕はお腹が空いてないからおばあちゃんがぜんぶ食べなよ』って言ったらどう思う?」
「そりゃあ・・・」
想像してみる。きっと、そんな状況以上に悲しい気持ちを抱くことはないだろう。
「悲しくなるかもね」
「せやろ。でも不思議とちゃうか? もし食欲の方が大きいんやったら、遠慮してくれる方が嬉しいはずや」
「でも、どうせ自分ひとりでは食べきれないじゃん?」
「せやろか? おせち料理やったら冷蔵庫に入れとけばしばらく日持ちするで? そうすれば次の日におばあちゃんはご飯をつくる手間をかけずに済む。でも『ラッキー』だなんて思わんやろ?」
「そうかもしれないけど、それは自分の孫だからであって、おばあちゃんだって誰にでも料理をつくるわけじゃないし・・・」
「ほな、はじめてやってきた見ず知らずのお客さんでもええわ。お客さんに料理を振る舞って一緒に食べるか、自分の分だけつくって自分だけ食べるか、どっちが満足感あるやろか?」
「それは・・・」
たしかに、一緒にご飯を食べる方が楽しいだろうなぁ。
「おばあちゃんだけやない。三歳くらいの子どもと暮らしてみたらわかるけどな、あいつら『なに食って生きてるんや?』と思うくらい、ぜんぜん飯食わへんくせに拙い手つきで料理を手伝おうとするねん」
「へぇ」
「これも子どもが貢献欲を持っている証拠や」
「それって料理に興味があるだけであって、貢献欲とは関係ないんじゃない?」
「言ったやろ、真の理由を考えるだけ無駄やって。料理を手伝うという行為そのものは、誰かに対する貢献や。なら、人が貢献につながる行為を欲しているという事実は疑いようがないやろ?」
「だとしても、子どもは失敗してばかりで、ぜんぜん役に立たないんじゃないの?」
「まぁその通りや。でもな、だからといって、欲望は嘘にならん。ご飯を食べ損ねたからといって食欲がないことにはならんのと同じや」
たしかにその通りだ。ニケはいつだって流れるように説明する。
「もちろん、人間の欲望の対象は状況によって変わる。戦時中みたいに食べ物がないときは、みんな我先にと食べ物に群がって、他人に分け与える余裕なんかなかったはずや」
歴史の授業の一環で、百歳を超えたお年寄りにそんな話を聞いたことがある。食べるものがなくて大変だったって。いまはたくさん食べ物があるけど、戦争のことを忘れずに大切に食べないとダメだとかなんとか言われたっけ。
「で、要するにな・・・」
「要するに?」
「人はありとあらゆる欲望を持つわけや。それやのに食欲や性欲や睡眠欲みたいに名前のついている欲望ばかりが注目されるのはおかしいってことや。食欲なんかたいしたことないねん」
永遠にレベル1の人生
「人間が貢献を欲望することがあるのは認めるよ。でも、お金によって命令されないと、誰も責任感をもって貢献しないんじゃないの? 実際、ボランティア活動に積極的に取り組む人なんて少ないわけだし。もし労働がなくなったら、子どもが遊び半分で手伝うみたいに貢献するだけで、すぐに飽きちゃうんじゃないの?」
「まぁその可能性はある。職場には八時間縛りつけられてるからクオリティの高い仕事ができるけど、休日のボランティアでは大した成果を得られへん・・・なんてことは、この社会では頻繁に起きてるやろな」
「ほら、やっぱり労働が必要なんじゃ・・・」
「でも、逆に考えることもできるはずや。いま労働に忙殺されてるから、ほかのことに責任感を持って取り組めていないだけとな」
「どういうこと?」
「たとえば編み物に責任感を持って取り組もうにも、夜遅くまでやってたら明日の労働に支障をきたす。だから途中で切り上げなあかんよな?」
編み物なんてやったことないけれど、もしそんな状況なら「明日も学校なんだから早く寝なさい」とお母さんに怒られそうだ。
「その結果、途中で投げ出しているだけという可能性はないか? もし労働がなくなったら、自分が重要やと感じるプロジェクトに責任感を持って取り組む可能性が高まるとは思わんか?」
「そういうものかな?」
「実際、労働に時間を奪われていてもなお、趣味に向ける人間のエネルギーってすごいやろ。土日しか時間がないのにプロ顔負けの料理をつくるワーキングマザーもおるし、超絶技巧を持ったアマチュアギタリストもおる。最近は趣味をYouTubeで披露して金儲けする人も増えてきたけど、ごく一部や。多くの人は一円の得にもならんのに短い土日で職人技を磨いとる」
たしかに、すごい人はすごい。
「さて、アンチワーク哲学は、この現象を説明することができる。単に『ふーん、人間はよくわからないことにも熱中するんだねぇ・・・』と傍観するだけではない、深淵な哲学なんやで」
ニケは自分がバカにされても笑っているくせに、たまにこうした自慢話を挟む。プライドが低いのか、高いのか。
「アンチワーク哲学がすごいのはわかったよ。じゃあ早く教えてくれる?」
「順を追って説明するで。人間の欲望は変化を起こすことを求めるって話をしたやろ。そして人間は、変化させる能力を増大させたがるねん」
「どういうこと?」
「赤ちゃんがなぜハイハイを習得するかわかるか?」
赤ちゃんがハイハイする理由? それは「そういうものだから」としか考えたことはない。と言うよりも、考えようとしたことすらない。
「どうだろう。わからない」
「不思議やと思わんか? 別に寝転がって泣き喚いていたらママがおっぱいをくれるし、温かいベッドで眠ることができる。わざわざハイハイする必要はないと思わんか?」
「でも、それじゃ退屈なんじゃない?」
「そう。退屈なんや。人間は退屈を紛らわさないと生きていけない。なら、人間はどうやって退屈を紛らわす?」
「それは・・・行為?」
「せや。でも、行為やったらなんでもええわけやない。赤ちゃんも、手足をばたつかせるという行為なら、生まれた瞬間からできる。はじめは自分の意志で手足が動かせるという変化を見て楽しんでいるもんや」
「へぇ。赤ちゃんを育てたことがないから知らないけど、そんなことで楽しめるなら羨ましいね」
「でもな、ずっとやってたら、手足がばたつくというだけの変化に飽きる。だから次はハイハイをして、自分が手足を特定の方法で動かせば、スムーズに視界が変化していくという現象を発見する。これは赤ちゃんからすれば天にも昇る快感やろなぁ」
「快感・・・?」
はじめてハイハイをしたときのことなんて当然覚えていないけど、少し想像してみる。ずっと天井を見つめていただけの暮らしだったのに、突然、自分の意志でどこにでも行けるようになる。きっと、薄暗い監獄の中から自由の荒野へと抜け出したような感覚なのだろう。
「でもな、それもすぐに飽きる。次はボールを投げたらボールが飛んでいくという変化を見てきゃきゃって笑いはじめる。で、また飽きる。次は立って歩いて、走る。そうすると、またハイハイとは異なる視点の変化を引き起こして楽しむことができる。そのうち道具を使うことを覚える。三輪車に乗ったり、自転車に乗ったり。大人になればバイクに乗ったり、車に乗ったりすることで可能な変化を増やしていく」
「大人になっても、そのプロセスは続いてるんだね」
「そうや。スコップで穴を掘るのも、包丁で魚を三枚におろすのも、ゴルフに夢中になるのも、自分の意志で変化を起こすことが目的や。人は身体や道具の使い方を学んで影響力を拡大させていく。大人もそれに快感を覚えるわけや」
「大人も快感を覚えるの?」
「何歳になっても、できることが増えたら嬉しいやろ?」
そう言われれば、はじめて自転車に乗ったとき。連立方程式の解き方がわかったとき。ペン回しができたとき。興奮した気持ちを思い出した。
「たしかにそうだね」
「つまり人間は力への意志に突き動かされているわけや」
「力への意志?」
またニケはよくわからない単語を持ち出してきた。
「そう。アンチワーク哲学では、自分の意志で変化を起こす能力を増大させるエネルギーを、とある哲学者の言葉を拝借して力への意志と呼んでいる。まぁ別に覚えんでも構わん。テストじゃないんやからな」
「じゃあどうして言ったの?」
「定期的にカッコいい単語を出しとかんと、哲学者っぽくないやろ?」
また見栄を張る。やっぱり自意識過剰なんだろうか?
「でも、力への意志って言われても、なんだかわかりにくいよ」
「そうか・・・ほな成長欲はどうや?」
成長欲。まだそっちの方が分かりやすい気がする。
「まだ成長欲の方がマシかな」
「どっちでもええわ。まぁ要するにや、人間には力への意志があるから、永遠にレベル1のままダラダラ過ごすような人生を望むことはあり得ないっていうことや」
永遠にレベル1の人生。たしかにそれはひどく退屈そうだ。
「だから結局、人間はほっといてもなんらかのプロジェクトに取り組むし、スキルアップを志すもんや。家の中でアニメをダラダラ観てるだけの人生に満足できる人なんかおらんねん」
「でもさ。ニケは家でダラダラとアニメを観ているニートなんでしょ?」
「あほか。こうやって壮大な哲学体系を構築するという偉大なプロジェクトに邁進してるやろが」
「偉大って、自分で言うんだね」
「なんでも繰り返し言ってたら本当っぽく聞こえてくるもんやろ? ヒトラーもそんなこと言ってたで」
ヒトラーを根拠にされても説得力はない。というか、やっぱり倫理観が欠けているな、この男は。
「それにな、周りのニート友達にもそんな奴はほとんどおらんか、おったとしても精神的に参ってるケースが多い。逆に打ち込める趣味か仕事かを見つけたらイキイキしはじめるんや。ほんで自分が成長することに喜びを感じるようになる」
「それは、力への意志があるから?」
「そう。ニートってな。『毎日ダラダラ過ごせて羨ましいわぁ』的な嫌味をよく言われるねん。でも、レベル1のままなにもしないような生活は人間にとって羨ましくもなんともない。ということは・・・」
「ということは・・・?」
「ベーシックインカムを配ったらみんなダラダラ過ごすっていう発想は、明らかに間違ってる」
ニートは正義のレジスタンス
「みんながなにかに熱中することは理解したよ。でもそれが畑仕事や子どもの世話に向かうとは限らないんじゃない? 僕だったら好きなゲームを極めようとするし・・・」
「それはそれで素晴らしいことや」
「え?」
ゲームに熱中することが素晴らしい? いったいどういうことだろう?
「現代の労働の大半が無駄であって、やればやるだけ社会が損をするって話はしたな」
少し前の方の話を思い出す。クソみたいな広告や、保険の営業で疲弊する女性。捨てられる恵方巻き。
「そうだね」
「無駄な労働をするくらいなら、ゲームしている方が偉いやろ? 労働はやればやるだけ本人も周りも不幸になるんや。せめて本人だけでも楽しい方がええんちゃうか?」
言われてみればそうだ。本当に労働が無駄なのだとすれば、やらない方がマシだ。でも・・・
「ゲームしたければ好きなだけゲームすればええ。ほんで、人の役に立ちたくなったら役に立てばええ。どのみち人は役に立つことを望むんやから、社会なんか勝手に成立するわ」
そんなに簡単なのだろうか? というか、哲学者がそんなにテキトーでいいんだろうか?
「社会ってそんなに簡単に成立するの?」
「大丈夫や。そもそもな、『社会が成立する』ってどういうことか、考えたことあるか?」
「出たよ。ニケの『そもそも論』」
「ええから考えてみてくれや」
「えっと・・・まず第一にはみんなが生き延びることだよね。ご飯を食べられて、家があって、電気やガスや水道が使えて・・・」
「まぁそんなところやろな。でもな、現代人にとってご飯をつくることはほとんど娯楽みたいなもんや」
「どういうこと? 食べないと生きていけないよね?」
「完全にゼロにはできへん。でもな、そもそも現代は餓死する人より食い過ぎて死ぬ人の方が多い。道歩いてるおっさんもオバハンも、だいたい腹出てるし、ダイエット食品なんかバカみたいに売れてるやろ? つまり食わんでもええもんわざわざ食ってるってことや」
「まぁ、たしかにそうだね」
ダイエットに夢中になる親戚のおばさんたちの姿を思い浮かべながら、僕は返事をした。
「それにな、パンみたいなシンプルな食べ物でも必要以上の手間がかけられとる」
「どういうこと? パンなんて質素な食事の代表例だと思うけど」
「パンって麦をわざわざ脱穀して粉にして捏ねて発酵させて焼いてから食うやろ? 生き延びるためだけやったら、そんなことせんでも麦をお粥にして食ってもええはずやねん。でも、『生き延びるため』をはるかに超えた目的を持って、人間はパンをつくって食ってるわけや。その大部分は『楽しい』とか『嬉しい』とかそういう目的のためなんや」
「だったらなに? パンがつくられなくなってもお粥を食べて我慢しろってこと?」
「違う。もっと肩の力を抜けばええってことや。そもそも人間は『楽しい』とか『嬉しい』という気持ちのためにパンをつくってた。食べるときだけじゃなくて、つくる過程もきっと楽しかったはずや」
「パンをつくる過程が楽しかった?」
「せや。はじめてパンを発明した人は、苦しみながらパンを焼いてたと思うか?」
少し想像してみる。きっとその人は、夢中になって実験室にこもる科学者のように、その過程を楽しんでいただろう。決して『生き延びなければ・・・』などと焦燥感に駆り立てられていたわけではないはずだ。
「きっと楽しかっただろうね」
「やろ? 『生き延びる』とかそんなことは微塵も考えてなかったはずやで。もともとパンを焼くことも、パンを食べることも遊び半分やねん。それがいつの間にか、『生き延びるため』というネガティブな動機にすり替わってしまった。いまでもパンをつくるのはやらんでもええ遊び半分のものや。それやのに強制的な労働やと俺らは思い込んでるねん」
パンを焼くことは遊び半分? そんな風に考えたこともなかった。人間の人生はずっと昔から、ただ生き延びるために苦しい労働に埋め尽くされて、その隙間にわずかな余暇を許されているものだと思い込んでいた。
「アホらしいと思わんか? やってることは別にやらんでもええ娯楽やのに、それが『生き延びるため』となかんとか言って自分らを追い込んで、苦しんでるわけや。なら『生き延びるため』なんて考える必要はない。やってる本人が楽しいかどうかだけを考えるべきなんや」
「やってる本人が楽しいかどうか・・・?」
「そう。それだけを考えればええ。ほかの例も挙げよか。狩猟採集民の人らの狩猟って、得られるカロリーよりも、それで消費するカロリーの方が大きいケースが多いらしいわ」
「え? それってつまり?」
「徒労ってやつや。ただし、生き延びるためのカロリーを目的にするならの話やな」
「でも、彼らにとってカロリーは最優先事項じゃなかった?」
「彼らも気づいてたはずや。生きることだけを優先するなら、狩猟なんかやめて朝から晩まで小麦を育てた方がいいって。でも彼らにとってそれはつまらなかった。だから好きな狩猟に夢中になってたんや。彼らにとって好きなことをすることが最重要事項やったんや」
「好きなことをすることが、最重要事項?」
「せや。それで社会は成立するんや。だからな、さっきは広告や営業が悪かのように言うたけど、それが好きなことなら好きなだけやったらええねん」
「そうなの? でも無駄なんでしょ?」
「『こんなもの売りたくないなぁ』とか『こんな風に営業したら迷惑だろうなぁ』とか思いながら営業をするのはあほらしいけど『これをみんなに知って欲しい!』『これを必要な人に届けたい!』と思って誰かに伝える行為は、その人にとっての『好きなこと』なんちゃうか?」
たしかに、好きな漫画やゲームを誰かに教えてあげるのは楽しい。広告や営業もそんな気持ちで取り組むなら、きっと喜びに変わるだろう。それはもう「労働」ではなくなっているはずだ。
「『無駄か? 無駄じゃないか?』という基準で考えるなら、パンすらも無駄ってことになる。だからそんなことは考える必要はない。みんなが『好きなこと』をすれば楽しいし、ちょっとくらいの苦痛は快感に変わる。はじめに言ったやろ。『役に立つ』ってのがどういうことか」
冒頭の会話を思い出した。そういえば、僕を喜ばせたり、僕の苦しみを取り除いたりすることは役に立つことだって、ニケは言ったっけ。
「少年が嫌な労働をしないこと、労働をやめて好きなことをすることは、無条件にいいことなんや」
労働をやめて好きなことをするのはいいこと。なぜなら、僕が幸福になるから。同じようにみんなが労働をやめて好きなことをすれば、みんなが幸福になれる。社会も勝手に成り立つ。ニケはそう言う。
逆に大人たちはこう言う。好きなことを我慢して勉強し、労働しなければ社会は成り立たず、僕も幸福になれない。だから我慢しなさい、と。
僕はどちらを信じるべきだろうか。どちらを信じた方が楽しく生きられるだろうか?
「それにな、無批判で労働を続けるってことは、無駄な労働が存在する社会を許容することになるやろ?」
「え? そうなの?」
「それって正しい行いやと思うか? 本当に無駄なんやったら、未来の子どもたちには労働のない社会をプレゼントしたいとは思わんか?」
さっきニケは、昔は戦争が正義だったと話していたっけ。現代では労働は正義。でも、それが嘘だったなら? 戦争をなくすべきなのと同じように、労働もなくすべきなのだろうか?
「俺は言い切っていいと思う。労働は悪や」
「労働は悪・・・」
「いまとなれば戦争は悪や。でも戦時中は、戦争は正義やった。当時にもし『戦争をやめよう』と声をあげる人たちがたくさん現れていたら、日本に核爆弾が落とされへんかったかもしらん。だから『労働は正義』とされている現代でも、勇気を持って『労働は悪』と叫んだり、ニートのように労働を拒否したりすることは、きっと未来への有益な貢献になるはずや」
そんなことができるのだろうか? もしそんなことをすれば・・・
「でも、頑張って労働してる人に対して『労働は悪』なんて言ったら怒るんじゃない?」
「怒ると思う。でも、怒らせたらええねん」
「え?」
「たとえば俺が戦時中に戦争に反対していたとして、少年は『頑張って戦争してる兵隊さんが可哀想』って言うか?」
「それは・・・」
もしかしたら言うかもしれない。戦争が正義の時代だったなら。
「怒られようがなにしようが、言うべきことは言うべきや。社会を変えようとするなら、怒られるのは当たり前やねん」
【続き】
■書店様・小売店様のご注文はこちらから
■個人の方のご注文はこちらから
■小説の解説動画はこちら
■思いっきり応援したい人は出版プロジェクトに参加できます!
1回でもサポートしてくれれば「ホモ・ネーモはワシが育てた」って言っていいよ!
