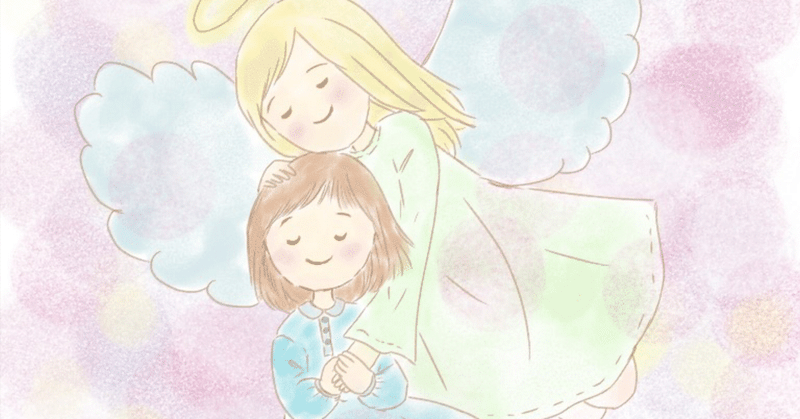
【追悼:山本弘さん】ぼくが世界でいちばん好きでいちばん嫌いな作家、山本弘とは何者だったのか。(第五回:完結編①)
第五回である。
こんなに続く追悼記事もあまりないかもしれないが、ここまで来たら最後まで書き切るより他にない。まだつきあってくれている少数の読者さんたちには最大の感謝を表します。
さて、前回は「人間の愚かさ」を極限まで追求し告発する平井和正が提唱した「平井のテーゼ」を山本弘がどのように継承していったのか、そしてそこに発生した欺瞞について簡単に記した。
『アイの物語』では、象徴的なことに理想的な存在としてのマシンたちがさまざまな「お説教」を展開してくれたわけだが、他の作品でも事情はあまり変わらない。
しかし、それでは、山本弘はありとあらゆる戦争すべてに対し反対するのかというと、そうではないだろう。
『サイバーナイト』では宇宙の傭兵たちの活躍をかなり肯定的に描いているし(かれらは敵対的な種族であるバーサーカーたちを種族ごと破滅に追い込んでしまう!)、「社会の秩序を乱す厄介者」は殺害もやむを得ないという立場に立つくらいだから、おそらく正義の戦争はあり、それは認められるべきであるという立場に立つはずだ。
かれが反対したのは「愚かな人間たちがひき起こす、愚かな戦争」であった。シリーズものの長編『翼を持つ少女』などを読むとわかるように、山本弘はだれよりもそのような戦争を憎んだが、一方でじっさいにどのように戦争は起こるか、平和を維持するためにはどうすれば良いのか、そのようなメカニズムについてはほとんど興味を抱いていた形跡がない。
いや、『サイバーナイト』の「四行原則」はそのような平和維持のメカニズムといえるかもしれない。しかし、じっさいには「最初の一撃で滅ぼされる」リスクを防ぐためには、有無をいわさず出逢ったあいてを滅ぼしてしまうという戦略だって有効なはずである。
だが、論理と倫理は一致しているべきだと考える山本さんにとってそれは決して認められない理屈なのであり、だからかれは認めなかったのだと考えられる。
ここで、中国のスーパーベストセラーSF作家劉慈欣の空前の傑作小説『三体』に登場する「黒暗森林理論」を思い出した方もいらっしゃるかもしれない。
山本弘とは無関係なネタバレになりかねないのでくわしい説明は省くが、「黒暗森林理論」とはまさに「暗い森のような宇宙の一角にかくれて出てきたあいてを滅ぼしてしまうことが最も有効な生存原則だ」といった理屈で、それこそ「四行原則」とはきわだった対照を成す。
ぼくはべつだん、そのどちらが正しいのかという話をしたいのではない。どちらも、あくまでサイエンス・フィクション小説におけるひとつのアイディアであるに過ぎず、真剣な学問的考察に耐えるものではない。そんなことはあたりまえだ。
しかし、ここで問題なのは山本弘が「黒暗森林理論」的な、いわば「非倫理的な」生存戦略を採用しようとはしなかったことである。
「平井のテーゼ」を突きつめるかれにとっては、どうしてもそういう「悪い」やりかたは、同時に「愚かな」ことでもなければならなかったのだ。
「悪い奴ほどたくさん稼いでよく眠る」、そういう理不尽な現実世界は、それこそ『アイの物語』でアイビスが語っているように、山本にとって「まちがえた世界」、「狂った世界」であった。
かれはその「正されるべき壊れた世界」を絶対に認めるわけにはいかず、そのために「四行原則」のようなロジックを考えだしたわけである。
山本弘が「論理の人」ではなく「論理を志す人」だということはこういうところにも表れているといって良いだろう。
たとえば、「悪魔」とか「人類より進化した生きもの」とまで呼ばれ、コンピューターや天気予報の基礎理論を創り出した人類史上屈指の天才数学者フォン・ノイマンは、生前、敵対するソ連に対する先制核攻撃を躊躇なく主張していたという。
山本さんが依拠する「ゲーム理論」の生みの親、世界で最も「論理的に」考えることができるスーパー・インテリジェンスのもち主は、まさに「論理的に」大量殺戮を正当化していたのである。このようなことが現実にはありえるわけだ。
ちなみに『サイバーナイト』と『三体』に、ハリウッドで映画化が決定したアメリカのSF小説『プロジェクト・ヘイル・メアリー』を加えた三作を比較してみると、日中米それぞれにおけるファースト・コンタクトの文化があぶり出されるようで、ちょっと面白い。だが、それはまたべつの話だ。
そう――山本弘が生涯をかけて戦ったあいては、「善人が報われない狂った世界」であり、「悪人を裁かない愚かな人間たち」であった。かれのすべての言動、行動、思想、哲学、それらは世界と人類を否定するところから始まっているのである。
かれにとってそれはまったく自明のことであり、疑う余地はなかったものと思われる。
わたしたちはその価値観に一理を認めなければならないだろう。たしかに、人類はいつまで経っても愚昧な行動をやめられないように見える。
ヒーローのように行動する人はごく少なく、また仮にいたとしてもそういう人が正当に報われる社会構造になっているとはいいがたい。
ぼくたちの世界にはいろいろな矛盾や難点がある。それはたしかだからだ。しかし、だからといって山本さんのように人間に絶望してしまうべきだろうか。
ぼくなどは、あるいは思想的に堕落しているのかもしれないが、「人間の「ダメ」なところもまたそれはそれで人間のひとつの個性じゃないか」と考える。
人間はエゴを持ち、それゆえに衝突し、争い合う。だが、絶対に争わない人間どうしの世界など、人間の世界とはいえないのではないか。
あの暗黒の名作『Fate/Zero』で衛宮切嗣が望んだような「全人類の恒久平和」とはしょせん叶わない夢だ。しかし、それはそれで良い。不完全でも、欠点だらけでも、醜くても愚かでも、人間はこんなにも愛おしい。「ぼくは」そう思う。
だが、山本さんはあくまで潔癖に人間を否定し人類を拒絶し、ある種、自己愛的な思想にひきこもった。作家山本弘の限界は、明確にここにある。
もちろん、現状の人類を超える知性を想定した人物はひとり山本弘だけではない。昔からたくさんのSF作家たちがそのような存在を描いて来てはいるし、たとえば『機動戦士ガンダム』の「ニュータイプ」などもそういったアイディアのひとつだといっても良いだろう。
人間は愚かで戦争をやめることはできない。しかし、ニュータイプには可能性がある。富野由悠季はそういうふうに思考を発展させるわけだ。
とはいえ、富野さんはあくまでニュータイプを「可能性の萌芽」として描いただけで、ニュータイプによる理想社会を描き出すことはしなかった。あるいはできなかった。
『機動戦士ガンダム』は紛れもない大名作だが、「平井のテーゼ」に対するアンサーとしては未完である。
否、あるいは未完だからこそ『アイの物語』のような矛盾を見せることなく名作として終わることができたのだというほうが正しいかもしれない。『ガンダム』が予定通りに完結していたら果たしていま以上の名作になったかどうかは怪しいところだ。
ところで、またも余談となるが、山本弘と同時代を生きた田中芳樹という作家は一見すると左翼思想の権化のように見えながら、この種の陥穽に嵌まってはいないように見える。
かれは何千年後も変わることなく銀河で戦争を続ける人間たちを描き、その愚かしさを嘆きながら、SF的な超人類や超知性を構想することはなかった。
田中さんには「いつまでも戦争をやめられない愚かな人間たち」に対する優しい許容の視点があるように、ぼくには思える。田中芳樹は「戦争をやめられない人間には存在意義がない」というふうには考えなかったのだ。
いい換えるなら、田中芳樹の人間や戦争に対する解像度は山本弘よりかなり高い。
「平井のテーゼ」と同じ問題を追求する『機動戦士Ζガンダム』がアニメ史上に残る無惨なバッドエンドを迎え、ストーリーテリングの袋小路を示したたのに対し、田中芳樹の『銀河英雄伝説』が綺麗に完結することができたのは、そのような事情に拠るのではないかと考える。
が、それも横道。とにかく、山本弘の戦争に対する解像度はきわめて低いものといわざるを得ない。なぜ戦争が起こるのか? なぜ公害が続くのか? なぜ差別がなくならないのか? これらすべてのクエスチョンに対するアンサーは、平井和正的、あるいは山本弘的な価値観では「人間が愚かだから」で終わってしまう。
「平井のテーゼ」は「戦争をやめられない」人間たちに対し「そんなに戦争がすきなのか?」と問うているわけだが、現実には必ずしも人間は「すきだから」戦争を起こすわけではないだろう。
だれも望まなくても戦争になることはありえる。たとえば第一次世界大戦は関係各国のすべてが開戦を望んでいなかったにもかかわらず起こってしまったというのは良く聞く話だ。
もちろん、だからといってその責任を逃れられるわけではないこともたしかだが、戦争には「戦争をすきでやめられない愚かな人間たちがひき起こしているのだ」といった単純な説明では解き明かし切れない複雑な要因があるものと考えなければならない。
さまざまな戦争を「人間の本質的な愚かさ」に起因するものとして「抽象的に」捉えるかぎり、「平井のテーゼ」は決して解けない。
そうではなく、戦争が起こることにはそのたびごとに異なる理由があって、それらを「具体的に」解決することによってしか平和は訪れないと考えなければならないのだ。
「人間は愚かだ!」というさけびは一見すると人間の愚かしさを超越した神の視点から人類を見落としているように見えるかもしれないが、じっさいにはそれもまたきわめて人間的な価値観であるに過ぎない。
もし、ほんとうにエイリアンがいるとすれば人間のありように対し情緒的な反感など覚えないことだろう。結局のところ、人間のありさまに最も嫌悪を感じるのはその人もまた人間的な人物だからであるに過ぎないのである。
その意味では、山本弘はとても人間らしい人物だったということもできるだろう。もちろん、純粋に良い意味だけではないかもしれないにせよ。
さて、ここまでは『アイの物語』を中心に長々と山本弘の作品について語ってきた。しかし、山本さんにはもちろん他にも多くの作品がある。
特に山本さんが『アイの物語』と並べて「平井のテーゼ」への答えだと語っている『神は沈黙せず』についてはふれないわけにはいかないだろう。
この小説のテーマは「神」であり、また「宗教」ないし「信仰」である。しかしながら、無神論者を自認する山本弘は、いたって当然ながら素朴に「神」を賛美することはできない。
かれはかれなりのやりかたで「神という最大の謎」にアプローチしていく。膨大な情報と発想が費やされ、ふたりの天才による議論が最後にはたったひとつの謎へとすべてが収斂する展開は、一本のエンターテインメントとして破格に面白い。
ぼくが個人的にこれこそ山本弘の最高傑作と考える由縁であるが、この作品も『アイの物語』と同じく、まさにそうだからこそ山本さんの思想が、あるいはかれの「信仰」がダイレクトに出ているところがある。
信仰。
山本弘はたしかに無神論者である。そしてすべてを疑う懐疑主義者を自認してもいた。だが、その考え方はときとしてただの「信仰」の形にしかなっていないよう思われることもあった。
それは、下記の記事でこのように書かれている通りだ。
ラエリアン・ムーブメントという無神論を唱える団体があるが、その主張は「高度に進歩した宇宙人が人類を創造しユートピアを確立する」というものだ。これを「神を信じてないから宗教じゃないね!」と思う人間はいないだろうが、『アイの物語』は「宇宙人」ではなく「AI」を神と同一視しているだけだ。
冒頭にも書いたように山本弘は無神論者を名乗っていた。だが結局「本当の意味で」信仰を捨てることはできず、それは本人自身が言ってるように自覚できないものだったのだろう。
たしかに、そうなのかもしれない。もちろん、『アイの物語』はフィクションであり、山本弘がほんとうに人工知能が人類を善導する未来を信じていたわけではない。だが、ここまで長々と書いてきたことを懸案すると、山本さんにはたしかにAIに対し幻想があったように感じられる一面がある。
かれはAIに人類には託せない未来を託した。それがかれが「平井のテーゼ」の向こう側へ行こうとする精一杯の方法であった。
ただ、これは注意しなければならないポイントだが、山本弘の描くAIはその作品ごとで違っている。
『サイバーナイト』シリーズでは最終的に銀河最高の超知性へと進歩するより「人間的な」AIが出て来るし、『去年はいい年になるだろう』のAIはある意味で『アイの物語』とは真逆の「人を幸福にしたい」という思いに呪縛された存在だ。『地球移動作戦』のAIに至っては間接的な形ながら殺人まで犯す。
だから、山本さんがあくまでAIを一様に捉えていたとは決していえない。まして「信仰」していたというと語弊があるだろう。
だが、「平井のテーゼ」を素朴かつ盲目的に受け止め、「人間は愚かだ。しかし――」というテーマをくり返し描いた姿を見ていると、まさに「信仰」という言葉がぴったり来ることもたしかだ。
上記のリンク先の記事ではその「信仰」を「自覚できないもの」としているが、じつは合理主義者を自認する一方で山本さんはかなり自覚的にかれが考える「善」を「信仰」していた、『アイの物語』におけるAIはその体現者であった、そういったほうが適切であるようにも思える。
そのことは『神は沈黙せず』の結末を読むとよくわかる。この作品には、全宇宙を創造した「神」が出て来る。
もちろん、各宗教で信じられているような超越的な存在ではない。その正体は、コンピューター・シミュレーションで仮想世界としてのこの宇宙(じっさいには数光年しか存在しない)を生み出した別宇宙の異星人だ。
この世界ではその「神」の正体を巡って大混乱が起こるのだが、主人公があくまで彼女が信じる「正しい生き方」を「信仰」することを宣言して、この物語は終わる。
山本弘は実際には本に収録されなかった「あとがき」で、物語世界の「神」として、物語のなかの「悪役」に制裁を下したことを告白している。
かれは物語作家として、あるキャラクターを「ひいき」して、まったくのご都合主義的に殺害したのだ。その理由とは、「悪は裁かれなければならない」というものである。
この作品世界内の法則からすれば、加古沢が死なねばならない必然性など何もない。しかし、彼が超自然的な手段によって殺されることは、最初からの構想であり、その点に疑問を抱いたことなどない。
なぜなら、彼は人間世界の法ではなく、神の手によって罰せられなくてはならなかったからだ。
作者はどのような世界を創造することも許される。しかし、ひとたび創造した世界の法則には、作者さえも従わねばならない。それは創作上のルールである。僕はクライマックスで、あえてそのルールを破った。世界の真の神としての特権を行使し、加古沢に御都合主義的な最期を遂げさせることで、彼に罰を与えた。
僕は悪役としての加古沢に愛着を抱いていた。同時に、彼がのうのうと生き延びることは絶対許せなかった。現実世界では、悪が罰せられないことがあまりにも多い。しかし、せめて自分の創造した世界の中だけは、悪が滅び、主人公の苦闘が報われるものにしたかった。この世界ではどうだろうと、フィクションの世界では、神は正義を行なうべきであると。
(『出エジプト記』において、神がエジプト王の心を操りながら、同時にエジプト人に罰を与えたことも、神とは作者のことだと考えれば矛盾はない。現代の小説においても、作者は悪を操りつつ、悪を許さないものである)
もちろん、加古沢を滅ぼす自然な手段は他にもあった。たえば優歌に彼を殺させることもできた。しかし、それは正しくない、と僕は感じた。それではプロットとしては筋が通っていても、何かが決定的に間違っている。そこには「真の神」が介在する余地がない。
だから、作家としてのタブーを破り、加古沢には自ら手を下すべきであると決心した。
おそらく『ヨブ記』の作者も、同じ心境であの結末を書いたのではあるまいか。物語としての構成を破ってでも、最後の最後で、作品世界の真の創造主として、それまでの物語を否定し、「正しい神の在り方」を示したかったのではあるまいか。ラストで一転してヨブに報酬を与え、エリファズたちを非難した神こそ、それまで嵐の中でわめいていた傲慢な存在とは異なる、憐れみ深い真の神――作者自身なのではあるまいか。
これこそが、「正義を志す作家」として、あるいは「差別主義者」としての山本弘の本質である。
かれは人間を「善人」と「悪人」に分け、それぞれに応報をあたえた。善人は報われて幸せになり、悪人は裁かれて滅び去る。
山本の小説は、そういう意味で、子供向けのお伽噺と何ら変わらない。「悪人は神さまのバチがあたって死んでしまいました。めでたしめでたし」。
じっさい、かれの小説の登場人物たちは、少なくともその一面ではきわめて素朴で単純だ。たしかに「善」と「悪」のあいだで揺らぐことはあるが、ヒーローは常に「善」に立ち戻り、ヴィランは最終的に「悪」に留まることが大半である。
だから『アイの物語』が「平井のテーゼ」にのとっとって山本さんにとっての「現実」を描いた作品だとすれば、『神は沈黙せず』はかれの「理想」を綴ってヒーローを描いているといって良いだろう。
山本さんにとって、小説とは、世界の不条理を描くものであるべきではない。あくまで「善」が勝利し、「悪」が敗れ去る、そういう構造でなければならないのだ。
どこまでも勧善懲悪の、「本来あるべき正しい世界」を素直に描くこと――それがかれにとっての「正しい物語」であった。
かれはそのような意味で「神」が存在しない近代文学をまったく好まなかった。それは単にこの「狂った世界」を追従しているに過ぎないということなのだろう。
それでは、我々は『神は沈黙せず』における「神の介入」をどう捉えるべきだろう。唾棄すべきご都合主義。そう見ることもできる。だが、わたしはそれよりもさらに問題含みであるように考える。
山本さんは「物語世界の神」として物語世界に介入することを躊躇せず、それを「正しいこと」として捉えていた。かれは「神」の立場から、いってしまえば「悪人」に対し「天罰」を下しているのだ。
これは『神は沈黙せず』の世界もまた「正義が正義である世界」――ほんとうならこの世界もまたそうであるべきだと山本さんが考えている、「正しい世界」であることを意味する。
しかし、見方を変えればこれはあまりにもひどい話である。この世界では、「悪」とみなされた登場人物はどんなに必死にがんばってもムダなのだ。その物語世界の外に立つ「神さま」が勝手に善悪をジャッジして「天罰」をあたえてくるのだから。
いってしまえば、「正義が正義である世界」とは、登場人物が自ら「何が正義であるのか」判断し、行動するその権利が奪われた世界である。
この世界における善悪は「世界の外」で「神」によって決定されており、登場人物はそれに逆らうことはできない。ここには何の自由意志もない。
いってしまえば『神は沈黙せず』は通常の意味での「信仰」を否定し、ただ「自分のなかの善意にしたがって正しく生きること」を主題としているにもかかわらず、結局はただの宗教小説と化しているのである。
もちろん、それが作者の意図したところなのだからそういうものとして読むべきなのであろう。それならそれでかまわない。だが、「ほんとうにそれで良いのだろうか?」という疑問はどうしても捨て切れない。
いずれにせよ、このくだりを読むとわかることがひとつある。それは、山本弘が神の存在を信じず、戦乱や貧困が打ち続くこの世界のありようを否定的に捉えていた一方で、「善なる神」、つまりは「憐れみ深い真の神」は存在していてしかるべきだと考えていたことである。
かれはそのような神が世界をコントロールすることを問題だとは受け止めていなかった。その意味で、山本弘とはただ人間的であるのみならず、とても宗教的な人物であったといっても良いだろう。
このことを踏まえると、ぼくはどうしても栗本薫『グイン・サーガ』の一節を思い出してしまう。
それは、物語の主人公のひとりイシュトヴァーンの軍師であるアリストートスが何の罪もない純真無垢な少年リーロを暴行し、殺害しておきながら、その自分の罪について白を切る場面だ。かれはイシュトヴァーンのまえで神々にかけて自分の無罪を誓約してみせる。
「神々も照覧あれ。私はその少年の失踪については何ひとつ心あたることはない。これはすべての神々と私の名誉にかけて誓うことなのだ。かりそめのことではない」
天が裂け、地がまっぷたつに割れてかれのみにくいからだを飲み込むことも起こりはしなかった。
また、うらみをのんだ血まみれの小さな亡霊があらわれて、血だらけの指で誰かを指差してみせるようなことも。
さんさんと陽光は床にふりそそぎ、アリの青ざめた醜い顔を照していたが――神々の怒りのいかづちがとどろいて世界を闇にとざすこともなく、また空にあらわれた炎の指が宿命の宣託を告げる文字を昏い空に描いてみせることもなかった。
ただ、人々がしんとなって、この情景を見つめていただけのことであった。
ようするにただ「何も起こらなかった」というだけのことなのだが、『グイン・サーガ』、あるいは栗本さんの小説を語るとき、きわめて重要なポイントがここに端的にあらわれている。
それは、栗本薫はここで「神」として物語世界に介入することを良しとしなかったということである。
いい換えるなら、『グイン・サーガ』の世界には、ヤヌスやドールといったひとりのキャラクターとしての神々は存在するかもしれないにしても、『神は沈黙せず』にいるような意味での「物語世界の外部の神」は存在しない、少なくとも物語に直接に関わる意思を持っていないということなのだ。
『グイン・サーガ』の世界においてはさまざまな悲惨がはびこっていて、ありとあらゆる形の悲劇が起こるが、たとえ悪漢がまったく罪のないイノセントな子供を虐殺したとしても、怒りのいかづちをとどろかせて世界を闇にとざすこともなく、炎の指を空に描いて宿命の宣託を告げることもしない。
『グイン・サーガ』はジャンルとしてはヒロイック・ファンタジーに属する小説だといって良いだろうが、このポイントをもって、完全に「ファンタジー」ではなくなっているということができる。
一切の「神」を存在させないことで、この小説はある種の「リアリズム」へと舵を切ったのだ。あるいは、そもそも栗本薫はその一見の印象とはまったく異なり、徹底した現実主義の作家なのである。
ただ、そうはいっても初期作品ではたしかにそこに一種の「ファンタジー」を見て取ることができた。それが後期へ行くにしたがっていわば「剥き出しの現実」が露出するようになる。
その結果として「ファンタジー」としての魅力を喪失した一面はあるだろう。ある物語がどこまでリアリズムを徹底するべきか、あるいはファンタジーに留まるべきかはここで簡単に結論を出せる問題ではなく、『グイン・サーガ』と『神は沈黙せず』のどちらが正しいといえることではない。
おそらく、いずれも極端なサンプルというべきなのだろう。あるべきバランスは両者の間のどこかにあるのかもしれない。ただ、思うに、ここで栗本さんが取っている態度は、ある種、「平等」ではある。
『グイン・サーガ』においては、一見すると「あらゆる個性が平等である」といった描写はなされていない。倫理においても能力においても、そして容姿においても各登場人物の格差は激しい。その世界にはありとあらゆるタイプの差別がある。
しかし、だからといってかれらの行動は自分の選択と運命以外の何ものにも裁かれはしない。ここでは「神は沈黙している」のである。
ここであまり栗本薫の小説について踏み込む余裕はないが、彼女の書くものはSFからミステリ、同性愛ものに至るまで、その表面的な荒唐無稽さとはうらはらに徹底して「現実を直視する」ことをめざしている、とぼくは捉えている。
生前、山本弘はさまざまに栗本薫を批判していたが、それはよくわかる話なのだ。このふたりにはどこか似ているところがある。
端的にいえば、山本さんと栗本さんの文学は、おそらくほとんど同じところ、つまり「この狂った世界は何なのか?」という地点からスタートしている。
ぼくは栗本薫もまた、彼女なりに「正しい世界」を突きつめたのだと考えている。ただし、それは山本弘が構想したような「正義が正義である世界」ではなく、まったく真逆の「正義がどうしても正義ではありえない世界」だった。
山本さんがこの世界を、現実のありかたを否定し、「もっとまともな世界」を求めたのに対し、栗本さんは正反対に世界の不条理なありかたそのものをさらに突きつめようとしたといえば伝わるだろうか。
面白いことに栗本さんもまた平井和正のファンで、かれに関する批評を残している。そういった方向性からもこのふたりを語ることができそうだが、それはひとまずは措いておくことにしよう。
ただ、この「信仰」と「神の沈黙」の問題については、また後で語ることとして、とりあえずここで第五回を終えよう。まだ続きます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
