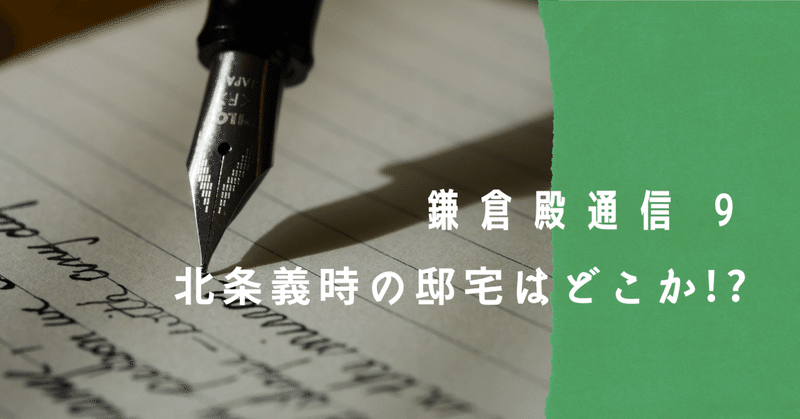
【鎌倉殿通信・第9回】北条義時の邸宅はどこか!?
鎌倉の有力な御家人は、一族で複数の屋敷を持っていました。鎌倉幕府の歴史書『吾妻鏡』を見ると、北条義時の邸宅も複数あったことが分かります。
一つ目は、建保元年(1213)に起こった和田合戦の記述に登場する「小町上」の邸宅です。この邸宅は、現在宝戒寺が建つ場所にあったと考えられているので、仮に「宝戒寺小町亭」と呼ぶことにしましょう。ここは義時の弟・時房の所有となった後、五代執権・時頼の邸宅となりました。その後、北条氏の嫡流・得宗家に伝領され、鎌倉幕府滅亡の際は高時の邸宅となっていました。宝戒寺は高時の菩提を弔うため、その跡地に建立された寺院です。宝戒寺小町亭の向かいには、義時の息子・泰時の「小町西北」の邸宅がありました。ここも、代々北条氏の邸宅として受け継がれていきます。
二つ目は、父・時政から受け継いだ「名越の邸宅」です。建久三年(1192)7月、北条政子はここで千幡(後の3代鎌倉殿・源実朝)を産んでいます。時政の後は義時に相伝されたようで、建永元年(1206)2月には、義時の名越の山荘で実朝の和歌会が催されています。この名越の邸宅は、長らく釈迦堂口切通の南東に位置する平場(大町釈迦堂口遺跡)がその旧跡ではないかと伝承されてきました。しかし平成二〇年の発掘調査では、時政や義時が活躍した頃の遺構は見つかりませんでした。そのため名越の邸宅は、材木座の谷戸・弁谷にあったとする説も出てきています。
三つ目が「大倉亭」と呼ばれる邸宅です。実朝の死後、京都の九条家から三寅(後の第四代鎌倉殿・九条頼経)を迎えるにあたり、この邸宅の南に御所が新造されました。義時は自らの邸宅と御所を隣接させることで、幕府内の地位を確固たるものとしました。
大倉亭は義時の立場を考える上でも非常に重要な邸宅ですが、いまだに場所が特定されていません。有力なのは、①二階堂大路の南説(位置は諸説あり)、②宝戒寺小町亭と同一説、③頼朝法華堂跡の南東説(大倉御所推定地の北)などです。

その他にも、和田合戦に先立って没収され、義時の所有となった荏柄天神社前の和田義胤の邸宅や、建久五年(1194)に得た安田義定の邸宅があります。かつての邸宅の場所を想像しながら、鎌倉のまちを歩いてみてはいかがでしょうか。
【鎌倉歴史文化交流館学芸員・大澤 泉】(広報かまくら令和4年5月1日号)
