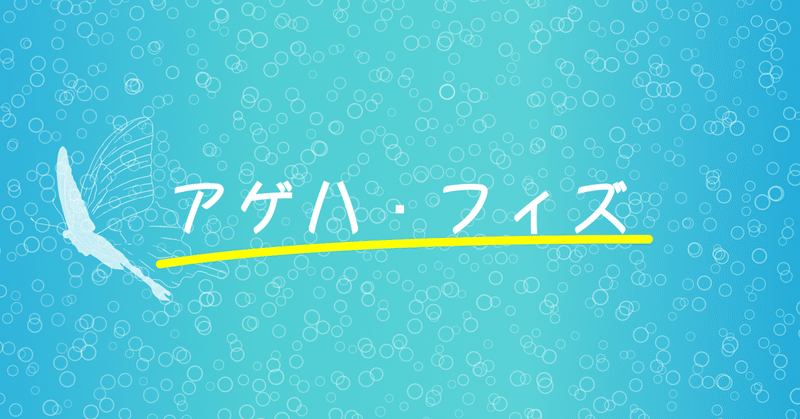
アゲハ・フィズ 第1話(1話完結 おまけ付き)
※こちらのお話は、note公式の創作大賞2023・イラストストーリー部門に参加しています。先に、お題となる宇佐崎先生のイラストをご覧になってからお読みください。お題イラストは下記からご確認ください。
科学部に所属する男子高校生、玄野カズミは入手した覚えのない謎の画像を前に、頭を抱えていた。パソコン室を拠点にし、画像生成AIも有する科学部の彼は、顧問の先生と身近な生徒をモデルにフェイク画像を作ったのではと目されたが、画像の出所や犯人探しに奔走するうちに、奇怪な事件に巻き込まれていく。
画像生成AIを用いた社会改変だと気が付いた彼は、黒幕と睨んだ部長と邂逅するものの、全てを引き起こしたのは自分であると宣言される。
プロンプトを工夫して世界を元の姿に戻すべく奔走するカズミは、試行錯誤の産物に翻弄されながら、ついに理想の世界へ辿り着く。
小悪魔な女子と天使な先生に振り回されるショートストーリー。
どこで入手したか全く覚えていない画像を前に、ボクは頭を抱えていた。どこにでもありそうな教室で、教卓を挟んで二人の女性が対峙している。見事な金髪と白衣が目を惹く女性は、科学部の顧問である美羽先生に見える。もう一方の黒髪の女の子は記憶にない。
美羽先生らしき人物は何故か傷だらけで、顔面蒼白で拳銃に弾を込めている。それを煽るような表情で眺めている制服姿の女子は、コウモリのような羽がついたリュックサックを背負っている。
シチュエーションの異様さからするとAIが生成したフェイク画像にも見えるが、画角や画質も考慮すると、目の前で起きた出来事をそのまま撮影した写真にも思える。どういう経緯でスマホに保存されたかさえ思い出せれば、真贋の判定は容易なのに……。
「これ、私?」
急に話しかけられて驚いたボクは、スマホを落としそうになりながら、反射的にスマホの画面をロックした。声のする方へ振り向くと、見覚えのない美少女が立っていた。
「変な写真じゃないなら、見せてやれば?」
彼女をパソコン室へ招き入れたらしいリナは、意地悪そうに言った。彼女の口車に乗るのは釈然としないが、ボクはさっきまで見ていた画像を彼女らに示した。二人は食い入るようにボクのスマホを見ていたが、リナは隣の彼女とボクを交互に見て、「二人は知り合い?」と言った。
ボクが首を傾げると、リナはスマホを指差した。
「コッチは美羽先生だけど、コッチはどう見てもアオイじゃない?」
リナに促されるまま、スマホの画像と目の前の人物を見比べた。ボクにジロジロ見つめられた彼女は、「加賀地です」と頬を赤らめて名乗った。ボクは無礼を謝って、自分も名乗った。すると彼女は、「女の子みたいな名前ですね」と目を細めた。
「先生ならともかく、同級生も盗撮して変なことに使うなんて。あのカズミくんが、ただの変態とはね」
リナは肩をすくめ、アオイさんの手を取った。
「こんな変態のいる部活、入らなくていいよ」
リナは戸惑っているアオイさんの手を引いて、入ってきたドアへ向かった。アオイさんの抵抗も虚しく、二人ともあっという間に廊下へ姿を消した。
「何しに来たんだ、一体……」
独りになったボクは、広いパソコン室で佇んでいるとスマホに新たな通知が届いた。リナから科学部のグループチャットに、「もう、誰も連れて行かない」とメッセージが書き込まれていた。その直前に「見学希望の子を連れて行くから、よろしく」ともあった。
正式な部員がボク一人の科学部を思っての行動だったろうに、勧誘する前に失敗してしまった。リナがあの様子では、廃部もそう遠くない。
ーーどうした?
見慣れない美羽先生のアイコンが表示された。「揉め事なら、相談に乗るぞ」と、メッセージは続く。隣の準備室へ通じるドアに視線をやった。部活の時間だが、その向こうは静まり返っていて、人がいる気配はない。
リナも見る場所で長々と事情を説明する気にはならないが、先生へ個別にDMを送るのも気が引ける。ボクは誰もいないパソコン室を出て、外から鍵を掛けた。
職員室へ立ち寄ったら不在だと言われ、呼び出しも提案されたが、やんわりと断った。まだ校内にいるのではという証言を信じ、生徒が少なくなった校内を虱潰しに歩き回る。校舎の一番上、四階の教室は空振りだった。一つ下に降りて、階段に近い方から当たっていくと、早速教室の片隅で揺れ動く金色が視界に入った。金髪の持ち主は、誰もいない教室で何かを探しているようだった。
ボクに気付いた先生は、作業を中断して顔を上げた。
「咲良と痴話喧嘩だって?」
彼女は近くの机にお尻を乗せると、手近な椅子をボクに勧める。白衣のポケットに手を突っ込み、周囲の様子を気に掛けながら加熱式のタバコを咥える。
「原因は、アイツか?」
先生の視線を追いかけると、後ろの出入り口にアオイさんが立っていた。彼女は熱い視線をボクらへ向け、こちらに近付いてくる。
「モテる男は大変だな。後悔だけはしないように頑張れ」
先生はボクの背中を軽く叩くと、タバコをもう一口吸ってポケットに仕舞った。机から腰を上げた彼女は、アオイさんの背中をジッと見つめる。
「二組の加賀地か。そのリュックーー」
先生が言い終える前に、その身体は黒板まで吹っ飛んだ。凄まじい力で叩きつけられた先生は、苦痛に顔を歪め床に突っ伏している。
「先生、先生?」
ボクは先生の元へ駆け寄った。ストッキングに包まれた美脚はいつの間にか傷だらけになっていて、白衣にも黒ずんだ血が滲んでいる。
「私は良いから、アンタは逃げなさい」
先生はボクの背中を押し、前をじっと見据えて立ち上がる。よろける彼女に手を貸そうとすると、先生は「早く行きなさい」と突っぱねた。
彼女の手にはいつの間にか拳銃が握られ、先生を吹っ飛ばした張本人、アオイさんを睨みつけながら、震える手で弾を込めている。立ち上がるのも精一杯に見える先生とは対照的に、余裕たっぷりに見えるアオイさんは教卓に両肘をついて、煽るような目で一挙手一投足を観察している。
「まさか、あん時の恩人とはな。終わるまで待ってやるよ、セ・ン・セ・イ」
アオイさんの瞳には怪しい光が宿り、禍々しい雰囲気が周囲に漂っているようだ。コウモリに思えたリュックの羽が、今は悪魔のソレに見える。
目の前に広がるこの光景、どこかで見た気がする。そう、あの画像だ。ボクはポケットをまさぐってスマホを取り出した。例の画像に近い構図でシャッターボタンを押す。撮れた写真は、机の散らかり具合や先生の傷の位置なんかは異なるものの、誤差の範疇と言えそうな仕上がりだった。
大きな物音に顔を上げると、視界は汚れた白衣に覆われた。ボクは咄嗟に手を出し、柔らかい身体を受け止める。先生はこちらを見上げ、「逃げなさいって言ったでしょ」と支えるボクの手を払い除け、膝に手をついて立ち上がる。
まだ教室の中にいるアオイさんは、背中のリュックサックを中心に、正体不明の影に囲まれていた。無数の大蛇を使役する魔女のようだ。彼女はボクに微笑むと、ベルトのような影で先生を薙ぎ払おうとする。ボクは先生の頭を下げさせ、それを間一髪で回避した。
目を丸くした先生の手を引いて、廊下を走り始めた。ほぼ素足だからか、怪我をしているからか、先生の足取りは重い。背後からジリジリにじり寄るアオイさんと、彼女が使役する謎の攻撃を気に掛けながらでは、あっという間に追いつかれそうだ。
「アナタだけなら逃げ切れるでしょ」
「しゃべる余裕があるなら、ちゃんと走って」
先生は時々引き金を引いて、アオイさんを牽制する。銃弾は謎の影で受け止められてしまい、影を減らす効力しかない。銃弾を受けて撃たれたところから千切れて霧散しても、すぐに新たな影が生まれてくる。
右手に階段、左手に渡り廊下が見えてきた。弾切れしたのか、先生は速度を落として弾を装填している。
「今は、とにかく距離を取ろう」
ボクは先生の手を引いて、渡り廊下の方へ曲がった。有効な問題解決策を思いつけないなら、まずは問題から距離を取る。それからじっくり考える。それが、部の教訓。
「ーーアレ、科学部の教訓って先生だっけ?」
ボクは一瞬足を止め、先生に疑問を投げかけた。その瞬間、シートベルトのような太い影がボクの足首を捉えた。ボクの身体はアオイさんの方へ引っ張られる。弾を装填し終えた先生の銃が火を噴き、先生は影から解放されたボクの手を引っ張った。
「まずは逃げるんでしょ? しっかりして」
先生はボクに小言をぶつけ、素早く周囲を見た。彼女は渡り廊下の頭上を目掛け、もう一度引き金を引いた。二発の弾丸は、天井のスプリンクラーを撃ち抜いた。しょっぱい水が、頭の上から降り注ぐ。
「ほら、走って」
先生はボクの手を引いて、水浸しの廊下を走り出した。この程度の工作が有効打になるとは思えなかったが、アオイさんはシャワーを浴びない程度の位置で足をとめ、鋭い眼光でこちらを睨みつけていた。
ーー今の何? 大丈夫?
パソコン室まで舞い戻り、準備室で息を整えていると、グループチャットにリナからのメッセージが届いた。そう言えば、スプリンクラーの作動に合わせ、火災報知器が鳴り響いていた。
どう返すべきか悩んでいると、先生が「誰かのイタズラだ」と送ってくれた。普段はボクとリナの公開DM状態だったグループチャットに、先生のアイコンが増えるのは不思議な感覚だ。
過去のメッセージを遡ると、この二年ぐらいはほぼボクのメモ、申し送りだ。リナのアイコンもほとんど無い割に、スクロールは多少長い気がする。
ボクがスマホをジッと見ていると、先生は「大丈夫?」と声をかけて来た。
「先生の方が痛そうだけど」
ボクがそう答えると彼女は、曖昧な笑みを浮かべた。
「そんなことより、どうやってあのリュックサックを奪うかだけど」
先生は話題を切り替え、彼女なりの作戦を話し始めた。これまでの背景や経緯も気になるところだが、アオイさんの鞄が重要らしい。
「あの鞄の正体と、先生が銃を持っている理由は教えてくれないんだ」
ボクが真剣に聞いていない作戦を事細かく話していた先生は、急に口を重くする。
「聞いても笑わない?」
ボクが頷くと彼女は、他に誰もいないのに、ボクにそっと耳打ちする。頬をほんのり紅潮させて離れていく姿に、何を聞いたか忘れそうになる。
「先生が天使で、あのリュックは悪魔を封じる聖遺物?」
ボクの復唱に、先生は小さく頷いた。突発的なワードを処理し切れないが、彼女の容姿に天使っぽさがないとは言えない。普段なら先生の方が小悪魔系に見えるが、今はアオイさんの方が小悪魔というか、魔女っ子に思える。
「じゃあ、あの変な影は」
「多分、封印されてる夢魔のせい」
「夢魔? 淫魔じゃなくて?」
ボクの問いかけに、先生はもう一度頷いた。
そういう分野に明るくなくても、サキュバスぐらいは知っている。夢魔を調べると、その対となる存在のようだ。いずれにせよ、悪魔としてそれほど強いイメージはない。
「封印されたまま契約したか、同調したか」
「同調って、アオイさんは」
「ーーだって、アオイさん……」
先生の言葉に、ボクは言葉を失った。確かに少々細身だったが、違和感は微塵もなかった。ただ、彼女の言葉が真実なら、スプリンクラーを嫌がったのも分かる気がする。
ーー見えているものだけを信じるな。
急に、誰かに話しかけられた気がした。辺りを見回しても、先生しかいない。聞き覚えのある、落ち着いた男性の声だった。ボクを不思議そうに見ていた先生は、小さな悲鳴をあげて飛び上がった。準備室の窓から、アゲハ蝶が一羽舞い込んだらしい。蝶は縦横無尽に飛び回ると、窓枠にしがみついた。
夢魔には毅然と立ち向かっていたのに、小さな虫を過剰に嫌がるとは。先生のこんな表情、滅多に見られない。ボクはこっそりカメラを立ち上げ、シャッターを押した。上手に音を消して撮ったつもりだが、先生には速攻でバレた。
彼女はボクからスマホを奪い取ると、今撮られた画像をカメラロールから削除した。一つ前に撮った画像が大写しになる。彼女は指で写真を切り替え、さらに一つ前の画像を表示する。彼女は何度か写真を交互に見比べ、「これ、どういうこと?」とボクにスマホを突きつけた。
一枚は間違いなく写真だが、加工して別の画像を作るような暇はなかった。実在する生徒と教師の画像データを学習させ、AIに生成させたとなれば、廃部や停学が見えてくる。顧問の教師だけならともかく、部の関係者じゃない生徒を丹念に隠し撮りしてモデル学習させたとなれば、処分は仕方がないと思う。それを本当にボクがやったのなら……。
「先生、ちょっとゴメン」
ボクは準備室を出て、隣のパソコン室へ移動した。ここまで高精細な画像を生成させるのに、自宅のパソコンではスペックが足りない。科学部用の端末に何らかの記録が残っていれば、ボクの罪状もハッキリする。できれば無罪であることを願い、自分のアカウントでログインした。直近の操作履歴を呼び出した。
適当にネットサーフィンを楽しんだり、自分好みに調整したAIとチャットを楽しんだ形跡はあるが、画像を生成させたり、メール等でどこかへ画像を送った履歴もない。明確に無罪とは断言できないが、ボクが作ったという確証もない。
先生にスマホを返してもらって端末の方を確かめても、メールやメッセージで画像を受け取った履歴はない。何もないところから急にこんな画像が生じるはずもないのに、出自も経緯も不明とは。
「それで、弁明は?」
端末の前でボクが腕組みをして考え込んでいると、先生が近付いてきた。丸く収める方法を検討していると、先生と一緒に準備室から移ってきた蝶が近くを通り過ぎた。先生は蝶を避けようと、ボクを盾に右往左往する。ボクは彼女に押され、変な画面を立ち上げていた。
ハードディスクの使用区分が表示された。ボクとゲストユーザーでない領域が確保されていて、ボクの権限では詳細を確かめられない。蝶との格闘を終えた先生に、「コレ、分かる?」と訊いたが、彼女は「私に分かる訳ないでしょ」と息を整えながら言った。
「顧問なのに」
ボクが呟くと、彼女は外の様子を気にかけながら口の前で人差し指を立てた。続けて、頭を低くするよう指示を出す。ボクは端末のシャットダウンをかけ、机と椅子の陰に身を潜めた。息を殺して、廊下の様子に耳をそばだてる。
パソコン室の前まで来た足音は、前方のドア前で止まった。外側から力が加わっても、鍵を掛けてある。相手は諦めたのか、後ろのドアへ移動した。先生はそちらのドア横で銃を構え、その瞬間をじっと待っている。
先生がボクに視線を送ってきた次の瞬間、引き戸が開けられた。黒い影をお供につれたアオイさんは、一気に飛びかかった先生を僅かな動きで回避した。アオイさんを捉え切れず、床に突っ伏した先生の背中に足を置き、「バレバレなんだよ」と低い声で言った。
「今よっ」
先生はアオイさんの足を掴んで、大声で叫んだ。作戦を聞いていなかったボクには、その合図の意味が分からない。ボクがボーッとしている間にアオイさんは先生の拘束を振り解き、黒い影に細い首を掴ませた。先生が咄嗟に掲げた銃は、別の影によって弾き飛ばされた。
銃は、手を伸ばせば拾えるところに転がっている。
「ええい、ままよっ」
ボクは震える膝を宥めすかし、目の前の銃を拾い上げてアオイさんに突撃した。初めて握る銃は、銃そのものも引き金もズッシリとしていて、走りながらではマトモに狙いをつけられない。すぐそばにいる先生へ当たらぬよう慎重を期すれば、銃撃なんて当たるはずがない。
真っ黒な触腕はボクの銃弾を払い除けると、新しい触腕で銃そのものをはたき落とす。武器を失っても構わない。文化部で運動音痴のボクでも、このまま押し倒せば体格差で押し切れるーー。
超常的な力を有するはずの華奢な身体は、逃げるどころか両手を広げてボクを受け入れた。彼女は恍惚とした表情で、「意外と情熱的なんだね」と耳元で囁いた。
彼女は化粧品とシャンプーの匂いを漂わせ、黒い影も使って身体を密着させる。ボクは太腿辺りに触れる感触で理性を保ちつつ、「先生っ」と叫んだ。例のリュックを持ち去りやすいよう、強引に大勢を組み替えた。
「全然打ち合わせと違うじゃない」
先生はぶつくさ言いながら、アオイさんのリュックサックを手中に収めた。力の根源を失ったアオイさんは、同時に意識も失った。全身から力が抜け、グッタリとボクにもたれかかる。周囲を埋め尽くしていた怪しい影も、いつの間にか消えていた。
ボクは自分の胸元で気絶しているアオイさんの身体をそっと起こし、手近な椅子へ座らせた。先生は床に転がった銃を拾い、「話をちゃんと聞かないのは、お前の悪い癖だぞ」とまだ文句を言っていた。
「聞いてるなら、返事ぐらいしなさい」
先生はリュックを検めながら、ボクへの小言を続ける。ボクが気のない返事をすると、火が着いたように怒り始めた。ただし、その怒りは彼女がリュックサックをひっくり返すまでしか続かなかった。
先生はリュックサックの口を大きく開き、何度か強く揺さぶった。揺さぶるたびに、顔は徐々に青白くなっていく。リュックサックから出て来たのは、ゴミにも思える小さな紙片だけだった。
ボクはそれを拾い上げ、中身を確かめた。封印に関する呪文か何かが書かれているのかと思いきや、情報の授業で使うためのアカウント、ログイン情報だった。誰のアカウントか、有効なIDとパスワードかどうかは分からない。
先生は何も入っていないリュックを抱え、茫然自失といった様子でその場にへたり込んでいた。まるで先生からも中身が抜け出たみたいだった。
「目論見が外れたからって、ショックを受け過ぎだろう」
いつの間にか先生の前へ移っていたアオイさんは、顔の前で手を振った。アオイさんの呼びかけで、先生は正気を取り戻した。彼女は即座に銃を眉間に突きつける。アオイさんは不敵な笑みを浮かべ、「生徒の身体はどうなってもいいのかな? セ・ン・セ・イ」と余裕たっぷりに焚き付ける。
「良くないけど、加賀地、ゴメンっ」
先生は左手に持っていたリュックを、アオイさんに叩きつけた。リュックで殴ったと言ってもいい。顔を押さえた彼女から僅かに距離を取ると、白い粉が詰まった試験管を白衣のポケットから取り出し、アオイさんの頭上で叩き割った。
「何すんだ、テメェ」
アオイさんは粉を振り払うと同時に、例の影で先生を襲った。先生はそれを屈んで避けると、リュックをボクに手渡した。
「もう一回詰めるから、守り切ってよ」
先生の意図を汲む前に、彼女はアオイさんと共にパソコン室の外へ出た。彼女は後ろでにドアを閉め、廊下でアオイさんを挑発している。煽られることに慣れていないのか、一連の行為で頭に血が昇っているのか、アオイさんは激昂した。先生の「こっちよ」という声が聞こえたかと思うと、二人分の足音はどんどん遠ざかった。
ボクは廊下の様子をこっそり覗き見た。激闘の痕跡に背筋がゾッとした。ボクは静かにドアを閉め、中から鍵を掛ける。先生に同行した方が良かったんじゃないかと、しばらくしてから悩み始めた。
授業用の端末の前で腕を組んでいると、アゲハ蝶が目の前を横切った。さっきと同じ個体かは分からなかったが、ボクは窓際まで行って逃げられるようにしてやった。窓の外から、蒸し暑い空気が入り込む。自分の荷物からノートか下敷きを持って来て、蝶をさっさと追い出そう。
ボクは自分の鞄のところへ行き、蝶を追い出すための道具と、すっかり温くなった炭酸水を取り出した。エナジードリンクみたいな、黄色い強炭酸が入ったペットボトルだ。一口飲んで蝶の居場所を確かめると、蝶はボクが机に置いたペットボトルに泊まった。蓋の上で羽を休ませている様子を見ると、蝶のことはどうでも良くなった。
先生から預かった例のリュックサックと、細長い紙片に視線を移す。授業用のアカウントなら、どの端末で施行してもログイン出来るだろう。本来なら御法度だが、誰のIDなのか、そもそも有効なのかどうかが気になって仕方がない。
ボクは目の前の端末を立ち上げ、記載してあるIDとパスワードを打ち込んでみた。すんなり認証され、味気ないデスクトップが表示された。壁紙は初期設定のまま、ファイルも綺麗に整理されていて、未使用にすら思える。
設定画面を開いても、個人を特定するだけの情報は見当たらない。本名ではなさそうなユーザー名と、九尾の狐っぽいアイコンだけは設定されていた。このアイコンは見覚えがある。
ボクは科学部用の端末を立ち上げ、自分のアカウントでログインした。最近使ったアプリケーションに、ほぼ同一のアイコンが並んでいる。オープンソースのAIを元にチューニングした科学部用のアプリ、シキソクゼQだ。開発者の名前を調べると、先ほど見たユーザー名が記載されている。
全く記憶にない名前だった。端末が引き継がれる科学部の端末ならともかく、卒業生の授業用アカウントなんて、いつまでも維持しない。
ボクはスッキリしないまま、科学部のグループチャットを開いた。タイムラインを遡れば、OB、OGとのやり取りも残っているはず。シキソクゼQの元となったAIがオープンになった時期を鑑みれば、そんなに何年も遡らなくても良いはずだが、近いアイコンやそれらしいユーザー名は見当たらない。
AIに関する話題が登場するのも、ボクが入部してからだ。正確には、ボクが一人で一方的に申し送りを繰り返している。稀に挟まるリナとのやり取り、先生とのやり取りはマトモに成立しておらず、ほぼ独り言の申し送りですら前後に脈絡がない。質問で終わっているような箇所の直後に「ありがとうございます」で長文が続いている。
このグループチャットを信じるなら、ボクが一人で疑問を投げかけ、一人で課題を解消し、シキソクゼQの開発へ至ったにも関わらず、開発者の名前やアイコンを自分とは無関係なものを選んだことになる。
ーー見えているものだけを信じるな。
また、あの声が聞こえた。周りには自分しかいない。アゲハ蝶は相変わらず、蓋の上で羽を休めている。蝶がしがみつくペットボトルの中で、新たな気泡が生まれては下から上へ消えていく……。
「そうか。消えたんだ」
メッセージの送り主と共にデータがごっそり消えたなら、チャットが一人相撲に見えてもおかしくはない。ただ、送り主にまつわる記憶まで消えているのは腑に落ちない。
ボクはもう一度、さっきのアカウントで利用履歴を確かめた。アカウントの持ち主は、授業で使用するソフトと、プリインストールされたウェブブラウザしか触っていないようだ。授業で用いたファイルを見ても、コレといった特徴はない。ウェブブラウザを立ち上げ、ブックマークや履歴を探ってみる。
ブックマークは標準のまま、検索履歴は夏休みのバイトとか、安く通えそうな大学や入試関連、ハンバーガーチェーンの期間限定メニューについてだった。最後に開いたページは、いかにも夏っぽい炭酸水のページ。
毎年ほぼ使い回しだろうに、マウスを動かすとカーソルに追従して気泡が出る仕組みになっている。一枚絵で良さそうな商品イメージも、一定の間隔で泡が生まれては消えていくアニメーションになっていた。
グループチャットで、受験や進路、バイトといった単語で検索をかけてみた。一つ上の学年に、部長なる人物が存在していたらしい痕跡が見えてきた。今年の年始から春先にかけて、不穏なメッセージとそれを打ち消すようなやり取りをした痕跡も残っている。「希死念慮」にどう対処すべきか、キーワードを変えて何度も検索した履歴まで残っていた。
あんなに大事にしていた部長のことを、ボクはすっかり忘れていた。思い出そうとしても、名前も顔も出てこない。画面の中の九尾の狐に笑われているような気がしてくる。
ボクはシキソクゼQを立ち上げ、部長のこと、消えた部長を思い出すにはどうすればいいか、なぜ消えたと思うか、取り留めのないことを質問してみた。それなりにモデル学習を積み重ねたつもりだったが、的を射た答えは得られなかった。
ボクはスマホを取り出し、例の画像を表示した。思い出せないと言えば、この画像の出自もだ。前後の記憶が綺麗に欠落している。思い出せないのではなく消されたとすれば、辻褄が合う?
ボクは次の入力を促すカーソルの点滅を見つめ、記憶の消し方を尋ねてみた。固定化された長期記憶の削除は難しいが、書き換えや改竄はそれほど難しくない、と。確かに、両親との思い出話でも、事実の誤認や刷り込みに近い瞬間はチラホラある。
事実と見間違えるインプットがあれば、記憶は切り替えられる。記憶や認識を書き換えれば、現実だって書き換えられるかも。目の前にはそれを可能にしそうな画像と、高精細な画像を生成するAIがある。
画像生成を通じて世界を書き換えられるか。ボクがAIに尋ねると、ペットボトルの蓋に捕まっていたアゲハ蝶は羽を広げ、ボクが開け放った窓の外へ出て行った。AIの回答を待つ間に、ボクは窓を閉めて空調を付けた。快適な空間で炭酸水を一口飲むと、AIが回答を吐き出していた。
「生成AIでバタフライエフェクトとは、大胆過ぎませんか?」
AIの回答を信じて何度か試行錯誤を積み重ねると、ようやく「その人」が姿を現した。もっとも、その人に関する記憶は失われたままのため、目的の人物かどうか確証はない。ただ、その人がボクの目の前にいて、その背中が特定の端末の前にあると非常にしっくり来る感覚があった。
彼はボクの問いかけに振り返り、メガネの奥の目を細め、柔和な笑みを浮かべた。
「それを信じてオレに辿り着いたお前も、大概だけどな」
その快活さは、希死念慮を抱いてボクを心配させた人物とは思えなかった。
「元気そうですね」
「そっちは随分、疲労困憊って感じだな」
アンタのせいだろうがと口にしかかったが、ギリギリで飲み込んだ。部長は手にしていた無糖の炭酸水を開け、ガブガブ飲んだ。無数の気泡に、目の前で何度も起きた事象改変を思い出す。
「泡のように消えるのも仕様ですか?」
ボクの問いに、彼は頷いた。彼はペットボトルの蓋を閉め、「ただし」と付け加える。
「発案者はお前だ。オレは実装したまで。オレが消えるまで試行錯誤を積み重ねたのも、お前自身だ」
彼はボクを指差して笑った。彼は手の中にあるペットボトルを目の高さへ持ち上げ、中の気泡を観察する。
「色即是空を落とし込んで、記憶も現実も消したいものはシュワっと消す。素晴らしく美しいアイディアだと思うよ、オレは」
彼の手の中で、新たな泡が生まれては次々に消えていく。画像生成で生まれたものも、そうでないものも、バタフライエフェクトの結果次第だ。
「話が済んだら、オレももう一度消してもらおう。世界に存在するのは、もう十分だ」
「本当にもう、未練はないんですか?」
ボクがそう言うと、彼は一瞬言葉に詰まった。
「本当は例のサマーフィズ、試したいんでしょ?」
彼は「ああ、そうだ」と何度か頷いた。
「今からでも行きましょうよ。何なら、ボクが奢ります」
ボクの誘いに、彼は首を振った。
「後輩に奢られるくらいなら、消えた方がマシだ」
せいぜい数百円の代物だ。高が知れていると思ったが、彼の決意は堅いらしい。ボクは彼の意思を尊重することにして、新たな画像生成のためのプロンプトを考え始めた。
「妙な事態を収拾したいなら、徹底的にやれよ。中途半端が一番良くない」
次を思いつけない雑念だらけの頭に、彼の横槍が事態を悪化させる。ボクの指はキーボードの上を彷徨うに任せ、新たな画像を生成させる。ボクは新たな画像をスマホに表示させ、それが真実であると念じ始めた。
「炭酸が弾ける音って心地いいよな。こうやって消えていくのも悪くない……」
さっきまでそこにいた部長は、青白い光を残して消えていた。最後の方は、声もハッキリ聞き取れなかった。
新しい画像でも、先生とアオイさんは教卓を挟んで対峙していた。先生の手から拳銃が消えていたのは大きな変化か。下半身を中心とした怪我はそれほど変化がない。
グループチャットは、先生の「どうした?」のメッセージで終わっていて、その後のリナのメッセージは無かったことになっている。アオイさんと彼女に画像を見られ、誤解を解けずに終わったのはそのままのようだ。
他にどんな変化があるのか、ひとまずパソコンの前で辺りを見回した。部長は無事に消えていて、隣の準備室に先生がいる気配もない。空調は動いていないが、窓は閉まっていて蝶の姿も見えなかった。
さっきまで手元にあったはずの例のリュックサックは、いつの間にか消えていた。新しい画像にはしっかり描写されていたが、ただの装飾という可能性もある。ボクはこの世界でも飲み差しの炭酸水を一口飲み、気持ちを切り替える。
落ち着いて耳を澄ませてみると、パソコン室の外がかなり賑やかなことに気がついた。賑やかを通り越し、うるさいと文句を言えるレベルだ。ボクはドアを開け、廊下を覗いてみた。
「よぉ、色男」
ドアを開けた瞬間、上から急に声がかかった。思わずビク付き、恐る恐るそちらに視線をやった。坊主頭が眩しいユウトが、野球部の練習用ユニフォームを着て立っていた。彼は目の前に広がる中庭を、他の部員と共に眺めているらしい。
パソコン室前の廊下も、左右の渡り廊下も、多くのギャラリーが窓際へ詰め寄り、近くを通り過ぎるのにも支障を来しているようだ。
ユウトと視線がかち合うと、彼は大きなため息を吐いた。彼はボクの首根っこを掴み、目の前で壁を作っている人混みに向かって、「ちょっとすみません」と声を掛けた。彼のデカい声に迷惑そうな表情で振り返るが、ボクの顔を見た途端、全員が少しずつ移動して場所を開け、最前列の窓際まで通してくれた。
窓の向こうに広がる中庭では、先生とアオイさんが激しい水の掛け合いを展開しているようだった。ただの水ではなく、水性飲料を溶いたインクのようだ。先生の方がかなり形勢が悪いようで、アオイさんは羽の生えたリュックを背負い、スカートの中が見えるのも構わず、アクロバットな動きを披露していた。
ボクを最前列に連れてきてくれたユウトは、ほんの少し怒った様子で「お前を賭けた決闘なんだろ? ちゃんと見とけよ」と言った。ボクが「はぁ?」と聞き返すと、彼はまたもため息を吐いて、「羨ましいよなぁ、本当」とボヤいた。
「高校野球のスーパースター、乾ユウト様を差し置いて、凡人のお前が二人の美女に言い寄られるなんてな」
「二人の美女って」
ボクがそう言うと、ユウトは「はあぁ?」と不機嫌そうな声を上げた。
「加賀地は加賀地だろ? アイツの愛ならオレは受け入れるし、先生との歳の差なんてないようなもんさ。お前、考え方が古いんじゃないか?」
彼の怒りも本物のようだが、近くにいる男性諸君も、同じ気持ちのようだ。嫉妬や怒りの視線が、あちこちから飛んでくる。ボクはユウトの怒りを宥め、周囲に軽く頭を下げて目の前の勝負に視線を戻した。
インクを受け止めるのに有効そうな先生の白衣はすでにお役御免状態で、中のブラウスに影響がおよび始めている。艶かしい黒のストッキングも要所要所で被弾があるものの、長い髪や顔は無事らしい。
対戦相手のアオイさんは、セーラー服の袖やスカートの裾に若干のインクが付着しているものの、深刻なダメージはないようだ。二つに束ねた髪の毛先は少し濡れているように見えるが、彼女の優位は揺るがないように見える。
羽が生えたリュックサックを背負っていると機動力に影響しそうだが、激しい動きを阻害せず、視覚的なズレを上手く使って狙いを分散させているようだ。彼女は今も宙に身を躍らせ、先生のインクを全てかわした。アオイさんが着地する瞬間を狙っていた攻撃も、リュックから伸びた太い鞭のような影に払い除けられた。
「おい、今の」
ボクはユウトに声を掛けたが、彼は目の前の勝負にのめり込んでいて、声が届かないらしい。周りのギャラリーも、今の出来事に特別興味を示していない。
ボクが首を傾げて前を見ると、アオイさんは窓ガラス越しに怪しい視線を投げかけた。可愛らしいウィンクまで送ってくる。一瞬の隙をついた先生の攻撃も、彼女は素早く切り抜ける。アオイさんの切り返しを避けきれなかった先生は、頭から大量のインクをぶちまけられていた。
ルールは全く分からないが、先生が負けるのも時間の問題に思えた。
ボクは窓際から身体を離し、後ろを振り向いた。
「すみません、通してください」
勝負に熱狂している人たちの最前列で、ボクは人混みをかき分けるべく奮闘する。さっきボクのために道を開けた人たちの迷惑そうな視線を浴び、ボクは頭を何度も下げてもう一度道を作ってもらう。人混みの中で揉みくちゃにされながら、なんとか行列の一番後ろへ出た。
人混みから離れ、パソコン室側の壁に身体を預けて息を整えていると、最前列にいるはずのユウトが、その背丈を生かしてボクを見つける。
「主役がそんなところで、何やってんだ?」
部活で鍛えられたバカデカい彼の声が、狭い廊下に響き渡る。周囲の迷惑そうな視線が一気にボクへ集中する。ボクは近くの人へ何度も「すみません」と小さく頭を下げ、パソコン室の中へ戻った。後ろ手でドアを閉め、中から鍵をかける。誰も入ってこないよう、もう一方のドアも戸締まりをチェックした。
外の喧騒は気になるものの、取り敢えずの安全は確保した。もう一度深呼吸して、現状を確かめる。今の画像は、先生の手から拳銃がなくなったバージョンだった。
他の変化を探るべく、グループチャットを立ち上げた。さっきの検索履歴は残っていたが、該当するメッセージは一つも引っ掛からなかった。念の為、ハードディスクの使用区分も確かめたが、ボクにチェックできない不可視領域はなくなっている。
立ち上げっぱなしになっていた授業用の端末をチェックすると、九尾の狐がまだ残っていた。ウェブブラウザの検索履歴も、さっきとほぼ変わらない。次はコレが消えるようにプロンプトを捻らねばならない。
さて、どうしたものかーー。
「なんか、大変そうだね」
ボクが端末の前で悩んでいると、後ろからリナが声を掛けてきた。自分以外誰もいないと思い込んでいたが、さっきから側にいたようだ。彼女は、校内の自販機で買ったばかりらしいエナジードリンク系のペットボトルをボクに差し出した。ボトルの外側には、水滴が着いている。
ボクが受け取らずにいると、彼女はそれを強引に机へ置いた。隣の席へ腰を下ろし、もう一本持っていたペットボトルの蓋を開け、意識が高そうなミネラルウォーターを一口飲んだ。
「見なくていいの?」
ボクが彼女に問いかけると、彼女は気怠そうに「興味ない」と答えた。
「アンタが誰とどうなろうと、好きにすればって感じ」
彼女は隣の席から、ボクのモニターを覗き込んだ。画面には、シキソクゼQの入力待ちが表示されている。
「ま〜た変な画像作ろうとしてんの?」
リナは険のある声で言った。
「実在の人物をモデルに変な画像作るのは禁止じゃなかったっけ」
「変な画像なんて作ってない」
「じゃあ、さっきの画像は何? まだ納得のいく説明、されてないんですけど」
リナは声を荒らげた。そう言えば彼女とのメッセージは、角が立ったままだった。
「同級生のそういう画像が欲しいのは分かるけど、誰でも彼でもってのは気に入らない。ユウトならまだしも、カズミだと何か腹が立つ」
リナは不満気にボクの顔を覗き込んだ。彼女はボクに身を寄せ、ボクはどこに目をやれば良いかが分からない。彼女は小声で「私を見て」と訴えるが、素直に応えられない。
ボクはリナの方を向いたまま、指に任せてキーボードを叩いた。エンターキーを押すと、新たな画像生成が始まった。画像生成が完了すると、自動的にボクのスマホへ送信するよう設定してある。
ほんの数秒でスマホに通知が来た。ボクはリナから視線を逸らし、新たに生成された画像をスマホの画面に表示した。今度の画像は、アオイさんが背負うリュックの装飾、形状が僅かに変化していた。
「また変な画像見てる」
リナはボクのスマホを横から見て、一人で怒っているらしい。不機嫌そうに頬を膨らませている。
「何であの二人なの? 私じゃダメ?」
リナはボクに詰め寄るが、ボクは新たな画像を脳裏に焼き付けて目を閉じた。リナに揺さぶられるのを途中まで感じていたが、ある瞬間から力が加わらなくなった。うっすら目を開けると、さっきまでボクに掴みかかっていたリナが、青白い立体映像、ホログラムのようになり、徐々に透明度を増して下から上に向かって泡のように消えて行く。
何度見ても、改変の瞬間は結構キツい。美しさもなくはないが、今まで存在していたものが有無を言わさず泡と消えるのは、儚いを超えた何かがある。
今度のバタフライエフェクトでは、リナが持ってきた炭酸飲料は未開封のまま、机の上に残っていた。グループチャットの最後のメッセージはさっきと変わっていない。世界の変化はまだ把握できていないが、少なくとも廊下の喧騒はなくなった。
隣で立ち上げていた授業用端末はシャットダウンされていて、例のアカウントへログインしようにも、手元に情報が残っていない。他人のIDとパスワードなんて覚えていない。良い方に転んだと信じて顔を上げると、机の上の炭酸飲料は窓から差し込む夕陽を浴び、キラキラと光を反射していた。
「まだ居たのか」
隣の準備室から先生が入ってきた。彼女は薄暗くなっているパソコン室の様子を見て、壁際の電気を付けようとする。
「あ、いいんだ。先生。オレ、もう帰るから」
ボクがそう言うと、彼女は「そうか」と白衣に両手を突っ込んだ。ボクは立ち上げっぱなしの目の前の端末をシャットダウンし、散らかっている荷物を鞄に詰め始める。それを見た彼女は、「気をつけて帰るんだぞ」と言い残し、準備室へ戻って行った。
新たに生成された画像でも足に傷を負っていた先生だが、特別な影響はないようだ。ボクは胸を撫で下ろすついでに、パソコン室中の端末、モニターの電源が切り忘れていないか、一つ一つ確かめて回った。帰宅に際して、不備はない。
荷物を詰め終えた鞄を背負い、パソコン室の外へ出た。外から鍵を掛け、ドアが閉まっていることを確かめた。後は職員室へ鍵を返して帰るだけのはずだが、鞄が妙に軽い気がする。
廊下の端で鞄を開け、中身を確かめた。弁当箱が入っていない。置き忘れるとしたら、教室の机の中だ。せっかく一階へ降りてきているのに、また上へ戻らねばならない。ボクは小さくため息を付き、教室へ戻る階段を登り始めた。
教室に居残りで自習する連中も流石に下校している。文化部も吹奏楽部以外は帰宅済みで、後はほぼ運動部と図書委員ぐらいだろう。ほぼ無人の校舎を歩き、二年五組の教室に辿り着いた。
見回りの先生による施錠を待つだけの教室で、ボクは忘れ物の弁当を探し当てた。鞄の一番下に押し込み、少々大袈裟に「弁当、ヨシ」と指差し確認をした。
顔を上げて外を見ると、綺麗な夕日が見えた。少し高いところから見る夕景に、妙な満足を感じていた。
「一緒に帰ろっか。ダーリン」
聞き覚えのある声に後ろを振り返ると、新しいリュックサックを背負ったアオイさんが立っていた。彼女はボクの腕を取り、「今日こそ、愛を語り合おうね」と身を寄せる。自然に腕を組んだ彼女はその場を全く動かないボクを見上げ、「どうしたの?」と言った。
ボクは視線を逸らし、背中の鞄を見た。やはり、コウモリや悪魔を彷彿とさせる羽は見当たらない。彼女とは元からそういう関係の世界かもしれない。ボクが無回答を貫いていると、彼女は怪しい微笑みを浮かべた。
彼女はボクの側を離れ、周りにある机を動かし始めた。掃除当番が綺麗に整列したそれを隙間なく寄せ集め、大きな台を形成しつつある。
「机なんか動かして、どうするんだ?」
机の塊を見て「こんなもんか」と呟いた彼女は、額に滲んだ汗を手の甲で拭った。彼女は自分が作った台に腰を下ろし、こちらを向いた。
「ココが良いんでしょ? やっぱり、顔に似合わず情熱的だよね」
彼女はボクを手招きし、胸元のリボンをいじり始める。夕陽に照らされた顔を見て、彼女を押し倒した瞬間、密着した瞬間を思い出した。匂いや声やあの触り心地は、何とも魅力的だったが、ボクは目を閉じて頭を振った。雑念を振り払い、彼女に背を向ける。
「押し倒しておいて、据え膳食わぬとはね」
後ろでアオイさんが何を言おうと、ボクはその場を離れるだけ。廊下まであと一歩というところで、開け放たれていたドアが急に閉められた。強引に突破を試みるが、全身の力を込めても微動だにしない。
もう一方の出入り口へ向かうと、いつの間にか机を降りて背後に回っていたアオイさんが、後ろからボクに耳打ちする。
「こんなチャンス、二度とないよ」
彼女の甘い声は、耳を通じて脳を直接揺さぶるようだった。ボクは足を止め、そちらへ振り向いた。学内でもトップクラスの女子と、放課後の教室でイイコトをするチャンスなんて、早々訪れるものではない。
彼女はボクの手を取り、机で作ったベッドの前まで連れて行く。もう一度机に腰掛け、改めてボクを誘惑する。
「ホラホラ、早くしないと誰か来ちゃうよ? それとも見せびらかしたい?」
アオイさんの瞳は赤紫に変わり、目の中に不思議な模様が浮かび上がる。黒一色だった髪の一部が、瞳と同系色に染まっていく。その変化へ呼応するように、彼女の鞄にはコウモリのような翼が生えてくる。
彼女は机で作ったベッドの感触を確かめ、「どっちが下になる?」とボクに尋ねた。
「背中が結構痛いんだよね、コレ」
彼女は当たり前のように胸元のリボンを外し、ボクに熱い視線を投げかける。その瞳をジッと見ていると、心も身体も吸い寄せられるようだ。その場で佇むボクを見て、彼女は微笑んだ。
「初めてでも大丈夫。私に任せて。なんとかするから」
彼女はボクを簡易ベッドに押し倒すと、上からのしかかる。
「さ、楽しもうか」
頬を紅潮させた彼女は、舌舐めずりをするとボクに顔を近付けた。吐息が肌に触れる距離まで接近した瞬間、ボクは勢いよく頭をぶつけた。ボクの頭突きをまともにくらった彼女は、鼻の頭を押さえを上げた。彼女の押さえ込みが弱った隙に、ボクは彼女の下から逃げ出した。
「テメェ、この野郎っ」
アオイさんはまだ頭突きのダメージが引いていないらしく、その場で悪態をつく他ないようだ。ボクはその間に、開いている方の出入り口へ向かう。
「逃すかよ」
アオイさんは手をかざして離れたところからドアを閉めに掛かったが、ボクは引っ掴んでいた彼女の鞄を放り投げ、ドアが完全に閉まるのを防いだ。アオイさんは「コイツっ」と叫ぶが、ボクが外へ出る方が若干早かった。
廊下へ出て後ろを振り返ると、教室は完全に出入り口を塞がれていた。さっきまで可愛らしい鞄だったそれは、見るも無惨な姿で床に転がっている。
「待てよ、コラっ」
密閉された教室の中で、怒号と共に何かを蹴散らす音が聞こえる。ボクは必死に近くの階段を駆け降りた。一目散にパソコン室の前まで戻る。
パソコン室の前でドアに手をかけるものの、鍵が掛かっていて開かない。ポケットに手を突っ込めば済む話だが、震える手では間に合う気がしない。ボクは「先生、ゴメン」と心の中で叫び、ノックもせずに準備室のドアを開けた。
「なんだ? 玄野」
薄暗い準備室で電子タバコを片手に雑誌を読んでいた先生は、目を丸くしてこちらを見た。見事な金髪と小悪魔なんちゃらな雑誌は見事に調和していた。
「ノックぐらいしろよ。二回じゃダメだぞ。三回な。三回」
ボクは「ゴメン、ゴメン」と先生の小言を宥めた。ボクの態度に更に先生は語気を強めたが、ボクは無視して隣のパソコン室へ移った。彼女はボクの後ろをついて周り、「無視するな」と軽く小突く。
ボクはいつもの端末を立ち上げ、システムが立ち上がるのを待った。
「先生、本当にゴメン。あとで幾らでも聞くから」
ボクの隣でまだ文句を言う先生が、そんな言葉で黙るはずもない。ボクは無視を貫き、パソコンにログインした。処理が完了する間にスマホでグループチャットを立ち上げ、履歴を確かめる。一つ前の世界と同様、部長の痕跡は綺麗に消えていた。
グループチャットを終了すると、例の画像が大写しになった。まだ近くにいた先生は、「ちょっと、何それ」と声を上げた。
「学内の人物、教員も生徒も学習させない、使っちゃいけないって約束したよね?」
先生はひとしきりボクを叱りつけると、今度は「うわぁ、マジかぁ」とボヤき始めた。
「廃部とか、休学とか、最悪なんですけど……」
先生はボクのスマホを取り上げたまま、恨み節をどんどん呟いた。ボクはそれも無視して、シキソクゼQを立ち上げた。準備を整えたシキソクゼQは、モニターの中でカーソルを点滅させ、次の入力を待っている。
「も〜、人の話、ちゃんと聞いてる?」
先生はよそ見を続けるボクに、可愛らしい膨れっ面で存在感をアピールした。不機嫌そうな表情でも、その美貌は微塵も揺るがない。
度重なるバタフライエフェクトでも揺らいでいない存在となると、ボクの記憶とそれからーー。
「先生、ゴメン」
ボクは先生を宥め、隙を突いてスマホを取り返した。
キーボードの上に指を走らせ、次のプロンプトを入力する。
「あ、また何かやってる」
先生の抗議も虚しく、シキソクゼQは新たな画像を生成し始めた。あと数秒でスマホに通知が届く。
「これ以上やると、休学どころか退学だから、今すぐやめなさい」
先生は身振り手振りで中断を要請するが、ボクはそれに取り合わない。先生は横からキーボードやマウスに手を伸ばすが、ボクはそれを静止する。先生は更なる強硬策として、端末の電源に手を伸ばした。ボクがそれにも抵抗していると、パソコン室のドアが外から凄まじい力でこじ開けられた。余りの衝撃に、先生はその場に尻餅をついた。
ドアがあった場所へ目をやると、着衣と髪が乱れたアオイさんが立っていた。両肩で息をしている彼女に、先生は「ちょっとアナタ」と突っかかる。アオイさんは、近付いてきた先生の首を引っ掴む。
「パソコン弄りしてないで、イイコトしようよ」
彼女は先生の首を掴んだまま、中へ入ってくる。
「お前に拒否権はない。分かるよな?」
彼女が低い声で言うと、先生の顔が苦しそうに歪んだ。先生は必死にもがくが、アオイさんの拘束からは逃れられない。
ボクはパソコンの側を離れ、アオイさんの方へ近付いた。
「理解が良いのは助かるよ。カズミくん」
彼女は先生の首を手放し、解放された先生はその場で必死に呼吸を整えている。彼女はボクの目の前まで来ると、ボクを素通りして背後の端末へ手を伸ばした。彼女は自然な動きでモニターを持ち上げ、周囲のコードなど気にせずその場へ叩きつけた。足元の本体も見逃さず、徹底的に破壊する。
足元に散らばった残骸を見て、彼女は満足げな表情を浮かべる。
「さぁ、続きをしようか。ダーリン」
彼女は手近な机を動かし、十分な広さを確保した。呼吸を整えた先生は、机の上で扇情的なポーズをとり、ボクを誘惑するアオイさんに「ちょっと、どういうつもり?」と非難した。アオイさんの表情は一気に曇り、二人の間で緊張が高まっていく。
ボクはスマホを握り締め、「ちょっと良いかな?」と上擦った声を出した。二人は怪訝そうな面持ちでこちらへ振り向いた。
「折角だし、キミの写真を撮りたくて」
先生は首を傾げたが、アオイさんは満更でもなさそうに「どうぞ」とポーズを取り直した。ボクはカメラを立ち上げ、シャッターを押す。今撮った写真がカメラロールに保存される。ボクはその写真をタップして、立て続けに一つ前の画像を表示する。先生が足に怪我を負っていない画像を目に焼き付け、ボクは強めに目を瞑った。
下校途中に女子とハンバーガーチェーンへ立ち寄って、期間限定商品を頼むなんて。相手がほぼ腐れ縁のリナであっても、テンションは妙に上がる。リナは冷たいシェイクを頼み、先に座席を確保している。ボクは爽やかな見た目のサマーフィズとやらを注文した。一つだけ頼んだつもりが、オーダーミスで二つ通ってしまったらしい。
ボクは小さなプラカップを両手に持ち、リナが待つテーブルへ向かった。彼女はボクを見るなり、「何で二つ?」と言わなくても分かるツッコミをした。ボクは彼女の前にそれを一つ置いたが、彼女はボクの前にそれを差し戻す。
「私はシェイクがあるから要らない」
彼女はキッパリと撥ね付け、ボクのスマホを睨み続けている。ボクはまだ口をつけていない方のドリンクを、空席の方へよけた。
「こんなの、どう生かすの?」
コウモリみたいな羽が生えたリュックサックを背負った美女と、ちょっぴり元ヤンっぽい金髪美人教師が教卓を挟んで向かい合うという、珍妙な画像。おまけに教師の方は足に怪我を負っていて、拳銃に弾を込めている最中だ。
「コンセプトアートを生かす課題だから、仕方ないだろ?」
この画像を元に、文化祭に向けた演劇脚本をひねらなくてはならない。リナは眉間に皺を寄せ、見たこともない表情で唸り声を上げた。ボクはそんな彼女を見て、笑ってしまった。「笑うな」と抗議する彼女に対し、ボクは誤魔化すようにストローに口をつけた。思いっきり吸い込んだため、炭酸の強い刺激に、軽く咽せてしまった。
ボクが咽せる様を見て、今度はリナが腹を抱えて笑った。ひとしきり笑った彼女は、空になったシェイクの容器を振って、「私もそれ、飲もうかな」と言った。
ボクはすでに口をつけていた方を持ち上げたが、彼女は問答無用でもう一方のカップを持っていく。流れるような動きでストローに口をつけた。一口飲んだリナの眉が、微かに上がった。
ボクらは飲みかけのドリンクを持って、店の外に出た。目の前を横切るアゲハ蝶を見送って、シュワシュワと弾ける気泡に心を躍らせた。
ボクは科学部の端末の前で腕を組み、オープンソースのAIを独自にチューニングする方法を検討していた。例の課題画像を生成させたというなら、課題解決のヒントになるシチュエーションぐらい、吐き出せるはず。
ボクには難しいプログラミングは分からない。手元のデータやモデルを学習させ、画像生成が完了したら自動でスマホへ送信しよう。スマホ側は件名で判定して自動保存するように設定すればいい。
とりあえず試しに一回やってみよう。これできっと、面白くなる。
おまけ(人物設定)
最後までお読みいただき、ありがとうございます。少しでも楽しんでいただけたら幸いです。 ただ、まだまだ面白い作品、役に立つ記事を作る力、経験や取材が足りません。もっといい作品をお届けするためにも、サポートいただけますと助かります。 これからも、よろしくお願いいたします。
