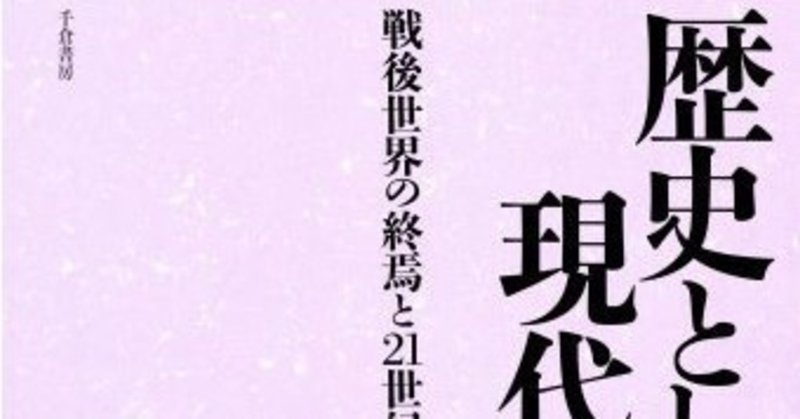
読書と共に消えた彫啄
(20190918記)
研究会や学会の中には、研究者や編集者、記者などではない、いわゆる一般市民にも門戸を開いているものがある。
専門の知識や議論を広く社会に還元しようという意図は素晴らしいと思うのだが、前提となる問題意識や議論に参加する上での態度にギャップがありすぎて、うまくいかないことも少なくない。
お誘いいただいて、とある研究会の立ち上げに参加した時もそうだった。一般参加者にもオープンとなっている懇親会で、四十半ばくらいの女性が突然声高にしゃべり出し、会場内の目が一斉にそちらを向いた。
その女性は視線を集めたことに怯むどころか、むしろ満足げな面持ちを浮かべると、初めて会うというI先生に、挑みかかるようにまとまりのない質問を浴びせた挙げ句、答えようとする先生の言葉を遮って自分の考えを一方的に話し続けた。
見苦しいやりとりが数分続いた。見かねた私は旧知のI先生に挨拶する風を装いつつ会話に割り込み、やんわりと「それでしたらこんな本がありますよ」「こういう議論が過去にあったんですよ」「こんな本を読んでみては如何ですか」と話しかけてみた。
しかし彼女は「私は本は読みません」「私は一切の先入観を持たずに先生の話を聞きたいんです」「本なんか信用できません」「当人に直接話を聞くのが一番手っ取り早くて間違いが無いはずです」と、私の言葉を一蹴した。
気づかないのか、目をそらしているのか知らないが、先行研究(歴史的経緯)を無視し、眼前の事象のみを切り取って感情をぶつける人が増えていることは、そうした行為を容易にしたSNSの普及が第一の原因であろうが、本を読まない人が増えていることとも密接に関わっていると思う。
読書経験が乏しいから、どれが定評のある本か、怪しい本かの見極めもつかないし、遡って議論の流れや学問の系譜を追うこともできない。そもそも長い歳月による彫琢を経てきた知的営為の存在に気づかない。
「当人に直接話を聞くのが手っ取り早い」し、それが「間違いがない」という発想自体が、いつでも何でもただで教えてくれる(でも真実である保証はない)wiki 的だと思うし、礼儀もわきまえもなくいきなり本人に吶喊してしまうというのも、一四〇字の制限を言い訳にして人との距離感をぶち壊してしまう Twitter と近しい短絡に見える。
本を読む行為は情報を得ることと同時に自ら考える時間を取ることでもある。
人の書き込みへの「いいね」やリツイートは、情報こそ得てのことかもしれないが、明らかに熟考、沈思を経ていない。
連日投稿される怒りとも嘆きともつかない木村幹さんの膨大なツイートを見ていると、本当にしんどいだろう、と思う。
あれだけ専門書も論文もきちんと書いてるのに、それを一顧だにせずトンデモ質問を浴びせかけてくる輩が後を絶たないのだから、その徒労感たるや察するにあまりある。
本を読まない人に「本なんか信用できません」と言われたことと合わせて、出版に携わる者として忸怩たる思いがする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
