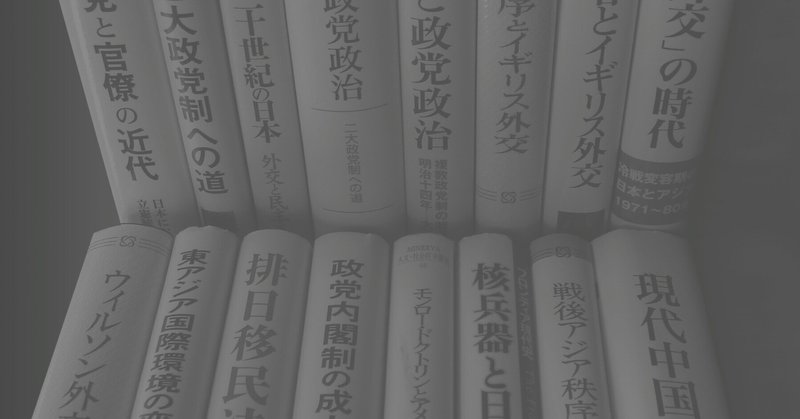
懐かしい作品に還る昼下がり
(2024/03/30記)
嵐が去った土曜日、春(初夏?)の陽気が心を誘うが、ここ十年で最もひどい花粉症に見舞われている私は、固く窓とカーテンを閉ざし、一日一錠で効くと言われているクスリを朝晩二錠ずつ飲み、なんなら部屋の中でもマスクをしようかという勢いである。
こんなときは薄暗い書斎にこもって歴史に逃げ込むに限る。
細谷雄一さんの『外交による平和――アンソニー・イーデンと二十世紀の国際政治』(有斐閣)。
君塚直隆さんの『パクス・ブリタニカのイギリス外交――パーマストンと会議外交の時代』(有斐閣)。
奈良岡聰智さんの『加藤高明と政党政治――二大政党制への道』(山川出版社)。
そして服部龍二さんの『幣原喜重郎と二十世紀の日本――外交と民主主義』(有斐閣)。
もはや古い友人とさえ呼びたくなる四人の研究者の、懐かしい初期作品を並べ、パラパラと読み返す。
メディアや論壇での活躍が華々しすぎてうっかり忘れそうになるが、この四人の優れた研究者の本質は史家である。
私はもともと、どのような学問分野においても真にユニークな研究を成し遂げる人は「史眼」を持つ、というのが持論である。
研究者には二通りがあって、どれほど研究しても事象と数字の羅列にしかならない人と、地道に検証と分析を積み重ねているうち、図らずも大きな歴史の物語、人間のドラマを描き出してしまう人がいる(どちらが、良い、悪い、という話ではない)。
四人は後者であり、問題関心もアプローチも表現手法もそれぞれに異なるのだが、読了後、胸に迫る想いに近しいものを感じてしまう。
細谷さんの著書は、一九五五年のジュネーヴ四大国首脳会談をピークに据えながら東西の緊張緩和に邁進したイギリス外相、アンソニー・イーデンの外交指導を描き、二〇世紀の国際社会の安定という側面から外交の本質や外政家のあり方を示そうというものだ。
全体像を踏まえれば、本書の通史的性格、そして国際社会全般への行き届いた目配りは明らかなのだが、個人的な読み所は微細なまでに浮かび上がるイーデンの人となり、あるいは表情であった。
読者は細谷さんの筆に誘われるまま、外政家イーデンの生涯においてジュネーブ会談がどのような意味を持つか、深く解することになる。
そのときイーデンを蝕む病。そして晩年…。私には本書を如何なる感傷をも交えずに読むことなど到底不可能だ。学者はそうはいくまいが、素晴らしいことに私は学者ではないのである。
同じことは君塚さんの著書にも言える。長い一九世紀を貫く会議外交の変遷を、ヨーロッパの歴史を後背に、各国のお家の事情や、イギリス外相・首相のパーマストンを中心とする魅力的なプレイヤーたちと共に描き切って、余すところがない。
臍をかむパーマストン、狡知をめぐらすメッテルニヒ、ほくそ笑むナポレオン三世らが繰り広げる虚々実々の駆け引きは、二昔前だったら「こんなに面白い本は学術書ではない」と言われていたことだろう。
ともすれば物語性が強く感じられてしまうほど、君塚さんの流麗な筆は抗いがたい魅力を持つ。だが、揺るぎない構成と膨大な一次資料の収猟が安易な批判を許さないのである。
たとえば二〇五ページの四章三節の終わり、華々しい外交的成果を挙げたナポレオン三世を描写した「この外交的な成果に気をよくした野心家の皇帝は、この後、パーマストンのそれとは異なった独自の会議外交を展開し、ウィーン体制の打破に向かっていく。」という一文のあとに、厳密に言えば蛇足と指をさされかねない「パーマストン老卿の胸に輝くブルーリボンは、どこか寂しげにその光彩を放っていた。」の叙情的一文を置くことができる研究者は多くあるまい。
実際、この逸脱を楽しめるかどうか、という差異は比較的大きい。その一文が生み出す余情を読者が真に味わうには、筆者をしてそれを草さしめた背景に思い致さねばならぬからだ。
一九世紀半ばのヨーロッパに会議による協調体制を築いた老外政家の死期を描いた第五章「会議外交の終焉とパーマストンの死」の末に置かれたパーマストン最期の言葉に大きな時代の終焉を想わない者はいないだろう。
こうした筆致は現在に至るまで変わらない。先日刊行されたばかりの新潮新書『教養としてのイギリス貴族』一〇一ページで、十六世紀から連綿と続くデヴォンシャ公爵家の栄枯盛衰を振り返った君塚さんは、第一次世界大戦以後の税制改革で傾いてしまった公爵家の財政を単身立て直した女傑、十一代公爵夫人デボラの最期をこう描写する。
「二〇一四年に彼女が九四歳で大往生を遂げたとき、六〇〇人以上にも及ぶ召使いや従業員らが公爵夫人の野辺送りに立った。」
普通、研究者はここで筆を止めるのだ。しかし、君塚さんは違う。その後、このように続けて憚らない。
「それは古の公爵家の栄光の名残にも思われた。」
明らかに研究者の閾を超える深い叙情。これを可能にするのものは何だろうか。
その昔、リチャード・スメサーストさんが、十年近く取り組んできた高橋是清の評伝を、いよいよ上梓しようとしたときの話を思い出す。
まもなく刊行された『高橋是清――日本のケインズ その生涯と思想』(東洋経済新報社)は、財政家としての高橋に焦点を当て、彼が国家の使命をどのように理解し、実践していたかを検討するものだった。
とりわけ私が感銘を受けたのは財政出動、金融政策を景気後退時の成長促進、あるいは景気加熱時のインフレ対策として使うという、どこかで聴いたような議論を、まったく独学で身につけ、実践していた高橋の凄みであった。
とある研究会でご一緒したスメサーストさんは、長らく高橋是清と寄り添った日々を振り返り、こんな話をしてくれた。
「私の妻は、もう何年も三人で暮らしていたようなものね、と言います。評伝を執筆する間、いつも私たちの傍らには高橋がおり、それは習慣のようになってしまいました」
なるほど、評伝を書くと言うことは一人の人間に深く入り込み、対話し、その人物の考え方やモノの見方をトレースする作業と言える。
その場合の立ち位置、視座がどこに置かれるかが分かる話で、これは興味深い問題を含んでいる。
君塚さんはイギリス外交史のスペシャリストとして、多くの政治家や国王の人となりを描いてきたが「書いていると、そのご当人が降りてくるんですよ。私はただ筆のままに書くだけなんです」というのが決まり文句である。
ここにはある種の韜晦があって、もちろん真に受けるわけにはいかない。
当人になりきって書くと言いながら、じつは膨大な資料、特に日記と手紙を綿密に読みこみ、その行間にかいま見える真実を丹念に掘り起こしているからこそ「ここまでは書ける」という奥行きが深いのであって、独りよがりな創作をしているのとは訳が違う。
註の付け方など編集者として注文を付けたい部分はあるものの、評伝寄りの立場から時代を俯瞰するという観点で奈良岡さんの大著もじつによく出来ていると感じる。
本書は、悪名高い対華二十一カ条要求や三菱財閥とのズブズブの関係など、どうにも評判の芳しくなかった加藤高明という人物を徹底的に調べ上げ、その実像と、憲政会という政権を担うことも可能だった第二党の関わりを明らかにしようとする意欲作だった。
多少心得のある人ならば、本書の特徴の第一として資料の精査に傾ける執念を挙げるはずだ。
この時期を語る際に軸となるのは常に原敬であり、それは『原敬日記』(福村出版)をはじめとする膨大な史料に跡づけられている。
一方、日記がない、手紙がない、とにかく一次史料が少ない。ゆえに原のライバルである加藤に対する風説や印象批評は絶えなかった。
本書の執筆に際しおこなわれた、限られた一次資料の洗い直しと執念の再発掘、二次史料の徹底した読み込みによって加藤像は大きな変更を迫られた。イギリス二大政党制を信奉する理念の政治家として生まれ変わったと言っていい。
本書に対する御厨貴さんの書評(毎日新聞二〇〇六年一〇月八日)に印象的な一文があった。
「著者は加藤に思い入れをしつつも、筆の運びはさらりとしている」
だがどうしたことだ。奈良岡さんがどれほど抑え込もうとしても、素っ気ない筆致から立ち上がってくる加藤高明の曰く言い難い魅力は。
服部さんが幣原喜重郎に向ける視線にも、奈良岡さんが加藤を眺める眼差しと似たところがありそうだ。
吉田茂や重光葵といった戦後史上の著名人に押されて目立たないが、日本の外政家として明治・大正期、昭和戦前期、戦後、という三つの時代に外交のフロントラインで活躍したのは幣原のみ、との指摘には一瞬、胸を衝かれる。
厳密に言えば本書の主人公は「外務省による一元的外交」なのである。他方、幣原という一人の外交官が国内外の環境変化に合わせて成熟していく様が描かれているとも考えられる。
アメリカに広がった人的ネットワークを利用したメディア工作もなかなか興味深いが、超党派外交への強い思いには圧倒される。
外交を政争の具に上らすのは「日比谷」の昔から日本の野党、メディア、世論の宿痾であり、現実政治の観点から見ればオール与党の超党派外交など空論でしかない。
それは第二次世界大戦後の安全保障について、全面講和論と単独講和論のどちらがより現実に沿っていたかを思い返すだけでも明らかだろう。
ただ、そうした理念を敢えて奉じてやまないところに人間幣原の骨頂はある。その姿はどこかで君塚さんの描くパーマストンや細谷さんの描くイーデンと重なってくる。
加藤も幣原も若き日と晩年では主張に異なる部分がある。それは変節ではなく、達観や成熟のもたらした大局観なのだろう。
硬軟織り交ぜた駆け引きを要する外交の世界と、そこに生涯を捧げる外政家たちの姿からは、手本とも反面教師ともなりうる国民国家、官僚、政治のあり方が透けてくるように思われる。
優れた史家の手になる歴史を読み、物語として楽しみ、さらには自身の問題に引きつけて考えることができるようになれば、SNS上の不毛な床屋政談も多少なりと改善されるのではないか。
そんなことをつい考えてしまう、うららかな春の午後である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
