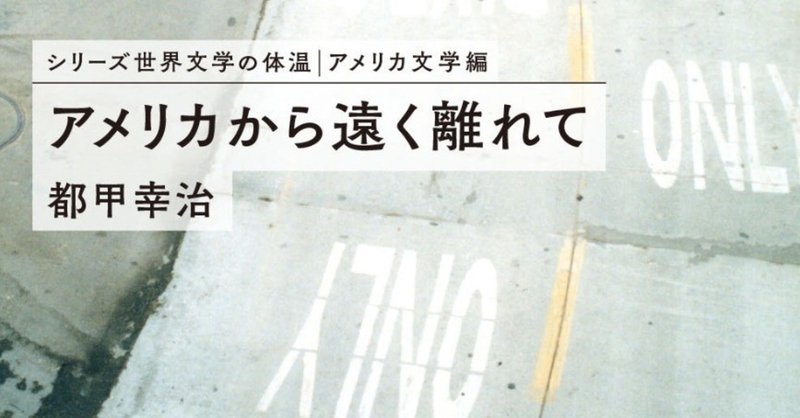
第4回 相性がいちばん(都甲幸治)
3年生になると進学先を選ばなくてはならない。法学部は向いてないから行かないとして、さあどうしよう。そこで僕が最初に考えたのが文化人類学だ。そのころ山口昌男に憧れていて、レヴィ=ストロースも読んだりして、こういうのもかっこいいな、と思っていた。
でも、船曳建夫先生と話していると決意がグラついてきた。いや、やめろと言われたわけじゃないんだけど、文化人類学ウラ話がすごいのだ。先生がニューギニアの集落に長期滞在して調査したときの話を聞いた。
集落に滞在といっても、よそ者である先生は村の中には住ませてもらえない。しょうがないから村はずれに小屋を建てて、その中で暮らしていた。楽しみは日本から持っていったインスタント味噌汁で、とにかく病気にならないようにだけ気をつけていた。
いったん重い病気になってしまうと大変なことになる。だって近くに病院なんてないんだから。というわけで、何年かに一回は盲腸などの病気になった文化人類学者が亡くなることになる。病院まで何日もかかかって運ぶ間に、日本では普通に助かる病気でも死んでしまうのだ。
うーん。ここまで言われて、それでも文化人類学をやりたい! と言う勇気は無いよ。もっとも今では、都市や若者のエスノグラフィとか言って、日本国内でも十分、文化人類学の研究はできるらしい。そんなの最初から言ってよ。
理論もアートも文学も好き、という僕は進学先を一つに絞りきれなかった。そこで登場したのが表象文化論という学科だ。ここは地域やジャンルを問わず、いろんなことが研究できるらしい。しかも僕にとっては高校時代のヒーローである蓮實重彦先生もいる。ここにしよう。
結果から言えば、この決断は失敗だった。もちろん蓮實先生をはじめとする教授陣は日本一のレベルで、学生たちも優秀な人ばかりだ。だから問題は僕だけにあったことになる。簡単に言えば、何でもできる学科なんてこの世界には存在しない、という一言に尽きる。つまりは、文科一類に進学したときと同じ間違いを繰り返してしまったわけ。
説明しよう。以前書いたように、何でもできる学科に進学したところで、必要とされる勉強量は膨大で、とても同時にいろいろなことなどできるわけがない。これは学生の方の問題だ。
そして教授陣に関してだが、全てを知っている先生なんているわけない。したがって、自分の専攻に近い部分はきちんと教え、遠い分野はだいたいで指導することになる。そうやって指導した学生がさして伸びてくるわけもない。
教師から見てよくわからないことをやっていて、しかも大したレベルに達していない学生と、教師とバッチリ同じ専攻で、さらにはけっこう良いものを書いている学生がいれば、後の部類の学生の方が優秀に見えるのは当然である。こうした学生だったら、ゆくゆくは自分の学問を継いでくれるかもしれない。
さあ、結果は明白ですね。当時の僕のような、自分の好きなものを決めきれずいろいろと手を出している学生と、教員の専攻をしっかりと調べ、それと合った研究を集中してやる学生とは、教員の評価がまるで違う。
もちろんただいろいろと勉強することはできる。でもしっかり教師に評価され、ゆくゆくは研究者にでもなろう、という気持があるのなら、話は違ってくる。いかなる学科であろうが、何でもできる、という謳い文句には欺されず、しっかり教授の専門分野を調べて、ピンポイントでこの人につく、と決めて進学するのが唯一の正解だ。そのことが僕には分かっていなかった。
もちろん表象文化論の授業で学んだことは多い。狂言師の野村萬斎さんの授業では、足袋を履き扇子を持ち、実際に動きながら謡を歌ったりした。渡辺保先生の歌舞伎の授業も楽しかった。
でもやっぱり表象文化論は仏文出身の先生主体の学科で、フランスの文学やアートに気持ちが向いていかない自分は居心地が悪かった。自分では気づいていなかったんだけど、当時から外国語は英語、音楽や文学はアメリカ、という方向性が僕の中にきっぱりあったんですね。
授業で発言をしてもすべりまくり、こいつはだめなんじゃないか、と周囲から見られていた僕にとって、唯一の安住の地は、たまたま通い出した柴田元幸先生の授業だった。何というか、ここでは話を聞いてもらえるし、運が良ければ褒めてももらえたのだ。
出会いは偶然だった。当時つき合っていた人に、都甲君、この時間空いてる? と聞かれて、たまたま通い始めたのだ。彼女はその後すぐに授業からいなくなったので、純粋に僕を柴田先生に引き合わせてくれた人、ということになる。
そのころ僕は柴田先生のことは知らなかった。表象文化論ではなくアメリカ科の先生だったし。というと、今では変に聞こえる。アメリカ文学、というより外国文学の研究者で日本一有名な人なのだから。けれども当時は先生も若かった。35歳ぐらいじゃないか。まだオースターの翻訳なんて影も形もなくて、モリス・バーマンの『デカルトからベイトソンへ』というデッカい本を国文社から出しただけだった。
先生はちょっと暗めの感じで、カフェテリアで先生の席に押しかけて無理やり一緒にご飯を食べても、僕が喋りすぎると「その話、僕が聞かなきゃならないやつかな」なんて言われてしまう。けれどもこっちが黙っていると、「大学の先生は向いていないと思うんだ。そのうち辞めたい」なんて言い出す。
そのころ、柴田先生はイエール大学での留学を終えて、東京学芸大学から東大に移ってきたばかりだった。でも威張るわけでもなく、むしろ自分は大田区の工業地帯出身だから、と、インテリ上流階級出身でないことを強調していた。
当時の偉い先生方は、家が代々、大学教授とか政府高官とかいうのが当たり前だったから、柴田先生の感じは新しかった。つまりは普通だったということだ。育ちが普通で、ロックなどを普通に聞き、普通の青春を送る。お金持ちでも貧乏でもない。だからこそ、普通の人の気持ちがよく分かる。
柴田先生がその後、翻訳やエッセイで一世を風靡したのは、こうした普通の感覚を持つインテリとしては日本で最初の世代だからではないだろうか。少なくとも授業に出ていて僕はとても楽だった。
ヨーロッパの哲学もアートも遠い、背伸びしても届かないような存在だったけど、ロックなら中学時代から聞いている。そして柴田先生の授業ではロックの歌詞の延長のような現代アメリカの短篇を次々と読んでいった。
授業のやり方はこうだ。10ページくらいの短篇を各自プリントで読んでくる。出席者は5人から10人くらいかな。最初に先生が「それじゃあどこからでも」と言うと、みんなが自分の読みを話し始める。
会話に詰まると、先生が作品の背景や作家の説明を解説し、ここが読みどころだ、みたいな解釈を示す。それでも先生の読み方が唯一の正解なわけでもなくて、学生の意見も聞いてもらえた。
もちろん、アメリカの大学院に行った後なら、この授業のやり方が典型的なワークショップ形式だとわかる。けれども、当時こういった授業の進め方をしている場所はあまりなかったのではないか。
昔は文学の授業は文学史や定説となっている解釈の説明を教員がするだけのものだったらしい。それを学生が熱心にメモを取る、暗記する、試験で再生する、終わり。それが意味がないとは思わないが、教えている方も聞いている方も退屈だろう。
しかし柴田先生の授業は違った。みんなで作品の読みを練り上げて作っていく、という実感があったのだ。そこでは、正解はどこか自分の外、あるいはもっと言ってしまえば、アメリカのどこかにあるわけではない。
自分の中に作品を落とし込んで、それを今までの経験や思索と対話させながら自分なりの解釈を生み出す。それをぶつけ合い、より読みを掘り下げていく。どんなに年が若かろうが、経験が浅かろうが、出席者の発言は無視されることはない。そして良いものは採用され、みんなで共有される。
言い換えれば、ここには僕の居場所があった。自分自身が授業に貢献できると思えば、予習にも一生懸命になれた。英語力の低さも気にならなかった。もっと語学をがんばって、もっと作品を読もうと思えた。要するに、僕はこの授業にまんまとハマったわけである。
それまで文庫本で買える日本文学や外国文学の古典を読んでいた僕にとって、柴田先生の授業で扱う作品のラインナップも刺激的だった。ポール・オースター、スチュアート・ダイベック、イーサン・ケイニン。こんなに良い作家が現代アメリカにはたくさんいるのか、と毎週が驚きだった。世界が広がっていく気がした。
今思えば、柴田先生はこの授業で作品を試し、学生の反応を見てから翻訳していったのではないか。彼がその後、訳書を出していった多くの作家を、何も知らない僕らは先行して読んでいった。そしてひたすら楽しみ、笑い、大いに論じた。自分の学科ではサッパリだったけど、これはこれで幸福な時代だ。
柴田先生の授業には、僕と同じように行き場をなくした感じの人たちが集まって来ていた。フリッパーズ・ギターを解散したあとの小沢健二さんもいたし、フランス文学や思想を研究しながら小説家を目指していた小野正嗣さんもいた。サントリーのOLを辞めたばかりの岸本佐知子さんもモグっていた。
というと、なんだか豪華な場だった感じがするけど、それはあとから振り返ってのイメージだろう。みんなどうしていいかわからなくて、でも何かはできそうな気がして、作品の読みに載せて自分の思いをはき出すために通っていた。
確かにここで面白いことが起こっているのはわかるけど、それが何だか分からない。こんなことをしていて、将来が開けるかどうかもわからない。当時の柴田先生の授業は、そういう感じの場だった。言うなれば、大学という場所に生まれた、ちょっとした自由な遊び場というか。そして人生に迷っているのは柴田先生も同じだった、と思う。
大学卒業の時期が来ても、僕はまだ進路に迷っていた。そして適性がないと分かっていたのに、そのまま表象文化論の修士に進んでしまった。これが三度目の間違いである。当時の僕は、相性が合わない場所でも、がんばればなんとか克服できるんじゃないか、と勘違いしていた。
正直言って、人生においてがんばればどうにかなることなんてそうはない。がんばりが通じるのは受験ぐらいなものだ。あとは恋愛でも仕事でも、相性が合わなければずっと合わないまま、人はどんどん追い込まれていく。がんばっても仕方がないのに頑張り続けるから、やがては鬱になるしかない。
どうして学校の先生は相性ってことを教えないのか。結局、居づらい場所からはさっさと逃げたほうがいいし、上手くいかない恋愛はがんばっても意味がない。不得意科目を克服している暇があったら、少しでも得意なことを伸ばすのに集中すべきだ。でもそのころの僕は、そんな簡単なこともわからなかった。
修士進学後、僕は学科の勉強へのモチベーションをどんどん失っていった。そしてあまり授業にも出られなくなってしまった。その一方で、気に入った授業は熱心に通った。
言語情報科学の小森陽一先生の授業では、谷崎潤一郎の『文章読本』を集中して読んだ。授業中に聞いた、先生のチェコでの子供時代に関する話は、その後『コモリくん、ニホン語に出会う』(角川文庫)として本になった。比較文学の内野儀先生の授業では、戦前に書かれた、植民地が舞台の日本の戯曲を読んだり、『ハムレット』の各種翻訳をひたすら原文とつき合わせたりした。
こう見てくると、大学院時代に学んだことすべてが今の仕事に生きているとわかる。問題は、僕が出ていた全ての授業が表象文化論以外のものだったことだ。そして僕の学科内での評価は限りなく下がっていった。やがて博士課程に進学する頃には、もう出願するのはやめようか、と思うぐらいになっていた。
すべてに自信を失った僕のところに、千載一遇のチャンスがやってきた。今は社会学者になっている坂口緑さんと一緒に、柴田先生に廊下に呼び出された僕は、ブコウスキーの長篇を訳してみないか、と言われた。
もちろん、やります、と答えた。どうして先生が僕に声をかけてくれたのかはわからない。他にももっと英語ができる人はいくらもいたしね。結局は、エッチなシーンが多いほうを僕がやることになり、坂口さんはもう一冊の方を担当することになった。なんだそれ?
こうして僕の翻訳第一作、ブコウスキー『勝手に生きろ!』が誕生することになる。でもそれまでにはまだまだいろいろあった。
プロフィール

都甲幸治(とこう・こうじ)
1969年、福岡県に生まれる。現在、早稲田大学文学学術院教授、翻訳家。専攻はアメリカ文学・文化。主な著書に、『偽アメリカ文学の誕生』(水声社、2009年)、『21世紀の世界文学30冊を読む』(新潮社、2012年)、『狂喜の読み屋』(共和国、2014年)、『読んで、訳して、語り合う。――都甲幸治対談集』(立東舎、2015年)など、主な訳書に、ジュノ・ディアス『オスカー・ワオの短く凄まじい人生』(共訳、新潮社、2011年)、同『こうしてお前は彼女にフラれる』(共訳、新潮社、2013年)、ドン・デリーロ『天使エスメラルダ』(共訳、新潮社、2013年)、同『ポイント・オメガ』(水声社、2018年)などがある。
「アメリカから遠く離れて」過去の記事
第1回 聖書と論語
第2回 サリンジャーの臙脂色の表紙
第3回 すね毛と蚊
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
