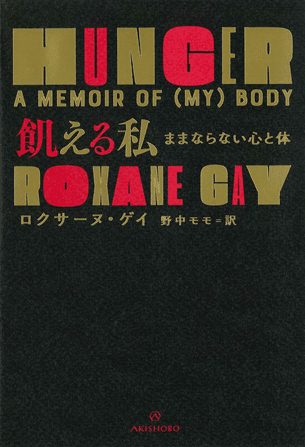【試し読み】日野原慶「FATをめぐるものがたり(2)──ふとっていることの語源学(エティモロジー)と物語学(ナラトロジー)」(『現代アメリカ文学ポップコーン大盛』より)
モノとしてのファット ものがたりとしてのファット
fat――「動物のからだのふくよかな部分を主として構成する、油を含んだ固形物質」(OED『オクスフォード英語辞典』)
名詞の「ファット」は脂肪を指す。物質としての脂肪。脂肪そのものが目の前におかれたとしたら、それに触れることができる。脂肪そのものと、それ以外のものとを、区別することもできる。
fat――「好ましくない意味合いで:脂肪をため込み過ぎた、ぶくぶくとふとった、肥満の」(OED『オクスフォード英語辞典』)
形容詞の「ファット」はひとを主語にとる(I am fat / You are fat)。そのとき指ししめすのはひとの状態で、この状態とそうではない状態との境界は、容易にはさだまらない。時代、文化、社会のありかたがことなれば、その境界線の引きかたは異なる。くわえて、ひとそれぞれのとらえかただって異なるのだから、その境界線は主観的にいかようにも引かれうる――他人に対しても、自分自身に対しても。
「美しさ」とか「幸福度」とかを測定するゆるがない基準などが存在しえないように、「ふとっている」という状態の厳密な範囲をさだめることなどできない――はずだ、いや――はずだった。しかし現実の世のなかに目を転じれば、すくなくともわたしが生きる社会や、この連載であつかう文学テクスト群がうみだされた社会において、ファット/ふとっていることが、ある集団を含み、その他の集団をのぞくカテゴリーとして存在することは言うまでもない。
「体重÷身長×2」――これは、そのカテゴリー化に用いられる装置のひとつだ。BMI/Body Mass Indexとよばれるその数値は、いつからか、ひとのからだの状態の指標となった。個別のからだがどの程度「平均的」な身体からずれているのか、その結果どの程度「病」を引き起こす可能性があるのか、それをはかるものさしとして用いられている。
ちなみに、上で「いつからか」と書いたが、当然のことながら、実際にはBMIがそのようなものさしとして扱われるようになった歴史がある。ファット・アクティビズムの現場におけるフィールドワークを通して書かれた研究書『「ファット」の民族誌:現代アメリカにおける肥満問題と生の多様性』(2018年)で、碇陽子はその歴史について(67-68ページ)、そして、その指標のただしさのあやしさについて、読者に明快な解説をあたえてくれる。
再度確認しておくべきは、肥満予防対策で頻繁に依拠される統計的データは、集合に内在する規則性について語っているのであり、個別事象の原因と因果の関係を示しているのではないという点である。しかしながら、統計的データを個人に当てはめ因果的に解釈することの問題性についてはほとんど無自覚のまま、「正常」「異常」などを割り当てる根拠として、BMIは利用されている。なぜなら、社会的リスクを、個人が責任を負うべきリスクとして認識させ、個人にリスク回避・予防のための行動形態をとらせる必要があるからだ。(69ページ)
相関関係と因果関係とのちがい、統計的データとしてのリスクとひとが実際に直面する危険性とのちがい――これらの位相のちがいを無視することで、ふとっているというカテゴリーに、「責任vs無責任」「理性vs非理性」「しっかりとしたvsだらしない」……などのものがたりが縫いつけられる。つまり、ふとっている状態と病との明白な因果関係を考慮せずor考慮できず、ふとることを選んだor選ばずにいることができなかった無責任な主体として、そのカテゴリーに含まれるひとびとに不当な烙印が押されることになる。
ふとっていることへのこのようなスティグマタイゼーション(stigmatization=汚名を着せること)に抵抗しようというのが、前回の連載で紹介をしたアメリカを運動の中心とするファット・リベレーション、ファット・アクセプタンスや、それらの影響のもとにある人文学的な研究、文学テクストに共有された姿勢だ。もちろん、さまざまなかたちで。
バイアスのかかった客観性
客観的であることを装うカテゴリーは、じつのところ対象を分類し区別するだけでなく、ときに過剰な、ときに不当で不正確な意味づけの温床となる。おなじ状況は「ファット」ということばの定義にもみられる。今回の記事のはじめに引用をした形容詞としての「ファット」の定義を、OEDはごていねいに“in unfavourable sense”=「好ましくない意味合いで」という言葉ではじめている。ひとびとの共通理解は、辞書がことばに与える定義に客観性をもとめる。でも「意味合い」にかかわるこの箇所は、そのような客観性をおびているといえるのだろうか?
obese――「とてもふとった、にくづきのよい; 抜きんでてふとった」(OED『オクスフォード英語辞典』)
このことばも、ふとっている状態をあらわすのによくもちいられる英単語だ。ただ、「ファット」とはつかわれる文脈が異なる。「オビース」(obese)のほうは、公衆衛生の分野やそれにかかわる話題において、ふとっていることが「病」とみなされる――「病理化」(pathologize)される――ときに多用される。2000年代に入り、公衆衛生の「敵」としてふとっていることが病理化されていったアメリカで、ひろくつかわれるようになったのはobesity epidemicつまり肥満症ということばだ。「エピデミック」は本来、感染症を意味する。ふとっている状態は、当然のことだが、感染しない。20代のころアメリカにいったわたしは、なんとなく科学的で客観的な雰囲気のただよう「オビース」のほうが、「ファット」にくらべニュートラルなことばであるように思い、ふとっていることが話題にのぼるときには、意識して前者をつかった。
でも、語源を見てみると、こちらの方にも特定のものがたりがうめこまれていることに気づく。ふたたびOEDを引いてみる。英単語のobeseは、ラテン語のobesusに由来し、これはobedereという動詞の過去分詞(動作の完了・受身の状態)だ。このobedereは、「~に向かって」や「~に反して」をあらわす接頭辞ob-と「食べる」という意味のedereからかたちづくられている。接頭辞ob-は「食べる」のedereにかかり、その意味を強める。英語におきかえるとしたら、over+eat=「食べ過ぎる」が適切だろうか――食べるという行為の正常な範囲(このような範囲自体も、明確に区切り設定することが可能なのか考えてみたくなる)からはみだして、食べること。obeseには、そういう具体的な行為のありかたが、痕跡としてきざまれている。
踏み込んで考えるならば、食べるという行為は個人でおこなう行為だから、ふとっているという状態を、食べるという行為に結びつけることは、その状態が個人の行為の結果であるという前提をもつことにつながりうる。みずからの食を管理できない無責任なひと――そういうものがたりが語源のレベルで喚起されはしないか。考え過ぎだと言われればそうかもしれない。ただ「オビース」がニュートラルなことばだと信じていた過去のわたしには、このことを教えてあげたいとはおもう。
『バッド・フェミニスト(Bad Feminist: Essays)』(原著は2014年、翻訳は2017年、野中モモ訳)の著者として知られるロクサーヌ・ゲイ(Roxane Gay)も、obeseという単語については、語源レベルでそこまでややこしく考えているわけではない。でも、もっと明白な暴力性をこの単語に感じている。『飢える私:ままならない心と体(Hunger: A Memoir of (My) Body)』(原著は2017年、翻訳は2019年、野中モモ訳:以下の引用もこの翻訳からのものです)で、「病的肥満(morbidly obese)」という言葉を取り上げて、彼女はつぎのように書いている。
こうした用語の数々はもうそれ自体がなんだか恐ろしい。「肥満(obese)」は不愉快な言葉で、「太るまで食べた」を意味するラテン語の「オベサス」に由来している。これは文字通り、理に適っている。しかし人々は「肥満」という言葉を使う際、ちっとも文字通りの意味では使っていない。彼らは非難を指し向けている。そもそも患者を傷つけないようにするべき医師たちがこうした用語を思いついたというのは奇妙だし、おそらく悲しいことだ。修飾語「病的」は、実際そういうわけではない場合にも、太った体を死刑宣告と等しいものとする。「病的肥満」という用語は私たちのような太った人々をまるでゾンビか何かのように仕立てあげ、医療機関は私たちをそのように扱う。(14ページ)
医療の文脈でも問題視されることなく使われる「オビース=肥満」ということばが、病による死を結末に用意するものがたりの主人公として、ふとっているひとを「仕立てあげ」るための装置であることを、ゲイはうったえている。
同じ認識は、現代のファット・アクセプタンス運動においても共有されている。運動の流れを汲んだファット・スタディーズのアンソロジーThe Fat Studies Reader『ファット・スタディーズ・リーダー』(2009年)の序文で、ファット・アクティビストのマリリン・ワン(Marilyn Wann)は次のように書いている。
ふとったひとたちを「オビース」と呼ぶことは、人間の多様性を医療化(medicalize)してしまうことだ。多様性を医療化してしまうことは、自然に生じているだけの差異に対する「治療方法」をさがしもとめるという、見当違いの試みに火をつける。体重の医療化は、ファットなひとびとへの共感をうむどころか、社会のあらゆる領域でファットにむけられた偏見と差別に燃料をそそぐことにつながる。(xiii)
「オビース」の例にみることができる、ふとっていることのカテゴリー化、病理化、医療化――特にそれらが行使する客観性をよそおった暴力――に、人文学の立場から抵抗することがファット・スタディーズの中心的な問題意識であるといえる。
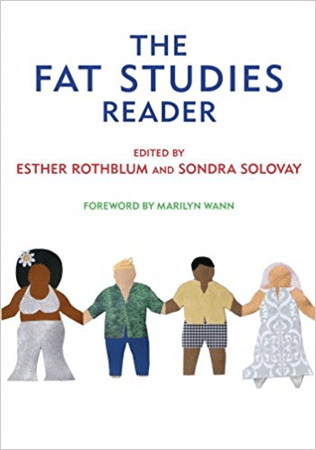
抵抗のためのものがたり構造
上で紹介したアンソロジー『ファット・スタディーズ・リーダー』では、どのような抵抗の実践が人文学の立場から可能なのかという点について、さまざまな提言がなされている。特に興味深いものとして、ほっそりとしていることを良しとする社会において規範となるような「時間性」(temporality)をずらし、その流れを挫くことの有効性を論ずる議論がある。「クイアな歴史をファット化する(“Fattening Queer History”)」という論文で、エレナ・レヴィ・ナヴァロ(Elena Levy-Navarro)は次のように書く。
特定の非-規範的なアイデンティティ――ファットはここに含まれる――を軽んじる歴史とは、ある現代的な時間性の理屈にしたがっている。その理屈においては、時間というものが、はばまれることなく流れる直線的な原因と結果の連鎖としてとらえられることになる。(17ページ)
ファットなひとびとは歴史そのものだ――そのこころは、不可避に到来する未来に向かうわたしたちの前進のなかで、それらのひとびとは放棄されなければならない過去であるということだ。(18ページ)
ダイエット商品やプログラムのCMを思いうかべると、この主張のポイントがわかりやすくなるかもしれない。そのCMにはおなじ人物をうつした二枚一組の写真がくりかえしあらわれるだろう。一方には、ふとっていたころの「過去のわたし」がいて、もう一方には、やせた「現在のわたし」がいる。やせた「現在のわたし」は、より健康で楽しみにあふれた「未来」を約束されている――ほっそりとしていることを理想とする社会・文化では、これが、非-ファットで規範的なものがたり構造となる。
たとえば、ここに男女の恋愛・結婚というようなエピソードが加われば、そういう社会・文化で大衆ウケするであろう反ファットかつ異性愛的なナラティブが完成する。現代の日本においても、そういうものがたりを思いだす/想像することは、むずかしくないはずだ。
『飢える私』の冒頭で、ゲイが「勝利の物語」という言葉で示唆しているのは、そのようなナラティブであると言える。
私の体の物語は勝利の物語ではない。これは減量体験記ではない。ここに痩せた私の写真があらわれることはないだろう。この本の表紙で大々的に褒め称えられるほっそりした私、かつての太っていた自分のジーンズの片足の中に立つ私の姿はない。これはやる気を与える本にはならない。私には、ままならない体とままならない食欲に打ち克つために必要なものについての自信に満ちた見識なんてまったくない。私の物語はサクセスストーリーではない。私の物語は、ただただ、本当の話。(6ページ)
誰もがたやすく想像できる規範的な、「勝利の」ものがたり構造を反復しないオルタナティブなものがたりを想像/創造すること。規範的なものがたりを支配する時間性をずらすこと。挫くこと。「勝利の物語ではない」とは、そういう意志の表明とも読み取れることばだ。でも、このままただしく抵抗的なものがたりが紡がれていくのか?――ゲイのテクストはそう素直ではない。ゆえにとても面白い。
次回の記事では『飢える私』を中心として、ファットをめぐる文学テクストのいくつかを、この観点から考えていきたいと思う。規範的なものがたり構造/時間性と、それへのオルタナティブという、すこし単純な図式ではあるが、ひとまずそれにのっとって考えてみたい。結果、ファットをめぐる文学テクストたちのなかにある類似点と、ゆたかな差異に気づくことができのではないかと思う。つづく。
引用文献
“fat.” The Oxford English Dictionary. 2nd ed. 1989.
“obese.” The Oxford English Dictionary. 2nd ed. 1989.
The Fat Studies Reader, edited by Esther Rothblum and Sondra Solovay. New York University Press, 2009.
碇陽子『「ファット」の民族誌:現代アメリカにおける肥満問題と生の多様性』明石書店、2018年
ロクサーヌ・ゲイ『飢える私:ままならない心と体』野中モモ訳、亜紀書房、2019年
執筆者紹介
日野原慶(ひのはら・けい)
大東文化大学にてアメリカ文学を研究。特に現代のアメリカ小説を対象にエコクリティシズムと呼ばれる環境に焦点を当てた文学批評をおこなっている。ごく最近のアメリカ小説などにも関心をひろげ研究対象としている。
*****
この記事の収録書籍
『現代アメリカ文学ポップコーン大盛』
青木耕平、加藤有佳織、佐々木楓、里内克巳、日野原慶、藤井光、矢倉喬士、吉田恭子
A5判、並製、376ページ 定価:本体1,800円+税
ISBN 978-4-86385-431-4 C0095 2020年12月刊行
文学からアメリカのいまが見えてくる。更新され続けるアメリカ文学の最前線! 「web侃づめ」の人気連載ついに書籍化。ブラック・ライブズ・マター(BLM)、ノーベル文学賞を受賞したばかりの詩人ルイーズ・グリュックなど最新の動向についても大幅に増補した決定版。座談会「正しさの時代の文学はどうなるか?」(ゲスト:柴田元幸さん)を収録。
http://www.kankanbou.com/books/essay/0431
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?