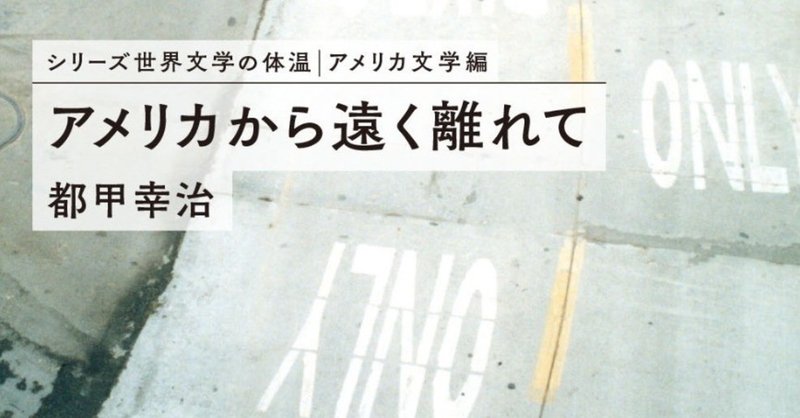
第3回 すね毛と蚊(都甲幸治)
大学にはうまく馴染めなかった。そもそも、小説や批評に興味があって、そうしたことを漠然とやりたいと思っていたのだが、それなら文学部でしょう、とは思えなかった。高校生の僕は哲学にも社会にも興味があって、入学時に自分の方向を決めてしまいたくなかったのだ。
調べてみたら、東京大学なら文科1類だと、3年生で専門課程に進学するときに、いちばん選択肢が多いらしい。しかも入るのもいちばん難しい。挑戦するなら最難関で、しかも可能性が広がる場所、と考えて願書を出し、なんだかすんなり入ってしまった。
今思えばこれが間違いだった。選択肢が多いのと、実際に多くのことができるのとは違う。大学の勉強は高校と違って専門性が高い。だから、文学なら文学、しかも英文学のように絞らないととても学びきれない。しかも最難関の学部が自分に合っているとは限らない。でも高校生の自分には、そうした大学の常識などわかるわけもなかった。
結果、大変なことになった。もちろん僕以外みんな知っていたように、文科1類は事実上、法学部だ。だから当然、法学や政治学を学び、将来は国家公務員として霞ヶ関で働きたい、あるいは丸の内の大企業に就職したい、という人ばかりがいる。そして彼らの多くは文学にも哲学にも興味がない。
ならば何に興味があるかと言えば、男女交際である。学生時代の人脈作りである。権力やお金である。もちろん法学や政治学もだけど。そして現実感のない僕はこうしたことには興味がない。というわけで、きちんと考えたつもりが、最も行ってはいけない学部に入ってしまった。
当然、友達ができない。いや、そこそこ社交的なので知り合いはできるのだが、そこから関係が深まっていかない。とにかく話が合わないのだ。しかも授業が面白くない。900番教室という、なぜかパイプオルガンがある大教室で法学や政治学の授業を受けていたのだが、そもそもなんでこうしたことを学ばなければならないのかわからない。
たとえば法学の授業に出ると、先生がこんな話をしてくれる。隣の家の木の枝が塀を越えて自分の家まで伸びてきました。秋になると、その枝から紅葉した葉が落ちてきて困ります。でも、木の所有権はもちろん隣家にある。さて問題です。その葉を掃除する義務は自分と隣人のどちらにあるでしょう。そして、勝手に枝を切ってしまったらどんな問題が起こるでしょう。
今思えば、とても良い授業である。身近なテーマを例に、所有権や法的な正義についてわかりやすく的確に教えてくれていた。でも当時の僕はこう思った。そんなことどうでもいいよ。隣人とちゃんと仲良くして、話し合って決めろ。人生には、それよりももっと大事なことがたくさんあるだろう。
もちろん、それよりも大事なことがたくさんある、というのは僕の偏見である。『論語』を読み、小説や批評を読んできた僕がそう思っただけで、隣家とのトラブルは現実においては非常に重要だ。そして現実を生きる我々にとって、そうしたことを考える法学は決定的に大事である。でもそのとき僕には、心底どうでもいいことを延々と話しているとしか思えなかった。要するに、適性がなかったんですね。
というわけで多くの授業が僕には苦痛だとわかった。特に、大人数授業で前の席に座っている学生の後頭部を見つめ続けながら、どうして僕はこんなところにいるんだろう、と思った。こんなことをするために大学に来たんじゃない。でも、それじゃあ何をするために来たのかはわからなかった。
こんなふうに思う多くの学生がハマるのはサークルだろう。しかし、サークルも僕の安住の地にはならなかった。高校時代の同級生で、一緒に文科1類に入学した友人が、神社仏閣巡りのサークルに誘ってくれた。神社の境内のしんとした感じや仏像の表情に惹かれていたから、試しに入ってみた。
けれども、これも完全に浮いてしまった。僕みたいに、祝詞を唱えてみたい、一度は座禅してみたい、そしてできれば悟りたい、なんて思っている人は誰もいない。要するに、親睦を目的とした、というか彼氏彼女を探すためのサークルで、いろんな女子大の学生なんかもいて、わりと派手な飲み会をする感じの場所だった。
そこで僕は間違った話題を繰り出し続けた。ニーチェの『ツァラトゥストラかく語りき』を読んで超人について考えたとか言っても、サンチェなら知ってるけど、なんて言われて笑われてしまう。サンチェというのは当時、読売ジャイアンツにいたルイス・サンチェスという選手の愛称ですね。僕は自分の実存をかけて話しているのに、80年代とんねるず風大学生ノリの笑いで返される。地獄。
というわけで、早くも大学1年で僕は居場所を完全に無くしてしまった。こうなると、普通は退学したりするんでしょうか。悲しい。けれども、二人の教師が僕を救ってくれた。文化人類学の船曳建夫先生と、アメリカ文学の柴田元幸先生である。
今思えば、何気なく出席してみた船曳先生の儀礼・演劇ゼミが僕の人生の方向を決めた。授業にもサークルにも馴染めなかった僕だが、ここでは全てが肯定されたのだ。ゼミ内容は、学部横断的に集まった学生が週に一回、輪になって座りあれこれ話す。そして企画を立て、東京でやっている演劇やスポーツなどを見に行く。年に一度は合宿もある、というものだった。
要するに、文学や文化が好きな学生が集まって好きにしゃべり、活動し、なぜかそこに先生も入っている、という奇妙なサークルだった。基本コンセプトは文化人類学の立場から現代日本を調査分析する、というものだったのだろうが、学生の誰もそんなことは思わず、というか先生も思わず、そのときのメンバーが持ち寄ったアイディアを実現すべく、しゃべったり動いたりするだけだ。
僕にとっていちばん印象深かったのは、文化祭でやった女装喫茶だった。僕が女将になり、他の男子5人ほどもそれぞれ女装して、お客さんの相手をする。出すのは抹茶と和菓子のみ。最初はただ好奇心で挑戦したのだが、やってみるとものすごく大変だった。
まずはすね毛を剃るところから始めた。もともと僕は中高生のころからすね毛が濃くて、体育の授業で校庭に座っていたら、隣にいた女子グループに「都甲君って顔のわりに毛深いねー」と言われたほどである。顔のわりにって何だ? もっとも、あるとき僕の脚を刺そうとした蚊が、皮膚に到達することなくすね毛のジャングルの中で死んでいた、なんてこともあった。
その剛毛をT字のカミソリで剃るのである。刃が毛に負けて、何本も剃れなくなった。それでも最後は脛から腿までツルツルにすることに成功した。色白の自分の脚を見て、なんだかセクシー、と思ったのを憶えている。ちなみにだが、そのあと再び生えてきたすね毛は、決して最盛期の勢いを取り戻すことはなかった。
次にメイクである。髪のセットである。下着である。完璧に女性をシミュレートすることを目指した我々は果敢に課題に取り組んだ。しかしながら、その過程は困難を極めた。メイクは複雑で長い時間がかかり、セットした髪はベトベトで、ブラジャーは肺を締め付け、極度の呼吸困難をもたらした。要するに体に合っていなかったわけですが。
ついに憧れのセーラー服を着てみた。がっかりした。セーラー服は外から眺めていれば可愛い。しかしながら実際に着てみると、手首やウェストなどおかしなところがすぼまり、その間の部分はぶかぶかで、しかも生地は通気性が悪く、すこぶる着心地が悪い。一体、暑いんだか寒いんだかわからない。誰がこんなに実用性の低い服を考えたのか。
二日目からは制服は諦め、着物に挑戦してみた。しかしこれも辛かった。複数の紐で胴体をギュウギュウ締め付ける。呼吸も食事もあったものではない。なんだこれは。普段ジーンズにTシャツ、パーカーというスタイルの僕にとって、女性用の服は和風も洋風も、想像を絶して辛かった。靴だけはローファーで勘弁してもらったが、ヒールも履いていたらもちろん、辛さは2倍だっただろう。
世の中の男性たちも、女性の活用なんて言っている暇があったら、短期間でも女性として生きて、世間の視線に曝されてみればいい。実際に経験すれば、現代日本で女性であることがどんなに困難かが、ほんの一部なりともよく分かる。これだけでも僕にとっては大いに収穫だった。
さて、開店して接客本番である。入店してくるのは女の子3人組、みたいなグループが主で、そこにカップルや男性グループが混じっていた。服装は女性のものだったが、いわゆるオネエ言葉は使わなかった。予想通り、女性客にどうしてオネエ言葉ではないのかとイジられた。あなたたち実際の女性たちはオネエ言葉を使っていないではないか、だから実際の女性を目指す自分も使うつもりはない、と理屈っぽく返した。あいかわらずめんどくさいね。
20歳の誕生日当日もお店で迎えた。それを聞いた仲間たちが、謎のダンスで祝ってくれた。嬉しかった。そして最終日にはおそらくゲイのおじさんもお客さんとして来てくれた。僕はね、若い人たちがこうして自分らしさを表現するのには大賛成。東京都内には自由に女装を楽しめる施設もあるから、いろいろと利用してみて、と親切に教えてくれた。単に文化祭の企画でやっていたのに、そこまで考えてもらってしまって、なんだか申し訳なかった。
さて、船曳ゼミはいつもは、週に一回集まってあれこれしゃべる。最初は先生が話題を設定していたんだけど、だんだんみんなの意見が多方向に逸れていく。それでは毎週司会者を決めて、その人にとって今、切実な話をしよう、ということになった。これはすごかった。恋愛の話をしだした女性が途中で、こらえきれずに泣き出す。それでもみんな、その場で一生懸命考えたことをきちんとぶつける。
こんな、ある意味危なっかしい場所をきちんと支えて、何を言っても否定されない、ましてや傷つけられない、という安心感をみんなに与えながら、話し合いながら成長していける場を作った船曳先生の力量は圧倒的だった。30年後の今、大学を退職したあとでも、学校とは関係ない形でゼミが続いていることには驚く。年末に1度あるオールゼミ・パーティに行くと、こんなに多くの人が船曳先生の世話になったんだ、と思って茫然としてしまう。
思えばこのゼミで、僕は初めて議論というものに出会った。権威を持った者が自分の意見を押しつけるわけではない。あくまで彼の経験や知識はサポートのために使われるだけで、問題設定をし、考えるのは学生一人一人だ。つまり教師を含めた参加者全員が対等で、成長途中という意味では未完成の存在である。
すべての意見は真理を含むが、自分の経験や視点により偏っている。そこに他の人が違う視点を提供することで、その偏りがほぐれていく。複数の価値観や考えがぶつかりながら、新たな思考が立ち上がる。弁証法やポリフォニーと呼ばれるものを、僕はこのゼミで体感した。もちろんソクラテスの対話編などを読めば、こうしたものは見られる。けれども日本では結局、学生の意見は全て否定され、教師がたった一人勝って終わる、というエセ議論が大半ではないか。
船曳先生はパリ第4大学やケンブリッジ大学で学んだ、ちょっと考えられないくらいのエリートだ。そうしたヨーロッパの大学で、彼は議論とはこういうものだ、という感覚を身につけたのだろう。でもそれだけではない。あの強固な平等主義は、もともと船曳先生の体質だったのではないか。フワフワとしながら芯がある感じは、とても勉強して学んだものとは思えない。
後になって船曳先生は僕らのゼミでの経験を『大学のエスノグラフィ』(有斐閣)という本にまとめた。読んでみたら、行き場を失い苦しんでいた時代の僕が過ごした時間が、本の中にまるごと保存されていた。ということは、船曳先生にとっても、あの頃は特別だったのかな。直接訊いてみたことはないけど。
おそらくあのころ、僕はこうした安心できる居場所を作る仕事がしたい、と決意したのではないか。少なくともあのゼミがなければ、今、大学の先生はやっていないだろう。当時はただ、目の前のことで必死だっただけだけど。
プロフィール

都甲幸治(とこう・こうじ)
1969年、福岡県に生まれる。現在、早稲田大学文学学術院教授、翻訳家。専攻はアメリカ文学・文化。主な著書に、『偽アメリカ文学の誕生』(水声社、2009年)、『21世紀の世界文学30冊を読む』(新潮社、2012年)、『狂喜の読み屋』(共和国、2014年)、『読んで、訳して、語り合う。――都甲幸治対談集』(立東舎、2015年)など、主な訳書に、ジュノ・ディアス『オスカー・ワオの短く凄まじい人生』(共訳、新潮社、2011年)、同『こうしてお前は彼女にフラれる』(共訳、新潮社、2013年)、ドン・デリーロ『天使エスメラルダ』(共訳、新潮社、2013年)、同『ポイント・オメガ』(水声社、2018年)などがある。
「アメリカから遠く離れて」過去の記事
第1回 聖書と論語
第2回 サリンジャーの臙脂色の表紙
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
