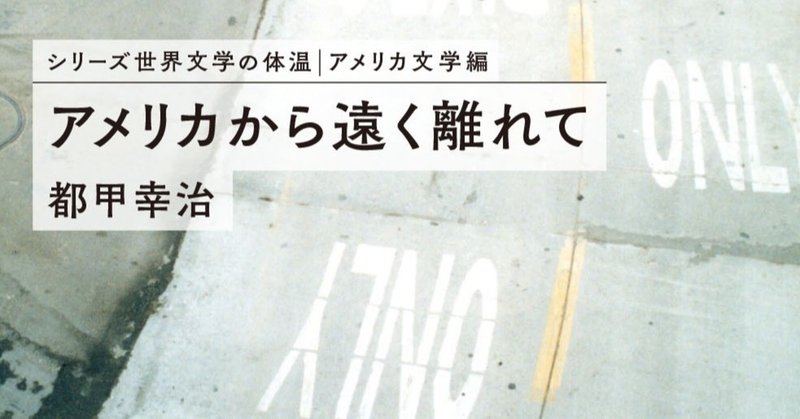
第7回 右車線入ってー!(都甲幸治)
アメリカに行ってみて驚いた。自分が思い描いていたのと全然違ったのだ。もちろんアメリカを描いた映画もテレビも観ていたし、文学作品も歴史書も読んでいた。何回かは旅行をしたこともあった。でも結局それは、アメリカの表面を撫でていただけだった。
たとえば街並みである。自分の中には、古いビルが立ち並び、その間を様々な人種の人々が歩いている、というイメージがあった。もろニューヨークである。だがロサンゼルスは違った。大体、ビルがあるのは中心街といくつかの地区だけで、大部分は平屋建てだ。
しかも歩いている人なんていない。僕が住んだ家からいちばん近くのスーパーまで、すぐそこに見えているのに歩いて20分はかかる。同様に、大学まではバスを乗り継ぐと一時間半はかかってしまう。だから、人力では到底たどり着けない。
それも当然で、ロサンゼルスと呼ばれている街の大きさは関東地方と同じくらいある。だから大学生もみんな車で高速を飛ばしてキャンパスまでやって来る。ちょうど日本の大学の自転車置き場みたいに、学校の駐車場に車がズラリと並ぶ。
家から一度だけバスで大学まで行ってみて、ダウンタウン近くのめちゃめちゃ恐い場所で乗り換えのバスをだいぶ待ったあと、やっぱり車を買うことにした。トーレンス地区のトヨタに行って、なんとか僕の予算でも買えるのを見繕ってもらった。
担当の営業マンは、以前は美空ひばりのバックでサックスを吹いていたミュージシャンだった。夢を追ってアメリカに来て、でも今は食べるために、自動車のセールスをやっているらしい。
そして店長は画家の中国人で、店内には彼の描いたペン画が飾ってあった。「外国にいると、アメリカは自由の国に映る。でも本当はそうじゃない。宗教心が強くて、ものすごく保守的な国だ」と店長に言われた。そのときの彼のむっつりした顔をよく覚えている。
納車の日、免許取り立ての僕はものすごくアガっていて、しかもアメリカでの初の路上で、車の運転の仕方を忘れてしまった。助手席に座った営業マンさんに「この車、アクセルどこですか」と訊き、その後、当然のように左車線に入った。
当然、右側通行のアメリカではそれは死を意味する。その度に営業マンさんは「アクセルはそこー!」とか「右車線入ってー!」とか叫んでいた。営業マンさん、ごめんなさい。
ようやく手続きを終え、アクセルとブレーキを不規則に踏んで車を大きく前後に揺らしながら、二時間ほどかけて家に戻った。人生でも最も恐いドライブだった。こんなに運転がヘタだったのに、三年後には平気な顔で高速に乗っていたのだから、人間、けっこう成長するものですね。
ここで疑問を持った人がいるかもしれない。遠くのトヨタから車で家まで帰ったというのはいいとして、いったいどうやって行ったのか。良い質問である。日本であれば電車とバスを使えば、都会なら大抵どこでも行ける。けれどもロサンゼルスはそうはいかない。こんなに広いのに電車の路線はほんの申し訳程度で、バスもものすごく不便だ。
これは歴史的な理由があって、もともとロサンゼルスは市電が縦横無尽に走っていた。だがそれでは人々は車を買わない。だから市電を自動車やタイヤの会社が買い取って、そのまま廃止したんだという。
で種を明かせば、ものすごーく親切な先輩にあらゆる面で助けてもらっていた。板津さんという女性で、僕と同じ南カリフォルニア大学に僕より前から通っていて、しかもアメリカに親戚もいるらしく、すさまじく英語ができる。しかも人柄も良い。アメリカの実際もすごくよく知っている。行動力も人間関係力もある。
僕は彼女に弟子入りするように、アメリカ社会の仕組み、レストランでの注文の仕方、チップの払い方など、アメリカ暮らしのすべてを教えてもらった。ある意味、神である。というか、彼女がいなかったら僕は生きて日本に帰れたかどうかわからない。
彼女は日本に戻るなり、そのあまりの優秀さからすぐに東大の先生になって、今では世界から駒場キャンパスにやって来る留学生たちの世話をしているらしい。確かに、あまり日本語ができない学生にとって、日本での暮らしは不可解かつ不安すぎる。というわけで、僕は最適な人に助けてもらったわけですね。
アメリカで助けてくれた人は他にもいた。何よりまず、ヴィエト・タン・ウェン先生だ。と言うと訊いたことがある人もいるかもしれない。『シンパサイザー』というベトナム戦争を舞台とした小説で2016年にピュリッツァー賞を獲った新進気鋭の作家だ。彼は1975年、南ベトナム政府が崩壊したとき母国を出て、アメリカに渡った元難民である。
もっとも、僕が出会ったときは作家じゃなくて、普通にアジア系アメリカ文学や文化について論文を書き、研究書を出している学者だった。いや、今もそうだけど。で、彼との出会いも僕にとっては衝撃的だった。
日本にいたとき僕は、サリンジャーが好き、フィッツジェラルドが好き、オースターが好きという、いわゆる村上春樹経由で現代アメリカ文学を知っていった、よくいる普通の読者だった。村上春樹的なアメリカ文学には特徴がある。この三人を見てもわかるように、白人・男性・東海岸中心なのだ。
というと、待ってくださいよ。カーヴァーは西海岸でしょうとか、オブライエンは中西部では、という人がいると思う。そのとおり。でもやっぱり白人男性中心であることはかわらない。そしてまた、「ニューヨーカー」という、名前のとおり、東海岸の雑誌で評価された書き手だということも。
となれば、アメリカに行けば、年輩の白人男性の先生について、まずはメルヴィルやトウェインといった古典を読む、というオーソドックスな流れを予想するじゃないですか。もちろん僕がハーバード大学やコロンビア大学など東部の一流大学に入っていたら、そうなっていたかもしれない。
けれどもそんなレベルの大学は全部落ちてしまった僕が入学したのは南カリフォルニア大学(USC)で、近所にあるカリフォルニア大学ロサンゼルス校の学生たちからさえ、University of Second Choice(仕方なく行く大学)とバカにされた。
結果から言えばこれが良かった。なにしろ、全米一の大学であるカリフォルニア大学バークレー校を出たばかりのウェン先生が、少数の学生に対して、持てるものを全てぶつけてくれる環境だったのだから。
当時周囲の学生は、学部を出たばかりの二三、四歳で、僕はいろいろあって三一歳だった。そしてウェン先生は僕よりなんと二歳下だ。恐ろしい。彼と一緒にレヴィ=ストロースやフーコーなどの文学理論を読み、アジア系アメリカ文学を読み、村上春樹を読むうちに、僕の中で大きな変化が生まれた。
アメリカのマイノリティ文学は、ユダヤ系のロスやマラマッドなどを除いて、政治的な主張や社会の不公正の描写に関しては優れていても、文学作品としての味わいは相対的に落ちる、という印象を日本で僕は抱いていた。
こうした感覚は九〇年代の日本ではわりと普通のものだったと思う。いや、今でもそう思っている人は多いかもしれない。けれども、実際にアジア系として文学作品を書き、そしてまたアジア系文学を研究しているウェン先生とともに多くの時間を過ごすことで、これが古い偏見でしかないことが分かってきた。
アジア系の作家も研究者も、アメリカの古典を読み、文学理論を読んでいる。したがって、白人男性が書いた主流文学の味わいもよくわかっている。その上で、自分たちが今できる表現として、自らが背負っている歴史を踏まえながら作品を書き、研究をしている。
SFにもポストモダン文学にも詳しく、『らんま1/2』など日本のマンガもアニメも大好きなウェン先生と学ぶうちに、僕の文学観に大きな変化が起こった。一言で言えば、政治的であることと文学的であることは両立する、ということになるだろうか。
マイノリティが書く政治的な作品は文学的価値は落ちることが多い、という、僕が日本で知らず知らずのうちに抱いていた先入観は、マイノリティの書き手への差別意識に基づいている。けれども、実際に彼らとつき合ってみれば、知的にも芸術的にもなんら、主流文学の書き手に劣ることがない人々だとわかる。ならば、なぜこうした偏見が日本の読み手の間に普及しているのか。おそらくそれは、日本における海外文学受容の悲しい歴史に基づいているのだろう。
森鴎外や夏目漱石の昔から、日本における外国文学受容とは、欧米の優れた作家の作品を理解し、できれば彼らの芸術を自分たちも身につけ、自前で作品を書けるようになる、というものだ。
そしてその外国文学の多くは、欧米の白人男性が書いたものである。となれば、彼らと一体化するには、自分がアジア人であることを忘れて、彼らの価値観を取り入れるしかない。そしてその価値観には、マイノリティへの差別意識も含まれる。
さて、するとこうなる。欧米人と並んだ存在になるには、自分がアジア人であることを忘れて、他のアジアやアフリカの人々を差別しなければならない。こうした奇妙に転倒した考え方が明治以来の日本を貫いてきた。
さてここにアメリカのアジア系作家がいる。彼らを前にして我々は苦しい立場に置かれることになる。ピュリッツァー賞などを獲っていることからもわかるとおり、彼らの作品はもはや、アメリカでは主流文学と言っていい存在だ。
もし彼らを優れた存在だと認めてしまうと、明治以降の国是である、欧米の人々を目指し、彼らの価値観と一体化する、という考え方自体が間違っていると暴露されてしまう。だって白人以外を下に見る考え方自体、ろくなもんじゃないからね。
そしてこの間違いを悟ると、自分がアジア人でありながら、なおかつアジア人やアフリカ人を差別しているという悲しい存在であることを受け入れなければならない。こうした認識は苦しい。けれども自己を直視することでしか、僕らは自由にはなれない。
ウェン先生との出会いだけではない。様々なマイノリティの学生との付き合いを通して、僕の価値観は大きく変わっていった。たとえば、ある授業でジーン・トゥーマーの『砂糖きび』について発表することになったときのことだ。
僕が組んだ学生は黒人の女性だった。ハーレム・ルネッサンスという二〇世紀の黒人文化運動の中から生まれたこの作品について話し合うなかで、アメリカで黒人であることがどういうことなのかを彼女は教えてくれた。
現代のアメリカでヒップホップが流行していることからもわかるように、黒人の音楽や服装は憧れの対象である。でもギャングスタ・ラップなどの聞き手にとって、黒人のゲットーはまるで内戦下のシリアのように遠い存在だ。
しかし彼女のゲットーについての語り方には、ごく身近な人々について話す響きがあった。仕事もない、勉強もできない子供たちが手っ取り早く金を求めて、麻薬の売買に手を染める。お金がなくても、人の家に盗みに入った先輩から、簡単に銃が流れてくる。
そんな銃で空缶を撃って遊んでいるうちはまだいい。でも不良同士の抗争では、恐怖から銃を持つようになる。相手も持っていると思えば、自分も持たざるを得ない。そしていざ武器を持てば、結局は使ってしまう。そしてもともとは普通だった子供たちがどんどん死んでいく。
「悲しいことに、銃はすぐに手に入るの」という彼女の声には、悲しみと共感が滲んでいた。そしてこう付け加えた。「血の一滴ルールって知ってる? 先祖に一人でも黒人がいれば、この国ではずっと黒人扱いされるのよ」
アメリカ史では、六〇年代の公民権運動以来、マイノリティの法的な地位は格段に改善されたと習う。けれども彼女の言葉、というよりその声の持つ響きには、とてつもない量の悲しみがあった。こんなに賢くて、良心的な人が、どうしてこんな悲しみを背負って生まれてこなければならないのか。
こんなことを言うと、アメリカの負の歴史にばかり注目している、と思われるかもしれない。けれども、もちろん日本だって決して楽園ではない。悲しい歴史や差別は当然存在する。
ウェン先生の温かさや、様々なマイノリティの学生の思いに触れながら、自分の中でアメリカ文学観が少しずつ更新されていった。三年間ロサンゼルスでもやもやと感じ、考えていたことを、僕はその後の年月で徐々に形にしているんだと思う。だからこそ、出会ったみんなには感謝してもしきれない。
プロフィール

都甲幸治(とこう・こうじ)
1969年、福岡県に生まれる。現在、早稲田大学文学学術院教授、翻訳家。専攻はアメリカ文学・文化。主な著書に、『偽アメリカ文学の誕生』(水声社、2009年)、『21世紀の世界文学30冊を読む』(新潮社、2012年)、『狂喜の読み屋』(共和国、2014年)、『読んで、訳して、語り合う。――都甲幸治対談集』(立東舎、2015年)など、主な訳書に、ジュノ・ディアス『オスカー・ワオの短く凄まじい人生』(共訳、新潮社、2011年)、同『こうしてお前は彼女にフラれる』(共訳、新潮社、2013年)、ドン・デリーロ『天使エスメラルダ』(共訳、新潮社、2013年)、同『ポイント・オメガ』(水声社、2018年)などがある。
「アメリカから遠く離れて」過去の記事
第1回 聖書と論語
第2回 サリンジャーの臙脂色の表紙
第3回 すね毛と蚊
第4回 相性がいちばん
第5回 コーヒー買ってきて
第6回 自分探しの終わり
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
