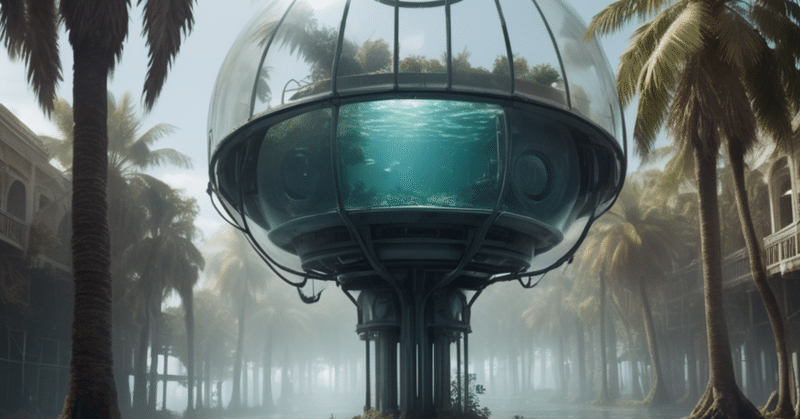
記憶に入り浸る危険性を知る男は、如何にして過去に閉じ籠もるのか―『レミニセンス』“Reminiscence”
*扉絵:コグニティブ・フォートトーク、イマジンアート生成
*この論考は映画『レミニセンス』“Reminiscence”のネタバレが含まれる。
主人公のニック・バニスターは相棒のワッツと共に過去の記憶を引き出す機器を操り、客が自身の記憶に浸る機会を提供する。戦争の尋問装置が過去を懐かしむ(nostalgia)ための手段や犯罪捜査の手法として確立する近未来のフロリダは、水没に瀕するディストピアとして描かれる。そして「記憶は香水と同じで少量がいい」と装置の危険性を十分認識するニックは、ファム・ファタルとして現れるメイの光と影を追って自らの記憶に入り浸り、現実を知ってなお過去に閉じこもることを選択する。相棒のワッツは彼の記憶を引き受ける証人として現実と向き合い、対照的な結末を迎える。
この映画はSF風のフィルム・ノワールではない。フィルム・ノワール風の純然たるSFだ。この基本的な視座を間違えると、物語の上辺を撫でるだけでモチーフを捉え損ねることになる。その上で重要なのが「記録としての記憶」だ。当人にとって都合よく改竄される末那識ではなく、心の深層に刻み込まれ全てを蔵する阿頼耶識に記録される過去を再現する装置を使い、主人公は現在と過去を廻る。その有様は何かに取り憑かれて溺れるかのようで、傍で見ているワッツが都度、彼を現実に戻す。
彼女は冷(覚)めている。酒をあおってボトルの底に答えがないと知っているワッツは、身を持ち崩す裏のある女を見抜き、密かにニックに想いを寄せるが故に彼の側に居続ける。そしてメイは彼を罠に嵌めるものの、そうせざるを得ない過去に引きずられながら、過去の延長ではない未来を望みつつ、二人の男を過去に閉じ込める。
その二人の男の内、彼女を過去の延長に引きずり込む元悪徳警官のサイラス・ブースは自業自得なのだが、他方のニックを解き放たないが故に、メイは正にファム・ファタルと言える。
彼女は未来を観る。土壇場で逃げるも程なくしてサイラスに捕まるメイは、麻薬を飲まされて万事休す。その合間に、彼女はサイラスに対して自身とニックしか知り得ないことを語りかける。メイはニックがサイラスに辿り着いて記憶を覗くことを確信し、秘密を託す。しかし同時に、自身の先がないことを知りながら、呪いの如くニックに対する未練を残して逝く。物理的に相対するサイラスはその不可解さに囚われ、彼を捕らえるニックは、彼女と過ごした甘美なる日々とその裏にある策謀、そして彼女の意(遺)志を知り、清濁織り交ざるメイの掛け替えのなさに魅了され、打ちひしがれ、恋い焦がれる。更には自身が記憶に溺れて彼女の来訪を逃してしまう失態と、その彼女を連れ去るサイラスを許し難いからこそ、禁忌の復讐を果たす代償を口実としてニックは過去に引き籠もるのだ。
全てはエンディングのナレーションに集約される。
The past can haunt a man. That's what they say. And the past is just a series of moments. Each one... perfect. Complete. A bead on the necklace of time. The past doesn't haunt us. Wouldn't even recognize us. If there are ghosts to be found... it's us who haunt the past. We haunt it... so we can look again. See the people we miss... and the things we missed about them. I see you fully now. Your darkness and your light. Shimmering... Like the city at dusk when it's most beautiful.
過去は決定論的世界そのものであるが故に因果を逸脱せず、その一々が完璧にして完全無欠なのだ。そして過去は人に執着させ、人は過去に執着する。
しかしワッツは過去に取り憑かず、現実と向き合い前に進む。それは彼女が冷(覚)めているからだけではなく、ニックが彼女を解き放つからでもある。彼は自身に対するワッツの想いを知って彼女を呪縛せず、娘を探してやり直すよう促す。メイに執着している自身のどうしようもなさを晒し、自身に未来がないことを伝え、その顛末をワッツに託して見届けるよう求める。
ワッツは託された意向と記憶を受け取り、ニックを見舞い続ける。孫娘を連れて彼を見舞うラストシーン近辺で彼女が述べる台詞“ Missing people is a part of this world. Without that sadness... you can't taste the sweet.”は金言だろう。そしてその哀しみに耐えることの出来ない者が記憶に閉じ籠もる。
この映画は個々の人間が各々の仮想世界に閉じ籠もる構図を巧く描いている。財力で個人の記憶を現実に再現する者、薬で酩酊する者、そして肉体を水槽に閉じ込めることで生き長らえつつ夢を見続ける者。この閉じ籠もり方が象徴的であり特徴的だ。肉体の軛がある限り、仮想世界に入り浸りつつ生存するためには生命維持装置で肉体を管理する以外に方法はなかろう。そして、記憶であれ仮想現実であれ、このような非物理世界への閉じ籠もりを描く上で、生身の生活を営む者たちが同時に異なる夢を見続けるという描写は成立するだろうか。
さながら夢遊症の群れが物理的に互いに干渉せず衝突もしないよう制御されるシステムにおいて、それが可能ならば他者との意思疎通など必要なかろう。そのような生ける屍が徘徊する様を想起するに、それは如何なる喜劇(と同時に悲劇)なのかと問いたくなるほどシュールで意義不明と言わざるを得ない。その意義不明な珍妙さは、生命が何故に物理現実を生きるのか、という前提を度外視しない限り解消せず、そのような世界は文字通り「均一なるマトリクスの向こう側」に沈み緩やかな死を迎えるだろう。
死にゆく者たちがゾンビの如く徘徊するのか水槽という棺桶に閉じ籠もるのかの違いは、当事者が何れに納得するか否かと同時に、それを外から眺める者たちにとっての印象や価値観、倫理観にも依る。その意味で、筆者は棺桶で眠ることよりもゾンビが徘徊することを悲惨な様態と捉える。電極を埋め込まれて操作される昆虫やラットを想定すれば、そのおぞましさが解るだろうか。
最後に、この映画の不遇について触れたい。『レミニセンス』はボックスオフィス・ボムと見做され、興行的に惨憺たる結果に終わるだけでなく、プロ・アマを問わず作品に対する評価が低い。その理由は既に述べた通りで、視座とモチーフを捉え損なうが故に起こる読解不足に起因するのだが、問題は作品の側ではない。俳優陣は十分に実力を発揮し、制作陣は問うに足る構図とモチーフを提示している。構成やナレーションなど、その有効性を問う項目はあれども、致命的な失敗はない。そうであるにもかかわらず十分に読み取らない批評が往年のフィルム・ノワールや類似の描写を持つ作品を引いて過小評価をするのは惨状としか言いようが無い。これではあまりにも制作者や演者が報われない。拙論が不相応な評価を覆す視点を提供し、この作品を理解する一助となることを願う。
サポートしていただけると大変ありがたいです。
