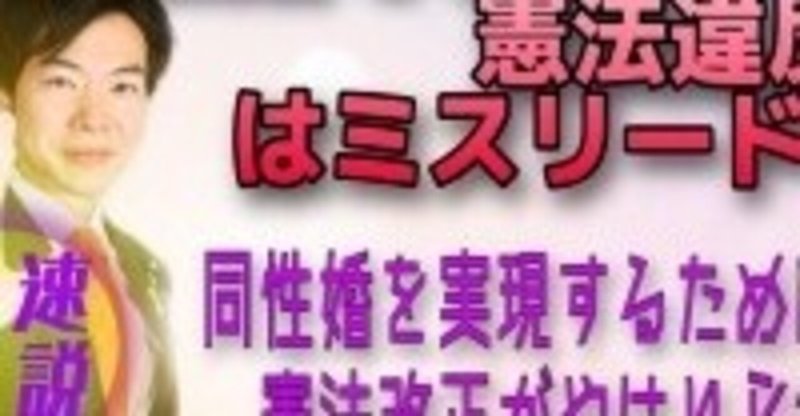
音喜多駿議員(維新)の同性婚違憲判決の解説は驚き桃の木山椒の木~同性婚は憲法改正なしにできないはウソ
維新の会の音喜多駿参議院議員。LGBTに対して、その不平等是正に取り組んできたようではある。が、彼の同性婚違憲・札幌地裁判決(2021.3.17)に対するブログ記事(「同性婚できないのは憲法違反」報道はミスリード。同性婚実現と憲法改正の論点を整理する)は、完全に誤りであるとともに、メディアに対する信頼を毀損するものである。
彼のブログの結論は、
「同性婚を認めないのは違憲」とするのは明らかにミスリードであり、むしろ「同性婚」の実現には憲法改正が必要ということが示唆された内容であると言えます。
である。この結論は、判決を読めていないから出る、誤ったものである。この結論となる「理由」についてつらつらと書いているわけであるが、これこそ「ミスリード」どころか、「完全な誤り」である。
憲法とは何か
そもそも、音喜多議員は、憲法とはなにかがわかっていないように思える。
憲法とは、国・権力を制限し、国民の権利・自由を守るための決まりである。したがって、基本的には、権力に対するもので、かつ国民の自由を守るためのものであり、国民の権利・自由を憲法が制限するものではない。
憲法24条が異性婚を定めているものとしても、同性婚を禁止する規定はない
今回の判決はあくまで「不利益を被る状態を何らかの形で是正しなさい」というものであって、むしろ憲法24条の婚姻における「両性」とは「異性同士」であると断じています。判決としては逆に、同性婚の実現には憲法改正が必要ですよと示唆するものなのです。
この音喜多議員の主張は、複数の点から誤りがある。
まず、本判決において、憲法24条は言葉通り、「異性婚」について定めたものしている。したがって、24条から同性婚が保護される、とはしていないということになる。これを「24条が同性婚を禁止している」というふうに読むとすべてがおかしな方向にいってしまう。
そもそも24条は、戦前の家父長制、イエ制度を禁止し、「互いが同意すれば誰に干渉されることもなく結婚できる」自由を保障するもの、と考えるのが自然である。あくまで、互いの合意で自由に結婚できるというものであり、家族や戸主らの同意、そしてそれがないと結婚を受け付けないという国からの制限を禁止するものといえる。
したがって、「異性」かどうかは24条の本質ではないし、24条が異性婚を前提としていても、それが同性婚を禁止するものでないことは明らかなのである。
同性婚に必要なのは、「憲法改正」ではなく、「民法改正」
音喜多議員によれば、今回の判決は「同性婚の実現には憲法改正が必要ですよと示唆するもの」とまで書いてしまっているが、裁判長からしたら"驚き桃の木山椒の木"というところだろう。
まず、現在の婚姻制度は基本的に民法に基づいている。民法は、憲法に書いてあることしか出来ないわけではなく、憲法に反しない範囲で自由に定めることができる。婚姻制度についても同様、家父長制を禁じる憲法24条(あるいはその他の憲法上の規定)に反しない範囲で、自由に定められる。したがって、民法に同性婚規定を設けたり、現在の異性婚を前提とする民法条文を改正することにより、同性婚は当然に(憲法に反することなく)認められるのである。
今回の判決も、同性婚が(憲法改正なく)認められることを前提としている。裁判所は、同性婚を禁止することは憲法14条に反するとしているわけであるが、逆にいえば、同性婚を認める制度は憲法に何ら反しないということなのである。また、より直接的には、今回の違憲判断は、「広範な立法府の裁量」があるにもかかわらず、同性婚についての異性婚と同様の法的効果に関する規定を設けていないことを問題としているわけであり、同性婚が憲法違反になるのならば、広範な立法府の裁量などあるわけがない。
そもそも裁判所は憲法に基づいて判断するわけであり、憲法違反になるものをしろとはいわないし、同性婚が憲法違反になるのであれば、同性婚禁止が憲法違反だというわけがないのである。加えていえば、裁判所が自らを制約する憲法を変えろということはありえない。
したがって、同性婚に必要なのは、民法改正であり、憲法改正ではないのだ。(もちろん、憲法24条を改正することによって同性婚を認めることも可能であるが、その場合には憲法を改正した上、民法を変える必要も生じる。また、少なくとも本判決は、憲法改正を経ることなく同性婚が認められることを前提としており、本判決から憲法改正が必要という話にはなりえない。)
パートナーシップ制度の問題ではない
なんらかの「法的手段」によりこの不利益が解消されれば良いとするもの。
具体的には、各自治体で先行しているパートナーシップ制度を強化し、法律で整備して婚姻同様の効果を保証する手法が考えられます。
この記述は、音喜多氏の前の記述との矛盾、あるいは根本的に判決の意味を理解できていないかのいずれかである。
まず、パートナーシップ制度を法律で整備し、現在の法律婚と同様にする、というのは、結局同性婚を民法などで認めるというものであり、「憲法改正しないと同性婚は認められない」という音喜多議員の前の記述と矛盾する。婚姻制度をパートナーシップ制度とするのかよくわからないが、いずれにせよ、パートナーシップ制度の強化という次元ではない。
あるいは、それでも(法律で定めても)パートナーシップ制度と法律婚が異なるものというのならば、地裁のいう不平等(憲法14条)は解消されない。もはや、意味不明なのである。
同性婚は「解釈改憲」でなくとも認められる
繰り返しになるが、同性婚に憲法改正が必要だということは、少なくとも本判決からはいえないし、本判決はそれを示唆するという「解釈」がまず誤りだ。
そして、前から述べている通り、同性婚を認めるか否かは民法条の問題であり、憲法は同性婚を制約していない。
たしかに、24条の「両性」を「同姓をも含む」とするならば、「解釈改憲」とみる見方も理解できなくはない。
しかし、本判決は、14条をもとに、24条関係なく同性婚禁止は憲法に反する=24条関係なく同性婚は憲法上の権利として認められるべき、というものであり、「解釈改憲」は不要なのである。
また、本質とは異なるが、解釈改憲が問題となるのは、基本的には憲法上の権力側の制約を(条文の趣旨をも含め)緩める場合である。
集団的自衛権の問題はまさにそうであるが、それまで日本(権力)は、集団的自衛権は憲法上制約されており、できないとされていたものを、「解釈」により集団的自衛権を認める、すなわち制約を緩める、外したのである。この場合には、条文を半分空文化させるものといわざるをえず、趣旨を含めて制約を緩めているために、大いに問題になるのである。
仮に、今後24条の「両性」に同姓を含むという判決がでたとして、家父長制を禁じる24条の本質から外れることはなく、誰かの権利・自由を制約するものでもないから問題にもならない。
議員は憲法を学ぶべき
以上より、音喜多議員の記述は明らかに誤りであり、それは判決の解釈や、護憲派、改憲派というレベルの問題ではない。
よく勉強し直して、ただちにブログ内容を撤回、訂正すべきだ。また、メディアに「ミスリード」とまでいってしまっているのであるから、メディアに対する謝罪も必要だ。
音喜多議員に限らず、国会議員が憲法や基本的な法律的なものの考え方を理解していないということは恥ずかしい。特に、憲法は国会議員自らを制約するものである。
まして、音喜多議員の場合は、複数の弁護士や専門家からも指摘されているのに、自分の非を認めない。プライドが高いのはわかるが、間違いは間違いだ。それが拡散され、国会議員様のいうことだから正しいと、それを信じる人もいる。
LGBT差別解消を目指すならば、国会議員=立法府の構成員の一人として、憲法ではなく法律による解決をまず目指すべきだ。そのためにも、憲法や法律の基本的な部分はよく理解し、また、素直に誤りは認めるのが国会議員としての責任のあるべき姿ではなかろうか。
音喜多議員に対するこれまでの記事はこちら
・音喜多駿議員(維新)の同性婚違憲判決の解説は驚き桃の木山椒の木~同性婚は憲法改正なしにできないはウソ
・音喜多駿議員のセコさ。ズルさ。そして、無知さ。
・音喜多駿氏には同性婚問題解決の意志はあるのか~わざわざ遠回りをすすめる音喜多議員
・音喜多駿議員はご都合主義で「差別主義」の塊であった、という話~家制度>同性愛者の権利…?
・音喜多駿氏は、LGBT問題解決の先導者にするのはヤバい、という話~迂遠な道を行かせる音喜多議員
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
