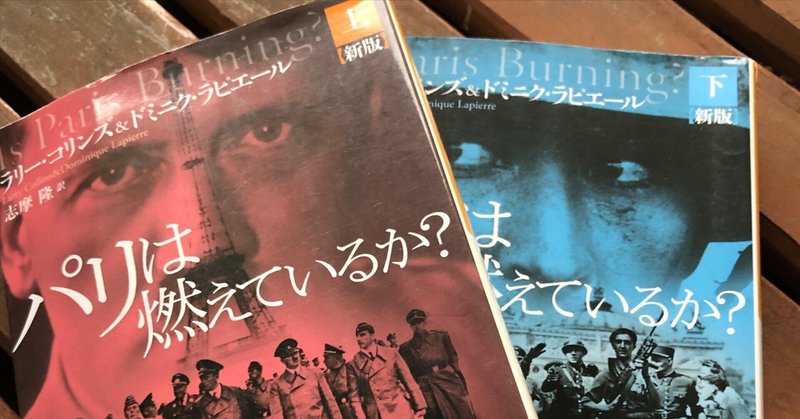
「パリは燃えているか」上下
【上巻】
多数の様々な役割を持った登場人物を時系列ごとに登場させ、1944年8月、ドイツに占領されたパリを解放に導くまでのストーリーを繰り広げている戦記ものの大作です。
まず、前半。
パリの解放に、というより結果的にパリを破壊の悲劇から守ったドイツのディートリッヒ・フォン・コルティッツ将軍のパリ軍政司令官就任から物語は始まります。ヒトラーから任を受けた時に感じたその狂気がドイツの凋落を予感させ、コルティッツに暗い影を落としていきます。パリの解放はこの時から始まっていたように思いました。
パリ解放はドイツの占領後四年の長きに渡っていますが、やはり連合国軍のノルマンディー上陸がその終わりの始まりとなっています。パリにいるレジスタンスたち、一般市民、ドゴール派、共産党たちが活動を開始します。その数多な人々の活写が素晴らしいです。
作品の冒頭に謝辞が延々と続いていますが、その相手がこれらの人々であり、この作品は周到で綿密なインタビューで完成したことを物語っています。
ドイツ軍の残虐さと撤退軍の惨めさ、レジスタンスの勢いとその脆さ、ドゴールとその協力者たちの焦りと行動、そして、パリを破壊の悲劇から守った一人の電気屋の活動、首相官邸に乗り込んだドゴール派の若いカップルの勇気、ドゴールをアルジェからシェルブールまで連れていくためにドイツ空軍の攻撃を避けながら飛行し、燃料は残り120秒分だけというところで着陸するという際どさ、と言った究極の状況にのみ得てして起こる奇跡的なドラマ……驚くほどのエピソードが散りばめられていて、その一つ一つに感動してしまいます。
パリ解放は英雄ドゴールと連合国軍によるヒロイックな活躍で行われた、などという三文芝居ではなかったことがよくわかります。
連合国軍のアイゼンハワーはドイツを直接攻めたいため、面倒なパリ解放など考えたくもなかったし、ドゴール将軍は共産党に政権を取られたくない一心だったし、かたや共産党はその逆であり、後ろにはソ連が控えていた。
イデオロギーと欲望と力と運がパリ解放という時を揺すぶっていたわけなのですで。
第二章は前半で終わり、後編で承前。パリ解放がなされます。
スペクタクルは終わりません。
【下巻】
連合軍に参加していたフランス軍率いるルクレール将軍がドゴールの意を受け、連合軍の命令に従わず、パリ解放に向かいます。この件、ワクワクしますね。
連合軍の要職にパリの窮状を訴えるまでにもドラマがありますが、パリ解放の考えなどなかったところを、180度考え方を転換させてしまうというドラマがあるのです。
そして、パリへ。
パリの美しさに恐れすら抱き、とても破壊などできないと考えていたフォン・コルティッツ将軍。連合国軍がやってくるなら(時間がないので)、パリの破壊は断念せざるを得なかったと言い訳できると考えていました。
しかし、ヒトラーはその言い訳をさせず、パリを破壊せよと言い募ってきます。
このせめぎ合いは1944年8月25日に頂点を迎えるのです。
コルティッツ将軍はドイツから援軍が入ってくるなら、パリの反乱を積極的に鎮圧し、各所を破壊せざるを得なくなるが、それが、連合国軍の到着に間に合わなければ、断念して降伏することができると決断しました。彼にはパリという、世界にとっての宝を破壊することは無意味である、と判断していたのです。
ルクレール将軍以下、途中ドイツ軍の攻撃に悩まされながらもパリに入り、熱狂的な歓迎を受けます(まだ、戦闘中なのですが)。第3部では、その歓迎ぶりのエピソードがやたらと続きます。
そして、ドゴールがやってくるのです。
共産党の介入をあっさり無視し、パリ市内を行進し、あっけないほどにパリ解放は完了するのです。
上巻に比べて内容が薄くなっていましたね。エピソードの量は多いのですが、その内容が似たり寄ったりの繰り返しで、驚くべき事実ではあっても飽きてしまいました。
下巻は、ドゴール派と共産党との戦いがもう少し詳しく描かれているのかと思ったら、要点は押さえていたけどあっさりしすぎであり、残念でした。
ドキュメンタリーとしては一級品だと思いますが、読み物としては下巻の構成はバランスが悪かったように感じます。
それから、上下巻に通じて言えるですけど、翻訳の文章に時折、奇妙な表現や言葉遣いがありました。書き慣れていない訳者なのか、編集者が弱いのかよくわからないけれど、これはないでしょう、というものが散見されました。
でも、悪いところはそのくらいであり、総じて素晴らしいドキュメンタリーでした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
