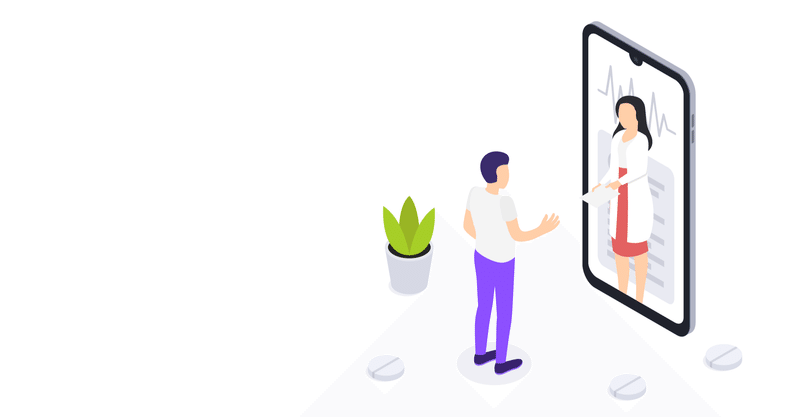
【初めての方向け】オンライン診療の流れと必要なもの解説
いま数年ぶりに蕁麻疹が復活していて、特に夕方以降、身体が痒くて仕方がないのです。
原因はストレスとも言われていますが、必ずしも心身にわかりやすく大きい負荷がかかったときに出るわけでもないので予測不能です。
タイミング的にはえーーーー今かーーーーーーいという気持ちでしたが、こんな状況だからこそ出てきたのかもしれないですね。
薬を貰いたいけれど、病院に行ってお年寄りがいたらどうしよう、もしかすると自覚症状なく私がウイルスを持っているかもしれないし・・・等々考えると足を運ぶ気にもなれなかったのでそうだオンライン診療を使ってみよう!とトライしました。
昔飲んでいたものに近い薬をさくっと貰えたらいいな、くらいの気持ちで、受診できる医療機関を探すところから始めました。(長いので結論だけ知りたい方は「4.まとめ」へ)
0.ヘルスケア相談から始めたい場合
私の場合、症状は前回の蕁麻疹発生時と同じなので、これは診察を受けるべきか?何科にかかればいいのだろう?といった相談フェーズはスルーしました。
もしそこから始めたい場合は、ダイレクトに病院予約でも悪くないですがLINEヘルスケアやfirst callといったサービスを事前に使うと良いのではないかなと思います。(その理由は次に書きます。)
1.プラットフォームを探す
iPhoneなのでApp Storeで「オンライン診療」と検索し、上からダウンロードしてみました。最初に落としたのは「curon」というアプリです。

アプリ上で必要情報を入力し医療機関を選択した後、クロンちゃんというアシスタントが予約をサポートしてくれるようです。こちらがクロンちゃん。
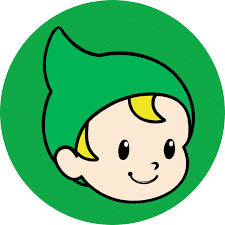
かわいい。5歳くらいかな。はやくクロンちゃんと喋りたい。
ところが氏名・住所・クレジットカード情報(※決済は現在クレジットカードのみ可能です。デビットカードやPayPalはダメ)など基本項目の入力後、医療機関のQRコード又は医療機関コードの入力を求められました。どうやらこのアプリ上で病院を探すことはできず、あらかじめcuronに対応している医療機関のコードを控えておく必要があるようです。
試しに以前蕁麻疹を発症した際に通っていた病院が対応しているかブラウザで検索してみましたが、していませんでした。
結局クロンちゃんに会うことはなく、この時点で面倒くさくなって離脱。(気が短い私・・・)
次にダウンロードしたのが「CLINICS」というアプリです。

こちらはアプリ内で病院を検索できるので、早速使ってみることにしました。
アレルギー科×東京都で検索したところ20くらい医療機関が出てきました。しかし初診からオンライン受診が可能な機関は限られていて(そういった絞り込み機能はないので1つ1つ自分で確認する必要があります)、さらにシステム利用料など診察・処方以外にかかる費用が病院によってまちまちなため、金銭面の不安が出てきてしまいました。
そこで方針転換して、まず病院を検索してから、納得できそうな機関が使っているオンラインプラットフォームに乗っかることにしました。
ここまででわかったのは、初診×オンライン診療は医療機関を見つけるまでのハードルが高いことです。よって前述の「病院にかかるべきか?」の段階にいる方は、まず相談ベースのプラットフォームを利用してせめて診療にかかるか否かと受診科目を明確にした方がいいと思いました。
2.病院を探す
ブラウザに戻ってきました。「オンライン診療 アレルギー科 東京都」のキーワードで検索してヒットした医療機関のホームページを見てみます。エリアで絞り込んでいるのは、処方箋や薬が早く届いてほしいという理由だけです。
※後から知ったのですが、厚生労働省がオンライン診療に対応してる医療機関を発表しているので、こちらで探してみてもいいかもしれないですね。
とある病院のページにオンライン診療の流れと料金、さらに科目ごと診察料の概算が記載してあったので、ここがいい!と決定。
詳しく見てみると、使っていたのは最初にダウンロードしたcuronでした。というわけで、QRコードのページを開きながら再びアプリを立ち上げます。
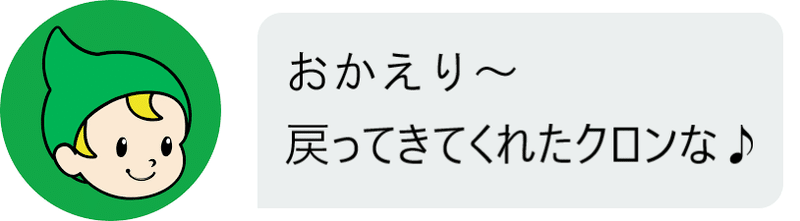
とクロンちゃんが思ったかどうかは知りませんが(あとクロンちゃんはこんな喋り方しません)、縁あって再会することになりました。
今度こそよろしくお願いします。
3.いよいよアプリで受診してみる
医療機関の登録が済むと、問診票の記入をします。症状や始まった時期などについて回答した後、保険証を画像添付します。この作業は3分くらいで終わります。
10:30に記入が完了し、病院側の空きが一番早くて11:30-12:00だったのでその時間帯に予約をしました。この30分の間に医師の方からアプリ上で連絡が来るそうです。
予約時間の10分前になるとクロンちゃんがリマインドをしてくれたのですが、「クリニックから連絡があるまでアプリを開いたままお待ちください」とのこと。
むむ、最大30分間このアプリを開きっぱなしで待つのかな?バックグラウンドではダメですか?等々疑問がわいてきたのですが、ここでクロンちゃんとはインタラクティブなコミュニケーションができないことが判明します。一見よくあるメッセージアプリのUIをしているのですが、入力欄がないため私から発言することはできないのですね。
そのため、びくびくしながらアプリの画面を表示したまま連絡を待つことに。
・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・
12:05。あれ、まだ連絡が来ないな。
こういう時はどうしたらいいのでしょうか?ヘルプページを見てみます。
答:「医療機関に直接ご確認ください」
おおーーー医療機関情報がアプリに載っていないという事は、自分で連絡先を調べるのですね。なるほど。手間だあ。
その後電話ですぐ病院側と連絡がとれて、改めて12:30からビデオ通話で診察を受けることができました。
事前に問診票に記入した内容の確認や追加の質問事項などをふまえて、今回も蕁麻疹で間違いなさそうですね、と診断がおり、処方する薬の内容と服用方法の説明を受けました。そして最後に薬か処方箋のどちらを郵送するか聞かれて終了。診察時間は約2分でした。
めちゃくちゃ楽だなあ・・・・・・
途中ビデオ通話の音声が聞き取りづらくなるなど若干の不備はありましたが(アプリではなく通信環境の問題だと思います)、この手軽さは涙モノでした。
むかし近所の眼科でおばあちゃん先生がとーってもゆっくり診療していて、毎回同じ薬を貰うだけなのに予約しても2時間待ちということが度々ありましたが、そんなことももうしなくてOK!ありがとうテクノロジー!
ちなみに今回かかった費用は以下の通りです。
診察・処方薬料等:980円(自己負担分のみ)
送料:520円
アプリ利用料:330円
--------------------------------------------------
合計:1,830円
明細はアプリ内のメッセージと登録メールアドレス宛に送られてきます。
またこの記事執筆時点でオンライン初診時は最大7日分の薬しか処方することができないため、長期で薬を貰いたい場合はどのプラットフォームを選択しても再診する必要があります。
受診から2日後、無事お薬が届きました!
宅配の進捗を知る方法がなく、本当に発送されたのか・いつ薬を受け取れるのかがわからず少し不安があったのですが、いまはオンラインですべてが完結しただけで感謝です。
4.まとめ
▶事前確認事項
- 診療科目
- (あったらベター)受けたい医療機関×科目のオンライン診療対応可否
参考:厚生労働省HP オンライン診療対応機関一覧
▶用意するもの
- オンライン診療用アプリ
- 保険証の表面写真
- クレジットカード番号
結論、オンライン診療の体験自体は劇的に良かったです!!
急患でない場合、診断にあたって患部の状態を明確に見せる必要がない場合などは、オンライン診療で十分だと思います。
これで処方箋をPDFとかで発行してもらえるようになったり、医療機関間でシームレスに私の受診・病歴をやり取りしてもらえるようになったりしたら最高ですなあ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
