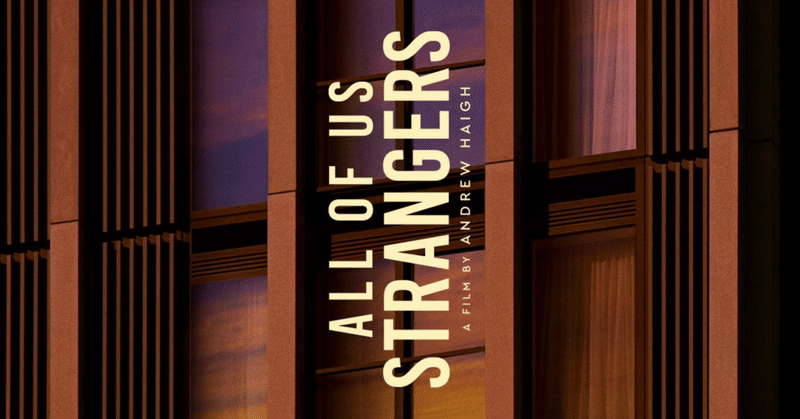
『異人たち』
登場人物の数は少なく、舞台となる場所もアパートと実家以外はほとんど登場しない。しゃべる台詞もそれほど多くなく、静謐な雰囲気に包まれたミニマルな作品だ。
だからこの映画は役者の「表情」が重要となる。主人公であるアダムの表情が。
冒頭、自室で脚本家の仕事をしているアダムはどこか寂しげで憂いを帯びた表情をしている。夜遅く部屋に訪ねてきたハリーに対しての戸惑いと温厚な表情。死んだはずの父と母に再会したときの嬉しそうで安心感のある表情。そういうアダムの表情で出来上がっていると言っても過言ではないくらい、彼の顔はこの映画の物語を物語る。特に前半部分なんかは台詞を発する必要がないんじゃないかと思うくらい、彼の心情が伝わってくる気がした。
もちろんそれは、彼の顔を照らす夕日や、哀愁漂う音楽、カメラの切り取り方や、編集から「わかる」ように作られているおかげであり、その点で、画面作りがとても丁寧で美しいと作品だと思う。
本作は、元は山田太一が書いた小説であり、1988年に大林宣彦が映画化した作品を、イギリスの映画監督であるアンドリュー・ヘイが舞台を現代に置き換えリメイクした作品だ。大林宣彦版は昭和の風景がノスタルジックに演出されており、夏の日差しを受けた食卓の場面、昼日中に父親と行ったキャッチボール、ランニングTシャツになって家族で花札に興じる場面など、そういったひとつひとつの懐かしい風景を抒情的に描いていた。
今回のアンドリュー・ヘイ版は、舞台がイギリスとなっていることから、「風景」としてのノスタルジックさは日本に住む者には感じにくいだろう。
しかし12歳の頃に亡くしたはずの両親と再会し、彼らにいまの自分を見てもらい、褒めてもらう。核となるその情景はアンドリュー・ヘイ版にも当然あり、やはりそれは抗いがたいほど魅力的だ。もう会えない人と再会し、いまの自分を受け入れてもらえる。おそらくあの光景に心を動かされない人は少ないんじゃないだろうか。
そして今回のアンドリュー・ヘイ版は、主人公のセクシャリティを変えることで、より彼が持つ孤独を強調するようなつくりになっている。大林宣彦版において主人公は、父とも母ともただ純粋にその再会を喜び、心に障壁となるようなものは何もなかった。しかし今作では主人公をゲイとすることで、より彼の孤独を可視化させている。ジェンダーについての意識が30年前で止まっている母親は息子からゲイであることを打ち明けられたとき戸惑いを隠せないし、父親もどう接していいのか距離感を測りかねている。しかしだからこそ、しこりとなっていたそれらを伝え、父親からも母親からも抱きしめられることでより彼にとっての「癒し」は強まることとなる。
また、大林宣彦版では悪霊以上の役割を持っていなかった「恋人」の存在は、今作において主人公の孤独や悲しみを癒す役割となっている。後半に進むにつれ、ふたつの「異人たち」の世界は融解していき、恋人であるハリーはむしろ主人公にとっての救いとなる。
両親もハリーも、彼ら「異人たち」は主人公の中にしかいなかったのかもしれない。しかし各々が別個の存在であり、それでもなお生きて行かなくてはいけないということ。自分が誰かに愛されていたということを思い描くことで、ようやく主人公は自分もまた誰かを愛することを思い描けるようになる。
人はみんな孤独だ。そんな使い古された文句は、しかしどこまでも真実であり、孤独だからこそ人は誰かとの繋がりを欲し続ける。
孤独な主人公は己との対話を繰り返し、自身の中にあった愛を見つけることで、ついに両親と別れを告げ、もうひとりの孤独な存在である"死者"と向き合うことができるようになる。
その瞬間、生も死も、現在も過去も彼らは超越し、あらゆる価値は等価となる。引かれ合う心は星のような瞬い光を放ち、やがて愛は永遠となる。
彼らが"幻"だったのかどうか、それはさほど重要なことではないのだろう。重要なのは、己の中にある愛を見つけること。そのことなのだから。
*
大林宣彦版は感動するけど色々と惜しい。惜しいけどそこが可愛げにもなってるという、私のなかではそんな印象の映画でした。リメイク版である本『異人たち』は主人公の孤独を強調することで、彼の「心を癒す」という側面が強まり、よりエモーショナルな作品に仕上がっていました。大林宣彦版の茶目っ気も好きだけど、アート性が高まったアンドリュー・ヘイ版の『異人たち』も私は好きだな。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
