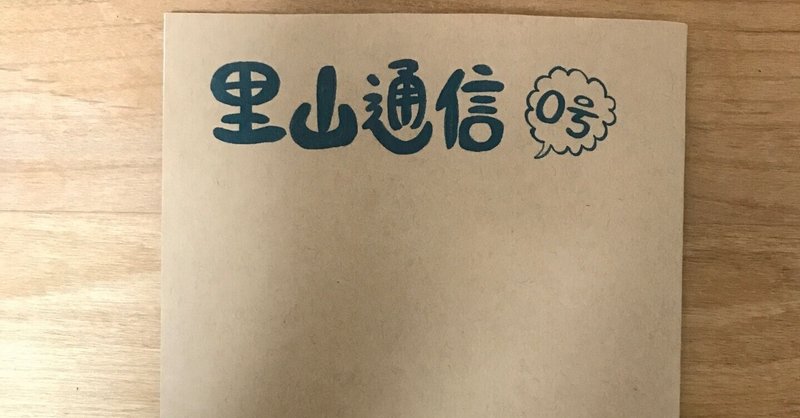
感想の練習1:『里山通信 0号』等
最近、地元である北陸、とりわけ石川県のことを考える時間が増えた。
石川県の片田舎、最寄駅まで片道不可能な場所に生まれたという出自は、私の中ではかなりアイデンティティの大部分をしめていて、その分都会育ちの人、とりわけ東京生まれの人への妬み、嫉みは深刻なものがあった。いまだに東京に居を構えようとする友人に対しては「やめといたほうがいい」などと根拠のない出過ぎた忠告をしてしまうし、誰かに対してなんらかの抵抗心を抱く時も、「そんなこと言うけどあなたは東京育ちじゃないか」などという論理の飛躍した言いがかりに頭が支配されてしまう。ぞっとする話だ。
『仕事文脈』vol.16の特集「東京モヤモヤ2020」内の座談会「東京生まれ・東京育ちのモヤモヤ」のなかに、「なんとなく東京出身と言うことが恥ずかしかった」「自分の田舎があることに憧れていました」などの発言を目にして、そういうもんなのかと驚いた。人が集まる中心地であり、文化の最前線としかいいようのない場所で生まれ育つということは、それだけその地に対しての言葉が溢れ、語りは飽和状態であるということで、そんな現在進行形で語り尽くされている場所の一人として生きるということは、その中に埋もれ、平凡な存在として生きることを余儀なくされるような感覚になるのかもしれない。
東京への嫉妬をこじらせた身としては、そんなモヤモヤを聞かされたところで「文化もなにもかも享受できるのだからそのくらい我慢してくれよ」などと嫌味の一つもいいたくなってしまうのだが、田舎への憧れは、なんだか一周回って気持ちはわかる気がする。だって、私もだんだん、石川県のど田舎生まれであることが自分に備わった「個性」のようであり、語るべきことの宝庫のように目をつけ始めているのだから。これがないということを想像するだけで、その寄るべのなさに体がすくむ。
『里山通信 0号』(里山社)を注文して読んだ。面白かった。冊子の大部分はライターのピストン藤井と里山社の編集者清田麻衣子の対談に占められているが、巻末に収められた両者のエッセイが圧倒的に好みであった。コロナ以降?どことなく雑談がブームで、雑誌やら本やらについても対談が増えた気がするけど、私としてはやはり自閉性を携えた文章の方が心地よい。あと、仲の良い会話を見ると、「この人くらいの年齢になったときこういう友達できるんだろうか」などとつまらない雑念がよぎってしまい、気が重くなったりする。まあ、これはちょっとだけ。
前に、藤井さんの本『どこにでもあるどこかになる前に。~富山見聞逡巡記~』(里山社)を読んだときにも感じたような気もするが、東京への憧れも、地方である地元への自虐的感覚も諦念も持ちながら、それでも地元に住むことを引き受けている人に対して私はずっと後ろめたさを感じていたように思う。
私がツーと言っても相手はカーとは答えてくれない。阿と吽の呼吸は合わない。そんな多くの間の悪い隣人たちで構成されるのが、富山という地域社会だ。
刹那的ともいえる酒の勢いに委ねず、シラフのまなこで他者とのズレを見つめていきたいと思うのだ。
「富山とはこういう土地である」などという言い切りは、私のようなすでに”よそ者”としての割合が強まってしまった人間がハッタリ的に繰り出すことはできても、それは手垢のついたポーズでしかなくて、ここでなされるような実際に住う経験の中で培われたリアリティに裏打ちされた言葉とは圧倒的に覚悟が異なる。
コロナを機に酒場的コミュニケーションから物理的にも精神的にも距離が生まれてしまった、そのことを郷愁的に語るのではなく、その変化を引き受け、むしろ以前は曖昧にごまかしてきてしまったものを、”この地”で見つめようとする。ここに書かれているのはその宣言めいたものだ。わたしには、到底、この言葉は書けない。自分の「個性」として、語るべきことの宝庫として、いわば「ネタ」として地元をまなざしているうちは。
富山に限らず、首都圏以外の地で暮らしながら、いま居る土地の魅力のみならず、課題も含めて正直な自分の思いを書くのがいかに難しく、勇気がいることか。
清田が藤井のエッセイに呼応するようにこのように書きつけていて、そうだそうだと思った。石川県のことについて「語るべきこと」を持っていると自負しながら、それを書くことをさぼってきたのは、上記の勇気を持つどころではない安全圏にいる自分に気づいているからである。そして、私が持っている「語るべきこと」の軽薄さにも気づいているからである。
たまにヨソからやって来て、ちゃぶ台を盛大にひっくり返して去っていく輩もいるが、こぼれた味噌汁やご飯粒を拾い、後片付けをしているのは地元民であることを知っているのだろうかと思う。間の悪い隣人同士、互いの違和感やズレの正体を見つめ続け、落としどころを模索することは必要だ。だって生活は続いていくのだから。
私が書くことは、ちゃぶ台返しにすぎないのではないか、いや、そのちゃぶ台のありかすらわかっていないなかで、妄想的にひっくり返した気になって得意になっているだけなのではないか。その土地に縁がない「ヨソ者」よりも、より一層傲慢で軽率な存在なのは、実質「ヨソ者」でしかないのにかつてそこが地元だったという理由で「ウチ者」(という言い方があるのか?)気取りをする自分のような存在なのではないか。
…と半ば大袈裟に嘆いてしまったかもしれないが、自分の中で地元に対するそういう後ろめたさがずっとあったことは事実で、それがどんどん濃くなり、今、手が付けられないことになっている。『里山通信』は小さい書物だが、それを暴くには十分な内容の充実度であったし、言葉が詰め込まれていた。元「ウチ者」こそ、反省的に地元を語らねばならないのだ。しっかりせいよ!と肩を叩かれる気分。
『里山通信』を読みながら、自然と、コロナ禍の初期のことを思い出していた。2020年の5月、近くのゲストハウスが日中デイユースで貸し出されていたのを利用して、5畳間の畳の部屋で、そこで地元にいる祖父母のもとに電話をかけまくっていた。あの頃の私は祖母に「石川県に帰りたい」「田んぼ道を歩いて風に吹かれたい」などと延々愚痴り続けていたのだった。この3年で、一人の祖母と、一人の祖父を亡くした。どちらも最期をみとることはできなかった。あの時電話をかけ続けていたのは、もう二度とこの人に会えないかもしれないという切迫感でもあったし、なぜ私は離れた土地に住んでしまったのだろうという後悔と罪悪感でもあった。
でもそこに、それだけでは言いようのない、石川県という土地への、心のそこから湧き上がるような執着も確かにあったのだった。そしてそれは今もかぼそく続いているのだった。
これは一体何なのか。地元愛とは決定的に違う、心のそこから引き付けられるようなこだわりは。それは結局、地元を「ネタ」として捉え、そこに自分を当てはめることで自分を特別がりたいという軽薄な欲求かもしれない。だとしても、そろそろ、この執着の謎と向き合ってみたいのですが、よろしいでしょうか。何をどう語っても「ウチ者」気取りにしかならない私の地元への言葉を懺悔のように晒すので、執着の根っこにあるものを探ることを許してもらえないでしょうか。そしてあわよくば、執着の先にあるものをたぐりよせてみてもよいでしょうか。
最近の私は、誰に謝っているのかもわからないまま、心の中でそんな念仏ばかり呟いている。
サポートいただいた分で無印良品のカレーを購入します
