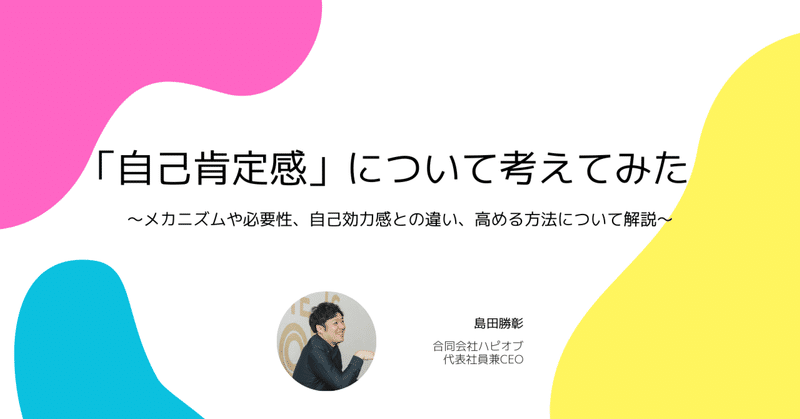
「自己肯定感」について考えてみた〜メカニズムや必要性、自己効力感との違い、高める方法について解説〜
皆さん、こんにちは。
令和元年に内閣府が行った調査によれば、「自分自身に満足している」という人の割合は、欧米諸国が80%台に対して日本は40%台とかなり低い。その他の各項目でも、欧米諸国等と比べて肯定的な意見は日本は少ない。

欧米諸国に比べて「自己肯定感が低い」という刷り込みは、私が学生時代からあった。つまりそれは日本人にとって「既知」なのだ。最近になって分かった傾向というわけでない。
私自身は教育学部出身ということで、自己肯定感については心理学などの観点からも学ばせてもらった。日本人の「謙虚さ」との関係性など、この事実は国民性とも絡んだ複雑な事情がある。
国際比較が全てではないが、ひとりの人間として自分に自信を持って生きることは、人生に満足する上では不可欠だと考えている。
今回の記事は「自己肯定感」について、そのメカニズムや必要性、私なりの高める方法などについてまとめてみた。自己肯定感と同じく重要性が高まっている「自己効力感」との違いにも触れる。
「自己肯定感」とは
「自己肯定感」とは、自らの在り方を積極的に評価できる感情、自らの価値や存在意義を肯定できる感情などを意味する言葉である。しかし、定まった定義はなく、他の類似概念との弁別も充分とは言えない。
上記の通り、そもそも「自己肯定感」という言葉はには定まった定義が存在しておらず、専門家によってその解釈は少しずつ異なっている。また、類似の自尊感情との違いが明確になっておらず、なんとなく言葉のイメージだけが先行しているのが現状だ。
私としては、「自信」や「受容」などのあらゆる肯定的な心理的要素の包括的名称となっているとの認識が最も理解しやすい。自らの現状や環境に対して様々な観点から肯定できるか。これが自己肯定感の根底だ。
「自己肯定感」のメカニズム
欧米諸国との自己肯定感の数値の違いを語る上で欠かせないのが「教育」の視点だ。発達期待(どんな人間に育ってほしいか)の視点で見ると、アメリカなどでは「自信を持てる子」が多数なのに対して、日本では「共感や同情・他の人への心配りができる子」が多数となる。
アメリカなどの欧米では、自己主張そのものに肯定的な文化があるが、日本では他人への配慮に肯定的な文化がある。その違いが、自己肯定感の違いを生み出している可能性は極めて高い。人間は、親や周囲の期待に応えて成長する生き物だ。それは世界共通である。
おそらくほとんどの日本人が、幼少期に「思いやりのある子になりなさい」と言われたことがあるのではないだろうか。私もよく言われた。それが悪いとは全く思わないが、少し言葉不足なのかもしれない。
最近は欧米諸国を見習って、日本でも自己肯定感を高めようと様々な取り組みが行われているが、文化的背景が違う中で表面上の取り組みをマネたところで結果はほとんど変わらないと考える。そもそも自己肯定感の定義すら曖昧なのだから、もっと議論の本質を問い直す必要があると私は思う。
「自己肯定感」の必要性
では、自己肯定感の必要性をどのように「定義し直す」のが良いか。それは先の示したグラフの「満足」の定義を揃えることだ。これは私の感覚的な意見ではあるが、日本人は人生の満足を「今」でなく「未来や過去」に置いている人が多い。
現時点でどれだけ満足しているか?と聞かれた時に、日本人の多くはゴール地点やスタート地点と比較する。つまり、自分自身の中で相対的に満足度を導こうとする。また、他人などの周囲との比較もあるだろう。
なぜ、現代において「自己肯定感」の必要性が増しているのか。それは、もっと多くの日本人が「今」に対して肯定してほしいという切なる願いが込められているのではないか。私はそのように解釈する。
少し前に「ウェルビーイング」に関する記事も書いた。この概念も似たような視点があると思っている。つまり、手段に目を向けるのではなく、今の状態や感情に素直になるということだ。「素直になる」という部分は、日本の国民性(強み)でもある。
「自己効力感」との違い
「自己効力感」という、自己肯定感と似た言葉がある。この言葉は、スタンフォード大学教授のアルバート・バンデューラ博士によって提唱され、恐怖症を克服した人の共通点を「自己効力感」として定義した。
一般的には、「自分は困難を克服できる」「自分は現状を変えることができる」と思うチカラ、チャレンジ精神や立ち直りの早さなどが該当する。この自己効力感こそ、現代のスタートアップ界隈に必要なマインドではないだろうか。
このように考えれば、似た言葉でも、その言葉の持つ性質は大きく異なることは理解できるのではないだろうか。「自信があるかどうか」の視点は、自己肯定感よりも自己効力感で示す方が適切なのかもしれない。自己肯定感が包括的要素であると考えると、自己効力感が部分的要素とも言える。

「自己肯定感」の高め方
では、どのように「今」を肯定するのか。この点については、普段から私が研修などでもお伝えしている視点も含めて書きたい。まず、私がよく研修でも見せる画像をご覧いただきたい。

見たことがある人も多いと思うが、これは「騙し絵」だ。見る視点によって見える絵が違うというもので、左も右も、それぞれどんな絵に見えるかは人によって異なる。
つまり、人生の「今」についても、捉えるポイントが違えば良くも悪くも見えるのだ。今いる場所が正しいとか間違っているではなく、正しいと思える角度から捉えることができているかの方が大切である。
冒頭で示した内閣府の調査も、捉え方によっては悪いデータに見えがちだが、そもそもあれは自己肯定感の低さを示したデータではなく(そもそも自己肯定感の定義が曖昧)、さらには日本人の発達期待の観点から見れば、周囲の期待に応えて育っている証拠とも言える。もちろん、日本人の発達期待そのものが良いか悪いかは別の問題だ。
「今」を多面的に捉えて、ポジティブな部分を見つけ、素直に受容する。この繰り返しが、結果的には「今」を肯定すること、今回の記事の定義でいう「自己肯定感」の向上に繋がっていく。人生の中で行っている数々のチャレンジは、今を多面的に捉える手段のひとつであるとも思っている。
私たちの機会提供
私自身は、人生の満足を高める上で、「今を肯定する」ことがとても重要であると考えている。これができれば、内閣府の調査項目にもなっている「自分の強みがあるか」「自分の考えをはっきり相手に伝えることができるか」「今が楽しければよいと思う」などの数値も自然と上がっていくはずだ。
私が代表を務めるハピオブでは、「すべての人が活躍する社会をつくる」というビジョンを掲げており、活躍を「イキイキと目覚ましく活動していること」と定義している。
そのような社会を実現するために、様々なプロジェクト創造に努めており、社会人には複業兼業の環境を、大学生にはインターンシップを、高校生には対話コミュニティのサービスを提供している。このような機会提供のすべては「今を肯定する」ことを目的にしている。
成功体験は、人生そのものを肯定する上でたしかに必要だが、それ以上に、「今を肯定する視点を持つ」ことの方が私は重要だと思っている。今後もさらにこのような環境を増やすことに邁進していきたい。
一緒に取り組む仲間を募集中
ハピオブでは、今を肯定できる環境を作り、「すべての人が活躍する社会をつくる」というビジョンの達成に向けて、様々な取り組みに挑戦中です。もしこのようなアクションに興味のある方がいれば、遠慮なく私のTwitterにダイレクトメッセージをいただけると幸いです。もちろん、プロジェクトそのものに参加したい方も大歓迎です。お待ちしています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
