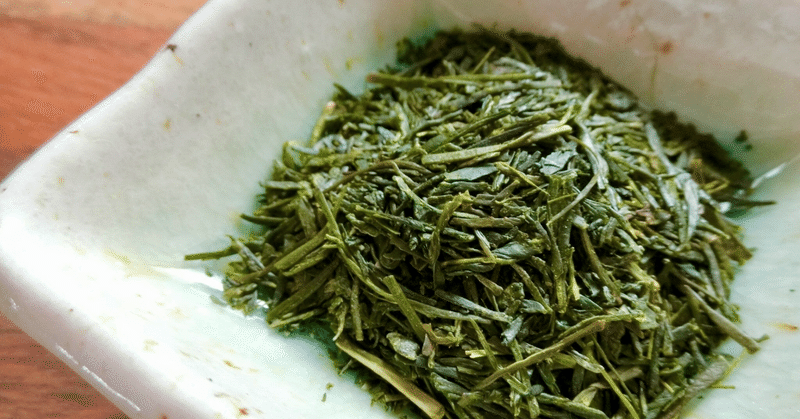
おもてなしを受けるときは相手の設定した文脈に注目するべし
コルクラボの定例会でサディこと佐渡島さんとTeaRoomの岩本さんとの対談を聴いた。岩本さんはお茶の世界のスペシャリストだ。お茶を嗜好品としてだけでなく、歴史や政治的な背景から理解・研究されている。
よってこの日はお茶のおいしい淹れかた、の話は2分くらいで(しかも対談前にさくっと教わった)普段聞けない世界にいきなり突入したのだった。
ぼくは対談の内容をnoteにしようと思ったけど、正直理解できた話は数パーセントでうまく言語化できる気がしなかった。そこでメモしておいた単語を持ち帰って、お茶をのみながら消化できたものをひとつ紹介したいと思う。
おもてなしは相手の設定した文脈を理解できると良い
岩本さんから、『水を窯に戻す音とお湯を窯に戻す音は違う』という話を頂いて驚いた。普通に生活をしていたら気づくことは難しいが、長く関わっているひとにはわかるという。
おもてなしの世界を理解するにはこうした感性を磨く必要がある。
他の例では料亭や旅館に行くときに見かける『打ち水』にまつわる文脈の話があった。あれはゲストが来る15分くらい前に行うことによって、空気のひんやり感が得られるものらしいのだけど(かけたらすぐにひんやりするものではないらしい)知っているひとは、そのおもてなしの心に気がつき、スタッフさんにお礼の一声をかけているそう。
それも「わざわざ打ち水あざーす」みたいな直接的な表現ではなく「植木の葉に滴る水が美しいですね」といった言葉選びをする。
打ち水をするかたのおもてなしの文脈をゲストが読み取って、文脈のなかでおこたえする。できるゲストにはさらに次のおもてなしが発生する。他のゲストには使わない茶器や食器がでてきたり、支配人からご挨拶をうけることもあるだろう。
目に見えない文脈に気づき、キャッチボールの取れるかたはVIPになっていく。考えてみればどんな世界にも起こりうる話だけど、大事な話のように思えた。
そういえば、ぼくのまわりにも似たような出来事があったのだった。
ぼくは妻の実家に里帰りをすると、とんでもないおもてなしを受ける。ぼくのムスコよりもだ。申し訳なく思うときもあるんだけど、きっかけがある。
ずっと昔、大学生の頃にはじめて遊びにに行かせてもらったときの話。ぼくはお母さんが出してくれた山菜のおひたしをうまそうに食べていたのだった。
ぼくは田舎の山育ちなので、ウドやミョウガ、ワラビといった食材がめちゃくちゃ好きなんだけど(酒のつまみにも最高だよね)妻の姉妹はお酒もぼちぼちで山菜も食べ飽きているのかそんなに口にしない。まぁ郷土料理ってそんなものだと思うんだけどインパクトはあったようで。
特にいくつかの食材はぼくの実家ではなかなか手に入らないことも知っていたので、それらを多めに入れて欲しいと伝えてお代わりをさせてもらった。こんなにピンポイントで食うやつはいないだろう。
すると、お父さんが「ふきは好きかね」と自作の酢漬けを出す。ひと切れでご飯がお代わりできる破壊力だ。
妻はその様子をぽかんとしながら見ていた。
あんたそんなに食うんかい、という心の声が聞こえていた。
お父さんはふきを食べるぼくに魔王(焼酎)のボトルをチラ見せする。
「ま、まおーがあるんですか!???」
その貴重さを理解していたぼくは正座をした。目からハートが飛び出して顔に飲ませろと太字で書いてあったと思う。
魔王のラベルを見た瞬間に正座をした男をみて、お父さんはとても喜んでくれたのだった。その後、ぼくは家族の一員になり付き合いは10年を超えるんだけど、いまだにかわいがってもらっている。
あれは奇跡だったな(遠い目)
さて、大幅に脱線したけど、相手のおもてなしの文脈に気がついて、コミュニケーションをとれる力があれば新しい世界が開かれていく、というのはほんとそうだなと思った。
このひとは違いがわかるひとだ、わたしが大事にしているものを理解してくれるひとだ、と伝わることは大きいよね。
ぼくはもっと感性を磨いて見えないものに気がつけるようになりたいと強く感じたのでした。
それでは今日も読んで下さりありがとうございました!
頂いたサポートは、次に記事を書く時のアイス代にしたいと思います!
