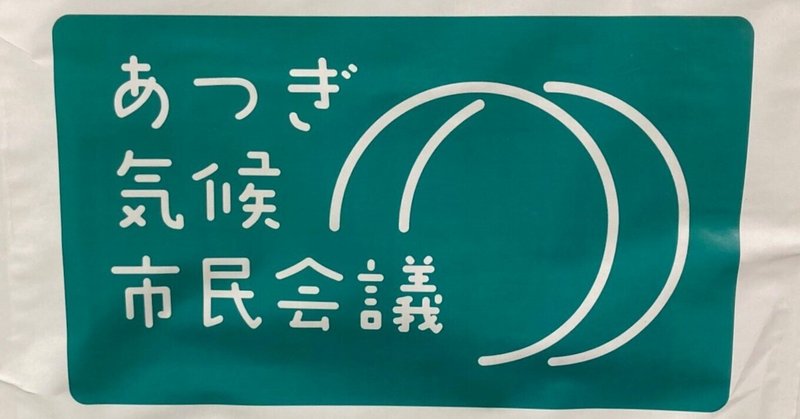
あつぎ気候市民会議の展開<第2段階へ>
〇第4回あつぎ気候市民会議・・・理解から討議へ
6月18日から始まった「あつぎ気候市民会議」は、9月17日に第4回を迎えました。
私は、今までは、動画資料を見ていましたが、今回は現地で傍聴できることになりました。
会場は、本厚木駅から徒歩5分の複合ビルの7階です。

これまでのあつぎ気候市民会議は、
第1回(6/18)オリエンテーション、気候変動問題の理解、じぶんごと化
第2回(7/16)厚木市の地域特性 カーボンニュートラルロードマップを理解 2050イメージを思い描く
第3回(8/20)テーマ別脱炭素への取組を知る
と、専門家から科学的知見をわかりやすく話してもらい、神奈川県や厚木市からも説明を受けて来た段階でした。
この第4回からは、討議となります。
第4回(9/17)テーマ別アクションプランを出し合う(分科会形式)
第5回(10/15)テーマ別アクションプランを深める(分科会形式)
第6回(11/26)アクションプランを作り上げる 2050イメージ見直し 一人ずつの意思を投票で反映
と予定されています。
〇ここで一つの手法・・・テキスト分析
さて、この第4回からは、アクションプランの市民提案の具体的内容を討議していくことになりますが、ここで事務局により一つの手法が使われました。
それは、第3回会議で出された参加者の意見・アクションプランのタネについて、テキスト分析を行い、枠組みを作ることです。

このテキスト分析により、事務局がアクションプランの枠組みを作り、それが示されました。あつぎ気候市民会議のHPにも掲載されています。

この枠組み自体を皆で議論して決めることもあり得るでしょうが、内容そのものの議論でもないので、特段の指摘がなければ、テキスト分析ということで、事務的にやることを是としてもらっているということだと考えます。
この枠組みに基づき、AとBの分科会に分かれ討議が行われます。AとBの分類は次の資料の通りです。

Aの部屋には、ファシリテーターも含め7,8人のグループが「い」「ろ」「は」「に」と4つ。Bの部屋には、「ほ」「へ」「と」と3つのグループがそれぞれ机を囲み、司会者席、講師席、傍聴席が回りに置かれていました。
〇脱炭素市民アクションプランの討議のあり方
会場で知り合いが傍聴に来ていて、Aの部屋に入ったので、Aの様子は後で聞くこともできるかと考え、私はBの部屋に入りました。
13時。はじめに、鷺谷雅敏実行委員長(あつぎ市民発電所・副理事長)より、今日は後半戦のスタート。これからは討議との話がありました。
そして、脱炭素市民アクションプランのあり方として、「市民」が2050年カーボンニュートラルに向けて描く社会、「市民が主体的に行う行動」、アクションプランの主語は「市民」であるとされました。
投影されたパワーポイントや配布資料にも、次のような記述がありました。
「市民が」〇〇する
「市民が」△△の実現のため〇〇する
「市民が」〇〇する そのために「市」(または事業者、企業など)が××する
「市民が」〇〇する そのために□□□の整備や条件が欠かせない
市民、行政、事業者に向けての提案で、身近なことから、社会システムの変更で効果があがることまで多様なもの。自分たちが行う行動で、自分たちだけでできなければ、みんなで行うことを考える。適切な補助金や規制を求めることもある。ただ、それらは市民が示すあるべき姿を後押しするものとしての位置づけである。等の趣旨のことが話されました。
また、テキスト分析について、会議中の様々な記録をリスト化し、アクションプランのグループ化、枠組み作りを事務局でしたことも説明されました。
ここで、各グループ内で自己紹介やこれまでの会議で興味を持った点を披露。Bの部屋全体で2名ほど欠席のようでした。自己紹介の中で、「前回は欠席しましたが」等の話も聞こえて来ました。
〇B-1 「省エネ・すまい」
13時20分。ここからは、分類されたテーマについて、掘り下げる話題提供ということで、この政策はこのように取り進めると考える材料としての専門家の話がありました。
Bの分科会は、まず、B-1の「省エネ・すまい」のテーマについて、
綿田茜氏(エコ窓普及促進会)「窓の断熱で省エネ&健康な住宅」
伊藤敦範氏((有)コムアソシエイツ代表取締役)「「住まい」の省エネを考える 設計・建築家の視点から」
青砥航次氏(厚木市民・NPO法人神奈川自然保護協会)「太陽熱の利用」
山本佳嗣氏(東京工芸大学工学部工学科建築コース建築環境計画研究室准教授)「省エネ家電 建物の消費エネルギー」
と、4人の方から10分ぐらいずつ報告がありました。
樹脂サッシ、ゼッチ等、内容も大変興味深いのですが、あつぎ市民気候会議のHPの動画資料に譲りたいと思います。
〇グループ「討議」のやり方
(14時12分から14時45分)グループディスカッションですが、かながわ気候市民会議in逗子・葉山でもそうでしたが、理解のためのものは皆で疑問点を出してその後に講師に聞く等をしていましたが、今回は討議です。質問があれば、グループ討議の最中に講師をそこに呼び出して聞くということはできることになっていましたが、討議の方は次のような段取りで行われました。
グループ討議では、重要だと思ったこと、アクションプランに取り入れたいことをピンクの付箋に書き出す。
ピンクの付箋の内容について、実現したいけれど課題になりそうなことを水色の付箋に書き出す。
ファシリティーターが緑色の付箋で出された話題がどの分類になるか、テキスト分析をもとに事務局で作った枠組みの番号を書いていく。
見てみると、ピンクがたくさん出ているところと、出されえたものに議論が深まり、ピンクと青が同じぐらい出ているところがありました。グループ討議の後の、各グループの発表は次のようなものでした。
窓がなく、低い天井で、脱炭素に優れた住まいを、暮らしにくいものではなく、ディスプレイや様々のテクノロジーを駆使して、暮らしやすいものとして提供する。
賃貸マンションやビルのオーナーに、住んでいる人がアピールしなければ、脱炭素は進まないので、みんなで意見を持てるために、理解を深める勉強会を市民講座等で実施する。
壁、屋根、窓を既に省エネなものにした体験者がグループ内に多かったが、するにしても自費負担だったので、業者選定、耐久性、信憑性等の体験談共有や行政による情報提示の仕組みを求めたい。
〇ここまでのやりとりについての疑問点をスタッフに聞く。
14時49分、休憩。
休み時間に、広報スタッフのイワサキさんとお話をすることができました。
質問1:脱炭素アクションプランの内容を討議する段になって、確かに幅広い要素を内容とするものもあったが、直前の講師の話題提供に引っ張られる可能性があるのでは。
答え:講師の話の中に、重要と思うものがあれば、その点の討議を行えば良いが、今日、話が出なかったことでもB-1の「省エネ・住まい」に関することであれば、持ち出してもらって良いことになっている。そこは各グループのファシリテーターが促すとか確認する等の役割を果たす。
質問2:脱炭素のために市民が何をやるかが強調されていたが、フランスの気候会議の結論が法改正に繋がった点や、熟議民主主義というと、政治、すなわち未来の選択を必要に応じて権限を持って実現するものの一形態との印象からすると、若干の違和感がある。
答え:市民が何をやるかの話についてだが、そのために市や事業者等が何をやるか、あるいはどういう制度の整備等が必要かというとの話も合わせて討議するので、広がりがあるものと考える。それから、行政のための会議とか、行政の下で市民が何をするかのための会議というふうに考えるのは、自分としても違うと思う。この会議の結果は、当然に市長や市議会の意思決定に影響を及ぼすべきものと考える。特に厚木の場合、この会議は、厚木市市民協働推進条例に基づく、あつぎ市民発電所という市民の団体と厚木市の協働事業なのだから。厚木市も、この会議の結果をしっかり政策に取り入れる必要がある。協働パートナーで一緒にやっているのだから。そこで出て来たものを市議会でもしっかり議論し意思決定していくことも多いに想定している。
(やりとりを、問と答えという形にしたので、実際、私がこういうことですかねと言って確認したことも、先方の答えという形で示す等している。)
現場での傍聴では、スタッフの方とこういう意見交換ができるのが一番ありがたいです。こちらの認識と共感する部分もあるとしてくださったり。まさに日本の熟議民主主義の最先端を、フロンティアを、いろいろ考えながら進んでいらっしゃるのだなと思いました。かながわ気候市民会議in逗子・葉山の関係者の方お二人も傍聴に来られていました。そのお二人ともお話することができました。こうした点でもフロンティア感が一層高まりました。
〇後半、B-2「消費・食・農・廃棄」
15時から、2つめのテーマについて、前半と同様な段取りが進みました。
浅利美鈴氏(京都大学大学院地球環境学堂・総合地球環境学研究所)
「大量消費・大量廃棄を見直すライフスタイル 実践紹介」
衣川晃氏(茅ヶ崎市はちいち農園)
「世界で注目されている耕さない農業 不耕起栽培」
浅利氏の話の対象範囲が広いこともあり、30分ほど(オンライン参加でまとめての質疑応答もあり。)、衣川氏が10分程度。こちらも大変興味深い内容ですが、内容は、あつぎ気候市民会議のHPに譲りたいと思います。
この後、第2回目のグループ討議となりました。
〇おわりに
気候市民会議は、今までの問題認識のフェーズから討議のフェーズに移り、テキスト分析での事務局による枠組整理、「討議」のためのグループディスカッションというように、手法の展開も確認できました。
ただ、その間も、何のための会議なのかという点、傍聴していて、どれだけどう感じられるかということが気になっていました。考え方の始点を市民が何をするかとし、市や事業者の行動へ広げて、必要な制度の整備等も念頭に置くと説明はされていましたが、どこまで本当にそうなるかということへの疑いを晴らす、第5回、第6回となることを期待したいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
