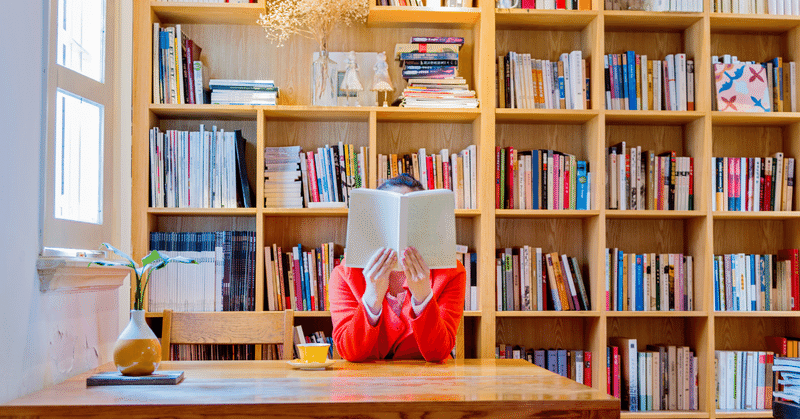
「読む」だけでは読解力は上がらない
国語(日本語)を教えているときに、よく保護者から「読解力を上げるには読書をたくさんした方がいいですか?」という質問をされます。
たしかに、「読解力」とはまさに「読み解く力」なので、読むという経験の積み重ねが大切であることは疑いようがありません。
でも、「読む」だけで自然と読解力が身につくのか?と尋ねられると、それは違うと思います。「読書好き=国語が得意」とは限らないということです。
読書はどこまで有効なの?
読書に対するある種の「信仰」は昔から根強い気がしています。
「〇〇君はよく本を読んでいるから勉強ができる」
「読書をしている子は頭がいい」
「国語が苦手ならまずは本を読まないと!」
これらと似たような会話をちらほら耳にします。
たしかに、本を通して吸収する語彙もあるし、慣れてくれば読むスピードも少しは上がるかもしれません。まとまった文章を読むための基礎的なスタミナも身につくはずです。
でも、読解力が身につくことはイコールではありません。
きちんとした統計ではないのですが、今までの自分の経験として、「本は好きだけど、国語はそこまで得意じゃない」という子は結構いました。極端に国語が苦手という子はいませんでしたが、読書をしているからといって国語の成績が上位になるわけではありません。
つまり、「うちの子は本をよく読んでいるから国語(日本語)は大丈夫」とはならないということです。
インプットとアウトプットのバランス
よく英語で「読む・書く・聞く・話す」の4技能が大切だと言われますが、同じく言語である以上、日本語だってそうです。
どうしても従来のテストでは、「読む」技能を測る設問が大多数だったので、そちらに目が行きがちですが、それ以外の要素も欠かせない存在です。
「読む」というのは、インプット型の作業ですが、それだけでは読解力は伸びていきません。「読む」ことを通してインプットした情報を、頭の中で分析して整理して、もう一度アウトプットすることが大切だと思います。
外国語学習だって同じではないでしょうか?
ひたすら多読精読を繰り返していても、実際にライティングやスピーキングの練習をしなかったら、語学力は伸びていかないですよね。
母語である日本語も同じことが言えます。
たしかに日常的な会話は自然と習得していきますが、論理的な読解力や表現力を身につけるためには、インプットとアウトプットを繰り返しながら実践していくしかありません。
「読む」というインプットの一方通行だけでなく、書いたり話したりしてアウトプットする作業が大切だと思います。
効果的なトレーニングは?
こういう話をすると、「じゃあ、一体何をしたらいいんですか?」という苦情質問が保護者からたいてい来ます。
一朝一夕で身につくものではないこと、一つの絶対的なウラワザがあるわけではないことは大前提として、個人的には「要約」のトレーニングが良いと思っています。
方法はいたってシンプルで、「読んだ文章を要約して書く」だけです。いきなり長い素材からはじめると挫折してしまうので、短い文章から始めるのがおすすめです。たとえば、200字の文章を50字程度に要約します。
物語は結構難しいので、ニュースや説明文などのような文章の方が扱いやすいと思います。
なぜ要約が良いのかというと、主体的に読む姿勢が身につくからです。漠然と読んでいるだけでは、要約に必要な文章の要旨を見抜くことはできません。「しっかり読んで!」と言われるだけでは伝わりませんが、要約というゴールがあることで、やるべきことが明確になります。
もちろん要約の練習は、子どもだけでなく大人にも効果的です。お子さんがいらっしゃる場合には、家族で一緒にやってみるといいかもしれませんね。
「聞く」「話す」のトレーニング
年齢が小さいお子さんや読むことに抵抗のある人の場合は、聞いた情報を要約してアウトプットする練習もおすすめです。
特に小学校低学年くらいまでは、耳から情報を理解する力が優れているそうなので、本の読み聞かせでもいいと思います。単純に「早く自力で本を読める方がいい」ということではなく、年齢や発達に合わせたアプローチが大切です。
小さい子が要約をするのは難しいと思うので、読んだ本の振り返りを一緒にしてあげると良いと思います。絵本の読み聞かせについては、三森ゆりか先生の『絵本で育てる情報分析力』がとても勉強になりました。
すべてをいきなり家庭で実践するのは大変そうですが、一つひとつの項目はとても参考になるので、少しずつ取り入れてみてもいいかもしれません。
ちなみに、大人がやってみても結構苦戦しそうなので、題材は「絵本」中心ですが、高校生や大学生くらいまで十分有効なトレーニングだと思います。
「読書」のその先で一体何をしたらいいのか、ということのアイディアがたくさん詰まっています。
また、ニュース動画の要約も良い練習になると思います。メモを取りながらニュースを見て、それを元にして要約するトレーニングです。
「文章アレルギー」のあるお子さんは、まずはこうした動画の要約から始めてみると、だんだん慣れてくるかもしれません。ただ、最終的には文章を読んで要約できるようになることが目標です。
いろいろなアプローチを試してみる
「要約がいい」と書きましたが、これすらも数あるアプローチの中の一つに過ぎません。いろいろな経験を通して、国語力は上がっていくものだと思うからです。
教科書や問題集も勿論役立ちますが、料理のレシピでもスポーツの実況中継でも、いろいろなものが学びの材料になります。
冒頭で挙げた「読解力を上げるには読書をたくさんした方がいいですか?」という質問。
わたし自身、読書は大好きですし、多くの文章に触れることにはメリットもあります。ただし、これは「趣味」としての読書です。
たくさん本を読めば読解力が上がる、というのは過剰な期待かもしれません。
そもそも、おそらく読解力をピンポイントで上げていく方法は無いのではないかと思います。表現力とか思考力とか、様々な要素が組み合わさって、全体的に成長していくものではないでしょうか。
だからこそ、いろいろなアプローチが大切ですし、インプットだけでなくアウトプットも組み合わせていく必要があると考えています。
わたし自身もまだまだ試行錯誤の連続ですが、主体的に取り組めるような仕組みについて、これからも考えていきたいと思います。
みな
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
