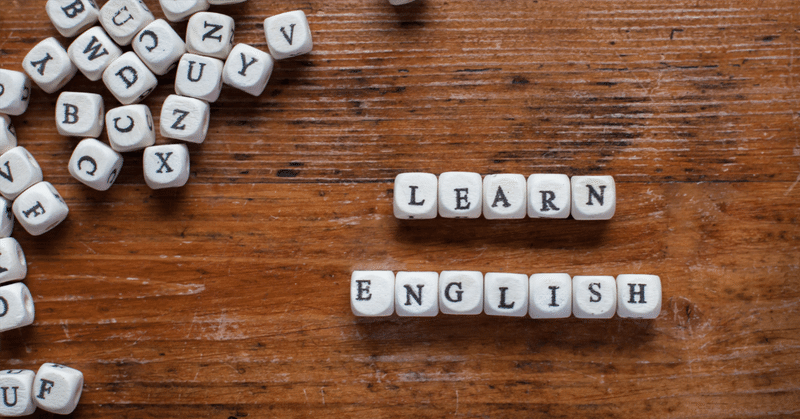
幼少期にできあがった「英語嫌い」を克服できたターニングポイント
今でこそ海外での生活が10年を超え、周囲で日本語以外が飛び交う環境が「日常」になりましたが、子どもの頃は英語の勉強がとにかく嫌いでした。
わたし自身は日本生まれ日本育ち。両親や親戚もみんな「日本人」で、海外との関わりはほぼゼロでした。
ところが、割と教育熱心な家庭だったこともあり、2歳になる頃には習い事をスタート。自分ではまったく覚えていませんが、2歳ごろから週に何度か英語の教室に通っていたそうです。
幼稚園の年長ぐらいになると、断片的な記憶がちらほら残っています。その頃は「お勉強」というよりも、ネイティブの先生と一緒に「遊ぶ」という感覚だったので、まだ楽しめていたようです。夏休みには英語のサマーキャンプにも通っていた、という話を親から聞いたこともあります。
***
英語に対する苦手意識やマイナスイメージが強くなったのは、小学1年生のとき。この頃から「お勉強」の要素が強くなり、宿題やテストの量も一気に増えました。
単語の綴りが全然覚えられなくて、夜遅くまで泣きながら勉強させられた記憶が今もはっきり残っています。「important」と「introduce」を何度も書かされたのはトラウマです笑。当時小1だった自分は「重要」も「紹介」も漢字すら読めなくて、単語の意味もよく分からず、ただひたすら丸暗記しようとしていました。
文法も散々で、「三人称単数?受動態?過去分詞?何ソレ???」という感じで、頭の中は常に疑問符でいっぱいでした。でも、子どもなりの適応力で「何となーく」雰囲気を掴むことはできていて、課されるテストではそこそこ成績が良かったため、周囲の大人は「大丈夫そう」と判断してしまったのだと思います。
そんなこんなで、大人の目線からは「トントン拍子」で学習が進み、小学校を卒業するまでの間に英検2級までは取得することができました。
実際にはほとんど理解できていませんでしたが、対策をギュウギュウに詰め込まれていたので、問題を処理する能力だけは身についていたのだと思います。マークシート問題ならでは……ですね。
中学校に上がるタイミングで他の教科との学習の兼ね合いもあり、ようやく英語学習を一旦ストップすることができました。
***
いま自分自身が教育に携わる仕事をしていますが、改めて振り返ると「なんて無茶&無意味な指導だったんだ……」と思わずにいられません。このときの苦い経験は、いまも「反面教師」として心に残っています。
こうして、自分の中で「英語が嫌い!」という感覚が、幼い頃から小学生にかけてジワジワと、そして確実に形成されていきました。
もちろん、あの頃の英語の勉強がすべて無駄だったとは思いません。中学校の英語の授業ではだいぶ余裕があったので、他の教科に集中することができましたし、英検の存在は内申点でもプラスになりました。
ただ、進学した県立高校は帰国生や海外にルーツを持つ子が多く通う学校で、当時の自分は「井の中の蛙」状態だったと気付かされました笑。
「あんなに辛かったのに、この程度のアドバンテージだったのか」とちょっと落ち込んだ記憶もあります。英語でエッセイもすらすら書けいないし、スピーチも苦手。まさに「勉強したけど、英語が使えない人間」の典型でした。
当時わたしが受けた「センター試験」はマークシート方式だったので、そこそこ得点はできましたが、英語学習に対するモチベーションはそれほど高まることはありませんでした。
***
さて、ここまでマイナスのエピソードばかりでしたが、大学に入ってからようやく転換点が訪れます!
ちょっとした思いつきと瞬発力で、20歳で初のパスポートを取得し、単身でタイに1ヶ月滞在することになったのです。
そして、その約半年後には、今度はカンボジアに1ヶ月滞在。それ以降、カンボジアを中心として、東南アジアに何度も足を運ぶようになりました。
このときの活動を詳しく説明すると長くなるので割愛しますが、これらの海外経験を通して初めて英語を「使う」楽しさを実感しました。
タイやカンボジアは英語圏ではありませんが、お互いの言語がわからないときは、英語を共通語にしてコミュニケーションをする機会が多かったです。特にカンボジアで知り合った友人たちとは、基本的に英語でやり取りをしていました。
***
このときに初めて「もっと英語を勉強したい!」と本心で感じましたし、言葉を学ぶことの楽しさを味わいました。まさにターニングポイントとも呼べる経験です。
また、学生時代の恩師の導きもあり、「英語(日本語以外)で資料を読むこと」の大切さも教えてもらいました。英語ができることで、アクセスできる情報の幅が広がるということを実感した経験が何度もあります。
幼少期は親や先生に言われるがまま英語を勉強させられてきましたが、大人になってから自分で学習目的を見つけたことで、一気に学びが楽しくなりました。
英語学習に限った話ではなく、学習全般に関しても同じことが言えるのではないでしょうか。「学び」をどうやって「自分事」に結びつけるかが大切だと思います。
ちなみに、幼少期から英語学習を始めることを非難するつもりはまったくありません。上記はすべてわたしの個人的な体験談です。さまざまな要因が絡み合った結果、わたしは当時の環境が合いませんでした。
「嫌だ」という意志をはっきり示すことができれば良かったのかもしれませんね。1歳下の妹は小学校低学年で「もう飽きたー」とあっさり辞めてしまい笑、わたしは隣で恨めしく眺めていました。
***
ただ、人生どこで転じるか分からないものですね。
「英語なんてもう嫌だー!」と泣きながら通っていたあの頃は、将来自分が海外で働くことになるなんて考えもしませんでした笑。
ちなみに、いま「英語は好きですか?」と聞かれたら、迷わず「好きです」と答えられます。
コミュニケーションツールとしての英語には幾度となく助けられてきましたし、英語を通じて広がった繋がりも貴重な財産です。これからも何かしらの形で、英語学習は身近な存在として続いていくのだと思います。
英語をはじめとする外国語に対する教育熱や需要は、日本でもまだまだ高まっていきそうですが、「どうやって英語と付き合っていくのか」というテーマはまだまだ議論の余地がありそうです。
唯一の「正解」があるものではありませんが、わたし自身も改めて今後じっくりと考えてみたいと思っています。ぜひ皆さんの意見やアイディアがあったら教えてください〜
みな
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
