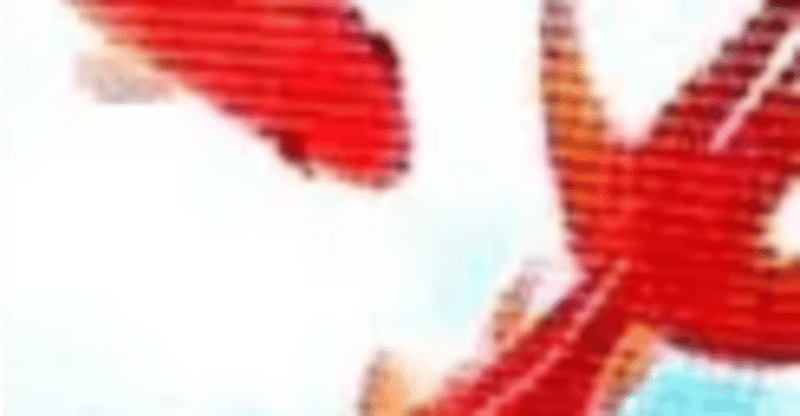
散歩の途中 7
金魚玉
「金魚あずかってくれないかしら」
勘定済ませてニュースの終いあたりのナイターの結果を見て腰を上げようとしていたらふみさんが金魚を目の前に差し出した。
何の変哲も無い赤一色の金魚2匹。ただ珍しいのは丸いガラスの玉に入って、ぶら下がるように紐が付いている。ガラスは手作りの感じで青い縁取りがしゃれている。
ふみは駅から桟橋のある港に行く途中にある小さな居酒屋である。ママさんの名前がふみ子だったのかふみえだったのか、結局知らないままだ。
なじみの客は「ふみさん」と呼んでいたが、そのふみさんが幾つなのか、どうしてこの町に来たのかは誰も知らないままだった。
酔った勢いで尋ねる客もいたが、ふみさんはあいまいな返事で話をうまく逸らせた。四十を少し行ったところ、生まれは九州、その後暮らしたのは大阪あたり、と見当がついた。聞いたわけではないが、週に一、二度通っているとちょっとした話しぶりに訛りが残る。関西弁は後付けだ。
のれんを出して三年目。カウンターに季節の菜、煮しめや瀬戸の小魚をうまく取り入れ、中鉢に盛り、客はそれを勝手に注文した。一人暮らしにはここで晩飯代わりに1,2本呑み、菜を頼めば十分で、仕事が早上がりのときは此処によってアパートに帰った。
ふみさんは不思議な人で、自分のことは何ひとつ喋らないけれど、人の話を聞くのは上手でいつの間にかカウンター越しにいろんな話をしてしまう。7人しか座れない狭い店で、常連客半分。あとは通りすがりというか、駅前と桟橋前のホテルに宿泊した造船所や港湾関係の出張者がほんのりとした赤提灯とのれんの「酒処ふみ」の手描き文字に引かれて立ち寄る。
繁盛していた。客の途切れることはなかった。小店のカウンターの中でのふみさんの背筋を伸ばした姿が美しかった。それでいて女ひとり生きている、という感じさせない潔さがあった。
ぼくなんぞはみっともなく生きて、仕事場の人づきあいにうんざりして、駆け込むようにこの店にやってきた。そんなときもふみさんは3杯目のコップ酒あたりから話の聞き役に回った。
ふみさんの金魚はそんなわけでアパートにいる。3日に一度、前夜取り置いた水で変えてやる。金魚は店に来た客が祭りの夜店で掬ったのをビニールで持ってきたのをそのまま置いて帰ったのをふみさんが2年近く飼っていたらしい。青い縁のあるガラス鉢の金魚玉はふみさんが知り合いの骨董屋から手に入れ、水草もいつも替えていた。
金魚の方はといえばどこにでもいる雑魚のような金魚だ。ようく見ると1匹は大きな目をして吊り下げられた鴨居から私をじっと見ている。もう1匹は決して目を合わせようとはしない。
ふみさんはぼくに金魚を託した二日後に、店に「しばらく休みます」と貼り紙して居なくなった。詳細は誰も知らない。店の大家にあたる電気屋の社長が「いろいろ訳ありで」と次の言葉を濁した。
常連の客も、ふみさんのきりっと伸ばした背筋を思い出して、話に深入りはしなかった。ふみさんは人の話はたくさんたくさん聞いたが自分のことは何ひとつ話さなかった。
一人暮らしのぼくも、金魚には困るのだが、元気で生きているので何とか付き合っている。3カ月に一度三日ばかりの出張があるのだが、金魚玉では窮屈だろうとバスタブに水を張ってホテイアオイを浮かべて置いたら、元気に泳ぎ回っていた。
いまはまた金魚玉でおとなしくしている。目を合わせる奴は相変わらずで、もう一匹は知らん顔のままだ。
ふみが閉まってもう半年になるが店はまだあの場所に変わらずある。あれでも灯が点っているのではないかと寄り道をしてみるが、まだあたりは暗いままだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
