
どうやって家族の理解を得たのか?:11年目の二拠点居住~働くところ住むところ~
11年目に入った二拠点居住。
二拠点居住をしている話すと、意外とよく聞かれる質問がある。
✓家族は賛成?反対?
✓(反対だったら)どうやって説得した?
✓どうやって家族の理解を得ているのか?

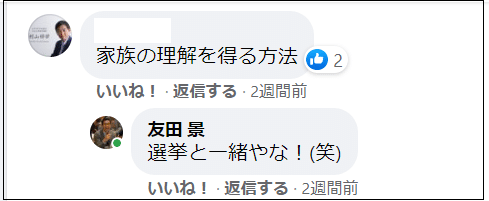
お金や仕事の心配はもちろんだが、
家族がどう思っているのか、家族との関係といった辺りがキーワードになるようだ。
移住・半移住然り。
ただ、一言で家族の理解と言っても、それぞれバックグラウンドが違うため、人によって正解も違うだろうから、アドバイスというより、参考例のひとつと思って読んでいただきたい。
なぜ二拠点居住なのか明確に
二拠点居住を考える場合、
「二拠点居住がしたいのか」
「結果的にそうなるのか」
のどちらかにだと思う。
どちらかによっても、家族への報告もプレゼンも違うだろう。
私の場合、大阪在住で東京で仕事が決まったとき、家族へ(妻へ)はほぼ事後報告だった。
というのも、当時はかなり無茶な働き方をしており、平日は子どもたちの寝顔を見ることしか出来ない日々が続いていた。
その生活を続けることが想像できず、いずれは辞めることになるだろうと思っていたところに東京での仕事のオファーがあった。
声をかけてくださった方と妻が面識があったため、特に問題がなかったというのもある。
(多分ね、、、(苦笑))
ただ私の働く場所が変わるだけで、家族の毎日の暮らしは変わらないということだ。
もし家族が一緒にどちらの拠点でも生活するとなったらまた話は変わってくると思う。
つまり二拠点居住をするにあたって、家族にどうして欲しいのか、自分はどうするつもりなのかを明確にすることは大切な作業だと思う。
奥さんに反対されなかった?
妻は懐が深く、許容範囲の広い人間なので、これまで私の決めたことに反対するということはなかった。
(選挙に出るという話をしたときも同じ感じ。)
学生時代から先輩後輩の関係で、付き合いが長い妻は、私の価値観を熟知しており、私がそういう選択をすることに「この人ならそういう選択をするだろう」と理解してくれていたと思っている。
最早、あきらめの境地かもしれないが、、、
もともと平日は子どもたちの寝顔を見るだけの生活だったため、妻としても生活は特に変わらないと思っていたが、後で聞くといるといないでは全然違うと言われた。。。
つまり、二拠点居住をしなければならない状況になり、結果的に二拠点になったとも言える。
家族みんなが一番幸せになる形を考えた結果、二拠点居住になったというわけだ。
ベストチョイスというより、ベターチョイスではあるけれど。
困ったのは病気の時と食生活
じゃあそれでよろしく、とスムーズにすべてが上手く回るわけではない。
私の場合、2拠点での生活を始めるにあたっての説得や理解は妻のおかげで、それほどひつようではなかった。
がしかし、スタートがスムーズだからといって、その後もスムーズかと言えばそうではない。
もちろん苦労もあったし、問題も起きたりする。
一番困ったのは、病気をしたとき。
喘息の発作が起きたとき、どうしようもなく、一人でタクシーに乗って救急センターへ駆け込んだ。
こういう時、すぐ助けてくれる人がいないということは心身共にに大変堪える。
マンションに誰が住んでいるかも知らないし、近所付き合いもなかったからだ。
処置を終えて、疲れ果てて帰宅し、そのまま寝てしまい、妻への連絡が途絶えて心配をかけてしまった。(この時はえらい怒られた)
次に、食生活。
1人でちゃんとした食生活を続けるのは本当に至難の業だと身に染みた。
健康診断でひっかかったのも東京時代で、今よりもずっと不健康だった。
でも、これらの問題は一人暮らしの場合と同じだろう。
仕事への理解なのか 生き方への理解なのか
私の場合、「二拠点居住がしたい!」と思い立ってこの生活がスタートしたわけではない。
自分がハッピーに働ける・生きるために選んでいったら、こうなっていたとういう感じだ。
ただ、やはり子供たちも成長していくにつれ、いろんなことが分かるようになってくると、自分の父親が周りの親とは違うことに気付いてくるし、思うところもあるかもしれない。
だから、子どもたちには父親がこういう思いを持って働いているよ、ということを折に触れ話すようにしてきた。
妻は学生時代からの知り合いで、付き合いが長いこともあり、長い時間一緒にいるだけあって、私の価値観や行動を大筋理解してくれているように思う。
家族と日常的にコミュニケーションをとり、お互いの考えや思いを共有しておくことで、決めたことに頭から反対されることはなくなる。
何か決断したとき、普段の言動やしぐさから醸し出すものとの間に、違和感やギャップがなければ、きっと家族は喜んで応援してくれるはずだ。
「この人はそういう決断をする人なのだ」という普段からの自身の在り方が、もしものときの理解や信頼につながってくるのではないだろうか。
私にとって大切なのは「何を」「どこで」ではなく、「どう」働くか。
この思いが家族に浸透しているからこそこの生活がいま成り立っていると思う。
誰だって、突然言われたらびっくりするのは当然だ。
何かが起きてからではなく、いつも自分の家族との関係を大切にしておくようにしたいと思っている。
親が子供にしてあげられることはほとんどない
子どもが生まれ「親として子供に何をしてあげられるか」と考えたとき、結局「親は子供に何もしてあげられないんじゃないか」という結論に至った。
家族という深いつながりはあっても、親子は他人であり、親も子供も自分で自分の道を歩いていくしかない、何が起きても自分で乗り越えていくしかないのだと。
それならば、父親として出来ることは何だろうか。
長男が生まれた当時、社会的にいいニュースがなく、女子高生ブームだったりと、大人になることに価値がないという風潮があった。
不満を吐き出す大人の姿を見るからそうなってしまう。
そういう父親の姿は見せたくない。
「大人になることは楽しい」
「早く大人になりたい」
と思ってもらうことなら私にも出来る、と。
「ハッピーな働き方を見せることを徹底的にやろう!」と決めた。
大人の世界は楽しいぞと感じてもらおう。
楽しいと思える仕事を選んで、人生を楽しめるようなチョイスをして、その姿を子どもに見せていきたい、と考えた。
何をしているか、でなく、どう働くかを基準に選んで決めてきたら、結果的に二拠点居住になり今に至る。
が、この生活だってずっと続くか分からない。
なぜなら、私が幸せに働く姿を見せるためにはアンハッピーな選択肢を選ばないと決めているからだ。
いつか二拠点居住がアンハッピーになったら、その時はよりハッピーな選択をするだけだ。
子どものために何かを我慢する、諦める、というのは子どもたちにとっては余計なお世話であって、親が楽しそうに働いていれば、その姿を見て、その風景を一緒に感じていてくれると信じている。
家族には、私のこういう思いをずっと伝えてきた。
だから私の選択や決定は私自身が幸せになるものだ、と家族が理解してくれている。
逆に、私も妻や子どもたちに対して、それぞれの決断を尊重しているし、私が決定権を持たないようにしている。
家族の理解を得る方法 まとめ
丁寧に、時間をかけて、相手を思いやりながら、いつでも自分の思いを本気で伝える。そこに手を抜いてはならないと思う。
そして相手を変えようとしないこと。
自分はこういう人間だ、と
自分も相手を認めるという姿勢と勇気を持って、お互いの選択・決定を受け入れる家族の形を常日頃から意識しておくことをお勧めたい。
このようなことを書いたら、妻から「えらそうに・・・」とお𠮟りを受けそうだが(苦笑)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
