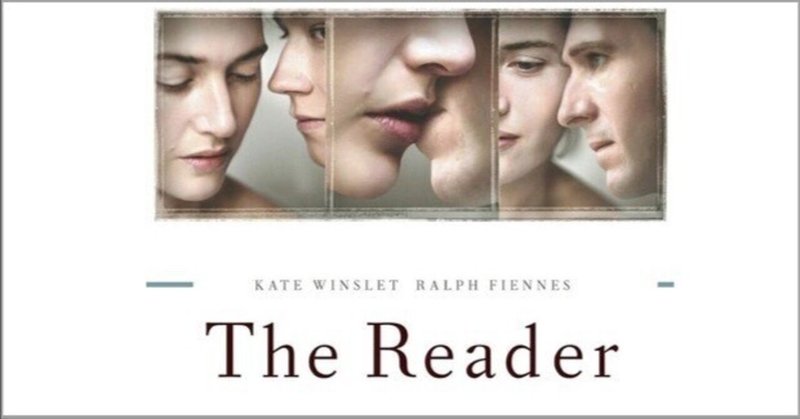
『愛を読むひと(2008)』を観ました。
若い青年と少し年上の女性のラブストーリーと思っていた。
なので、この作品がホロコースト(第二次世界大戦中にナチスドイツがおこなったユダヤ人の大量虐殺)に関係するお話だと知らなかった。
これは日本の宣伝側の「ホロコーストという内容はあまり出さないで、若い男と大人の女性にラブストーリーって感じを前面に出して売りましょう」という方針があったのだと思う。私は逆に、そのイメージで観ようとしてこなかった(なので、日本の宣伝写真や予告はどうしても使えなかったです)。
物語の入り口はラブストーリーというか、官能小説みたいな展開で、年上の女性にのめり込む、若い青年という感じであった。
しかし、そんな若い青年にとって夢のような時期は短い夏のようにあっけなく終わり、年上の女性は突然姿を消してしまう。
若い青年は大学生になり法律を専攻して、その授業の一環である裁判を傍聴する。そこで裁かれている女性が、あの夏に出会った年上の女性であった。
私は個人的に「ホロコーストってなんなのだ?」というのが高校生くらいからあって、そういうドキュメンタリーとか映画を見る人であった。実際にドイツ、ポーランド(アウシュビッツ)やイスラエルに行った時に、「ホロコーストは全然過去のことじゃない」とわかったし、「心の奥に刺さったまま錆びついた釘のような、二度と忘れたりすることのできない問題」であることを知った。
もし「ホロコーストを全然知らない」って人がおられたら、できたら今作を見る前に数分だけ、ドキュメンタリー(例えば以下のような)とかと見てから観られるといいかと思います。きっとよりこの映画に入り込めるんではないかと。
実際私たちは、住んでいる国の方針に従わないって選択は、なかなかできないと思うし、かつて日本が戦争中に「戦争はやらない方がいい」って言ったら「こいつは非国民だ!」とかで逮捕されるようなことがあったりした。
他の離れている国の戦争ならなんでも言えるが、自分の国が戦争に関わったら、今の日本でもなんでも言っていいとは、ならないかもしれない。
私が小さな子供で、親から「このままでは生きていけないから、食べ物を盗んできなさい」と言われたら、おとなしく従って盗んでくると思う。盗んできて親に喜ばれたら、きっとうれしいと思う。それで捕まってはじめて「盗んだらいけないのか」と知るのではないかと思う。
「盗まれた人のことを考えたことがあるのか?」と言われてはじめて、盗まれる人の気持ちを考えるのではないかと思う。
今作のハンナ(ケイト・ウィンスレット)からは、こういう疑問を持たない子供のようなものを感じた。ブレーキの緩んだ自転車みたいなもので、後ろから押されたり、下り坂でスピードが出てしまうと、なかなか自分では止まれない。
好きな人には会いたいし、嫌いな人に会いたくない。楽しいことはしていたいし、嫌なことはしたくない。求められるとうれしいし、嫌われると悲しい。
”相手のことを思っているからこそ怒る”ということであったとしても、相手の思いを汲み取れなければ「この人は私のことが嫌いだから怒っているんだ」としか思えない。
そういう、『思ったままの自分でしか生きていけない人』であれば、自分にとって有利になるような根回しするようなことなんて、しようとしてもできないだろう。
それは、本人に元からあったものか、壊されてなったものかはわからないが、ある種の心の障害みたいなものではないかと思う。
小さい頃裏切られすぎて人を信用できないとか、小さい頃に喜ばれたのが忘れられなくて要求されたら断れなくなったとか。そういうものが大きくなって、多くの人が通常と言うような枠の中に収まらなくなってしまった。
今作のハンナは、たとえ世界中の人に非難されたとしても、たった一人の人に理解されることだけで、生きていけるできる人であったのかもしれない。でもそれは強いようで、逆に危うくもある。
というのも、たった一人の人に呆れられたり、嫌われたりすれば、それでもう「生きている意味がない」となってしまいかねないのである。
犯罪を犯した加害者を非難するのは当然ではあるが、私が同じ立場になったら、なんの疑問もなく加害者になってたかもしれない。いや、自分が加害者であるなんて、気づきもしないんじゃないかと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
