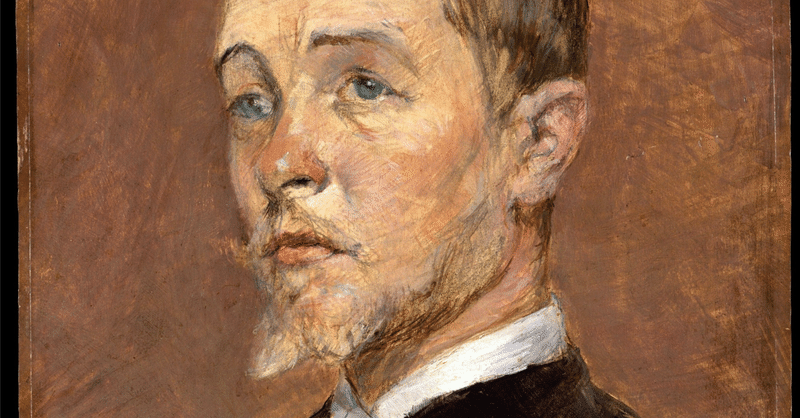
「安楽死・尊厳死を語る前に知っておきたいこと」安藤泰至著を読んで
日本尊厳死協会に加入しようとして、リビングウィルの用紙を見て驚いたのだ。輸血や点滴も拒否するかどうかチェックする欄がある。
疑問を持った私はもうちょっとだけ考えて見ようと思い、そのガイド役に岩波ブックレットのこの本を紐解いたのだ。
最初、この本を読み始めてブックレットの半分は用語の解説・定義であることに不満を持った。死にゆく人の苦しみを軽減させるという崇高な事態に、言葉を捏ねくり回しているようで不快ですらあった。
しかし、苦しみを軽減させるために安楽死を選ぶ方法は積極的安楽死か医師幇助自殺に限られ、日本では医師が罪に問われる方法であることを知る。
また、読んでいて私は延命の限りを尽くして尚回復の見込みがなく苦しみが続く場合と設定した条件に曖昧さはないはずだったのに、曖昧な点が浮かび上がってきた。
リビングウィルでも聞かれる延命治療の種類だ。点滴、輸血は当然望むとして胃ろうはどうだろうか?透析は?人工呼吸器は?生体移植は?延命の限りを尽くすことはそれらを受け入れることにほかならない。
ここで、リビングウィルのチェックの意味とこのブックレットの用語を厳密化することの意味が朧気ながら分かったような気がする。
だけれども、「尊厳死」という言葉にはどこか人間の尊厳のために「痩せ我慢」をすると言ったイメージが私にはある。苦しかったらのたうち回ったって、泣いたっていいじゃない。尊厳なんて無くったっていいじゃない。たった一回の人生が終わろうとしているのだから。それでも最後までダンディズムに拘りたい人はそうすればいい、あなたのたった一回の人生なのだから。
この本の中で、「よい死」「悪い死」という分類に又しても私は苛々する。そんなものは無いと私は思う。世間のイメージ、通念を分類することに何の意味があるのだろう。死は1回性の出来事で人それぞれに異なるが死んだ人は語ることができないのて、生きている人は憶測で語りたがる。
デュシャンや寺山修司が「死ぬのは他人ばかり」と言ったが、死が間近になってすら、経験した親しい人たちの死から私も自分の死を推し量る。
そう私は途方もないことを望んでいる。一世一代の死の場面なんだから、全力で治療してほしいと望んでいる。それが叶わなかったらモルヒネをバンバン使って、モルヒネが効かなくなったら致死量の薬物により「安楽死」させて欲しいと願っている。医療従事者には迷惑な患者だ。
筆者は「良い死」=「安楽死」「尊厳死」の陰に隠れた医療の不備があり、改善されればリビングウィルなど書かなくてもいいはずだと主張する。
そういう問題かなあ。医療従事者にとってはそういう問題かも知れないが。
私にとっては1回性の人生、かけがえがない人生、長い死への道のりを生きなくてはならない。そうして辿り着いた死の淵に可能ならば豊かな一生の想い出に縁取られながら息絶えたい。
私は愚かなこともたくさんしてきて、たくさんの人に迷惑をかけてきたけれど、私の人生は私のもので取り替えることはできない、そしてすべての人はその人の宇宙とも言うべき人生を生きている、と言った考えは間違いではなかったと思う。愚昧さと真正さにおいて私は私の人生が愛おしい。
そういう意味では人生は長い長いパフォーマンスであり、ハプニングなのだ。
ブックレットは佳境に入る。とりあえず筆者の「よい死」「悪い死」という分類を受け入れて読み進もう。以下抜粋。
「悪い死」については、多くの人に共通するイメージが浮かびやすいのではないだろうか。たとえば、激しい苦痛に苛まれた死、必要以上に生命を人工的に引き延ばされた死、誰にも看取られることのない孤独な死、遺された家族に大きな後悔や罪悪感を遺すような死、といったものだ。
それゆえ、私たちにとって「よい死」が思い描かれるとすれば、それはこうした「悪い死」のイメージのネガの形にならざるを得ないとも言える。すなわち、苦痛の少ない死、必要以上の延命を拒否した自然な死、家族や温かい医療者に看取られた死、遺族が少なくとも大きく後悔することのない死。
ここで注意しなければならないのは、容易にイメージできるそうした「悪い死」は、実は「悪い生」なのだということである。…私たちが「彼は彼らしい死に方をした」と言うような場合、それは最期の死の瞬間のことを指して言っているのではないだろう。多くの場合、そうした時に私たちが表現しようとしている「彼の死に方」とは、その人が、自分の病気がもはや治らないことを知り、死を覚悟してから、実際に亡くなるまでをどのように生きたか、ということなのである。
終末期ケアのパイオニアの1人キューブラーロスは言ったそうだ。「生きている人間に対する正しい接し方を覚えていれば、死にゆく人の権利を覚える必要はありません」
弟子のケスラーの「死にゆく人の17の権利」の最初に挙げられたのは、「生きている人間として扱われる権利」であった。
「死なせる」ことによってしかその尊厳が守れないのではないかと私たちに思わせるような「人間としての尊厳を奪われた生」を生み出しているかなり大きな要因は、そのような現代の悪しき医療文化にあるのではないだろうか。…と筆者は言う。
私は、何度かの入院で医療従事者の献身に感動した人間なので著者の言う悪しき医療文化とは何なのか理解できていない。そんな私だから「安楽死」がかつてナチスにより高齢者や障害者、杉田水脈氏によると生産性のない人々を抹殺することに使われていたことには驚き、現代ではないよね、と思ったが秘密裡に行われているらしい。
その一方で、…がんや難病を含め、いわゆる「治らない病気」の患者のQOLを高めるためのありとあらゆる手段を用いた全人的ケアであること、「よい死」に向けてのケアというよりは「よい生」を支えるためのケアだということを確認しておくべきだろう。
少なくともいま私たちは、どんな形であれ「よい死」を実現しようというような動きに対してもう少し警戒心をもってもよいのではないか、と著者は言う。
私は人工透析も人工栄養補給も人工呼吸器も費用の心配がないなら受け入れたいと思うが、多分医療費を払えなくて断念することになると思う。
現在、欧米を中心に合法化への動きが進んでいる積極的安楽死や医師幇助自殺を肯定する基本的な考え方は「死の自己決定権」であると言ってよい。
また、日本で「安楽死」や「尊厳死」が語られるときには「終末期」という限定が入っていることが多いが、少なくとも欧米で安楽死する人々のかなりの部分は、そうして自ら死を選ばなければ、かなり長く(数年程度)生きることができた人々であることを知っておくべきだろう。
また、安楽死や自殺幇助を選ぶ人々が挙げる理由は「耐え難い身体的苦痛」よりも「自律性の喪失」や「尊厳の喪失」のほうが圧倒的に多い。
著者は「自己決定権」を行使する前の医師からの十分な説明と情報による「インフォームドコンセント」が必要であるという。それは当然のことだと思う。なにしろ私には医学的知識がないのだから、医師がいい加減なことを言ったらそれを基に私は判断せざるを得ない。それは怖ろしいことだと思う。
また著者は、この「いのちは自分のもの」という語りもまた、「フィクション」の一つであるという。医療をめぐる選択のなかで、たしかにこのフィクションがある程度必要かつ有用であるような場面は存在する。…やはり私たちが、(多少のためらいは感じつつも)「自分のいのちは自分のもの」だと言わねばならない部分があることは、否定しがたい。
そうなのだ。かつて私のいのちは国のものと言わされていた時代があったからこそ「自分のいのちは自分のもの」と言うことは相対的に善なのだと思う。
ただでさえも多忙で過労状態にある医師は、一人一人の患者の話にじっくりと耳を傾けて、一緒に悩んでいる時間はなく、マニュアル通りの説明を手早く済ませて、「あとはご本人と家族で決めて下さい」となる…。一応は「自己決定」という形で、患者を体よく「死なせる」方向に誘導されることもあるという。
しかし、スティーヴン・ローリーズたちが行った研究で脳損傷などによるロックドイン・シンドロームの患者168人のうち91人から回答があり、そのうち安楽死を望んでいる人はわずか6人だったという。…重い病気や障害によって今の健康な強い自分を支えているような生きる意味や価値が失われても、人は価値観の転換によってしぶとく生きていくことができる「レジリエンス」を持っているのだということを過小評価してはいないだろうか。
こうして、反発したり、納得したりしながらブックレットを読んできたが、最後の一文で合意した。著者は生命倫理学者なので善悪を問題にするのだろう。けれど私はニーチェではないが善悪の彼岸に「死」はあるのだろうと思う。
最後の一文を紹介する。
本当に「死」について考えるということは、そうした「絵に描いた死」を考えることではなく、むしろ自分がどう生きるか、どのように「いのち」に向き合うのかを考えることにあるのではないだろうか。(了)
返信転送
出席者パネルが閉じました
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
