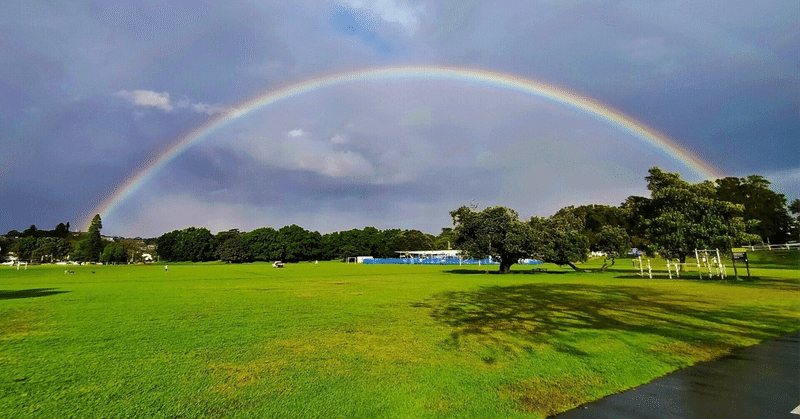
SF短編小説「オール・マイティなカード所有者」5️⃣
ピンク・ダイヤモンド鉱石の採掘と夢のような話
ヘリの操縦は女性だった。オーストラリア生まれの長身の三十代の女性で、耳にはシャネルのイヤリングをして、髪を後ろに結びポニーテールにしていたが、胸のあたりまで長いと想像した。操縦はそこそこ経験を持っているとのことだった。ただどういうこともこの地では起こり得るわけで、彼女の隣には副操縦士として、これまで我々をジェットで日本から運んでくれたパイロットの安藤さんがその任務を引き受けることになった。
広大な砂漠地帯を2名の操縦士以外は、国籍不明の男性とその他の三人を乗せて飛び立つと、すぐさま目的地を目指して低空飛行から徐々に中空へと高度を上げた。
やはり安定したビジネス・ジェットよりはヘリは右へ左へと意識してか知らないが揺れながら飛んでいるのが落ち着かなかった。しかし一時間もすれば、高度をゆっくり下げて着陸体制に入っていた。地面に丸にHのマークが描かれていて、そこに寸分違わず着陸した。大きく風を切るプロペラがゆっくりと速度を緩めやがて静止した。
僕たちは大地に降り立ち、着陸地点から数分の所にある施設に入った。その施設は筧社長の祖父の関連会社と繋がりがあり、到着後僕たちはすぐに要人用の客室に案内された。
そう言えば何となくお腹が空いていたことに気付いた。それは宇沙子の目が僕を見つめる時に、連鎖反応的に僕にも現れる現象だった。あくびをすればつられてする一種の伝染効果が二人の中にはあるのだ。それを察してか、筧さんの彼女がまず食事にしないかと提案したのだった。先ほどのパイロットの女性を含んで六人の会食となったが、時間は昼近くになっていた。
パイロットはアニーと既に自己紹介していたが、操縦技術については定評があると社長も軍関係者から聞いていた。ただあまり詳しいことは話せない事情があるようだった。というのは、彼女は今は軍属ではなくなっているが、オーストラリア軍では特殊部隊に属していたし、その後警察のテロ対策の部隊でもいたことがあるようだった。それなら口数が少ないベールに包まれた女性を想像してしまうが、アニーはいたって快活に振る舞っていたから驚いた。
「ピンクのダイヤモンドが見つかれば私だって欲しわ」そう社長に話していた。社長だって一時命を預ける身であれば、鉱石の一つを渡しても悔いがないはずだった。
ところであなたもお気付きだと思うが、アーガイル・ダイヤモンド鉱山は2020年11月に実際に閉山している。しかしその近くまで今僕たちが来ているということは、何か新しいことが始まるような予感を感じさせた。それはきっと宇沙子と一緒にUFOに遭遇するという特別なことがあってそう感じさせているような気もした。一攫千金を夢見たアメリカの黄金狂時代の時とは違って、それは新時代がこれから始まる開拓者のような境地に近かった。筧社長が目指した鉱山がクローズしていて違う場所を目的地にしなければいけないことは既に織り込み済みだったようで、案内人(パイロット)として選定していたのは、長い間鉱山に従事していた人が数人と筧社長の祖父の代から同鉱山の経営に携わっていた男性たちであった。アーガイル鉱山から少し西に行くとマーリン鉱山があるが、そこは既にるルカパという会社が採掘権を持っていて、僕たちが目的地としている場所とは違った。
結局僕と社長の二人で現場に行くことになった。そこまではアニーの操縦によるヘリで安藤さんがその時も帯同することになった。僕は宇沙子のことが気になっていたが、昨夜僕が先にベッドにいると宇沙子が神妙な顔つきでゆっくり近付いてきて(そんな顔の時には大体何か言いたげな時だ)耳元で囁いた時のことをふと思い出した。
「あのね、言ってなかったんだけど、ロックのこと。彼はね、この間真央が病院に連れて行ったでしょ、巻き爪と狂犬病の注射で。注射より巻き爪の治療の方が痛かったらしいんだけど、その後で真央が結構大量に段ボールに餌を買い込んで来たのをテラスの外から見えたから見てたらしいのね。それで仕分けをしているのを見て、自分のために主人であるあなたが色々世話を焼いてくれているのをとても喜んだそうなの。」
僕は彼女のひと言一言をじっと聞いていて、それからベッドに座った宇沙子の左手を引き寄せて抱きしめてやった。すごく暖かな身体を感じて、いつになくしっとりとなって彼女を求めている自分がいたのだった。そしてベッドに横たわった彼女の肢体が滑らかに、そして肩から爪先まで綺麗な流線を描いているのを美術品でも見ている風に眺めていた。
筧社長が、僕が宙をじっと見続けているのを不思議な顔をして見ているのに気付きやっと現実に戻った。ヘリの旋回するブレイドの音がけたたましく機内にも響き、宙に上がった時にやや不安定に左右に振られてはいるが勢いよく地上より少し高い位置から高度百メートルくらいの位置に上昇した後に目的地に向かって進んで行った。操縦しているアニーの横には副操縦士の安藤さんが任務についていた。僕らを連れていく場所の詳細は言えないけど、まずヘリは鉱山のあった場所のヘリポートに着陸し、その後は筧社長、僕が現地の案内人二人と共にランドクルーザーで約三十分ほどの距離にある川の近くまで走り、着替えてそこから歩いて数分のところの川床に降りた。川は二股になっており、片方には流れがほとんどなく、ショベルカーとブルドーザーが数台行き来していた。本来は川は清流なんだろうけど、工事業者の作業で水は汚れていた。我々は臍の上まで隠れるようなゴム長のツナギの長ズボンを履いていた。よく渓流釣りで見かけるような格好のズボンで、四人の手には各々ツルハシやスコップ等の道具が握られていた。一時間が経過し、そろそろ二時間がという頃に、案内人の一人が川床に降ろしたツルハシに硬い物が当たり「カキーン」という鋭い金属製の音がして、僕らは作業を止めた。
もう一人がツルハシの先端の周りをスコップで適当な深さに掘って徐々に中心の方に掘り進めていた。我々に疲労感と共にあったのはある種の期待感だった。その先には失望感ではなくて、どうか歓喜の叫びに繋がってくれと祈るような気持ちになっていた。そして最初にツルハシを入れた男がスコップの下に梃子の原理で硬い物体を押し上げようとした。それを数回繰り返してやっと地上に顔を出したのは、何か黒々した鉱石らしかったが、既に幾つかに分離されてしまい、それらの鉱石を少し離れた場所で川の水をかけて汚れを取り去っていた。
その場所にいたツルハシの男は、こっちに大きく手をあげて合図した。その横にいるスコップを持つ男もニヤニヤしているのが分かった。男たちは早く来いと現地語で叫んでいた。現地語の意味は分からなかったが、わくわくする心境を吐露する表情は見てとれた。
社長と僕は道具を捨てて走った。殆んどがボロボロに砕けてはいたが、確かに彼らの手の中で輝いていたのは1センチ四方のピンク色のダイヤモンドだった。その小さな結晶のような原石は、社長の手の中に二つと僕の手の中に二つ収まっていた。二人は彼らにお辞儀をする動作するしか仕方なかったが、それが何を意味しているのかはもちろん彼ら二人にはよく理解出来たようだった。
結局その原石は、一つは社長の手からフィアンセ(結婚予定とその時知った)の手に、一つは安藤さんの手からアニーの手に。そして僕の手から宇沙子の手の中に。もう一つはきっと社長のコレクターになるんだろうと、帰りのジェットの中で僕は思った。
地球の南半球と北半球とでは季節も逆転している。日本では見えない南十字星も見ることが出来た。世界各地で異常気象による大雨や洪水や山火事や大地震が起きていても、僕は宇沙子の手は絶対離さないでおこうとオーストラリアで十時星を見上げながら誓った。
エベレストの14座の最後の一つを目指して登る女性のことを想像しながら、僕と宇沙子は帰路に向かうプライベート・ジェットの機内で次の計画を話し合っていた。
※一部編集済み(2023.9.18)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
