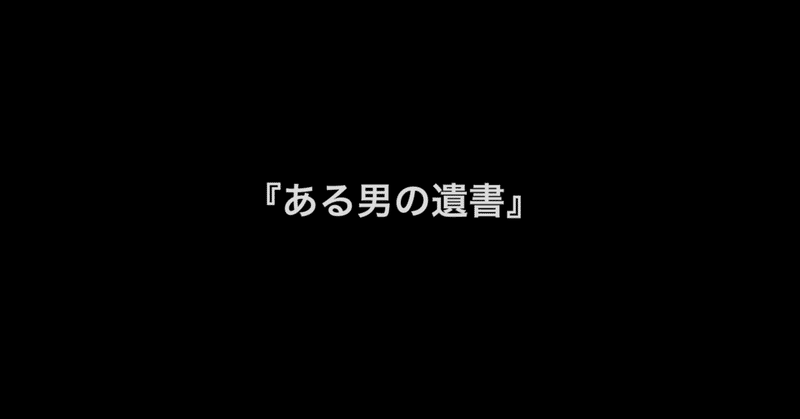
ある男の遺書(3)
前回↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-
どうやら、橋爪の友人が遺書を残して亡くなったらしい。橋爪と同い年だというからまだ若かっただろうに。そして僕を驚かせたのは、この遺書を僕に読んでほしいと橋爪は言ってきたのだ。遺書を読んだことなど一度もないし、ましてや赤の他人の遺書なんてなおさらだ。別に読む気にもなれないのだが、橋爪もなかなか引かない。
橋爪が言うには、これは遺書というより手記に近いという。これを手記として読んでみた僕の感想を聞きたいというのが橋爪の願いらしい。なんで僕なんかが、と聞くと、ただひと言、「あいつと君は似ている」と言うのである。そんな理由で読まされる僕の身にもなってほしい。遺書を読んで感想まで求められるのだ。こんなことがあっていいはずない。何度か押し問答を繰り返し、結局僕が折れた。
「すまない、ありがとう」とだけ橋爪は言った。
こうなったら仕方がない、読むしかない。
僕は茶封筒から中の便箋を取り出した。便箋は10枚に及んだ。とりあえず1枚目を開いて、まず驚いた。この遺書にはタイトルがあったのだ。遺書にタイトルなど不自然すぎる。なるほど、手記として読むとはそういうことか。
以下、その遺書の内容を紹介するが、全文を公開することは控え、また、一部の過激な表現は内容が変わらない程度に僕の方で改めた。内容はほとんどそのまま伝わるはずである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
『人間、失格』
今日、僕は死にます。
もう限界です。
自分なりに精一杯生きてきました。
これ以上の悲しみに、僕は耐えれる自信がありません。
悲しいのです。
ずっと、悲しいのです。
悲しくない時なんかありませんでした。
悲しいという単純な言葉に帰結していることが、また悲しいのです。
事態はもっと複雑で、混沌としているはずなのに。
(中略)
助けてください。
いや、助けないでください。
差し伸べられた手を取るのが怖いのです。優しさが怖いのです。いや、優しさの影に悪を見てしまう、それが怖いのです。仮に手を取って裏切られたら最後。それこそ僕は地獄の底へと墜落します。
僕は誰にも助けられたくないのです。
いっそ、道端に落ちてるタバコの吸い殻くらいに僕を認識してくれればいいのです。僕はみんなに煙たがれる存在なのです。あぁ、タバコの煙になりたい。煙になって消えてしまえたらどんなに幸せでしょう。
(中略)
疎外感。これがまず僕が日々感じていることです。僕は何においても疎外されていると感じます。
でもそれは多くの場合、僕の方から避けているのです。
その結果、僕は「幸福」というものから絶縁されたのです。自業自得です。
無慈悲。日々の流れはなんと無慈悲なんでしょう。この世で最も無慈悲なものは「時間」ではないでしょうか。「時間」と「無慈悲」は同義語である、とは言い得て妙でしょう。僕は時間の過ぎていくのが耐えられません。それでいて何もかも時間に委ねたいと思いつつ、また時間ほど鬱陶しいと思うものはありません。僕の現在は暗鬱とし、未来を考えると恐怖に怯え、過去は僕を束縛します。それでもただ時間は過ぎていくのです。
ケチを極めました。吝嗇家なんてクソみたいな言葉です。吝嗇に「家」をつけた人間は、もしかすると僕と同じくらい愚かな人間なのかもしれません。
ケチはケチなんです。ケチを極めると自分にもケチになるものです。僕は自分にすら何も与えることはありません。自分に対して吝嗇を働くのです。それが本当の吝嗇家です。あぁ、ばかばかしい。実に、ばかばかしい。
滑稽のあらゆる形態を覚えました。滑稽の最も似合う男となりました。こんな文章を書くなんて滑稽の極みでしょう。僕は物書きに向いていません。物事を正確に描写することが叶わないのです。それだけの気概も才能も素直さも欠けているからです。僕は嘘つきで、見栄っ張りです。演技を働くのです。僕には喜劇も悲劇もあったもんじゃない。ただ滑稽。僕の全部を捨てても滑稽だけは根強くあとに残るくらいです。
僕はつまるところ、妬んでいるのです。
親しい人や、そこまで親しくない人、作家の同僚や先輩後輩、テレビに出演している有名人や、政治家や資本家、どこかの社長から電車で隣に座った人まで。ありとあらゆる人間を妬んでいます。妬まずにはいられない。妬むことが生きていくということなのです。僕の細胞ひとつひとつが妬みを養分としています。僕は妬みによってできた汚物です。
裏切り。嘘つき。道化。僕が生きていく上で最も大切にしていることです。悪とはなんでしょう。怒り、傲慢、強欲、暴食、嫉妬、怠惰、肉欲。これらは罪ではあっても悪ではありません。強盗、殺人を犯した者も罪人ではあっても悪人でない。悪とはなんでしょう。悪とは欺瞞、とくに自己欺瞞のことではないでしょうか。
陶酔。それも自己陶酔。なんとあさましい。みじめ。卑劣。僕は上っ面だけはよくできています。人付き合いもそれなりに上手いです。老若男女、誰とでも仲良くなれます。人たらし。それが僕のひととなりです。中身は空っぽ。空虚、あぁ、空虚。僕は輪郭だけで生きています。人間の底辺です。これを人間と呼んでいいのであれば。
人間、失格。
このタイトルはいい。
あの『人間失格』は日本で最も有名で、最も読まれている小説です。
僕はこれを、この遺書のタイトルに使ったのです。僕はそういう人間なのです。そもそも遺書にタイトルをつけるなんて、もう、救いようがありません。
失笑。
笑え。怒れ。皮肉を言え。同情しろ。冷笑したまえ。叩け。殴れ。蹴り飛ばせ。嘲弄、誹謗、軽蔑、非難、中傷、あなたたちの最も醜い部分を俺に見せろ。
(中略)
もう僕は死ぬより他にないんです。
結局、僕は、ただ、誰よりも人を愛していただけだったのだ。そうして裏切られた。ただそれだけのことだ。
今日、僕は死にます。
生まれ変わったら猫にでもなります。
沢田京介
1999年××月××日
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
読み終えた僕は大きくため息をついた。
たまらず、もう一度大きく息を吐いた。
「どうだった?」
橋爪は煙草の煙をくゆらせながら聞いてくる。
「どうもこうもないですよ。こんなの読ませて、一体何がしたいんですか」
僕はそう言いながら便箋を折りたたみ封筒の中へしまった。
「いや、悪いことした。でもぜひとも君には読んでほしかった」
短くなった煙草を橋爪はまだ吸い続ける。
「これ、日付が13年前ですが……」
「あぁ、13年前に彼は死んだ。ちょうど君くらいの歳で死んでしまった」
「太宰治を嫌いな理由……」
「え?」
「いや、以前に橋爪さんが太宰を嫌いだっておっしゃってたじゃないですか」
「あぁ、そうだったか?」
「もしかして、この遺書のせいでは?」
僕は封筒を橋爪に返した。橋爪は受け取ることもせず、テーブルにぽつんと置かれた封筒をまじまじと見ていた。
「元々、嫌いだ」と橋爪が吐き捨てるように言ったとき、マスターが、「まこと、今日はもうよしたらどうだ」と言った。
まこと、とはおそらく橋爪の下の名前だろう。
僕は混乱していた。なぜ橋爪は13年前もの遺書を今も持っているのか。そもそも友人の遺書をなぜ持っているのか。そしてなぜ僕に読ませたのか。いずれも判然としない。聞きたいことが多すぎた。でもおそらく橋爪はどれも明確に答えはしないだろう。そこが少し腹立たしいようで、彼の顔を見てると聞くに聞けなかった。
→つづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
