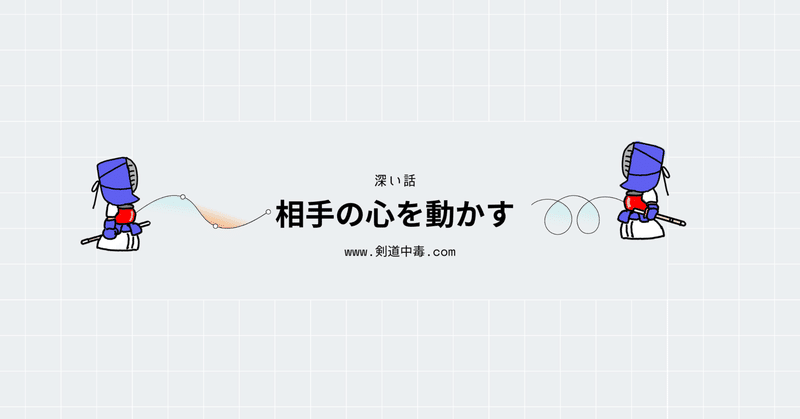
相手の心を動かす
焼肉屋さんに行くと、いつも思うことがあります。
「たれの皿が浅い!」
そう感じたことはありませんか?
肉をたれの皿に入れると、たれが溢れてしまいそうになります。というか、ときどき溢します。行儀が悪いと思われるかもしれませんが、圧倒的に浅い皿を用意しているお店の方が悪いのではないかと。

個人的には、たれはまんべんなくつけたい派です。したがって、たれの消費量は多い方だと思います。とにかく、焼き肉屋さんのたれの皿、あれをもう少し深い皿にしてほしいのですが……
デザインにはこだわりません。100均の皿でいいので、関係者の方には、ぜひ検討していただきたいです。
焼肉のたれ用皿と同じく、ぎょうざのたれ用皿も浅いと感じています。できる限り、たぷたぷに浸したい派です。しかし、餃子のたれ用皿は餃子の高さに対して、3分の1ほどの深さしかありません。
もう少し深くても良いと思いませんか?せめて、餃子の高さの半分くらいの深さが欲しいところです。
浅いって、何かと不便だと感じる今日この頃です。
攻めって何だ?

こちらは深いと感じました。深過ぎて、もはや迷宮入りの深さかと。
梶谷プロのYouTube動画で紹介されていた
「攻めって、いったい何だ?」
という質問です。
梶谷プロは多くの人の悩みにズバッと斬り込んでいました。深い悩みではないでしょうか。私は「攻め」というものは、剣道愛好家の永遠の課題だろうと思っています。
おそらく、日本一になったことのある剣道家でも、明確な答えを探すために修行を続けているのではないでしょうか。剣道でずっと勝ち続けることは困難だからです。それは、全日本選手権で連覇が難しいことでもわかります。
そんな深い悩みにズバッと答えている、梶谷プロの動画がこちら。
梶谷プロは動画の中で、次のように簡潔に解答しています。
「攻めとは、相手の心を動かすこと」
単純明快。実にわかりやすい解答ではないでしょうか。まさにその通りだと思います。それ以上でも、それ以下でもない、100点満点の答えです。しかし、それがなかなかできないから、みんな困っているのも事実。
一方、梶谷プロの解答は浅いようにも思えました。全体の3分の1くらいの深さはあるかもしれませんが、それでもまだ浅いのです。サムネイルには徹底解説と書かれていますが、たぷたぷになるくらいの深い皿を用意してほしいと感じました。
逆胴フェイント面
梶谷プロが動画内で「攻め方」の例として取り上げている技が、「逆胴フェイント面」でした。梶谷プロの得意技なのでしょうか。一本集などで何度か見たことがある技ですが、難易度の高い技のように感じます。
「逆胴フェイント面」については、解説動画もあります。使う、使わないに関係なく、どのような技なのか見てみましょう。
高校生くらいなら有効な技なのかもしれません。全国レベルになると、こんな技を使ってくる者も出てくるのでしょうか。
ちなみに、以前中体連の大会に審判員として参加したとき「逆胴は基本的に取らない」と聞いたことがあります。かなり狭い範囲のローカルルールの可能性は高いのですが、一般的に中学生で逆胴は有効打突になりづらいようです。その観点からも、あまり意味のない技といえるかもしれません。
そもそも、逆胴のフェイントから面を打つ際に刃筋正しく打てるのかという疑問もあります。なんだか右手で無理矢理竹刀を振り回しているような印象です。正しく打つことは、なかなか難しいでしょう。
「逆胴フェイント面」に代表される梶谷プロの攻めに対する考え方は、相手を避けさせて、隙を作って打つというもの。つまり、相手を避けさせるためにフェイントを使います。
びっくりしたなぁ~、もぉ~~~
というやつです。それはそれで、攻めとして成立することは間違いありません。打突の好機として、剣道連盟の資料にも「避けたところ」と記載されています。
梶谷プロの動画内で「攻め」の具体的な方法として解説されていたのは、このような「相手を除けさせる方法」のみでした。したがって、この動画を見た中高生が「おお、そうか!」と納得してしまうのではないかと考えます。
しかし、攻めの方法は他にもあるので、その点では「浅い」と言わざるを得ません。
そもそも、この記事の読者は「逆胴フェイント面」は使わないと思います。そもそも昇段審査などでフェイント技は評価されるのでしょうか。
フェイントは評価されるのか?という疑問

「フェイントも一種の攻めである」
その考えは間違いではないと思います。多くの書籍には「フェイントの動作を徐々に小さくしていくべき」と書かれているため、フェイントは攻めの「ほんの入口」にすぎないでしょう。
フェイントの評価は★2つくらいかと考えます。そもそもフェイントというのは相手を騙す技です。
くっそ~!騙しやがったなぁ~!!
へへぇ~ん。騙される方が悪いんだよ~~!!
なんて会話が聞こえてきそうな技。そんな打突を見て危惧した八段の先生は「相手を騙すような技を使うな」と言ったとか、言わなかったとか……
試合審判規則の第1章「総則」第1条「本規則の目的」にある「公明正大に試合をし」という部分にほんの少しだけ引っ掛かるような、引っ掛からないような……。ややモヤモヤする部分があるのではないでしょうか。
私の知っている限り、六段以上の昇段審査でフェイントを使っている人は見たことがなありません。カラーバス効果によって見えないのかもしれませんが、おそらくフェイントは昇段審査で評価されないと、多くの人が認識しているのでしょう。
そもそも、フェイントを有効的に使うには、攻め勝っている状況でなければなりません。そう考えると、フェイントなんて使う必要はない。寧ろ危険なのです。
フェイントは隙となる
打突の好機はいくつかありますが、中でも技の起こりは審査でもっとも評価されるポイントでしょう。一方、フェイントはどうでしょうか。
フェイントを成功させるには、技の起こりを相手に見せて、ワンテンポ遅らせて技を出す必要があります。つまり、技の起こりがわかりやすい。しかも、無防備な状態を相手にさらけ出すことになります。
諸刃の刃というよりも、寧ろ隙だらけの状態です。
高段者がフェイントをあまり使わない理由、評価されない理由はこの点にあるのではないでしょうか。とくに出ばなを狙っている人にとっては、またとない鴨が葱を背負っているカモネギチャンスです。

また、 加齢とともに反応が鈍くなってきている 鈍感力を鍛えている私はちょっとやそっとのフェイントには驚きません。逆に引っ掛からなくて申し訳ない気持ちでいっぱいです。
それでは、どのような攻めが評価されるのでしょうか。
相手を引き出す攻め

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
