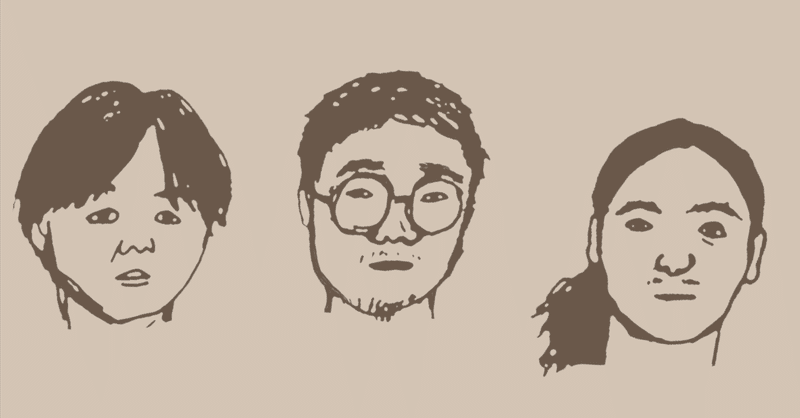
[趣旨文2] 注文の多い「からだの錯覚」の研究室展2:言語学との対話、ことばとからだのイビピーオ(伊藤雄馬 × 小鷹研理 on 金井学)
趣旨文1につづいて、この投稿では、月末に迫った錯覚展示のゲストトークに焦点を当てる。ゲストトークは、3日間の展示の中日にあたる26日(土)に、有料(1500円)で開催される。ゲストとして言語学者の伊藤雄馬さんをお招きし、アーティストで僕の古くからの友人でもある金井くん(金井学)が、司会を引き受けてくれた。以下では、この異色の組み合わせに至った背景について触れていこうと思う。参加に迷っている方は、どうか参考にしていただきたい。
まずは、既出である、チラシの紹介文を再掲する。
前展の特別企画 「メディアアートとの対話」から2年、本展では「言語学との対話」として、在野で活躍する異色の言語学者・伊藤雄馬を迎え、本展を主宰する小鷹研理とのゲストトークを行います。トークは、世界各国で制作を行うアーティスト金井学による司会ですすめます。
2022年に入って各地で公開されている、狩猟最終民ムラブリの生活を記録したドキュメンタリー映画『森のムラブリ』に出演し、各方面から注目を浴びる伊藤雄馬は、彼らが用いるムラブリ語を研究する日本で唯一の研究者でもあります。伊藤は、ムラブリ語の中核に、概念化の装置とは異なる、<いまここ>に現前する身体体験の表出を見出すとともに、そうした起源的な言語使用から、人間に特有の営為としての芸術がいかに派生したのか、研究と実践を通じて大胆に探究しています。この種の伊藤の姿勢は、錯覚を通してミニマルな自己に深くコミットしようとする小鷹研究室のアプローチと通じているようにみえます。
ゲストトークでは、ダニエル・エヴェレットによる名著『ピダハン』で紹介された、”現前的体験”を指示する動詞「イビピーオ」をキーワードとして、互いの実践を足がかりに、複雑に絡み合う身体・言語・芸術の諸相を解きほぐしていきます。
振り返れば、2年前のゲストトークでは、アーティストの谷口暁彦さん、インターフェース研究者の水野勝仁さんをお招きし、「メディアアートとの対話」と題して、「からだの錯覚」とメディアアートとの接点を探る議論を繰り広げていた。
このとき、お二人を誘った背景には、SNS等を通して、既にお互いがお互いの仕事に対して言及し合っている、という暗黙の関係があった。もともと、僕自身の仕事が、メディアアートの文脈で評価されることも少なからずあったわけで、「小鷹研究室がメディアアートと対話する」という構図そのものは、それほど奇をてらったものではなかったはずだ(対話は非常に有意義なものであったので、関心のある方は、ぜひログをご覧いただきたい)。
で、メディアアートの続編となる今回が「言語学」である。これまで小鷹研の活動を追っていた人でさえ、ん?の反応となるかもしれない。というのも、小鷹研究室の扱う錯覚は、どれも一般的な意味での言語の作用からはかなり遠いところにあるし、そもそも、当の研究室を主宰する小鷹自身が、ナラティブな水準で行う自己変調のアプローチに対して特段の関心が持てないことを、(かなり露骨なかたちで)各所で繰り返し述べてきた。例えば、僕が2021年に参加した、あるソーシャルVRに関するクロストークイベントにおいても、ソーシャルVRにおいて顕著な、ナラティブな演出に対する違和感を述べている。このイベントに関する古谷利裕さんの記事を読んでもらえれば、少しは感触がつかめると思う(イベントのアーカイブも見れます)。
とはいえ、ご存知のように、近年では、あらゆる学術領域において、「ナラティブ」という概念が、ある種のマジックワードのように流通している。「ナラティブ」と向き合う態度こそが、政治的に正しく振る舞うことを生業とする、洗練された現代人に求められる、最低限の嗜みであるというばかりに。
昨年、あるコンペで、手を透視する体験であるXRAYSCOPEの審査を受けたときのことである。その際、僕たちは、経験的にXRAYSCOPEで最も強烈な体験を引き起こす、「じゃがりこ」と「えのき」を、手の中を透かし見る対象として選んだ。狙い通り、ほとんどの審査員に対して、その錯覚は強烈な体感を与えることになった。結果的にその錯覚は、受賞の名誉に預かるわけだが、全ての審査員から好意を得られていたわけではない。むろん、そのこと自体には、なんら不服に思うところはない。ただ、そうした水準とは別のところで、審査中に首を傾げるような瞬間があった。
ある一人の審査員が、XRAYSCOPEの体験中に「これ、うけをねらってるでしょ」という言葉を投げかけててきたのだ。言葉のトーンは、まるで穏やかなものとは言えず、明らかに不快な感情が漏れ出ていた。どうやらその方にとっては、「じゃがりこ」なり「えのき」という対象は、極めてアイコニックなものとして捉えられており、僕たちが「ネタ」として、その対象を選定したと感じられているようだった。はっきり言って、ものすごく腹立たしい気持ちになったし、すぐにでも全力で否定したい気持ちに掻き立てられたのだけれど、その作品が学生賞の対象となっていたことを慮れば、僕がその場でしゃしゃりでてしまうのは、あまり得策ではなかった。結果、僕は努めて平静を装いながら、ジェントルな対応でその場をしのごうとする学生の様子を、頼もしく見守っていたのだった。
そのときのやりとりを見れば、その審査員が、XRAYSCOPEの体験をナラティブな水準で受容していることは明らかだった。その審査員が信仰するナラティブ体系では、「じゃがりこ」や「えのき」といった対象は、極めてチープな陳列棚にしまわれているものだったのだろうか。あるいは、アイコニックに対象を選定するのであれば、もっと高度な文脈に接続し得る、政治的に洗練された対象を選定せよ、とでも言いたかったのかもしれない。そのような審査員の意図を察して、学生が、(申し訳程度に)文化的な違いが体験の差異を生むような二、三のアイデアを挙げると、その審査員は非常に満足そうに頷いて、その場を立ち去っていった。
心底うんざりした。
話をもとに戻す。僕は、小鷹研究室の錯覚体験(の説明)に、言葉や文化が要因として混入してくることを、これまで徹底的に避けてきたし、これからも、その方針は変わらないだろう。要するに、そのような言語的要因が、錯覚の体験質を変えることがあっても、僕自身が「からだの錯覚」に要求するリアリティーの琴線に触れるものではまるでない。このようなことを声高に叫ぶことが、現代において受容されている、ほぼ全ての芸能に対して喧嘩を売っているに等しい、天をも恐れぬ所業であることは重々承知している。一応、僕自身、芸術における文脈の機能を過小評価しているわけでは全くないことについては断っておきたい。とはいえ、世の中には、ナラティブの水準の中で閉じているようにしかみえない作品が氾濫し、それらの多くが、僕の守備範囲から大きく外れることは確かだ。そして、僕自身がコミットしている「からだの錯覚」の領域において、「この自分」を直接的に転倒させたいと望むのであれば、その種のナラティブな演出に時間をかけることは、端的に言って時間の無駄である。言語は、その再帰的な埋め込みを可能とする仕様によって、無限の自由度を手に入れたのと引き換えに、特定のセンテンスの中に、現実に根を張った「この自分」を投影させることを諦めたのである。ざっくりいうと、以上が、僕の言語観である。
少し脱線すると、以上の意味で、僕自身は、「言語が話者の思考に影響を与える」とする言語相対論(サピア=ウォーフ仮説)に対しては、どちらかというと、決定的な影響を与えないという立場(弱い仮説)をとっている。ここでいう「決定的」という名の判定基準には、「からだの錯覚」によって生じることのある、あの轟に値するだけの瞬間最大風速が認められるか否かこそが試されている。例えば、文化の違いによって、幽体離脱の体験率が大幅に異なる、などのデータがあるだろうか。あるいは、ある言語の話者は、総じて三人称視点で世界を見ているであるとか、ある特定のタイプの教育を授かった者が、おしなべて共感覚的な特性を獲得する、などという報告があっただろうか。そのような知見の一つや二つでもあれば、僕は、自分自身の信仰を変えるだけの用意はできている。しかし現状はそうではない。文化間の差異を見出すことにあれほど熱心な認知言語学の分野から、からだの錯覚(例えばラバーハンド錯覚)の感受性の強度が文化間で異なるといった、"いかにもありそうな"話すら、一向に提出される気配はない。
こうした言語観を持っている僕が、言語の可能性について再考せざるを得なくなったのが、異端の言語学者であるところのダニエル・L・エヴェレットによる著作『ピダハン』との出会いだ。
エヴェレットの観察によれば、ピダハンの文法には、関係詞と完了形が存在しない。完了形は、ある事象を現在とは異なる時系列に定位させ、関係詞は、特定の事象を(時間を捨象した)一般的な属性として概念化する効果を持つ。これらは、総じて、特定の事象を「現在」から遊離させる働きを有していることがわかる。しかしながら、そのような(現代の言語観では当然とされる)言語仕様は、ピダハンからは拒絶される。というのも、——エヴェレットによれば——ピダハンの言語と文化は、直接的な体験ではないことを話してはならないという文化の制約を受けており(直接体験の原理)、言語が「この現実」を超えて遊離するような事態は、言語文化的に許容されないのである。
ピダハンは、イエス・キリストの"奇跡"の話に、全く関心を示さない。実際、その種の話を繰り返し繰り返し聞かされてうんざりしたピダハンは、イエス・キリストを実際に見たことのない者(エヴェレット自身)が語る、イエス・キリストに関するいかなる話にも、まるで興味がないことを宣言する。直接体験を重んじるピダハンにとって、宗教的なエピソードが、どれもが著しく抽象的であり、実証性に乏しく、まるで信用するに足らないと感じられるのは無理もない。こうして、キリスト教会の支援を受けるかたちで、ピダハンの集落でフィールドワークを行なっていたエヴェレットは、その研究活動の予算の根拠となっていたピダハンの改宗というミッションに、ものの見事に失敗するのである。
世界の多くの聖典、つまりキリスト教の聖書も、コーランも、ヴェーダも、ピダハン語に訳したり、ピダハン語で論じたりすることができない。なぜならそうした聖典には生きた証人の存在しない物語が数多く含まれているからだ。だからこそこれまで300年近くかけても、伝道師たちがピダハンの信念を少しも揺るがすことができなかったのだ。
このピダハンの一種の<頑なさ>は、例えば、ユヴァル・ノア・ハラリ(に限らず人類学者一般)が主張する、我々人類であるところのサピエンスが、狩猟採集から農耕へと移行するうえでの決定的な契機となった「認知革命」によって獲得された認知特性、すなわち「架空の事物について語り、その実在を話者間で共有的に信仰する能力」の保有原則に反しているようにみえる。実際、驚くべきことに、ピダハンには、原住民族には当然存在するとされてきた神話や創世記といった類の物語が存在しない。ピダハンは、人類学のテキストに照らしてみる限りに、人間の<条件>を満たしていない、そのようには言えないか。
そのうえで、「からだの錯覚」の研究者としての僕自身の関心は、このような、——一種の視野狭窄にすらみえる——実証主義的なピダハンが、ぼくたちよりも、むしろより濃密な「虚構」を体験している、という事実にこそある。例えば、僕たちにとって、夢は覚めてしまえば、「実際には起こっていなかったこと」として処理されるが、ピダハンにとっては、夢は端的に起こったことである。夢と現実を混同しているというわけではない。夢も現実も「実際に体験された事象」としては等価であり、実証主義の地平の中で、同列に価値づけされるのだ。その種の原則は、"精霊"に対する態度においても同様に発揮される。
『ピダハン』のプロローグでは、エヴェレットは、ピダハンの集落のほとんどが騒々しく川岸に集まって、対岸の特定の場所にいるらしい何者かを指さして、「イガガイー(精霊)」と叫んでいる場面の記述がある。ピダハンたちが、はっきりと何かを認識して、正確にその対象を名指しているの一方で、エヴェレットと彼の家族には、ピダハンが指差している場所に、何ら精霊らしい手がかりを見出すことができなかった。
クリステンとわたしは、ピダハンたちを残して家に戻った。いま自分が目撃したものは何だったのだろう。あの夏の朝から20年以上もの間、わたしは自分の西洋文化とピダハンの文化とでは、現実をこんなにも別々に捉えることができるということの意味の重大さをつかむために、努力してきた。わたしには、川岸には誰もいないとピダハンを説得することができなかった。一方彼らも、精霊はもちろん何かがいたとわたしに信じさせることはできなかった。
この『ピダハン』のプロローグ部分を読んだ時の興奮は、僕の読書体験の中でも一二を争うものであった。僕にとって、こうした事例は、この自分が全く異なる<自分>に変態(錯覚)できる可能性を提示されていることに他ならない。
それでは、僕はいかにして、ピダハンのリアリティーに近づくことができるのだろうか。あるいは「ピダハン錯覚」はいかにして可能か?
例えば、僕が生後すぐにピダハンの集落で養子として入り、ピダハンの言語の中で育ったならば、イガガイーの降臨に対するピダハンの喧騒に参加することができたのだろうか。仮に、本当に言語の違いが、この種の現実の質感に対する圧倒的な断絶を作り出すというのであれば、それはまぎれもなく驚くべきことであると思うのだが、実際には、ピダハンの遺伝子がサピエンスの主流と異なる系統のものである可能性も否定できない。こうした問いに対して説得力のある解を与えるには、遺伝と環境の問題がどのように交錯することで(あるいはあまり交錯することなく)、ピダハンと僕たちの体験質の違いを生み出しているのかについての、注意深い議論が必要となるだろう。その意味で、この問題は、僕の研究の守備範囲からは外れているのかもしれない。それでも、僕にとって「ピダハンであるとはどういうことなのか」という問いには、「西洋人であるとは〜」「江戸時代の人であるとは〜」のような問いとは、まるで異なる重みを持つものであることは間違いない。今のところ、「からだの錯覚」の問題系と同列に論ずることができているわけではないが、いつか、バラバラなものが一気に繋がるような、そんな繊細な一本の補助線が見つかるかもしれない。
以上のような事情で、僕は自分の授業の中で、5年ほど前から、ピダハンの話を紹介している。毎年の授業の感想を見る限り、ピダハンの各種のエピソードは、20歳そこそこの大学3年生の脳裏に強烈な爪痕を残している、という手応えがある。それは、現代で主流派となった我々の無意識の中に、「ピダハンであるとはどういうことか」という感覚が、潜在的に根付いていることと無関係ではない。僕たちは、ピダハンを知っている。ただ、そのことを知らなかっただけなのだ(「知の無知」)。
話を、ゲストトークに戻そう。伊藤雄馬さんのことは、今年の春に、僕自身が購読しているvideonewsのゲストで出演しているのを見て、始めて知った。
伊藤さんは、タイ・ラオス国境に暮らすムラブリ族のドキュメンタリー映画「森のムラブリ」に、現地コーディネータとして出演していた。実情は、伊藤さんが現地でフィールドワークしているところに、撮影隊がたまたま出会し、予期せぬ形で出演する運びとなったらしい。映画について触れておくと、まず何よりも、伊藤さんの存在感が突出して際立っている。「森のムラブリ」の魅力の一つが、間違いなく、(特別な説明もなくいきなり現れた)このよくわからない伊藤さんが、完全アウェイの地でむちゃくちゃ活躍してるぽい、、その異質な光景にあることはまちがいない。
videonewsの番組では、中盤以降、ムラブリと僕たち文明人との違いについて議論が交わされる。伊藤さんの説明によると、ムラブリ語は、完了形と起動相(be going to)が同じ形式で現れる。つまり、「既に終わっていること」と「これから起きること」が、文法的に区別されない。具体的には、「目の前に現前していること」(ワー)と「それ以外のこと」(ア)で、時制が二分されるという。つまり「いまここ」から離反している事象について、それをより細かく分節化する手段を、ムラブリは文法的に放棄しているのだ。
無論、このムラブリ語の言語の仕様は、ピダハン語を強く連想させる。だから、番組の後段で、伊藤さんの口から、「ピダハン」という言葉が出てきたのは、何も意外なことではない。伊藤さんによれば、ピダハン語もムラブリ語も、フィクションを精緻に分節化する方向で進化した装置とは、まるで異なる様相を示している。番組の中で、コメンテーターである宮台真司氏は、表現(expression)と表出(explosision)という対立図式で、これらの言語仕様の差異を説明している。僕の理解では、ピダハン語やムラブリ語などの<表出>の言葉は、「いまここ」において、自らの身体において感応していることを、ほとんどそのままのかたちで外部へと投射するインタフェースとして特化している、ということなのだと思う。
英語大学院での中心的話題の一つです。吉本に似た概念伝統が社会学にあります。それを踏まえて表出explosionと表現expressionと簡略化します。表出は場に直接結合し、表現は場から遊離するぶん人に結合します。定住後も祝祭や性愛は表出の時空であることで、表現の時空である社会の外に立つのです。 https://t.co/dqQhjmSrVa
— 宮台真司 (@miyadai) May 1, 2022
伊藤さんは、ムラブリ語の特徴を説明するにあたって、ピダハン語における、「イビピーオ」という単語にも触れている。「イビピーオ」とは、訳すのが非常に難しい言葉なのだが、基本的には「まさに今、何かしらの体験している」ことを伝える概念である。エヴェレットによると、イビピーオという発話は、何かが体験の内側に入ってきた際(飛行機が来た!!)も、その逆で、体験の外部へと消失した際(飛行機はたったいま飛んで行った!!)も、同様に適用される。

僕にとって、「イビピーオ」という言葉は、からだの錯覚における、<やばい>・<きた>の言い換えである。セルフタッチ錯覚において、他人の手だったものが、突如自分の手となるときの感覚、あるいは、蟹の錯覚や芋虫の錯覚において、自分の手だと感じているものが、突如感覚を失い、自分と無関係の「モノ」に堕落するときの感覚、この際の、<自己感>の濃度がシグモイド関数的な急勾配で上昇したり減退する感覚、そのときの<やばさ>こそが、「イビピーオ」という言葉が含意する体験の本質である。この線で敷衍するばらば、「イビピーオ」を失った現代人全般が喪失している現実体験の強度を、僕自身が、からだの錯覚を通じて取り戻そうとしている、そのような図式がみえてくる。
言語学者である伊藤さんも、——コロナ禍でフィールドワークが制限されていることも影響し——、ここ数年、身体と言葉の関係に注目する活動を展開されている。(僕とはまるで異なる方向から)武術的観点から呪文や呪術といった形式を通して、「イビピーオ」の体験質を探る試みをされているようだ。僕の理解では、呪文も呪術も、ナラティブ的な水準の手前で、言葉を一種のモノのようにして半ば物質的に身体に直接働きかけようとする媒体形式である。このように考えると、僕と伊藤さんは、違う方向から同じことにアプローチしようとしているようにもみえる。
めちゃ楽しそうだったので、喜んで捕まりました🦀
— 伊藤雄馬 映画『森のムラブリ』見てね (@yuma__ito) October 16, 2022
錯覚はもちろん、ピダハン語の「イビピーオ」がもたらす作用を感じられるワークや、芸術ってなに?みたいなことも話せたらと思ってます。
来てね! https://t.co/ygb10L3Gu6
僕が、伊藤さんに強烈に関心を持つに至った経緯は、もうこれだけの背景を述べれば十分だろう。そういえば、伊藤さんは、言葉と身体との関係を探求する中で、芸術についても深い関心を示している(ことも触れねばなるまい)。最近刊行された雑誌(kotoba)で寄稿されたテキストの中では、詩が生成する(あるいは受容される)上での、言語環境的な条件について触れられているし、最近の伊藤さんのnote連載も、裏テーマとして芸術の問題が見え隠れする。
これらのテキストには、小鷹研究室的な問題系(「既にある風景」)と接続しうる論点を多く含んでいるのだが、この調子ですすめていくと、いつまでも終わる気がしないのでやめておく。ただ、ここまで、言葉と身体の問題ばかり記してきたが、(前回および前々回のゲストトークと同様に)本ゲストトークの場では、「芸術」もまた、極めて重要な論点となるはずだ。というか、言葉と身体が交差するところには、芸術の萌芽が満ちあふれている。そんなことを確認する時間になるかもしれない。
このあたりの伏線を回収してくれる(かもしれない)司会は、金井くんにお願いした。4年前の『からだは戦場だよ2018Δ』における、伝説の?スペシャルトーク(古谷利裕 x 金井学 x 小鷹研理)以来の登壇である。
僕と金井くんは、もう15年以上前の、IAMAS以来の旧知の中であり、芸術における理論と実践を、これほどまでに深い射程で交錯させようとしている作家を、僕は他に知らない。金井くんは、これまでにさまざまな国に滞在し、各地でレジデンス活動を行なってきた。ちょうどNYにおける1年間の海外研修を終えたばかりのところで、タイミング良く今回の司会を引き受けてくれた。さまざまな文化における美術を眼差してきた金井くんには、美術のフィールドワーカーとしての顔がある。だから、今回のゲストトークは、異なる領域(美術・言語)における2人のフィールドワーカーが集う、という側面もある。おもしろい。
実は、先日、出張で関東地方をかすったついでに、金井くんと、来るゲストトークのための簡単な下打ち合わせのようなものを行った。お互いに話した感触では、僕も伊藤さんも金井くんも、すこしずつ微妙に立ち位置が異なっている、ということが指摘できるかもしれない。ゲストトークでは、それらの差異を対立として捉えることなく、しかし安易に同調するというのでなく、違いが違いとして尊重されることで、『ことばとからだのイビピーオ』の問題系が孕む地平の豊かさが、かえって炙り出されるような、そんな時間になればよいと思う。
というわけで、「人体の幾何学的展開」(すでにこのタイトルに、強い可塑性(だがそれは決して野放図なわけではない)への志向を感じる)のゲストトークに、僭越ながら司会として関わらせて頂きます。尊敬する友人でもある小鷹研理、そのパースペクティブに今回接続されるゲストは伊藤雄馬さん! https://t.co/CtehYFQERL
— Manabu Kanai (@terrain_vague) October 15, 2022
最後に申し込みについて。展示は無料ですが、ゲストトークのみ有料(1500円)です。ゲストトーク中は、展示は(フルではなく)部分的に解放されるような状態となる予定です。メールでのお申し込みをお願いしています。11月23日までに予約いただいた方には、特典として、錯覚ブックレット『即錯23』を無料でプレゼントします。
具体的な予約方法は、以下を参考にしてください。
それでは、ご予約をお待ちしています〜。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
