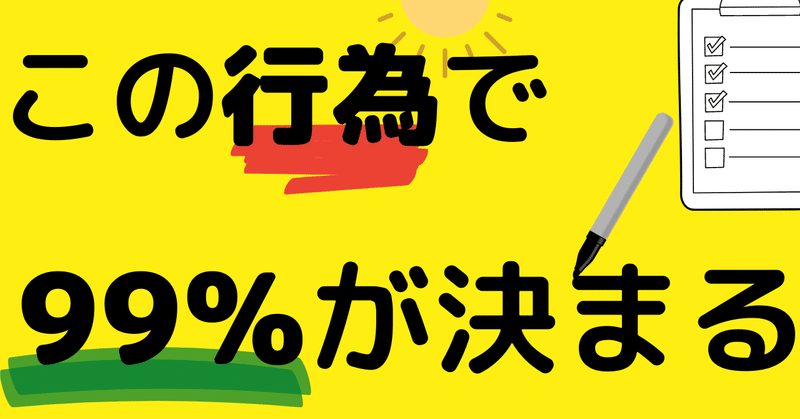
【基礎知識 徹底解説🔥】為替レートの決定理論&主要概念:国際金融論💵No.1
今後、定期的に投稿していく
【国際金融論】シリーズにおいては
私が現在学習している内容である
「国際経済学の分野」について学んだことを
アウトプットしていきたいと思います👍
前回の記事【為替レートの決定要因:③】のリンクは以下です
ぜひこのシリーズにて基礎理解を深めていただいて
理論を学習されることを推奨いたします💖
はじめに:モデルの導入前に
開放経済における対外取引は、財・サービスに係る「経常取引:Current Account」と、金融資産に係る「資本取引:Capital Account」に大別されるということは、こちらの記事で解説しています💖
これらの取引の根本的な
相違点は、次の2点です
資本取引の単位費用が
経常取引の単位費用より小さいこと資本取引の所要時間が
経常取引の所要時間より短いこと
これらの相違から
国際取引に障壁(=資本規制や取引数量制限、莫大な取引費用の存在など)がない場合
内外の資産市場はほぼ常時均衡状態にあると見なせますが、内外の財(サービス含む)市場は必ずしも均衡状態にあるとは限らないのです
要するに、資本の移動というのは
時間が掛かることが多いです
「金融市場における資本」とは
少しニュアンスが違うかもしれませんが
財市場における資本を考えてみます
工場や家を建てる時間が
1年以上掛かるケースが多いことに対して
鉄鋼原料が貿易される時間は相対的に
短いというイメージで良いと思います📝
短期と長期の違いについて
今一度、ここで「長期と短期の違い」について確認しましょう
国際マクロ経済学における「長期」とは
財市場と資産市場の両者が
均衡状態に達する期間を指します😌
その一方で「短期」とは
瞬時に均衡状態に達する資産市場のみが
均衡する期間を示していると理解してください
私が解説する内容は、内外の財市場・資産市場が共に均衡状態にある場合の
為替レートの決定理論を取り扱うことにします
以下では、まず為替レートの均衡に
関する古典的な概念である「購買力平価説」
および購買力平価と密接な関係にある
「実質為替レート」について
説明することを試みます😉
その次、貨幣市場に着目した
為替レートの長期均衡理論である
「マネタリー・アプローチ(貨幣接近)」に
ついて考察してみようと思います🌈
また、購買力平価説および
マネタリー・アプローチに基づく為替レートの実証分析についても言及できたらと思います
そして、私が卒業論文を
執筆するときに留意点を指摘しながら
理解を深めていくことにします💝
為替レートの長期的均衡モデル:Part①
為替レートの決定理論について
これから丁寧に解説していきたいと思います
長期均衡モデルで大切なことは「財・資産両市場の均衡」を考慮することにあります☺️
短期とはまた異なる視点を持っていることは
上記で解説いたしましたが
まずは長期のモデルから順番に解説していきたいと思います
登場する記号一覧は、以下の通りです
$$
P_i : the price of No.i good \\
S : Local currency exchange rate \\
{P_i}^* : the price of No.i foreign good \\
( i = 1, …, n )
$$
購買力平価と実質為替レートの関係性
モデル(1) :一物一価の法則
2 国間の財市場において裁定が
完全に機能する場合には同一通貨で測ったときの同一財の価格は等しくなるはずです
この法則は「一物一価の法則;Purchasing Power Parity」
と呼ばれ、為替レートの決定理論の1つとされています📝
一物一価の法則は、 任意の i 財に
関して以下の通りに定式化されます
$$
PPP : P_i = S \times {P_i}^*…(1)
$$
もし、自国通貨で示した外国の第 i 財価格が
国内価格よりも安い場合
両国における i 財価格が均等になるように
裁定取引が働きます
この結果、外国から i 財が
輸入されることとなり、i 財の国内外での
均衡価格が実現した時点で
為替レートが決定されるのです👍
$$
If, P_i < S \times { P_i }^* \\is established\\---------\\
No.i good will be imported \\to Domestic country \\from Foreign country.
$$
PPPが成立するための条件
では、本当に「一物一価の法則」は
国際経済学ならびに現実経済を
説明できているのでしょうか??🙄
ここで、財の一物一価の法則が成立するための条件について整理することにしましょう
PPPが成立するための条件や仮定は
以下の通りになります
財の国際取引に対して障壁が存在しないこと
財の取引コストが存在しないこと
財の価格に関する情報が完全に共有されること
これらPPP成立条件について
以下に解説していくことにします📝
①財の国際取引に対して障壁が存在しないこと
これらの障壁には、関税や数量制限とい った法的規制に加え各国の取引慣習等による
目に見えない貿易障壁があるのです
実際の現実社会では、米中貿易摩擦の問題や
ロシア-ウクライナ間の紛争において
ロシアに貿易制限を掛けたりと「制約や障壁」は少なからず存在するのです
EPAなどの自由貿易協定はあくまで
その協定に加盟している国家が対象になります
したがって、本当に世界で「障壁&制限なし」に自由貿易を実施することは不可能に限りなく近いのです💦
②財の取引コストが存在しないこと
本当に全ての財が、国際貿易の対象品目かと
言われると、また違うのかもしれません
運送料や保存料、為替のマージン、両替コスト、貿易業の人件費など「取引コスト」は
必ず存在しているのです
これを「無し」と仮定することは
かなり現実から乖離してしまう
のではないでしょうか??😢
具体的な財・サービスを取り上げると
散髪や医療サービス等が該当しますね
これらの財・サービスは取引コストが極端に
高くなる財・サービスの分類であり
「非貿易財」と呼ばれます
この「非貿易財の存在」が
一物一価の法則が成立しない要因になります
③財の価格に関する情報が完全に共有されること
財価格に関する情報が非対称的であれば
国際取引において同一財が異なる価格で
取引されることがあるのです
この「完全情報の仮定」もなかなかハードな条件ではないでしょうか?
いま、あなたはアメリカの食材の価格をすべて認知していますか?
また、貿易コストや現地の生産状況など
「あらゆる情報」を会得できた上で
消費行動の意志決定ができているでしょうか?
私は遺憾ながら、できていません💦
このような国際経済における情報の非対称性も
PPPが成立しなくなる要因であることを理解してくださいね
購買力平価説に対する見解
このように、一物一価の法則は厳密な意味で
成立することは想定しがたいと判断されても
致し方ないのではないでしょうか??
このインプリケーションより、PPPはあくまで経済現象を抽象化するための概念的な関係であると理解することができるのです
すなわち、ミクロ的な概念である
一物一価の法則をマクロの均衡条件として
一般化したものを
「購買力平価(Purchasing Power Parity:PPP)」と考えるということです
この解釈によって今回の議論は
まとめられると思います
今回の為替レートの決定理論に
関する解説は以上とします☺️
次回も購買力平価説について
より深く理解を深めていくことが
できるよう丁寧な解説を心がけて参りますので
ぜひご期待いただけると幸いです💗
For You:マガジンのご紹介🌟
こちらのマガジンにて
【国際経済学🌏】の基礎理論をまとめています
また、経済学理論集などは
こちらをぜひご覧ください💖
今後、さらにコンテンツを拡充できるように努めて参りますので
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます📚
Ending:最後までご愛読いただき誠に有難うございます!
あくまで、私の見解や思ったことを
まとめさせていただいてますが
その点に関しまして、ご了承ください🙏
この投稿をみてくださった方が
ほんの小さな事でも学びがあった!
考え方の引き出しが増えた!
読書から学べることが多い!
などなど、プラスの収穫があったのであれば
大変嬉しく思いますし、投稿作成の冥利に尽きます!!
お気軽にコメント、いいね「スキ」💖
そして、お差し支えなければ
フォロー&シェアをお願いしたいです👍
今後とも何卒よろしくお願いいたします!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
