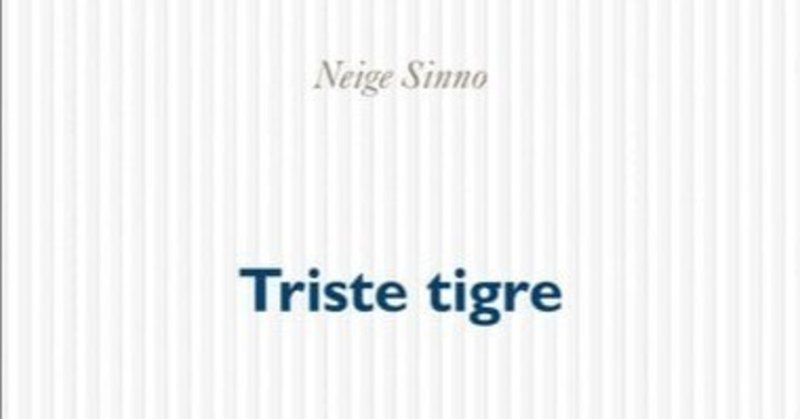
アルファの彼岸へ
日本では新学期が始まって早一ヶ月たち、新緑のさわやかな初夏でしょうか。もしかしたらもうそろそろ梅雨も心配になっているかしら。でも日本でもかつてはヨーロッパやアメリカのように九月が新学期であったのご存知でしょうか。例えば漱石の『三四郎』では学年は九月十一日に始まり、三四郎に午前十時頃学校に行かせ、『こころ』では逆に「私」は六月に卒業式があり、あまりにも暑く、家に帰ってすぐに裸体になった、と言っています。予算の年度がその時も四月からで、ずれていたので、その後学年度をそれに合わせて今のように新学期は春になったそうです。
フランスは今のこの時期は夏の大型バカンスへあと一ヶ月とちょっとなんで、イースターの名残のキリストさんの昇天、その後彼が言い残した聖霊降臨、あと時代がやたらと先に進むが第二次世界大戦のドイツとの休戦記念日と続く休日によって気を紛らわしています。その後日本では信じられないほどの長さの夏休みで楽しみ秋の新学期に備えるわけ。
日本の新学期とちょっと違うのは新刊の本がたくさん出るのがフランスの新学期の特徴。最近は発行品目数は減少傾向だが、秋に一気に約500冊の新刊が出て、本屋さんのショーウィンドーを賑やかにわかす。これはクリスマス商戦に向けて、本の評判は一昼夜で作れないとのことなので、二、三か月かけて口コミで作るためなんだとか。そのためなのか、読書の秋が深まる頃にちょうどよく文学賞が目白押しになっている。去年そのいくつかの賞を受賞し、文学に興味ある人々のサークルよりもうちょっと広いとこでも話題になったのがNeige Sinno(ネージュ・シノ)という変わった―MarieとかNathalieって名前じゃなくて日本語で雪って意味の―名前の作家のTriste tigre(『悲しき虎』とでも訳しておきましょうか)。
伝統ある文学賞の前哨戦といってもいい、若者あるいは気が若い人が読むLes Inrockuptiblesという雑誌の賞、そして年取ってその雑誌を卒業して読むと言ってよい新聞のLe Mondeの賞をももらい、とうとう四大文学賞の一つFemina賞を受賞。惜しくも最も権威があると思われているゴンクール賞は逃してしまいましたが、そもそも自伝のような作品であり、小説とは厳密にいえない作品がゴンクールの候補になったこと自体画期的なこととして話題になりました。というのは2018年には風刺週刊誌『シャアリー•エブド』(Charlie Hebdo)襲撃事件の体験記と言ったらいいのだろうか、Le Lambeauという作品がその完成度が評価されていたにもかかわらず小説という形式ではないと判断され、ゴンクールの候補にならず物議をかもしたこともあったからです。(Le Lambeauはその完成度から他の前述のFemina賞及びRenaudot賞の特別賞を授与される。ちなみに去年2023年度のゴンクール賞は"Veiller sur elle"というイタリアと南仏を舞台にしたマルセル・パニョル(Marcel Pagnol)ばりのノスタルジックな物語が受賞している。)。
この作品『悲しき虎』―以下理解の簡便さのため題は日本語に訳した形で記す―が話題になったのは単に小説という形式ではないということだけではもちろんなく、作者自身が被った義父からの性虐待という不穏な主題にもかかわらず、その筆致は極めて冷静で、言葉を的確に選びながら丁寧に語っているところから来ている、とみています。おおよそこのような主題を扱った作品を修飾する時に安易に用いられる赤裸々とかスキャンダラスといった言葉とは縁遠い作品だったので、そのため話題になったのでしょう。
ゆっくりとのんびりとした筆致で家族の構成、義父と母親との出会い、アルプスのふもとの田舎での家族の牧歌的生活とその地方でのその家族の立場などを描いていますが、フランスのインテリ固有の晦渋な表現などなく平易なフランス語で朴訥に語っていきます。会話の引用ではないのに地の文でdes trucs comme çaとおおよそフランス語の文章では見受けない表現、またçaの多用など。日本語にすれば「こんな感じ」、「アレ、ソレ」。その朴訥さが当初ニュアンスに欠けるように映り、取り調べの供述調書の犯罪の背景の説明みたいに感じられ、犯罪の小説化のレファレンスと言ってよい犯罪学者でもあった加賀乙彦の著作を知っている身としてはありきたりな感じがしてしまいました。
でも辛抱して読んでいくと例えばナブコフ(Vladimir Nabokov)の『ロリータ』(Lolita)の分析が分析として書いてあるだけではなく地のテクストに織り込まれ、それがテクストを自由自在に扱えるいかにもフランス人的で、主題が重い―どこにも逃げることができず、体験を他人と共有できず、結果的に逆説的だが虐待者自身にしか理解を求めることができないことなど―にもかかわらず理知的であり、情念に堕ちていかないのです。
その後もヴァージニア・ウルフ(Virginia Woolf) の異母兄による虐待への言及、その他の小説、随筆、論文など様々な引用があり、それらに対する解説と自分への性虐待の体験を交差させて描くなど文章に陰影というか躍動感があります(でもトニ・モリソン(Toni Morrison)による”The Bluest Eyes”の性虐待の迫真の描写の引用は皮肉にもノーベル賞作家との筆力の差を浮き彫りにしてしまう計らざる効果がありました)。全体的な印象としては、感情的ではなく抑制的で、音楽にたとえると和声の進行に破綻がなく、不協和音がたまにあるだけで旋律が最終的には落ち着く解決がちゃんとある感じ。アンリ•デュティユ(Henri Dutilleux)の音楽のようだと言えば分かってくださる方もいるでしょうか。
インテリ向けの文体の実験といういかにもという文学的たくらみが感じられるわけではなく、それでも素朴な地の文の間に文学作品の引用そしてそれらの分析があり、またそれだけではなく詩的というかアレゴリカルな文章があり、結果的に豊かな重層的な文体を駆使した作品になっています。その一例としてたとえば義父のこと、ひいては義父に関する記述を―一部ですが―現在形で書くんですよね、フランス語で標準的に過去を表す複合過去や単純過去じゃなく。このような不自然なフランス語が平易な記述の中にしこりのように現れ、露骨なあるいは暴力的な性描写によって不快になるのとは違った形の戸惑いを読者に感じさせます。
そしてこの様々な種類のテクストが織りなす重層性の魅力がいかんなく発揮されるのが後半の第二部。本文が276ページで後半は163ページから始まり、相変わらずのんびりした文体なのですが、虐待者の心理の通常なあり方、被虐待者の虐待を受けた後のあり方を、ハンナ・アーレント(Hannah Arendt)の『エルサレムのアイヒマン』(Eichmann in Jerusalem)における虐殺の執行人、つまり虐待者との面談の報告や、性虐待裁判における鑑定書、逆境的小児期体験に関するThe New Yorkerの記事、と他の人のテクストを「間テキスト性」なんて言葉を出してくるのが恥ずかしいぐらい引用し、そしてその様な虐待・被虐待関係の一般的な考察を踏まえたうえで自分が義父から受けたこと、そしてその裁判の様子を描き、そうすることによって性虐待の一般的考察が血が通った人間におこった悲劇であることを読者に痛感させ、そして性虐待の当事者の体験に普遍性を与える。
そして次の文章で作品を閉めくくります、「この世界の境界に留まるすべを学ぶことこそが試練だ。自分の運命の線上を綱渡りするように歩むこと。よろめく、でも念を押すが落ちてはいけない。落ちて倒れないこと。」
(Apprendre à rester sur le seuil de ce monde, voilà le défi, marcher comme des funambules sur le fil de nos destinées. Trébucher mais, encore une fois, ne pas tomber. Ne pas tomber. Ne pas tomber.)
funambulesとは綱渡り。年配の方なら思い出しません?大江健三郎の『厳粛な綱渡り』を。あれも小説でもなく論文でもなく極めて主観的なエッセイを集めたものでした。大江関連でうんちくを続けさせていただければ、彼が多大なる影響を受けていたウィリアム・ブレイク(William Blake)の『無垢と経験の歌』(The Songs of Innocence and of Experience)に収められている詩「虎」(The Tyger)に着想を得たアメリカの女性作家マルゴウ・フラゴウソウ(Margaux Fragoso)の近所の優しいおじさんであった男にこの作家自身も子供の頃性虐待を受けていたことを書いたエッセイというか自伝の"Tiger, Tiger"がしばしば言及されているのを見ると、この作品の題『悲しき虎』はここにヒントを得たと言えます。(明示的にはそう言っているところはないのですが)。
さて確かに『悲しき虎』は小説ではないのですが―ある出版社から小説ではないという理由で出版を断られたそうですー、この作者は敢えて小説ではない形式を選択したそうです。作者曰く、フィクションを書くことの特権はその内容に関しての―作り事であるという―誹りから逃れることができることであるが、敢えて自分はその特権の外に出る、と。作者は方法論的選択の決意を表明しています。それと同時に小説という枠から出たが文学ではあると作者は主張します。
そこで思い出したのは加藤周一が「文学の擁護」って評論で小説中心の20世紀以降の英米系で主流で日本でも影響力を持つ文学観を批判し、小説でないものでも概念的・論理的把握を超えて語らざるものを読み取らせるようとするものはそのことによって芸術的表現力に接近し、まさしくこのような言葉を超えようとする言葉による芸術的表現力とは文学にほかならない、と文学を再定義しています(加藤周一の場合は前者、すなわち小説中心の文学観を西洋に発祥した歴史的に浅いものとみなして、それに対して中国の政治色の強い歴史もの―史記ーを中心にした文学観を射程に入れて新たな文学の概念を提唱しているのでしょう)。加藤周一の1964年のテクストを持ち出してくるのは牽強付会のようですが、でもネージュ・シノのテクストはそれだけの喚起力があるんだ、と居直っておきましょうか。
居直りついでにいえばこの作品の普遍性は文学的なものだけではなく、別のジャンルの一見無関係なものと同時代的な共振性を有することにもあると思います。去年2023年のオスカーを総なめにしたあの『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』(Everything Everywhere All at Once, Daniel Kwan and Daniel Scheinert, 2022) がその「共振」相手です。
作者ネージュ・シノは先ほど引用したテクストよりちょっと前から終わりを告げるように、音楽で言えばcodaのように次のように言います、「どうやったら他人を抑圧することに転ずることなく大きな力に達することができるのであろうか。どうやったら新たな悪に陥ることなく穏やかに悪を超越することができるのだろうか。そして、どうやったらこの穏やかさを陰がある世界と同じように私たちに重要で、魅力的であるようにすることができるだろうか。」(Comment faire pour s’élever à une plus grande puissance sans que cela tourne à l’oppression d’un autre ? Comment transcender le mal dans la douceur et non dans un nouveau mal ? Et comment faire pour que cette douceur nous importe, nous fascine autant que le côté obscur ?)
映画『エヴエヴ』では母親が憧れていたが手に届かなかった(アメリカ語で言う)アルファ(つまり体力も知力も優秀)になるか、その母親にアルファになるためしごかれたけど挫折した娘のようにシニカルになり空虚の入り口の丸に飛び込みニヒリズムに居直るか、という一見もっともらしい二項対立に陥るが、父親―おおよそアルファの正反対でひ弱―が無理にアルファとして戦い続けようとする奥さんを優しくその道は間違っていると聡し、さらに『エヴエヴ』は多重世界を想定しているので、別のアルファの世界モードの中におけるビシッとタキシードで決めた父親も、これまた瀟洒なドレスを着こんだ成功者の奥さんに向かって穏やかにいう、すなわち、どんな世界にいたとしても奥さんとコインランドリー屋を営み税金申告を一緒にやりたい、と。まるでアルファであることを無化するような発言をし、力か無力(でニヒルに居直る)か、もしくは無力なものが力をつけ反撃をし力をやっつけるという結局は同じように力に頼る、という力に支配された世界とは別の世界、生き方をはからずも力が支配する世界の勝者アルファが示唆しているのです。どうでしょうか、先の『悲しき虎』から引用した文と「共振」しませんか。

『エヴエヴ』はその大衆性からか、愛で力が支配する二項対立を無化しようとちょっと安直で、でもまぁそれは間違ってはいないと思うのですが、それでは陳腐で納得しない向きはたくさん出てくると思うのです。『悲しき虎』では「普通の世界」(le monde normal) と「別な場所」(l'autre lieu) という二つの世界を想像し―マルチバース!―、この二つの世界が偶然に重なりあったときに悲劇や新たなことが起きると、作者は考えています。他者と共有できない「別な場所」(l'autre lieu)を各自みんなが持っているということを言葉ではない形(indicible)―視線、しぐさ、雰囲気で—確認すること、そのことによって「別な場所」(l'autre lieu)は消えることはなく人々の深奥に存在し続けるが、ひとは「普通の世界」(le monde normal)と共存できるのではないか、そしてそれがきっと先に言及した綱渡り(funambules)、つまり闇に陥落せず綱渡りをしていくこととネージュ・シノは『エヴエヴ』ほどではないにせよ、いささか楽観的に言っているのではないのでしょうか。楽観的と言っても、暗澹となる体験の当事者に裏打ちされた言葉であり、それをその当事者が引用する豊富なテクストに支えられることを目撃するにあたって、世界に対するこの彼女の楽観性に賭けても悪くないかな、と思ってしまいます。
あらゆる人間の争いはネージュ・シノがいうような力による力の圧倒と言うメカニズム、そして『エヴエヴ』がそのむなしさを指摘するアルファの覇権争いが原因なのです。「正義の力」や「正義の暴走」などという言葉は人間の野蛮な力への意志を直視していない欺瞞です。そう考えると『エヴエヴ』を安直、『悲しき虎』を楽観的と馬鹿にする向きの方が浅はかと言えるのではないでしょうか。
最初の一見拙いと思える素朴な文章からは想像し難い、過去の文学、哲学はもちろん同じ体験を持った人に関する報告書や彼ら自身の文章と、ネージュ・シノ自身の当事者として消すことができない重い体験に関するテクストとの豊かな対話はしなやかな知性によるしたたかな戦略の結果であり、それは当然小説というカテゴリーを超え、知的な感動と興奮を与える重厚な文学作品でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
