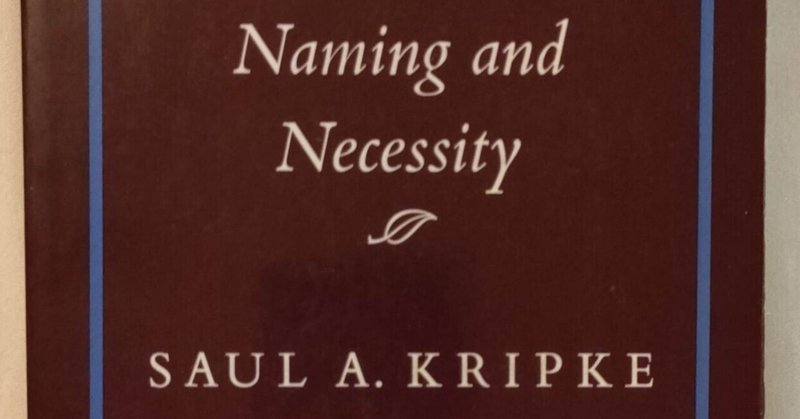
軽快さと絶望―Kripke試論―
クリプキと僕
ソール・クリプキ(Saul Kripke)が今年2022年の九月の十五日に亡くなった。言及するにはいささか旧聞に付すが、僕にとっては重要な哲学者であったので、時宜がズレていてもちょっとこだわって彼について書いてみたい。
おそらく1980年代に大学生だった僕の世代は雑誌『群像』に連載されていた柄谷行人の哲学試論の『探究』で言及されたいたのを読んで彼の名を初めて知ったのではなかろうか。そのおかげで個人的体験だが、パリ第八大学に留学した1990年にフッサール(Edmund Husserl)の仏語訳者のケルケル(Arion Kelkel)先生のヴィトゲンシュタイン(Ludwig Wittgenstein)の授業でまだフランス語文献を渉猟することができなかった時に柄谷行人が援用したと思われるクリプキの私的言語の本Wittgenstein on Rules and Private Languageをレポートにまとめて単位をとった経験があり、それ以来その軽快な語り口で人々の興味を引き、それでいてパラドクスという思考の崖っぷちに連れていく、読者に考えることを猛烈に強いる哲学者としてその名が頭にこびり付いていた。
クリプキと挑発
そう、クリプキは挑発的な人であった。果たしてヴィトゲンシュタインを全て読んだのかは疑問で―十四歳で幾何と微積を独学でマスターしたなどの「天才」エピソードがたくさんあるので、たぶん大部分は読んだのであろうけど―というのは、なにしろ上記の本ではヴィトゲンシュタインの『哲学探究』の693篇ある命題とその後のおおよそ50頁にわたる付論のうち僅か一篇の第201命題だけにこだわり(正確にはその言い換えのような次の命題202も語っているけど)、それでいてその後のヴィトゲンシュタイン解釈のコースを変えてしまった人なのだ。こういう比喩は適切ではないかもしれないが、哲学界のアニキみたいな存在で、厳格であるはずの哲学議論に専門的な言葉など使わず、世間話をする口調でモノ申していくのである。その人を食った物言い―"68+57=5である、なぜならばあなたがプラスと思って+を見てしていた計算は実はクワスであったからだ!"―は充分に挑発的で、分析哲学特有の地味な議論の細部が分からなくても、既成の議論に挑戦してみたい向き―すなわち向う見ずなの30年前のパリ大学の学部生だった僕―にはじつに読んでいて疲れるが、頼もしい存在だった。
ちなみにこの足し算のアポリアに対してクリプキは懐疑的解決というものを示す。ちょうどこの論考の主眼である固有名とその記述とまたその指示対象に関する齟齬に関して共同体という社会性を導入して説明するように、過去における自分の演算がプラスであったという主張とへんてこな懐疑論者が突きつけて来るクワスであったという齟齬は社会的に、すなわちプラスであったかそれともクワスであったかというかという過去の事実への言明の正しさを探ることではなく、他の人々との対話、つまり社会の中で決定される、とクリプキはいう。言ってみればそれは真理/偽が決定される科学的言明ではなく、信念にかかわる言明であり、クワスであった疑惑は残るがそれまで常に125になるプラスをしていたと信念が社会的に投影されるからプラスであると、きわめてヒューム(David Hume)のように懐疑的に解決される。
そもそも僕がかじっていたフランス現代思想自体が十分挑発的であった。それは価値中立的に議論を進めるものではなく、過去の哲学者、プラトンやルソーとかを、あるいは彼らが使う伝統的哲学的語彙を援用しながらもそれらに備わっていると思われている正統性、論理性を所与とすることなく、むしろそれらに挑戦する営為であった。そして20世紀とはこの伝統に由来する正統性が全て疑問に付された時代であった―音楽の調性崩壊、ゲーデルの不完全性定理やコーエンの連続体仮説の証明の不可能性の証明による数学の盤石と思われていた基礎の危機、絵画における遠近法の消失、そして意識によって統御される存在であるはずの人間に無意識を見い出し、さらには合理的存在が合理的に他の合理的存在を大量殺戮するという非合理性を剥き出しにしてしまった、価値転倒というか価値がダイナミックにリシャッフルしたのが20世紀であった。
クリプキと『名指しと必然性』
話しをクリプキに戻そう。その後僕はジジェク(Slavoj Žižek)のThe Sublime Object of Ideologyというおおよそクリプキの名とは不釣り合いのところで出会い、ヴィトゲンシュタイン解釈の文脈―彼の解釈があまりにも独特でヴィトゲンシュタイン自身を反映していないのではないかとKripkensteinと揶揄もされる―、日本で言えば柄谷行人の彼の引用によって有名になった文脈とは全く違ったところで彼を知ることになり、早速Naming and Necessityを購入したものであった。
この本は1970年に行なった連続講演の記録であり、一説によると一切の原稿なしで講演を行なったようで、しかもその講演録であるこの本の論旨は到底校訂したとは思えないぐらい放恣で議論の筋道を追うのが容易ではない。まさしくクリプキの軽快な知性が縦横無尽に躍動した知的刺激に満ちた作品だ。もしかしたら分析哲学のトレーニングを受けたものにとってはそれほど困難ではないのかもしれないが、さっき言ったようにフランス現代思想をかじっただけのものにとっては分からないところが多い。だが、詳細な論理展開が追えないにせよ、この本が類に見ないもので、画期的なものであったことは分析哲学の素人が読んでいても伝わってくる。
クリプキとフランス現代思想
その画期的なところはジジェクが援用することが象徴するように分析哲学の文脈にとどまらないところである。それではその射程の深さを紹介して、さらにそこから僕が今の世界の状況を読み解く示唆を与えてくれると思っているクリプキの主張を紹介しよう。
まずこの本のキー概念の一つである「原初の洗礼(initial baptism)」。通常分析哲学ではなるべく特定の文脈に依存しない平易な言葉を使って論を重ねていくものだが、クリプキは「洗礼」というどっぷりある特定の文化的というか宗教的な意味を担い、科学的議論とは一見縁のない表現を使う。普通の哲学の議論、特に分析哲学のそれは価値中立性を標榜しているが、実際はある価値のコンテクスト(パラダイム、エピステーメー)に依存していることに無頓着か依存していることを隠蔽している欺瞞があるが、ここにおいてそれらを露呈するとまで言わないが、揶揄したいといういたずら心をクリプキに読みとろうとするのは行き過ぎであろうか。というのはこの彼のいたずら心があったと思えるからこそ、図らずも彼自身の意図を超え彼の名指しの理論が精神分析と接近することを可能にしたと思うのだ。
まずは精神分析を復習しよう。精神分析においては父の名による(au nom (non) du père)禁止の法で世界が秩序立てられると考える。つまり母−子未分化で近親相姦可能な世界に父の名の下(au nom du Père)で否定(non)を突きつけ、(近親相姦の)禁止の法を打ち立て世界を構造化する。ファルスとして母と一体化していたのが(父親のような)ファルスを持った主体になる。パパ-ママ-僕のエディプス三角形の成立。これがラカン(Jacques Lacan)の基本テーゼであったはず。
未分化状態で存在していたのが父親の名の下でその状態にくさびが打ち込まれ、そのことにより主体として分化させられ、名前が与えられる。「僕」という代名詞かクリプキが言う固有名詞かはここではおいておいて、独立した個人(in-dividu)として命名されることに着目しよう。
僕の名前「健太」をつけた人は僕の両親だ。そしてその両親のお互いの名前をつけたのはそれぞれの両親、すなわち祖父母だ。とたぐっていくと、一体人類はいつ誰が命名という行為を始めたのか、という疑問に行きつく。最初の命名者は、となるとそれはもはや歴史的事実を追うというよりは神話的、あるいは聖書的な事柄に属しているとも言えないか。つまり「原初の洗礼」。
それまでの原罪を洗い流し、新たな名が与えられ世界に入っていくことが「洗礼」の定義ならば、原初的状態から抜け出すため存在に名を与え、それらによって世界を作っていった行為こそが原初の洗礼なのではなかろうか。(もちろん正確にはクリプキの原初の洗礼はこのような意味ではなく、ある名前の起源を伝達の鎖を遡っていったときにたどり着く最初の命名行為のことを言っているのであって、命名行為自体の原初をたどっていない。しかし、論理的逸脱をゆるして頂けるならば、命名行為自体も起源の不明性に陥るという類似性があると言えなくはないか。)
実際フランス現代思想を体現していると言っても過言ではないデリダ(Jacques Derrida)はその著書De la grammatologieで、原初の暴力(violence originaire)として命名行為(nommer)をあげており、それは名前を与え、存在を他の物と区別してとらえ、分類することだという。
ところでのちにデリダはケンブリッジ大学から名誉博士号を授与されるが、その時にクリプキが代表格であると言っていい分析哲学の界隈からデリダは現代フランス哲学を侮蔑の対象に貶めたとして猛烈に反対され声明文も出されるほどであった(クリプキ自身は反対声明に署名していない)。水と油のような研究領域―分析哲学とフランス現代思想—にいるクリプキとデリダ。しかし二人は命名行為に関しては「原初の暴力」、「原初の洗礼」と奇妙な共鳴がある。
このように形而上学―「形而上学」という言葉を現実に根を持たない思弁、とちょっと前まで分析哲学をかじった人たちが大陸の思想的営為を罵倒する時に使っていた言葉としてではなく、この世界の基礎的なあり方を探究している学問と考えるならば—の水準においてもクリプキの主張は深い射程を持っており、一見敵対している分野ともその深さにおいて繋がるのである。
クリプキと記述理論
それではその深さの水準においてもう少しクリプキの主張がどう革新的であって、それがどのように今の世の中を見ることの助けになるのかを見て行くことにしよう。
彼はまず分析哲学の礎を作ったラッセル(Bertrand Russell)、フレーゲ(Gottlob Frege)のその当時有力な名前に関する記述理論(descriptivist theory of names)に疑義を呈し、むしろ 古典的なミル(J.S. Mill)に親近性を示し、まるで17世紀に起きたフランスにおける新旧論争(querelle des anciens et des modernes)の再現よろしく―ただしクリプキは旧の方に身を置き、つまり時流に抗い―新しく支配的な議論はおかしく、古臭いと思われている方がずっと射程が広く一般的であった、とお家芸の挑発をするのである。
ラッセル・フレーゲは名前とはそれに関する記述であると主張した。どういうことか。例えば「ゲーデル(Gödel)」という固有名(name)は「算術に関する不可能性定理を証明した人」という記述(discription)に置き換えられるということである。ところがクリプキは果たしてそうなのか、と疑問を呈する。例えば不可能性定理を証明したのはゲーデルではなく、実際はシュミット(Schmidt)という人で、その人はウィーンの街で変死体で見つかったとしよう、という仮定をクリプキはおく(このようなきわめて不埒な物言いがNaming and Necessityにはふんだんにあり、それがさきほどのように「クリプキのいたずら心」と言わしめる)。この場合普通の人は「ゲーデル」という名を使いながらも実際はシュミットのことを言っている―だって記述理論によれば「算術に関する不可能性定理を証明した人」という記述はその指示対象(referent)、つまりその名前が表しているもの・対象はシュミットなんだから―。「ゲーデル」と言いながら、それが記述理論によればその記述が指示(refer)しているのはシュミットという人になってしまう。本当にそうなのか、これはおかしいんじゃないか、というのがクリプキ。
もちろん大多数の人はゲーデルが不完全性定理を証明した人と思っているが、それだけでは「不完全性定理の証明」という記述をこの人にあてはめることはできない。というのは「ゲーデルが算術に関する不完全性定理を証明した」という時、ゲーデルが指示対象になってなければならないからである―でもクリプキの想定した例では指示対象はシュミットという矛盾。このように名前に関する記述理論を突き詰めるとパラドクスに直面することになる。
ところがふてぶてしいクリプキはここで動揺することなく、僕たちはこの例において、実際ゲーデルを指示しているのだと、うそぶく。
ちなみに「ゲーデル」と言って、算術の不可能性定理の証明が通常あてがわれる(attribute)人を意味すると言うことは出来ない、それでは一般的に定理があてがわれている人が指示対象であるという循環論法に陥ってしまう。指示対象とは確定されている記述を必要十分に満たす対象であり、だからこそ「ゲーデル」に不可能性定理があてがわれるわけであるが、この場合は記述があてがわれているから指示対象という循環論法に陥る。したがって循環論法に陥らず、何か独立した基準で指示対象にたどり着かなければならない。
クリプキは指示対象を示す責任を他人に任せる(pass the buck)という。どういうことか。ここで再登場してもらうのがさきほどの「原初の洗礼(initial baptism)」だ。僕は親による原初の洗礼によって「遠藤健太」と命名され、それが私の親によって指示対象の僕、「遠藤健太」という固有名、「昭和40年に埼玉県所沢市XX病院で生れた男」という確定記述らが、親の知りあい、親戚に伝搬していく。あるいは誕生に立ち会った人によって伝播していく。つまり「遠藤千年(僕の母の名前)によると『遠藤健太』は昭和40年埼玉県所沢市XX病院で生まれた」→「遠藤千年から聞いた須藤一郎によると『遠藤健太』は昭和40年埼玉県所沢市XX病院で生まれた」→「遠藤千年から聞いた須藤一郎から聞いた佐藤二郎によると...」、という形で指示対象には循環論法に陥らず昭和40年に埼玉県所沢市XX病院で生まれた人で、「昭和40年に埼玉県所沢市XX病院で生れた」という記述と「遠藤健太」という固有名で伝達の連鎖(chain of communication)を追って行けば到達できる。
もちろんこのようにして指示対象とその名前は自分の近くにいる人だったら、具体的に誰が誰から聞いたことを同定することは容易であろう。では、歴史的人物、そう僕たちの例のゲーデルだったら、具体的に誰が誰にゲーデルの名前とその情報を伝達したか追うことは難しく、またしっかりと指示対象を参照するかわからないし、ゲーデルに関する記述が合っているかどうかも不明だ。しかしクリプキ曰くここで着目したいのは誰を頼って指示対象に至ったかではなく、実際の伝達の連鎖である。周囲にいる人たち・共同体(community)の話し相手とのつながりを追って指示対象自身―例えばゲーデル―まで戻り、参照できるということである。
ここまで来て浮かび上がってきたのは、記述理論の指示対象軽視に対するクリプキの不満である。記述理論を標榜する人たちは固有名とは記述によって確定されるというが、そこでは決定的にその固有名を持つもの—指示対象―に対する言及が不足している。クリプキによればそのことが畢竟固有名とそれを担うものとの関係を間違って捉えることにつながるという。言ってみれば記述理論による名前とそれを指示する対象は社会とは無関係な個人—方法論的個人主義が想定する、つまりデカルトから始まる西欧近代の伝統的個人―が確定するもので、指示対象を抽象的に捉え矮小化している。クリプキのいたずら心、挑発に乗じて言わせてもらえば、記述理論は固有名や記述という概念の間の関係を論理的に確定することにより一見厳密に見えるが、クリプキの不謹慎な例―算術の不可能性定理を証明した人は実はシュミットという人で、ゲーデルがその人を殺しその成果をくすねたことを示唆する例―においては、ゲーデルが算術の不可能性定理を証明した人であるが、指示対象はシュミットであるという、矛盾を解決できないのである。
クリプキと見取り図
クリプキは講演の記録であるこの本において記述理論を覆すような厳密な理論を披露することはしない。そこでは記述理論が直面する背理とそこから露呈するこの理論の限界を示し、それに対して僕たちが実際にある固有名をもつものに言及している仕方を示唆するだけにとどまる。つまり彼は指示対象を確定するための厳密な必要十分条件を構成している理論(theory)を求めようとしているのではなく、人々がどのように名前の指示対象をとらえ、名前を伝えていくのかの見通しの良い見取り図(picture)を与えたい、と再々言っている。
そうは言いながらもクリプキは記述理論を7つの要件に分解し、それらを詳細に反駁しているが、彼曰く、そんな細かいところの誤謬より記述理論は基本的な考え方が間違っているとのこと。つまり、名前に関していくつかの性質=記述を見い出し、それがあるものを選別し、指示対象が確定されるというのは間違いであって、クリプキはそんな「孤立した部屋」で確定されるものではなく、実際はいく人もの対話する人によって作られている共同体における伝達の連鎖を手繰ってたどりつく可能性のあるものである、と言っている。だからこそ、もっとそれに関しての見通しの良い見取り図を提供したいとクリプキは言っているのであろう。
その見通しの良い見取り図をクリプキは僕たちに渡し、次のように言うだろう。名前の指示対象の確定は私たちがそのことの性質をどうとらえるかよりも、共同体の他の話者、そしてどのようにしてその名前が伝わってきたかという歴史に依存する、と。その歴史を辿ることによって指示対象に到達するのである。
さてここまでが哲学専攻の学部生が書くようなNaming and Necessityの射程の深さを紹介するレポート。ここからはクリプキの不埒な挑発の顰にならって、Naming and Necessityがもっている分析哲学を逸脱する社会的な可能性の中心を探って行こう。
クリプキと共同体
クリプキは指示対象にたどり着くのは共同体(community)内の他の話し相手との対話(communication)だと言っていることを見てきた。共同体...、哲学徒に取っては居心地の悪い言葉だ。不穏ささえ感じてしまう。だってそうでしょう、哲学はその発祥以来、プラトンのイデア、絶対的存在である神の存在証明に尽くした中世のスコラ哲学、デカルトの普遍学(mathesis universalis)、カントの超越論的観念論、ヘーゲルの絶対精神、あの西欧世界の鬼っ子のマルクスだってプロレタリアを類的存在としそこに人間の普遍性を見出しその開放が人間性の回復と見たのであった。そう、哲学は常に人類を普遍的世界へ開放することを目指した知的営為なのだ。それに比べ共同体と聞けば閉じた特殊性に居直った八紘一宇、Blut und Boten(血と土)といった不吉なものを思い浮かべるが、それは大げさなことであろうか。
共同体という存在はその性格上一意的というより複数であると考えることは不自然ではない。さらに共同体はしばしば閉鎖的である。そう考えると厄介なことにならないだろうか。
クリプキはしばしば伝達の連鎖における伝達者の誤認、伝達内容の錯誤の可能性に言及する。例えば―今回は数学者じゃなく物理学者―ファインマンのことを市場(いちば)かどっかで誰からか聞いたが誰かは忘却し、さらにファインマン・ダイアグラムなんて知らないが、有名な物理学者であることは知っている伝達の連鎖の末端にいる人を例に出し、まさしくその人がある共同体にいることによってその人はその連鎖を通して固有名「ファインマン」によって指示対象としてファインマンに言及できるのである。
複数の共同体が存在し、ある指示対象にそれぞれの共同体に固有の―しかも誤認、錯誤にまみれの―伝達の連鎖が存在したら、同じ名前、同じ指示対象を話しながらも、全く違ったことを語っている可能性が出てくるのではなかろうか。
あるいはクリプキとは逆向きにこう考えられないだろうか。共同体に伝達連鎖が生じるのではなく、実は様々な原初の洗礼(先の僕の名前に関しての例で言えば、遠藤千年による「遠藤健太とは...」、須藤一郎による「遠藤健太とは...」)があり、それに依存した多数の伝達の連鎖が存在するが故に異なる共同体が生じるとは考えられないだろうか。しかも共同体の閉鎖性から固有名に対する理解に対して相互排他的になる可能性があるのではないか。となると、共同体間の伝達・コミュニケーションが取れなくなる可能性が出てくるのではないか。
分断の時代と言われ久しい。上の理屈でこの社会的分断の説明を試みれば、ある出来事―当然それは固有名を伴う―に対する言及がいくつもの連鎖を通って伝達され、それぞれの異なった伝達の連鎖に従っていくつもの異なる共同体が形成されることになる。ということはたとえそこにおける錯誤を覆すような事実に直面したり、別の連鎖の同じ指示対象についての別の言説を聞いても―別の(言説の)共同体に属する人から「間違い」を指摘されても―、自らが属する伝達の連鎖の名前とその記述を修正すことは難しいのではないか。(クリプキの不埒の例がその典型でシュミットという指示対象がありながら、算術の不可能性定理を証明した人はゲーデルがからシュミットに修正されることは難しいだろう。) このように同じ固有名を用い話ながらも指示対象や記述の誤認や齟齬に依存したいくつもの異質の伝達の連鎖によってできる共同体であるから、共同体間での対話が―同じ固有名を使いながらも指示対象や記述が違うから―不可能になるのではないか。
クリプキと「左翼」
たとえば「左翼」という言葉。クリプキと違ってゲーデルやファインマンといった超然とした存在の名前ではなく、もっときな臭い名詞を例に出してきて恐縮だが、インターネットではここ数年で主に政権政党を支持する人たちや周辺諸国に強硬的態度でいる人たちなどが政府の社会政策批判をする人、外交において対話を重視する人を非難する言葉としてすっかり定着してしまった。
もちろんこの言葉はフランス革命の時に王の処遇に急進的であったものが議会で議長から見て左側にいて(保守的)穏和派が右に位置していたことに由来していることは誰でも知っていることで、そのフランスではそれ以降保守または国粋的な人、ひいてはそれを代表する政治家を「右翼」、そして社会政策の充実を求めたり、人の在り方の多様性に寛容な人そしてそのような政治家を「左翼」と呼ぶことは絶えずなされていたし、アメリカではliberalとかconservativeと呼ぶことが多いが、leftやright (wing)ということばはずっと使われていた。
ところが日本では、僕が日本にいた1980年代においては左翼という言葉は研究か運動の場―あるいは公安の文書?―で使われていたが普通の人は自民党の政府に反対する人たちを革新陣営、野党、市民活動家、学生運動というグラデーションをもって呼び、左翼という言葉は使っていなかった気がする。せいぜい島田雅彦がデビュー作で芥川賞をとりそこなったことで有名になった作品でサヨクとカタカナでいじらしく使ったぐらいではなかったか。
それがここ十年―主にソーシャルメディアといういささか特殊な場を中心にしてだが―亡霊のようにこの言葉がよみがえり、攻撃的に使われている。それに対して「左翼」の指示対象とよばれてもよい人たちは完全に同一化はなかったと思うが、革命を断念し独善的な性格を露呈したそれまでの左翼の代表であった共産党と区別(決別?)するために造語「新左翼」という言葉で自分たちのことをよばれても別に違和感を感じなかったと思う。
複数の伝達の連鎖によって形成される互いに非連結的な共同体。指示対象も記述も錯誤と誤認にあふれ、ただ伝達の連鎖を伝わっていく空虚と言ってもいい固有名。
その典型的例が「左翼」だ。なぜ完全に死語ではなかったが確定記述はもちろん指示対象さえも同じでない可能性が高い―ここで蓋然的にしか言及しないのは1980年代当時に「左翼」という言葉が用いられていた数多いコーパスと今誹謗に使われている「左翼」のインターネット上の膨大なログの実証的比較はこの理論的考察には手に余るからだ―言葉が亡霊のように復活し社会において暴力的に振舞うことができるのか。そしてその相手を誹謗するために使われる「左翼」と社会の多様化とその多様性の共存を目指す「左翼」は収斂することはあるのか。つまり複数の伝達によって生じた非連結的な共同体は連結できるのか。
クリプキとジジェク
これらの僕の質問の回答へいざなってくれるのはKripkensteinの文脈のではない別のクリプキを紹介してくれたジジェクだろう。
ジジェクはクリプキから着想を得ているが、そこから離れ、名指しの基本的偶然性(radical contingency of naming)を主張する。つまり名指し自体が遡及的に指示対象を構成すると主張するのだ。さきほど亡霊のようによみがえったというのはこういうことなのだ。
クリプキ曰く固有名は固定指示子(rigid designator)としてあらゆる想像できる世界において指示対象を名指す。またジジェクによるクリプキ解釈では固有名と指示対象は言ってみれば双対関係にあり、名指すことによって指示対象が召喚されると、そこから様々な記述内容が、つまり先ほどから問題にしている錯誤にあふれる伝達内容が確定されるというより過剰な含意(connotation)としてあふれ出てくるのではなかろうか。
国家に寄生する人たち、周辺諸国に言いなりになる人、財政に無責任な政治家、日本の伝統を否定する人たち、と言った雑多な記述が原初の洗礼の時に「左翼」という名前が指示対象を遡及的に徴することによって左翼というものを形成するのだ。左翼だから国家に寄生したり周辺諸国に言いなりになるのではなく、「左翼」という名指しのもと指示対象が選ばれ、「左翼」が含意するものが事後的にかつ過剰に確定記述となり、それが伝達の連鎖によって、人々に伝わり、その名前と指示対象を受け取り、ある種の―攻撃的な?―言説の共同体を作っていくのである。
ではなぜ今?それは結局、固有名、指示対象、記述という概念を確定し、その論理関係を探っても―それが分析哲学の真骨頂であった―1980年代における用法と今の用法との差異の原因は出てこないだろう。つまり言語を使った伝達行為は社会的行為であり、言語は社会の入れ子であり、社会の形に依存するといったところか。
ジジェクに倣っていえば社会的闘争のイデオロギーの競合において「左翼」という言葉の過剰な使用によって惹起される指示対象を攻撃することによって、攻撃している人たちはその人たちの不全感を充填している(指示対象はジジェク御用達の対象a !)。そしてその不全感はもちろんのこと固有名‐指示対象‐記述の関係の論理的な(logical)分析によって説明されるものではなく、ジジェクのように精神分析によって比喩的に(analogical)よってしか近接できないのかもしれない。
そして僕がいた1980年代の日本における社会は経済という整流器(安直に精神分析の言葉を使わせてもらえば貨幣というシニフィアン)によって人々のあり方―フランス現代思想的に言えば「欲望」?―が一様化されていて、社会的闘争は政治的平面ではなく経済的表面における競争においてその特徴が現れていたため、「左翼」に過剰な形で言及がなかったのではないか。
クリプキと軽快さとそして絶望
名指しが基本的に偶然ということから言語行為の恣意性―すなわち社会的なものに依存する―が分かったが、ということは1980年代と今のソーシャルメディアを中心にした「左翼」の使用の著しい落差が示すように言葉の―すなわち固有名、指示対象、記述の―関係が恐ろしいほどの相対主義に陥らないだろうか。ちょうどヒュームが自然界の物理法則が神から与えられた所与であるということに根本的な懐疑を示し、その法則とは自然界には存在せず、人間の心(mind)において結びつけられ、自然に投影された習慣ではないか、という懐疑的陥穽におちたように。
繰り返すが指示対象や名前の記述の誤認や錯誤は伝達の鎖に依存して、そのことによっていくつもの共同体が作られる。そしてそのことが―ちょうど「左翼」の濫用が示唆するように―原因で現代の様々な紛争が起こっているのではないだろうか。
つまり、別の伝達の連鎖によってできた共同体の人との合意は言葉による論理性によっては不可能であり(共同体の非連結性)、その解決には近代が信じてきた教育を通した言語による合理性の啓蒙ではなく、理性ではなく感情の領域に深く依存する善意、あるいは利害による妥協、譲歩もしくは強制によってしか理解の齟齬は解決できないのではないか。
クリプキの軽快さにつられどうやら僕たちは深い絶望の縁に連れて来られてしまった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
