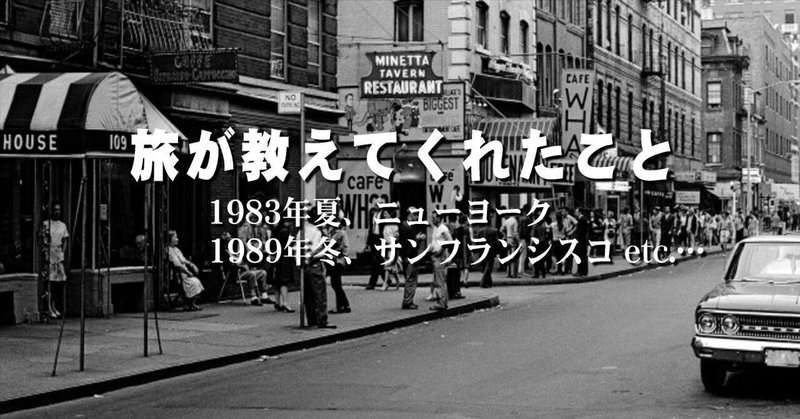
旅が教えてくれたこと (14) 旅について思うこと…
旅のスタイルなんて人それぞれだ。「旅から学ぶ」なんて話もひとそれぞれだ。「旅は楽しければいい」というスタンスは、けっして間違ってはいない。
「まえがき」で書いたように、僕も旅は楽しければいいと思っている。何かを学ぶために旅をしているわけではない。結果として旅から学んだことはたくさんあるが、他人から見れば「それがどうした」という程度の話だと思う。でも、旅を楽しくしたり、旅によって人生を多少でも豊かにしようと考えるのなら、「旅」というもののあり方について、少し考えてみるのも悪くない。
僕は最近、旅を楽しみ、旅から得るものを増やすためには、ある種の「旅のノウハウ」があるかもしれないと思うようになった。本書の最後に、そんな個人的な「旅のノウハウ」を少し書いておこう。むろんこれから書く話はまったく個人的な意見であり、誰に強制するものでもない。戯言だと思って頂いてもいっこうに構わない。
僕は旅をするにあたって、特に海外を旅行するにあたっては、ある種の「旅の所作」のようなものが必要だと考えている。つまり、旅の中での「身の振舞い方」のことだ。特に海外へ行ったときの所作は重要で、所作を間違うとコミュニケーションがうまくとれなかったり、身に危険が迫ったりする。逆に所作を間違わなければ、周囲の人を不愉快させず、現地の人と楽しいコミュニケーションがとれ、安全で快適な旅を送ることができる。
旅の所作を決める最大のポイントは「眼差し(まざざし)」だ。旅先の土地や人に向ける眼差しである。人は、考えていることが必ず眼差しに出る。特に、恐れ、怯え、侮蔑や軽蔑、差別や優越感などは、必ず眼差しに出る。
例えば、あなたがニューヨークの街を歩いていて「背が高くて体格のよい黒人」から突然話しかけられた」としよう。その時に、もしあなたが「一般に黒人は教養が無く乱暴な人が多い」という認識を持っていたとしら、話しかけられたとたんに確実にビクッと怯え、それが表情に出てしまうだろう。その黒人は、たまたま道を聞きたかっただけかもしれないし、時計を持っているあなたに時間を聞きたかっただけかもしれない。しかし、話しかけた相手が急に怯えた顔をして身を引いたら、「こいつは何だ? 黒人のことを差別しているのか?」と不快に思うかもしれない。その結果、不快な顔で去っていくだけならまだよいが、「こういう奴は気に食わないから金でも盗ってやれ」と思って路上強盗に変身するかもしれない。
もう1つ例を挙げる。旅行中のタイの田舎町でバス乗り場の近くに1軒しかない安食堂に入ることになったとしよう。客はあなた1人だ。その店以外に食べるところがない土地だ。バンコクなど大都市のレストランと較べれば小さく汚い食堂で、食堂を切り盛りするおばさんが1人と、その子供らしき汚れた服を着た幼児が店の中を走り回っている。そこであなたが「汚い店だなぁ、むさくるしい子供だなぁ」と感じて、そのまま顔に出したとしよう。そういったネガティブな表情や感情は、絶対に顔に出てしまうし相手に伝わる。それからおばさんに料理を頼んでも、けっして美味しい料理は出てこないだろう。逆に、「こんな店で食べるのも面白いなぁ」「子供もかわいいなぁ」と思ってにこやかな表情で料理を注文したとする。そうすれば、おばさんは一生懸命料理を作るし、おかずもおまけしてくれるかもしれない。
「眼差し」とは、このあたりのことである。では旅を楽しく安全にする「自然な眼差し」、そしてその「自然な眼差し」が生む「自然な所作」を身に付けるためには、どうすればいいのだろうか。
■異なるものを、その場でありのままに受け入れる
これは簡単なようでけっこう難しい。国が違えば、気候・風土・文化の全てが異なる。気候や風土を受け入れることならまだしも、異なる文化を体験の瞬間に受け入れるのは意外と難しいのだ。文化が異なる国や民族の習慣といったものに対して、自分の国のそれと比較して「嫌悪感」や「侮蔑感」を持つケースがある。特に発展途上国、低所得国の文化や習慣・習俗に対しては、日本の…と言うよりも、近代の欧米的価値観を尺度にして、一段低いもの、文化的ではないものとして見がちだ。また、嫌悪、侮蔑までいかなくとも、見て「狼狽」するケースは非常に多いだろう。
僕は、旅先において「文化の違い」「習慣・習俗の違い」といったものを何でも全てよいものとして受け入れろと言っているのではなく、少なくとも「先入観を棄て、何も考えずに、優劣をつけずに、まずは受けいれる…」べきだと言っているのだ。訪問先の国家や人種に対する先入観などもってのほかだ。自分が見たありのままの姿を常に無条件で受けれる準備ができていれば、初めて訪れた国で初めて眼にした相手国の人の習慣や習俗を、「平静な眼差しで見る」ことができる。それによって相手と対等のコミュニケーションが成立する前提ができる。狼狽の眼差し、嫌悪や侮蔑、差別の眼差し、またはそれらと裏返しの優越感の眼差しなどを、相手に見せなくて済むのだ。
■旅先の風土や歴史をできる限り詳しく知る
渡航先国の風土や歴史について、あらかじめ知識を持っていることは非常に重要だ。ただ、旅に出る前にわざわざ勉強しろ…というだけの話でもない。ガイドブックなどを読んだ付け焼刃の知識だけはなく、もう少し幅広い「教養」的な知識を身につけていた方がいいと思う。とりわけ世界の近現代史全般、列強の植民地政策とアジア・アフリカ・中東諸国の独立の経緯…といった部分は重要だ。むろん、これには自分の国である日本との関係も含まれる。加えて、ある国のある地域の民族固有の歴史や現在の政府との関係…といった知識もあるといい。こうした知識を持っていれば、世界中どの地域へ旅行しても、その土地の人々の価値観や文化の基底を流れるものが何かわかる。誰が誰に抑圧されてきたか、また現在抑圧されているか…を知っていれば、接し方や話の内容も変わる。その国における移民の存在や動向についても知っておきたい。そうしたことを踏まえて話し、振舞うことによって、コミュニケーションも深まるし、やっていいこと、言っていいこと・悪いことの判断もつく。何よりも、その地域に住む人達への「眼差し」が自然なものとなる。
こうした知識はガイドブックを読んで得られるものではない。普段から国際ニュースや新聞記事に留意し、様々な本を読むことが大事だろう。そしてこうした知識を持つことは、確実に旅をより面白く充実したものにしてくれるはずだ。
7
旅先で出会う人、関係ができた人と、付き合いが深まっていくのは楽しい。また、深い付き合いではなくとも、ほんの一時出会った人との会話やコミュニケーションにも、心が躍る時がある。でも、どんな出会いであっても「相手の持つ背景や属性」についての洞察がなければ、本質的なコミュニケーションのベースとなるものは成立しないと考えるべきだろう。その人が、その国でどんな職業に就いているのか、どんな境遇なのか、どんな家族的背景を持つのか、そしてそうした事実の総体が、その人を社会の中でどんな立場に立たせているのか…をある程度洞察できなければ、コミュニケーションは深まらないし、相手の気持ちに踏み込むことはできない。逆に、そうしたことを洞察して、それをきちんと態度や眼差しで表現できれば、互いの信頼関係は深まっていく。例えば、その相手の出身地(国内外を問わず)や出自を知れば、その国のなかにおける相手の立場がわかる場合が多い。また職業は、その人の社会的立場だけでなく思想的な傾向に大きな影響を与える。あらゆる出会いの場面で、瞬時にそうしたことを洞察して、相手に対する信頼を得る態度をとることができれば、旅の深みは増し、楽しさも増すはずだ。
■自分の国と相手の国との関係に留意する
日本人である自分と、訪問国の人である相手との関係性も重要だ。まず留意すべきは、訪問国において日本人がどのように見られているか?…ということ。さらに、相手がその国でどんな立場にあるか、どんな個人的背景を持つかによっても、日本人全般に対する認識は異なる。アジア地域であれば、日本人全般に憎しみを感じている人もいるし、逆に日本の文化に憧れを抱いている人もいる。
いまさら言うまでもないことだが、アジアには日本の植民地支配の傷跡が残る地域は多い。本書で政治的な発言をする気はないし、何が事実かを議論するつもりもない。ただ、植民地支配の傷跡…というのは、相手がそう感じているかどうかだけが問題であり、植民地支配を行った側は、そうした相手の感情を無視することはできない。特に、旅先においては相手の人が持つ対日本人感情を忖度することは非常に重要だ。その気持ちがないと、旅先でトラブルを呼び込むことになる。
あとは、相手と自分の社会的立場の違いや宗教の違いといったものも、関係性を考える上で重要だ。
■差別しない 差別されない
さて、僕は本書にも書いた1980年代のアメリカに長期滞在している折、様々な差別や侮蔑的扱いを受けた体験がある。バスで中西部や南部を旅していた時など、「東洋人」というだけで空席のあるレストランへの入店を断られることなど、日常茶飯事だった。ナッシュビルの街中にあるカントリーのライブハウスで、理由も言われず入場を拒否されたこともある。多人種が共存して暮らすニューヨークでは直接的な差別を受けた体験は少ないが、それでも欧米人が持つ東洋人、特に東アジア系の人種の容姿に対する差別感は、相当なものがある。具体的な行為として差別されていなくても、そうした「相手の眼差し」「微妙な態度の変化」は敏感にわかるものだ。
むろん、アメリカ人の間でも差別はある。誰もが知る「WASP」の優位性は当然だが、東部の人間がいわゆる中西部や南部出身の「田舎者」に対して侮蔑的なことばで笑いものにすることは多い。むろん、アメリカ国内における人種差別の現状については、ここであらためて書くまでも無い。
最近仕事でよく行くタイなどでも、国内でそうした容姿や出身地に対する差別はある。バンコクなどに住む都市の高所得者を中心としたタイ人が、イサーン地方出身者、しいてはイサーンの方言を話す人間をバカにするのはごく一般的なことだ。また南部出身者は、肌の色が濃いというだけで差別される。人間の外観で差別・侮蔑する性向はどの国でも同じだ。
でも、こうした「差別」を当たり前のこととして、自分自身もそうなってしまったのでは、旅先でいいことは何もない。例え人がどうあろうと、自分自身は誰も差別しないというスタンスは、特に旅先では重要だと思う。
まだまだ書きたいことはあるが、僕が「旅の所作」を身につけるために必要だと思うことは、概ねこんなところある。ここに挙げた点に留意することが、旅先での「よい眼差し」を生み、それが「自然な所作」「正しい所作」につながると思っている。全ての出会う人に対しては「自然な眼差し」を、そして明らかな社会的弱者に対しては「同情の眼差し」は絶対避けて「優しい眼差し」を心がけたい。
海外旅行をする人は、よい旅の所作を身につけて欲しいと思う。よい所作を心掛けることで、旅先でのコミュニケーションはうまくいく。ひいては、旅先でのトラブルも避けることができる。結果として旅が充実し、楽しいものとなる。
僕は、多くの人の旅が、楽しく安全で充実したものとなることを心から願っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
