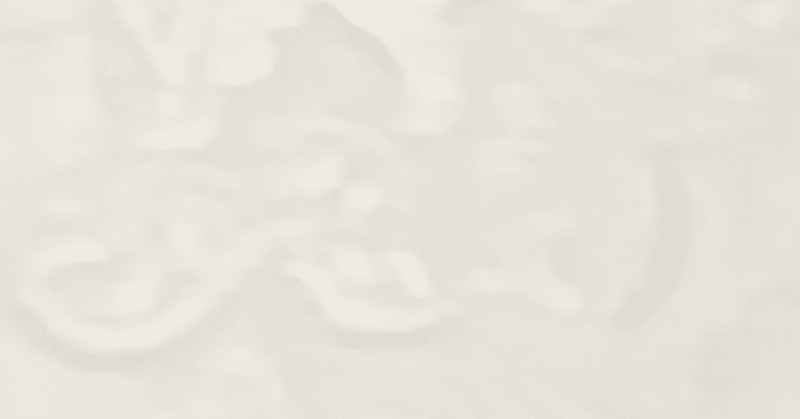
大人に捧げる童話 『暖炉のある家』
雪の降り続いたあとの、夜でした。しんしんとした冷たい空気が、首筋や足元から、ヒタヒタと忍び寄ってきます。
澄んだ空に月がひとつ。
世の中の凡てを青白い光と漆黒の影に変えて、月はただただそこに浮かんでいます。
その、古い煙突の家もまた、青白い光と、影のコントラストに彩られて立っていました。
静かな夜です。
家の中から漏れてくる灯りを誰かの気配が揺らしても、外は静かに、夜の中を通り過ぎてゆくのでした。
その家に、気配はふたつ。ひとつはサーナ。ひとつはムーナ。
サーナは暖炉のそばで本を読んでいます。ムーナは、長椅子で編み物をしています。
何を編んでいるのか、ムーナはしばらく編んではほどき、ほかの毛糸を取り出しては新しく編み進めて、またほどき。その度に色とりどりの毛糸玉が、あっちへコロコロ、こっちへコロコロ。じゃれつく猫もいないのに、毛糸玉は虚しく転がります。
突然、ムーナは編む手をとめて、歌を唄い出しました。編み物に飽きたのでしょうか。彼女の口から、細く高い旋律が流れます。
「やめてちょうだいムーナ。耳の中がザラザラするわ」
サーナにピシャリととめられて、ムーナは一番好きな節を唄えずじまい。仕方なしに長椅子から立ち上がりました。
「どこへ行くのムーナ」
サーナが鋭く呼びとめます。
「…どこへも、行きやしないわ。ちょっと、窓の外を見たいだけ」
外は、庭も、垣根にも、雪がこんもりと積もって、月の光を一面に跳ね返していました。
そう、ひとつのシミもない、あの白雪姫の頬のよう。
「ねぇ、サーナ」
ムーナが話しかけます。
「別世界だわ、この家の中と、外。隣り合っても、決して交わらない。まるで、異次元だわ」
「難しいこと言わないでよムーナ」
サーナは本から視線をあげて言いました。
「頭痛くなっちゃうわ」
ムーナはそっとため息をついて、サーナを振り返りました。
「あなたって、どうしてそうなのかしら」
「そうって? 何が? 」
「…その本、面白いの? 」
「面白いから読んでいるのよ」
「役に、立つの? 」
「また難しいことを言うつもりなの? 」
「難しい、かしら? 」
「難しいわよ」
「そう、かしら? 」
「それよりもお食事は何にするの? 」
「…。玉ネギと、キャベツがあるの。だから、ポトフを、」
「ポトフ? またなの? 」
「ポトフは、身体が温まるし、煮込むほど、美味しくなるし、」
「私あまり食欲ないの」
「食べない、ってこと? 」
「ミルク粥なんか良いわね」
「…アーモンドが、ないわ」
「アーモンドなんかいらないわ」
ムーナは、顔をゆがませて、
「私、美味しいミルク粥なんか、作れない」
と、呟きました。
「呆れた」
サーナは、眼を大きく見開いて、
「いつも作ってあげてたのに」
と、天を仰ぐ仕草をします。
「あの味を忘れちゃったの? 」
すると、ムーナが眼に涙を浮かべたように見えたので、サーナは慌てて、
「いいわよポトフで。ただしニンジンをたくさん入れてちょうだい」
と、言いました。
「わかったわ、サーナ」
ムーナは泣くのをやめて、窓ガラス越しにサーナを眺めました。
空ではちょうど、大きな雲がやってきて、月を覆い隠そうとしています。
「ニンジンを、たくさん、入れるわ」
ムーナは、暗い窓ガラスに映るサーナの姿を、指でなぞりました。
「向こうにいるはずのないサーナが、窓の向こうにいるみたい」
ムーナが、少しおかしそうに言うと、
「ムーナいいかげんにして」
サーナが怒ったような声を出したので、ムーナは急いでポトフを作りに台所へ向かいました。
月がすっかり雲に隠れると、外は、何も見えなくなりました。
台所の小窓も、青黒いインクで塗り潰したように真っ暗です。時おり、北風が小窓を震わせますが、中からは何も見えません。ポトフの材料を丁寧に切りながら、ムーナはふと小窓に眼をやり、自分の姿を確かめてすぐに眼をそらしました。
「何も見えないことと、何もないってことは、同じじゃないわ」
ムーナはそっと呟くと、昨日の内に仕込んでおいたカボチャのパイを、オーヴンへ入れました。
次に、ポトフの鍋を火にかけます。やがて、鍋がフツフツと沸騰し始めて、台所に野菜の甘い匂いが漂い出した頃、空には再び月が顔を出しました。
月の青白い光が、森の向こうへと続く小道を、明るく照らしています。
ムーナは、輝き出した小窓の外の世界を眺めながら、
「お月様は、あんなに黄色い姿なのに、どうして、光は青白いのかしら? 」
と、呟きました。
「ムーナ! お鍋が吹きこぼれちゃうわ! 」
いつのまにか台所の入り口に立っているサーナが、ムーナに向かって叫びます。
ムーナはびっくりして、持っていた大きなスプーンを落としてしまいました。
「ほら! 危ないじゃないの」
サーナが鍋の蓋をさっと取りました。
「弱火にしているから、大丈夫よ」
ムーナが言っても、サーナはききません。
「底の玉ネギが焦げちゃうわ。かき混ぜるものをちょうだい」
早口にムーナを急かします。
ムーナがまた何か言おうとしたとき、玄関のドアをコンコン、と叩く音がしました。
コンコン。コンコン。
最初は弱く、次には強く。控えめなようでいて、叩く音は、粘り強く誰かの来訪を告げています。
「誰かしら? 」
サーナは鍋の中をかき回しながら、
「私は忙しいのよ」
と、言いました。
サーナがちっとも出ていくそぶりを見せないので、ムーナは仕方なしに歩いていって、ドアの向こうへ尋ねます。
「どなた、ですか? 」
「テンと申します」
「テン、さん…。」
覗き窓から、毛むくじゃらの耳が見えました。
ムーナが再び尋ねます。
「森の奥深く暮らすあなたが、この家に何のご用? 」
「今夜は百年に一度の月読みの祭り。だのに、共に祝う仲間もない私です。どうか一緒に未来を占ってくださいませんか? 」
「月読み、祭り? そんなお祭り、知らないわ」
「ご存じありませんか? 百年に一度、月が私たちの行く末を告げるときがあるのです。それが今夜なのですよ」
「ふうん。…ちょっと、待っていて。サーナに訊いてみるから」
ムーナは、サーナにテンが来たことを告げました。
「テン? 天使様のこと? 」
「違うわ、サーナ。イタチの、親戚よ。外に突っ立ったままだと凍っちゃうから、入れてあげても良いでしょ? 」
ムーナは、サーナの返事もきかずにドアの鍵を開けてしまいました。
「お初にお目にかかります、お嬢さん方」
つぶらな瞳に尖った口先。細長い胴体に、長くフサフサした尻尾を巻き付けて、テンは慇懃に挨拶しました。
「あらホント。イタチそっくりね」
台所から出てきたサーナが言うと、テンはムッとした顔をして、
「あんな野蛮な者共と一緒にしないでいただきたい。あの者共は節操のない無頼漢。私たちテン一族とは生まれが違うのです」と、言いました。
「どこが違うのよ」
サーナが言い返します。
「私には同じ姿に見えるわ」
「ところが実はまったく違うのです」
テンはムキになって答えます。
「まず歯の数が違います。私たちは38本。あやつらよりも一対多い。これは大きな違いですよ。実に大きい」
「そうかしら」
ムーナがクスッと笑いました。テンは一層ムキになって説明します。
「何より私たちの名前です。テンというのは天使様の天の文字からくる尊い名前なのです。イタチ、などという胡散くさい名前とは、わけが違う。身にまとっている毛皮だってこんなに艶やかで柔らかで、あやつらのゴワゴワした堅い毛皮とは比べものにならんでしょう? 」
「もういいわ、わかったわ」
ムーナはテンをなだめるように、
「では尊いお生まれの、あなた様にお伺いするけれど、月読みの祭りって、何をするのかしら? 」
と、尋ねました。
テンは少し気を取り直して答えます。
「読むのです」
「読む? 」
サーナが訊き返します。
「そうです」
テンは得意げに言いました。
「私たちテン一族に与えられた特権なのです。私の身体の色をご覧なさい。月と同じ色でしょう? 私たちは、月のお告げを読み取って、この地上の者へと伝える、月の使いなのです」
確かに、テンは今宵の月と同じような、くっきりとした黄色の毛皮に包まれていました。
「でも」
サーナは首を傾げて、
「月は真っ赤なときもあるわよね」
と、呟きました。するとテンは少し慌てて、
「あぁそのときはその、…そう、眼、眼が赤くなります。私たちの眼も、月と同じように赤く光るのです」
「ふうん」
サーナがまだ何か言おうとするのを遮るように、テンがまくしたてます。
「とにかくこの記念すべき夜に、この森に棲む月の使いである、すなわち月色のテン一族は私ただひとりなのです。本来ならば仲間が集まり月のお告げを待ちながら夜通し唄い踊っているはずなのに、あまりに淋しいじゃあありませんか」
「尊いお役目の方でも淋しいときがあるのね」
サーナが言うと、テンは悲しそうに、
「私は長く生き過ぎました。この地上に産み落とされてから百九十四年目。その間に森の仲間も皆、死に絶えてしまって…」
「そんなに長生きしても、ヨボヨボにはならないの? 」
ムーナが不思議そうに、
「あなたは、とてもキレイな毛皮をしていて、とても若々しいわ」
と、テンの周りをくるくる回りながら眺めます。
テンはまた慌てたように、
「いえ、それは、…それは月のおかげです。月の使いである私たちは、月の光を浴びていつまでも若々しくいられるのです」
テンはそう言い終わった後も、
「ええそうですとも、だから、うム…」
と、口の中でモゴモゴしていましたが、突然、
「さぁ! お嬢さん方! 」
まるでサーカスの司会者のように、元気に言いました。
「どうです、私と一緒に今宵は楽しく過ごしませんか? 未来のことだって知りたいでしょう? 」
「知りたいわ」
ムーナが真っ先に答えます。
「そうでしょう」
テンは頷いて、
「私だけが読み取れるのです」
と、誇らしげに胸をそらしました。
「ねえ、サーナ、良いでしょう? 」
ムーナはサーナに向かって頼みます。
「今夜は、テンさんに、泊まっていただきましょうよ」
「よっぽど退屈していたのねムーナ」
サーナは笑って言いました。
「あら、あなただって、退屈していたはずだわ」
ムーナが言い返すのをまるで聞こえなかったのか、サーナは台所へ眼をやって呟きました。
「お食事の時間よ」
「あら、そうだわ、私ったらオーヴンの中を見るのを、すっかり忘れていたわ」
ムーナが急いで台所へ戻ります。
「良かった。ちょうど、良い頃合いみたい」
ムーナはそう言うと、テンに向かって、
「カボチャのパイは、お嫌いかしら? ポトフは、いかが? チーズも、パンもあってよ。それとも、テンさんは、何がお好き? 」と、尋ねました。
テンは、リスが好きと言いかけて、
「リリリ…リンゴのように鮮やかな赤い色のお酒が好物です」
と、すまして答えました。
「赤ワインね、そうでしょ! 」
ムーナは謎々を言い当てたときのようにはしゃいで、再びサーナに向かって頼みました。
「ねぇサーナ、あのワインを少しだけ、飲んでもかまわない? ほんの少しだけ、…いつまでも樽の中に、眠らせとくだけじゃ、もったいないわ」
サーナはムーナを静かに見つめ、
「飲みたいの? 」
と、念を押すように訊きました。
「えぇ、とっても! なんだか今夜は、あのワインが飲みたい気分なの。飲まなくちゃいけないような、気がするのよ」
ムーナの瞳が輝いたのを気づいているのかいないのか、サーナはムーナの顔をじっと見たまま、
「わかったわ」と、言いました。
そして、暖炉の奥の壁にある、地下室へと続く扉を開けて、闇の中へと消えてゆきました。
「サーナには、秘蔵の樽が、あるのよ」
ムーナはテンに説明します。
「ちっとも、飲ませてくれないの。彼女の、宝物よ。私が、樽に近寄ると、機嫌が悪いの。部屋の状態が、変わるんですって。そのくせ、自分は日に一回は、樽の様子を見にいくのよ。あんな古ぼけた樽のワインを、ろくに飲みもしないで大切にしまっておくなんて、私には理解できないわ」
「愛好家とはそういうものです」
テンが、さも自分もそうであるかのように言いました。
「よほど良い年の、良い土地でできたブドウを使っているのでしょう。そのような貴重なワインをいただけるとは、私もワイン好きのひとりとして大変な自慢話ができる、というものですよ」
サーナが、少し大きめのデキャンタに、ワインをなみなみとついで戻ってきました。そして言いました。
「これは食事の後に飲んだほうがいいわ。少しクセがあるから料理にはちょっと合わないのよ。これだけで飲んだほうが美味しいわ」
「それはいい! 」
テンが大げさに手を広げて言います。
「なかなか通の飲み方ですね。私は赤ワインならいくらでも飲めるのです。食事の後だって軽く、」
「ムーナ。暖炉に薪が足らないのじゃなくて? 少し火が弱くなってきたわ」
サーナはテンを無視して、ムーナを呼びつけました。ムーナは、ポトフを水色のスープ皿によそっていましたが、暖炉のそばまで来ると、
「そうかしら。あんまり、薪をくべすぎても無駄になるだけよ。充分、火は強いと思うわ、私」
暖炉を覗き込みながら、言いました。
茜色の炎は、ムーナの顔も茜色に染めながら燃え続けています。
「そう? 」
気のない返事をして、サーナは自分が読みかけていた本を片付けると、長椅子を占領している毛糸玉を、ポンポンと籠に放り込んでいきました。ムーナは、暖炉の炎を見つめていましたが、すぐに、熱さで顔が火照るのに耐えきれないといった感じで立ち上がりました。そしてサーナに向かって、
「私の、毛糸をぐちゃぐちゃにしないで! わかってて、やっているの? ただでさえ、先へ進まないのに」
と、叫びました。
「何が進まないですって? 」
サーナはキョトンとした眼でムーナを見つめ返します。
「…編み物が、よ」
ムーナは急に気の抜けたような顔をして、テンに向きなおると、
「テーブルへどうぞ、お客様」
と、微笑みました。
月は益々くっきりと黄色く、冴えた夜空に張りついています。地上のあらゆるものの、影の美しさが際立つほどに、青白い光がそこかしこを照らし続けていました。
家の中では、食事を始めた彼女たちを、暖炉の炎が静かに暖めています。
一瞬、何かを話しかけるように炎の勢いが増したのですが、そのことに気づいた者は誰もおりませんでした。
「このポトフはまあまあいけるわね」
おかわりを入れてもらいながら、サーナが言います。
「サーナったら、さっきまで『あんまり食欲ない』って、食べるのを渋っていたくせに」
ムーナは、サーナの好きなニンジンを多めに入れてやりながら、テンに言いました。
「素直じゃないの、この人」
「私は素直だわ」
サーナが反論します。
「素直過ぎるだけよ」
「それが、いけないんだと、思うわ」
ムーナはパンに手を伸ばしながら言います。
「あなたのこと、よく知らない人が聞いたら、きっと傷つくわ。そういう、しゃべり方だもの」
サーナは、口の中のニンジンを飲み込んでしまうと、
「この家から出なけりゃ知らない人となんてめったに話さなくてすむわ! 」
と、叫びました。
ムーナは、隣のテンにちらっと眼をやって、
「それで、すむかしら? 」
と、サーナに訊きます。
「すむわ」
サーナは落ち着いて答えます。
「家には暖炉があるもの」
「答えになっていないわ、サーナ」
ムーナは首を振りながら、
「それだって、いつかは、古くなって使えなくなるもの」
と、言いました。
「古くても一度も壊れたことなんかないわ」
サーナはききません。
「安心していていいわ。あの炎が燃え続けている限り私たちは大丈夫よ」
「サーナ」
ムーナは言います。
「もっと、いろんな人と、話をしてみたくはない? この世界に、私たち以外の人がどれだけいるのか、想像しただけで、ワクワクしてこないかしら? 」
「ねえムーナ」
ムーナの眼をじっと見据えて、サーナは訊きました。
「あなた一体何が言いたいの? 」
ちょっとだけ、サーナの眼に吸い込まれそうな表情をしたムーナでしたが、すぐ我にかえって、
「そうだ、カボチャのパイを、出さなくちゃ」
と、台所に立ってゆきました。
サーナは、今度はテンのほうを向いて言います。
「この家は快適でしょう? 」
テンもまた、サーナの眼をじっと見たまま、
「…とても素敵な眼をなさっていますね。ええ、そう、まるでリスが…」
「え? 」
サーナがいぶかしげに訊き返すと、テンは急に慌てて、
「いや非常にけっこう! 快適この上ありません。きっと夏の暑い日でも楽しく過ごせるのでしょうね? 」
と、切り返すのでした。
「もちろんよ」
サーナは言います。
「外が暑いときも寒いときも。この家の中だけはいつだって快適だわ」
テンはウンウン頷いて、
「いやよくわかります。外から見たときのこの家の雰囲気といったら、道行く人々が思わず立ち止まらずにはいられないくらい素敵でしたからね」
「そう? 」
サーナは得意げです。
「また住んでおられるおふた方が素晴らしくお綺麗で」
「ふたりじゃないわ」
「え?…ああ、一心同体というわけですね? そういえばおふたりは似ていないようでとても良く似ていらっしゃる…」
「この家はムーナがいて私がいるから快適になるの。どちらが欠けてもいけないのよ」
サーナは、にっこりと微笑んで言いました。
「だって私は薪が割れないし。ムーナは暖炉の火をおこせないんだもの」
テンは、ポトフの最後のひと匙を口に運びながら、
「私は薪も割れるし、火もおこすことができます。そうですとも、おふた方のどちらか一方を悲しませることなんてしやしません。どちらか一方をなんて…」
と、誰に言うともなく囁きました。
「テンさんはお優しいのね」
サーナが言うと、
「いえいえ、あなた方のお優しさに比べたら私なんて物の数にも入りません」
「そんなに私は優しくなんかないわ」
「お優しいですとも。私を家の中に入れてくださって、あと百年は生き延びることができるように食事を与えてくださる、」
「ポトフで百年も長生きできるのかしら? 」
サーナが首を傾げると、テンは
「おや? カボチャのパイはまだですかな? ちょいとお手伝いを…」
と、もう少しで舌舐めずりしそうな口を必死に押さえて、台所へと走ってゆくのでした。
台所では、ムーナが何か悩んでいる様子です。
「どうかなさいましたか? オーヴンからカボチャのお化けでも飛び出してきたのですかな? 」
テンがおどけて尋ねると、ムーナはまだ温かいパイを、テンの鼻先へ突き出して言いました。
「切り方が、わからなくなったの」
テンは眼をパチクリさせて、
「はあ、それはまた、困りましたね。…ところでひとつご提案なんですが、パイに物差しを当てて真っ直ぐ切ってみる、というのはどうでしょう? 」
すると今度はムーナが眼をまん丸にして、
「それじゃあ二等分にしか、ならないわ。曲がった物差しなんて、ないもの。三等分になんて、できないわ」
と、うろたえた顔で言いました。テンはしばらく考えていましたが、
「では六等分にして、ひとり二つずついただくということにいたしませんか? それなら真っ直ぐな物差しでも、…いえ、もしそれで納得がいかれるならば、の話ですが…」
と、ムーナの顔をそっと覗き込みながら言いました。ムーナは一瞬、パッと明るい表情になったのですが、すぐに、
「それだって正確に、六つに切れるとは限らないわ…。二つまではちゃんとできる自信があるの、ほんとよ。でも、それから先は、やったことが、ないの」
と、力なく俯くのでした。
「なあに、大丈夫です。もし、仮に大きさがバラバラになったとしても、いいですか、ひとり二つずつ食べるのですから、一番大きいのを食べた人は、次は一番小さいのを食べりゃあ良いのですよ。簡単なことです」
テンの言葉で、ムーナはやっと元気を取り戻して言いました。
「テンさんがいてくれて、良かったわ。もし、私ひとりだったら、このままパイの前で、石になっていたところよ」
「ムーナ! ムーナ! 」
サーナの呼ぶ声がします。
「ムーナ! 大変大変! 窓の鍵が壊れているわ! …壊されたのかしら? …イーホーのまじないをしなきゃ。ドングリはどこ? 」
「サーナ、落ち着いて。大したことじゃ、ないわ。ドングリは、棚の上から二番目の、ビスケットの缶の中よ」
サーナはもどかしそうに缶の蓋を開けると、ドングリを両手一杯に持って外へ出てゆきました。
「イーホーのまじない…。はて、いったい何です? 」
テンがムーナに尋ねます。
「昔、イーホーが、言っていたの。窓やドアの鍵が壊れたときには、家の周りに、ドングリをばら撒くと良いって。それが、魔除けになるんですってよ」
「イーホー? 」
「お父さんの、名前なの。もうずっと前に、消えちゃったわ」
ムーナはなんとかパイを六等分に(それもほぼ正確に!)切り分けると、三つの青い小皿に二つずつ、取り分けました。そして、テンに手伝ってもらって、テーブルへと無事、運んだのでした。
でも、サーナは戻ってきません。
「サーナったら。どれだけ、ドングリをばら撒けば、気がすむのかしら? 」
ムーナは、サーナが開けたままにしてあった缶の蓋を閉めながら呟きました。
「お父上は、どうして消えてしまわれたのですか? 」
テンがムーナに尋ねます。
「さあ、知らないわ。ある日、突然、消えたのよ。突然にね」
「突然…? 」
「ええ。…そのとき、イーホーの魂は、確かに天使様が、連れてお行きになったわ。そこまでは、知ってるのよ、私」
「そこまでは、とおっしゃいますと? 」
「あとの抜け殻が、消えちゃったのよ」
「は? 」
「熊に喰われたか、雪崩に流されてしまったか…。とにかく、イーホーの抜け殻は、どこを探しても、見つからなかったの。おかげで、サーナは今でも、イーホーがこの家にいるって言ってきかないのよ」
ムーナは少し顔をしかめて言いました。
「困った人。…イーホーは、サーナや私に、何もしちゃくれなかったわ。本当に、たいしたこと、してくれなかったのよ。いつも、その暖炉のそばに、うずくまっているだけだったの。それでも、サーナにとって、イーホーは彼女そのものなんだわ」
「よほど、お父上を愛していらっしゃったのですね」
「父上じゃないわ」
いきなりサーナの声がしたので、ムーナとテンはびっくりして振り返りました。
そこにはサーナが、雪まみれの靴を履いて立っています。
「いつから、そこにいたの、サーナ」
ムーナの問いかけには答えず、サーナは靴についた雪をはらいながら、
「わからない人たちね」
と、呟きました。そして、さっさとテーブルにつくと、黙々とカボチャのパイを食べ始めます。
ムーナとテンも、慌てて席について、パイを口に運びます。
サーナは怒っているふうでもなく、かといって楽しいというような表情もせず、パイのお尻にフォークを刺して言いました。
「イーホーは奇跡をおこせるのよ」
テンはパイの焦げた欠片をゴクンと呑み下すと、
「ほぅ。それは、月の使いとしては、詳しくお伺いしたいですな」
わざとらしく弾むような声を出して、サーナを見ました。
サーナは、表情を変えずに話し始めます。
「イーホーと森を歩いていたときのことよ。足を毒蜂に刺されたの」
「サーナさんがですかな? 」
「そうよ」
サーナは当然、とでも言いたげな顔をして続けました。
「とても凶暴な蜂よ。大きな熊だって刺されたら倒れてしまうくらいの強い毒なの」
「あぁ、あの蜂ですな。私も花の蜜を探すときには、よくよく気をつけておりますよ」
テンが、ウンウンとしたり顔で頷きます。
「イーホーはすぐに毒を吸い出してくれたわ。けれども私はその毒に特別弱かったのでしょうね。痙攣をおこして死にそうになったの」
「そんな話、初めて聞いたわ」
ムーナは、驚いたようにサーナを見つめます。
「そのときイーホーが赤い液体を飲ませてくれたの」
サーナは、少しうっとりしたような顔をして言いました。
「今でも昨日のことのように覚えているわ。錆びたドアノブのような味がした。そしてとまりかけた心臓が息を吹き返したの。私は生き返ったわ」
「それは素晴らしい! いったいどのような薬でしょうな? 」
テンは驚きの声をあげました。
「できれば今後のために、私もつくっておきたいのですが」
「誰にもつくれやしないわ」
サーナは突き放すように言います。
「だってイーホーの奇跡なんだから」
「奇跡、なの? 」
ムーナが訊きます。
「だって、その赤い液体は、イーホーが確かに持っていたのでしょう? 」
「そうよ」
「イーホーの知恵、なのではなくて? 」
「奇跡よ! 」
サーナはききません。
「わからない人たちね」
呟くと、そのあとは、また黙りこくったまま、パイを食べ続けます。
沈黙が、流れました。
パチッと、薪がはぜます。
食器とカトラリーのかち合う音だけが、テーブルの上を滑ってゆきました。
最初に沈黙をやぶったのは、やはりテンでした。
「私ぐらい長く生きておりますと、世界のあちこちの、様々な興味深い話がもうたくさん転がり込んでまいりますな」
「まあ、どんな? ぜひ、聴かせて欲しいわ」
ムーナが身を乗り出します。
「そうですな、例えば…。ある南の島での話ですが、そこはピンクフィッシュの宝庫なんです」
「ピンクフィッシュ? 」
「ええ、もう海岸沿いにパシャパシャひしめき合うほど泳いでおりまして、これがその姿形の美しさもさることながら、味もまた格別によろしいのです」
「それじゃあ、皆が、先を争って捕りあうわね」
「いえいえ」
テンはプルプルと首を横に振ると、
「その島でピンクフィッシュを捕るのはただひとり、タルナという男だけです」と、言いました。
「許可が、いるの? 」
ムーナの問いにまた首を振ると、テンは、
「あるとき、島を訪れた旅行者が島の民に訊いたそうですよ。誰だってピンクフィッシュを好きなだけ捕れるはずなのに、どうして君たちは指をくわえて見ているだけなんだ。何もタルナからわざわざ買い求めなくたって、ほら、足元にたくさん泳いでいるじゃないか、って」と、身振り手振りを加えて言いました。
ムーナは、興味津々で訊きます。
「そしたら? 」
「そうしたら、皆、口を揃えてこう言うのだそうです。ピンクフィッシュを捕るのはタルナの仕事だから、と」
「ふうん」
「つまり彼らは、近い未来の幸せよりも、遠い未来の幸せのほうが遥かに大切だ、ということを知っていたのですね」
「どういう、こと? 」
「タルナひとりだけなら、ピンクフィッシュをどんなに捕ったところで、絶滅するということはあり得ません。つまり、いつまでもその美味を味わうことができるのです」
「皆で、いっぺんに捕ってしまうと、すぐになくなってしまうのね」
ムーナは感心して言いました。「ま、彼らにこういった助言をしたのも、何を隠そう月の使いである私の先祖なんですがね」
テンは付け加えると、ちょっと胸をそらしました。
ムーナは、眼をキラキラさせて、
「ねえテンさん、もっと、お話してちょうだいな」
と、せがみました。サーナもじっとテンを見つめています。
「お安いご用です」
テンは、もったいぶるように少し考えてから、また話し出しました。
「東の、森に囲まれた、とある小さな国には面白い風習がありまして。もし犬に噛まれたときには、その犬を飼っている家の、ピックルスをもらって傷口に塗ると治るそうなんです」
「ピックルスを? 細かく刻むの? 」
「ええ。ところがある日、セイトーという家の子どもが、隣の家の子どもとケンカをして、その子に噛みついてしまった」
「まあ」
「噛みつかれた子の親がセイトー家に怒鳴り込んできて、腹いせにセイトー家のピックルスを全部、持っていってしまったのだそうです」
「傷口に、塗るの? 」
ムーナとサーナは、おかしくて吹き出しました。
「犬に噛まれたときの話よね? 」
「そうなんです」
テンも含み笑いをしながら、
「噛みついたのは子どもなのに、おかしいでしょう? …まあ、いわば、嫌がらせのようなものですな。そして、噛みつかれた子の親は、セイトー家の子どもが、いかに礼儀知らずかを吹聴してまわりました。今回の件を、会う人会う人、事細かに話し続けたそうです」
サーナは眉をぴくりと動かして、パンを一欠片、口に放り込みました。
「ところがその、セイトー家のピックルスが、大層のこと美味しかったのだそうです。しかも、噛まれた傷も、綺麗に治ってしまいました」
テンは、思い出したようにチーズを口に運び、ゆっくり味わってから、また続けました。
「悪い噂というのは瞬く間に広がるものですが、その噂の背に乗って、セイトー家のピックルスが優秀であるという噂も、瞬く間に広がりました。ピックルスを欲しいという人々が、セイトー家に押しかけたのです。そこで、セイトー家では、ピックルスを細かく刻んで『犬の歯』という名前で売り出しました。今や、どの家庭にも欠かせない、定番商品になっているそうです」
「なんだか良い気味」
サーナが呟きました。
テンは、さもありなんといった具合に、
「この、セイトー家の成功も、そもそもは私の仲間の助言通りに行動したからこそなのですよ」
と、再び胸をそらしました。
「助言って? 」
サーナが尋ねると、
「…それはまあ、東の国の人々にしか理解できないことなのですが…、…つまりですな、つまり、その年はピックルスの材料のために、畑を入念に耕しておくように、と伝えたのです」
「へーえ」
「テンさんたちの月読みの力は、あちらこちらで、役に立っているのね」
ムーナが感心したように言うと、
「当然至極、というものです。月は、凡てを知っていますから。そして私たち一族は、それを正確に伝えることができるのです」
ムーナに尊敬の眼差しを向けられて、テンの尖った鼻先は、今にも天井に届きそうです。
ムーナにせがまれるまま、テンの話は続きました。北の果ての不思議な民族の話、西の山の頂を覆う、珍しい草花の話。
「行ってみたいわ! 私、この眼で、確かめてみたい」
ムーナは声を弾ませて言いました。
「そうでしょうとも」
「できっこないわ」
サーナの言葉が、ムーナに突き刺さります。
「どうして、」
「あなたはこの家を出られっこないからよ」
ムーナは、今度はテンに向かって訊きました。
「今夜は、月読みの祭りなのでしょう? 私の未来は、どうなっていて? 」
「そうですね…。残念ながらまだ月のお告げが出ていないようなのですが、ひとつ、私に言えることは…」
「言えることは? 」
「そろそろワインを飲んだほうが良いってことです」
サーナはポンと手を打って、
「あらそうね。そうだったわ。ムーナ。ワイングラスを持ってきてちょうだいな」
と、言いました。
ムーナが持ってきたワイングラスを並べると、サーナは注意深くワインを注いでゆきます。
「さあ、乾杯いたしましょう! 」
テンが景気良く言いました。
「私たちの未来に! 」
深い深い色が、そのワインの年数をものがたっています。密度が濃いので、向こうを見透かそうとしても、赤黒い霧がかかったように見えません。年老いた樹木のような香り以外にも、複雑な香りが漂うのですが、味は瑞々しく伸びやかで、喉をスイスイと通ってゆくのでした。
「あぁ美味しい! 大変結構ですな」
テンは一気に飲み干すと、二杯めを注いでもらい、そしてサーナやムーナのグラスにも注ぎ足しながら言いました。
「どんどんまいりましょう! 」
「ええ」
ムーナは、サーナの顔をちらりと見やりながら答えました。
サーナは黙ってクイっと飲み干しています。
「お強いのですかな? 」
テンの問いかけに、サーナに代わってムーナが答えます。
「弱いはずよ。だって、滅多にアルコオルなんて、いただかないもの」
「さようですか。いやしかし、こんな素晴らしいワインは久しぶりですよ。私は幸せものです、ええ」
テンはそう言いながらも、三杯、四杯と、次々に杯を重ねてゆきます。そして同じようにサーナやムーナのグラスにも注ぎ足してゆくので、彼女たちも次々と口へ運んでゆきます。
だんだん、三つの顔が、紅く染まり始めました。
「ところで月のお告げはまだなのかしら? 」
黙って飲み続けていたサーナが、テンに訊きました。
「え? えぇ、そうですね。…月はなんというか、まあなかなか気まぐれなものですから、こう、という正確な時間でというわけにはまいりません。昔から、月の満ち欠けを女性の気まぐれな心に例えていたぐらいで、」
「それを言うなら秋の空よ」
サーナは、今度はムーナに向かって言います。
「ね。月は気まぐれですってよ。それでもあなたは月に自分の未来を委ねるの? 」
「委ねるわけじゃ、ないわ」
ムーナは答えます。
「参考に、したいだけ。…何か、お導きがあるかも、しれないじゃないの」
「だからあなたは出られっこないのよ」
サーナはおかしそうにクスクス笑って言いました。
「この家にいなさいな。それがあなたにとって一番幸せよ」
ガタッと音がして、鍵の壊れていた窓が開きました。そして雪の上を渡る冷たい空気が、勢い良く入り込んできます。
「嫌だわ。暖炉が消えちゃうじゃないの」
サーナが、顔をしかめながら閉めにいきました。
「イーホーのまじないは効かなかったようですな」
テンがムーナに囁くと、
「おまじないなんかで、壊れた鍵は、元に戻りゃしないわ」
半ば、呆れたようにムーナが言います。するとサーナが、
「でもおまじないをするからにはそれは何か意味があることなのよ」
と、言いながら席に戻ってきました。
「例えそれが全く馬鹿げた方法でもね」
外は、夜更けを過ぎて、身体の奥まで本格的に凍るような空気が忍び寄ってきています。そんなことも厭わないほど、家の中はワインの香りに酔いしれていました。注いで、注がれて、また注ぎ足して。デキャンタになみなみと入っていたワインは、もうほとんど残っていません。
「サーナ、お願い。もうあと半分だけ、入れてきてちょうだい。半分だけで、いいから」
ムーナは、サーナにねだります。
「一生の、お願いよ」
そう言われてサーナも仕方なしに立ち上がりました。そして火照った頬を押さえながら地下へと降りてゆきます。
サーナの姿が扉の奥へと消えたとき、ムーナは素早く立ち上がると台所へと急いで走ってゆきました。そして小さな緑色の瓶を持ってくると、その中の透明な液体を、まだワインの残るサーナのグラスに一滴、二滴と入れました。
「…これで、良いわ」
気が抜けたように椅子へ座り込んだムーナに、テンが訊きました。
「いったい…。私にはわかりかねるのですが? 」
「私は、サーナの一番の幸せを、ちゃんとわかっているわ」
ムーナが言います。
「彼女は、天使様のところへ、行きたいのよ。いいえ、行くべきなんだわ。だって、天使様の元にはイーホーが、いるもの。サーナはイーホーのそばにいたいから、この家に、まだイーホーがいるだなんて、自分をごまかしてきたの。でも、もう大丈夫。私は笑って、彼女を送り出して、あげられるわ。そうよ」
ギシッと、地下からの扉が開きました。閉じ込められていた空気が、サーナとともに部屋へ入ってきます。紅い顔のサーナは、それでもしっかりとした足取りで、テーブルの上に、デキャンタを置きました。そして、飲みかけていたグラスのワインを、一気に、飲み干したのでした。
…細く高い旋律が、聞こえたような気がしました。サーナは耳を押さえようとして右によろけたかと思うと、そのまま、床に落ちていきました。
テンが駆け寄ってサーナの胸に耳を当てます。でも彼女からは、もはや何も聞こえてはきません。
「テンさん、私の門出を、祝ってちょうだい。これから私、外の空気を吸って、生きていくの。まだ今まで吸ったことのない、いろんな世界の空気をね! 」
ムーナの輝く瞳を見ながら、テンが囁きました。
「乾杯しましょう」
そしてテンは、ムーナと自分のグラスに、ワインをなみなみと注ぎ足して、それからグラスを高々と持ち上げて言いました。
「ムーナさんのこれからに乾杯! 」
「さよならお母さん! 」
びっくりした顔のテンをよそに、ムーナはグラスのワインを一気に飲み干しました。そして、…そして、どうしたことでしょう。ムーナもまた、サーナと同じように、耳を押さえようとして、そのまま床に落ちたのでした。
「…してやった。してやったぞ。 はっはあ! ざまあみろ! とうとう俺様のものになった! この家も、こいつらも、もう俺様の自由だ! …親子だったのか。まあいいさ、俺様には関係ないことさ。とにかく、こいつらふたりとも喰っちまえば、あと百年は生きられるだろうよ。まずは若くてバカなほうからいただくか。年取って利口なのは消化しづらいからな」
初めからこの家と、サーナとムーナを手に入れようと目論んでいたテンは、なかなかにすばしこい、小ずるい動物でした。酔っているムーナの隙をついて、テーブルに置かれた小瓶の中味を、彼女のグラスにも入れておいたのでした。
「しかし待てよ。すぐに喰っちまったら、こいつらの身体の毒が俺様にもまわるかもしれんな。ウム、少し間を置くとするか」
テンはテーブルのワインを手に取りました。
「まったく、このバカのおかげで最後の手間がはぶけたってもんだぜ」
テンは、ムーナの身体を小突きながら、すっかり嬉しくなって笑い出しました。
「笑って〜彼女を〜、送り出してあげられるワ! アハハハハハッ」
「…さぁ。罠をしかけましょう」
ギクっとしてテンが振り向くと、そこにはユラユラと立ち上がったサーナがいました。ゆっくりと窓のそばへ近寄って、外の地面を見下ろしながら呟きます。
「あのドングリにそろそろリスがやってくる頃ね。素早く捕まえるの。そして罠のおとりに使うのよ」
そしてクルッとテンのほうに向きなおると、呪文を唱えるように言いました。
「きっと真っ黄色なエセ占い師がかかってくるわ」
「ヒッ」
テンは声にならない悲鳴をあげたまま、サーナから眼がそらせません。何しろ、彼女の胸に耳を当て、彼女が抜け殻になったのを確かめたのは、他ならぬテン自身なのです。だのに、その抜け殻が口をきいて、しかも自分を捕まえようとにじり寄ってくるのですからたまりません。
「ロープはどこかしら? 家中に仕掛けるんだから長いものでなくちゃ。細くて丈夫なのが良いわ。…ガラスの粉が混ざったやつにしましょう。噛み切ろうとしても口が裂け肉に食い込んでいくだけで切れやしないんだから」
テンの黄色い毛皮は、もう針金のように総毛立って、ピリピリと音を立てているかのよう。逃げようとしても、サーナの眼に居すくまされて動けません。
「足がちっッとつくぐらいの高さにしておくと、生きたまま首を絞めあげることができるの。どんなズル賢い奴だって逃がさないわ。必ず捕まえてみせるんだから」
もう、テンは眼をこれ以上ないくらいに見開いたまま、ガタガタ震えてしまって歯の根が噛み合いません。生きたまま首を絞めあげる罠といったら、まさしくテンがこの世で一番恐れている狩人の罠のこと。
「…ば、ばば化け物っ」
もつれる足をやっとのことで玄関まで運ぶと、テンは家の外に転がり出ました。そして、一目散に森へと逃げてゆきます。
サーナは、その様をじっと見送ると、しっかり玄関の鍵をかけました。そして、いつのまにかスヤスヤ寝息を立てているムーナに、毛布をかけてやりながら囁きます。
「お父さんはねムーナ。いつだってあなたの気づかないところで見守ってくれているのよ」
そして、ゆっくりと地下への階段を降りてゆきます。
土の匂いのする地下室には、大きな樽がひとつ、ポツンと置かれていました。
彼女は梯子を上って樽の上に手を伸ばし、蓋をそっと開けました。
タプン、と、話しかけるように揺れる水面はどこまでも赤黒く、ムッとするような濁った香りが立ち込めています。
彼女の手が躊躇うことなく、その中のものを掬いあげました。
徐々に持ちあげられる、頭、首、胸。
それは、彼の抜け殻でした。
すっかり白い骨と化した彼の身体を、愛おしそうに引き寄せて、彼女は頬を重ねます。
「イーホー。あなたのおかげでまた奇跡がおきたわ。安心してね。家もムーナも無事でいるから」
夜が過ぎ去り、朝が来ようとしていました。白々と差し込んでくる光に、暖炉の炎はほとんど透き通ってしまって見えません。
けれども、その炎は確かにそこにあって、すやすやと眠るムーナの身体を暖め続けているということを、ムーナ自身も、否応なく、どうしようもなく、ちゃんとわかっているのでした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
