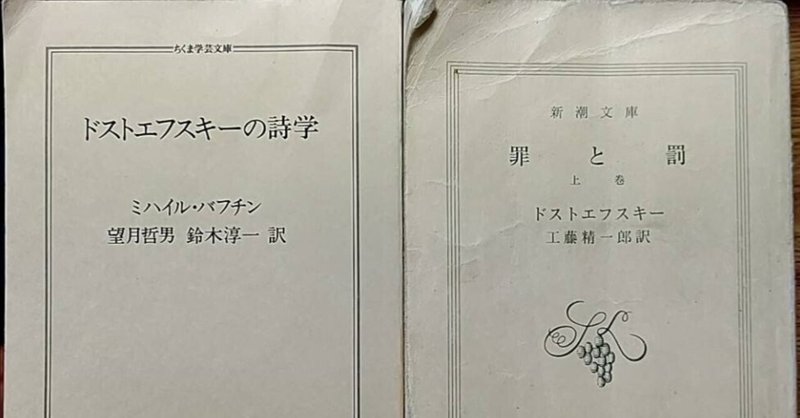
読んだふり感想文『ドストエフスキーの詩学』(ミハイル・バフチン)
「読んだふり感想文」では、本文は読まずに解説とか序文、後書きからどんな本なのかを予想したり、疑問点を挙げたり、感想を書いたりします。本文を読む前に先入観を持っておくと、本文も結構真剣に読むことができると考えています。自分の先入観を修正したり、疑問をクリアにできたりします。また、本の議論全体をあらかじめ俯瞰できるので本文の細かい議論の中で迷子になることが少なくなるかなと思います。
今回はミハイル・バフチンの『ドストエフスキーの詩学』(望月哲男/鈴木淳一訳, 筑摩書房, 1995年)解説(望月哲男)の感想文です。最近ドストエフスキー作品に興味があるので解釈の参考にしたいと思っています。
本書は5章にわたってバフチンがドストエフスキーの「詩学」を検討するものであり、その際に「ポリフォニー文学」と「カーニバル文学」という概念持ち込んでいます。
ポリフォニー文学?
第1章でポリフォニー文学の解説がなされます。これは作者が小説内の事件を対象として語るモノローグ文学の反対概念になります。
そこでは登場人物は、作者と対等の権利を持った自立した存在(自らの意識と声の主体)として設定されており、人物相互の関係も外在的な要因によってあらかじめ決定されているものではない。
私はこの主張に対して賛否両方の立場を持っています。賛成の根拠は、実際にドストエフスキーの作品の登場人物たちはそれぞれリアルなバックグラウンドとそこで紡がれた思想を持っており、自身の思想との関係の度合いも異なるということです。例えば『罪と罰』のラスコーリニコフとレベジャートニコフでは自らの信じる思想に対するコミットメントに大きな違いがあります。両者共に使命感を帯びて行動してはいますが、ラスコーリニコフは自身の思想が自身のみに課されたものとして、その実行へと絶えず駆り立てられて実際に殺人を行うのに対して、レベジャートニコフは未来社会がその正しさゆえに自分が特段努力することもなくいずれ訪れてくれると考えているように見られます。様々な思想がそれぞれの強度でぶつかり合うという点で「ポリフォニー」(多声的)というのは当たっているでしょう。また、『悪霊』でのドストエフスキーのように、明確に作者が登場人物たちと同じ世界に住んでいて、いわば物語の事件に巻き込まれてしまっているという表現もなされています。これは表現形式の面でポリフォニーを裏付けるものでしょう。
しかし同時に、重要な部分でモノローグ的な語りがなされることもあります。『罪と罰』ではラスコーリニコフがドストエフスキーの作り出した舞台から逃れられないことを示すような描写がなされます。以下の引用は、ラスコーリニコフが英雄的殺人の思想から逃れ、その重苦しさから解放された直後の場面です。
あとになって、彼はこのときのことと、この数日の間に彼の身に起ったことを一秒、一点、一線も見のがさず、細大もらさず思い起すとき、必ずひとつのできごとに行きあたって、迷信じみたおどろきにおそわれるのだった。それはそのこと自体はそれほど異常なことではないが、あとになってみるとどういうものか彼の運命の予言のように思われてならなかった。 というのは、へとへとに疲れ果てていた彼が、直線の最短距離を通って家へ帰ったほうがどんなにとくか知れないのに、どういうわけか、ぜんぜん立ち寄る必要のなかったセンナヤ広場をまわって帰ったことである。その理由は自分でもどうしてもわからなかったし、説明もつかなかった。まわり道といっても大したことはなかったが、どう見てもぜんぜん必要のないことだ。たしかに、どこを通ったかまるでおぼえがなく、家へ帰ったことが、これまで何十度となくあった。それにしてもなぜ? 彼はあとになっていつも自問するのだった。いったいなぜあんな重大な、彼にとってあれほど決定的な、同時にめったにない偶然のめぐりあいが、(通る理由さえなかった) センナヤ広場で、ちょうどあの時間に、彼の人生のあの瞬間に、それもあんな心の状態のときに、しかもこのめぐりあいが彼の全運命にもっとも決定的な、最後的な影響をあたえるには、いまをのぞいてはないというような状況のときに起ったのか?まるで故意に彼を待ち受けていたかのようだ!
まさにこれからラスコーリニコフがセンナヤ広場を通り、そこでリザヴェータたちの会話を聞き、殺人の実行から逃れられなくなってしまうところですが、それに先立ってこのように語られるのです。この時点ですでにラスコーリニコフは殺人を犯す未来から逃れられないことが確定している。そのような印象をこの文章は読者に与えます。ここでこの文章を記しているドストエフスキーは明らかに、登場人物と平等の立場ではなく、彼らの運命を司るもの、あるいはその運命を歴史のように記録するものという立場に立っています。明らかにドストエフスキーは物語の外部の安全地帯に座しています。
バフチンのこの本で一番気になるのはこの矛盾です。果たして、上記の場面、ドストエフスキーとラスコーリニコフの関係をポリフォニー文学という解釈原則の中で語ることができるのか、この部分は取るに足らない例外として処理されるのか、あるいは解釈原則が変更されるのか、これがこの本を読む上で第一の疑問になります。(私はラスコーリニコフに共感する形で読むのが好きなのですが、その際に、何者かに運命を握られている感覚を覚えます。なので、この矛盾をもってバフチンに反論したいというわけではありません。自分の好きな読み方を基礎づけてみたいのです)
ここでちょっと注意しておくべきなのかもしれないのが、バフチンと私の関心の違いです。バフチンの解き明かそうとしているものは「ドストエフスキーの詩学」であり、つまりドストエフスキーが魅力的な作品を書くときにどのような考えや手法が根底にあるのかという点に関心があると思われます。それに対して私の関心はドストエフスキーの作品に登場する人物たちの内面のドラマです。このような視点の違いから、上記のような私がバフチン(の解釈のダイジェスト)に覚える違和感が解消される可能性があります。この点は一応留意しておきたいと思います。
非完結性
次の点は詳しくは論じませんが、ドストエフスキーの登場人物の理解に役立つかもしれない指摘です。「非完結性」と「開かれた意識」という二つの指摘が第一章から第二章にかけてあるようです。
まずは「非完結性」に関して
彼〔バフチン〕によれば、ドストエフスキーの小説世界の非完結性は、永遠に未完結な存在である人間を描こうとする作者の積極的な姿勢の反映であり、非完結性自体が彼の詩学の高次元での統一性を保証しているのである。
これは解説であるため、「ドストエフスキーの小説世界の非完結性」ということで具体的に何が指摘されているのかは分かりませんが、個人的には例えば『罪と罰』のエピローグを想起しました(もちろん『カラマーゾフの兄弟』の最終場面も、それまでのドミートリイ・カラマーゾフ裁判から離れて新たな物語の開始を予感させる大いに不穏なものではありますが、あれはあくまで予定されていた第二部への布石であって、完結した作品がなおも非完結性を持っているということとは事情が異なるのでしょう)。『罪と罰』の最後ではラスコーリニコフが獄中で強烈な回心ををとげ、ソーニャと共に復活するという筋書きになっています。しかし、エピローグ全体がそれまでの生き生きした詳細な抒情的語りではなく、事実の列挙に近いような書かれ方をしています。そのことから、ラスコーリニコフとソーニャの復活は物語を終着点に導くような説得性を持っていません。ラスコーリニコフの変わりやすい心情の起こした気まぐれとも取れてしまいます。清水正は、『罪と罰』の後日談として、例えば元娼婦であるソーニャが客の子を宿しており、それが強烈な嫉妬をラスコーリニコフに引き起こさせる展開だって考えられると述べています(『ドストエフスキー「罪と罰」の世界』D文学研究会, 2008年, p. 18)。
このような、物語の終点で人物の変化が止まってしまわないような点に「非完結性」を見出しているのであれば、バフチンの指摘は私にとって興味深いものです(そうじゃないならそうじゃないで面白そうではあるけど)。また、バフチンは上述のように詩学、文学論のレベルで非完結性の問題を取り扱っているので、その議論はおそらく私の想定していないものになるでしょう。その点も楽しみです。
開かれた意識
次に「開かれた意識」です。これは単純に、登場人物の内面を語るときに手がかりになりそうな指摘ということで、興味深いと感じられたものです。現時点で私から賛否を示すものではありません。
バフチンによれば、ドストエフスキーの主人公の本質をなすものは、社会的なタイプとか、個人の心理学的な性格といった形で客観的に定義できる部分ではなく、彼が世界と自分自身を見る視点もしくは意識である。この意識は徹底的に開かれた意識として想定されている。すなわちそれは他者および外部世界との相互作用を通じて自分を知ろうとしながら、自分に対する外部からの限定や定義(「本人不在の定義」)を常に覆そうとする。そして同時に自分の内部からの自己定義をも相対化してしまう(バフチンによれば「自己」とは既存のものではなく、関係の中で算出されるものである)。
一見ドストエフスキーの小説の主人公は共通点を持っていないように見えるけど、その意識と意識の運動に注目すると共通点を持っているという指摘です。確かに、『罪と罰』のラスコーリニコフ、『カラマーゾフの兄弟』のアリョーシャ、『白痴』のムイシュキンなど、なんとなく「素直」くらいは共通点として見出せそうですが、あまりそれで何かが明らかになるということはありません。一方、バフチンはより深く人物の内面に入り込んで、その外部との関係性も視野に入れているようなので、人物理解のヒントになりそうです。
イデエ(登場人物の哲学)
次はイデエ、あるいは登場人物の哲学に関する指摘です。これは第三章のテーマになります。
ドストエフスキーの作品においては、個人の世界観の集約的表現としてのイデエが中心的な役割を果たしている。つまり彼の主人公は何らかの意味でイデオローグである。しかしイデエはそこで主人公たちそれぞれの経験、感情、自意識、肉声と結びついているのであって、主体としての主人公から切り離したうえでその客観的な正否を判断し得るような、単体としての抽象的なイデエ(「誰のものでもないイデエ」)はそこに存在しない。
よく、ドストエフスキーの小説は何らかの哲学を表現するものだと言われることがあります。それは間違っていないと思いますが、不十分な解釈だと思います。何かの思想を表現する、一般的な意味での哲学書の役目としては彼の小説は不完全(論究がなされていない)し、哲学書以上の役目を担っています(思想の誕生と発展の過程、思想同士に相剋、思想と人間の距離もまた描かれます)。その点の指摘として、興味深いと思います。しかし、この「誰かのイデエ」という指摘は詩学の観点からなされるいわば議論の足がかりになっているようです。ここでもまた私の興味ある論点が議論の前提にあり、その先にバフチンの議論が進んでいくということが起こっているようなので、読むときには自分の興味のみに従うのではなく、ある程度議論に身を任せようとも思います。
カーニバル文学
この感想文で紹介するものとしては最後に、バフチンの「カーニバル文学」論があります。
バフチンはここで小説一般のジャンル的な源泉の一つとして、叙事詩、弁論術と並んで、「カーニバル文学」というカテゴリーを設定している。それはカーニバル的世界の諸特徴 − 異質な人間同士の無遠慮な接触、常軌を逸した振舞い、ちぐはぐな組み合わせ、高尚なものの卑俗化、死と再生のメタファーとしての戴冠と奪冠、蘇りを促す笑いやパロディーなどの要素 − を反映したジャンルである。
ドストエフスキーの作品に見られる、個々の登場人物が思想をぶちまけるシーンや夢、亡霊との対話などはこのカーニバルに含まれるのではないかと思われます。これらのシーンはそれぞれ象徴的なもので、さまざまな解釈を許すように見えるだけに、どの解釈も説得力に欠けるというきらいがあります。バフチンはおそらく個々のシーンを検討するというより「カーニバル」という包括概念を検討するのでしょうが、これがどのようにポリフォニーと結びついて述べられるのか、興味があります。
以上です。思いのほか長くなったわりに、論点をもう少し盛り込めただろうという心残りがありますが、とりあえずは本文の読書に入ろうと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
