
『たべるのがおそい』全巻購入特典『Little 8』と全作ガイド 西崎憲
このページには『たべるのがおそい』を全巻購入してくださったかたへの特典の案内と、掲載された全作品のガイドを掲載しています。
『たべるのがおそい』全7巻を買ってくださったみなさまに特典として電子冊子を差し上げています。PDF, mobi, epub, kepub, azk, などの形式でダウンロードできます。
入手方法ですが、メールで全巻が写った写真を送っていただければ、折り返しダウンロードのURLを送ります。
book.for.hill@gmail.com
こちらがメールアドレスです。こちらまで写真を添付で送ってください。 Twitter の西崎のツィートに写真でリプライする形でも構いません。
「全巻購入」とありますが、現在6冊持っていてあと1冊購入予定という段階であれば、6冊分の写真を送ってください。
電子書籍の場合はその旨をしるしてください。
部屋のどこかにある、という場合も、ある分の写真と「みつかりません」などの説明を書いてくださればOKです。
メール例
タイトル:【たべおそ特典希望】
本文:『たべるのがおそい』特典『Little 8』を希望します。写真は添付しています。よろしくお願いいたします。
たべおそ Little 8
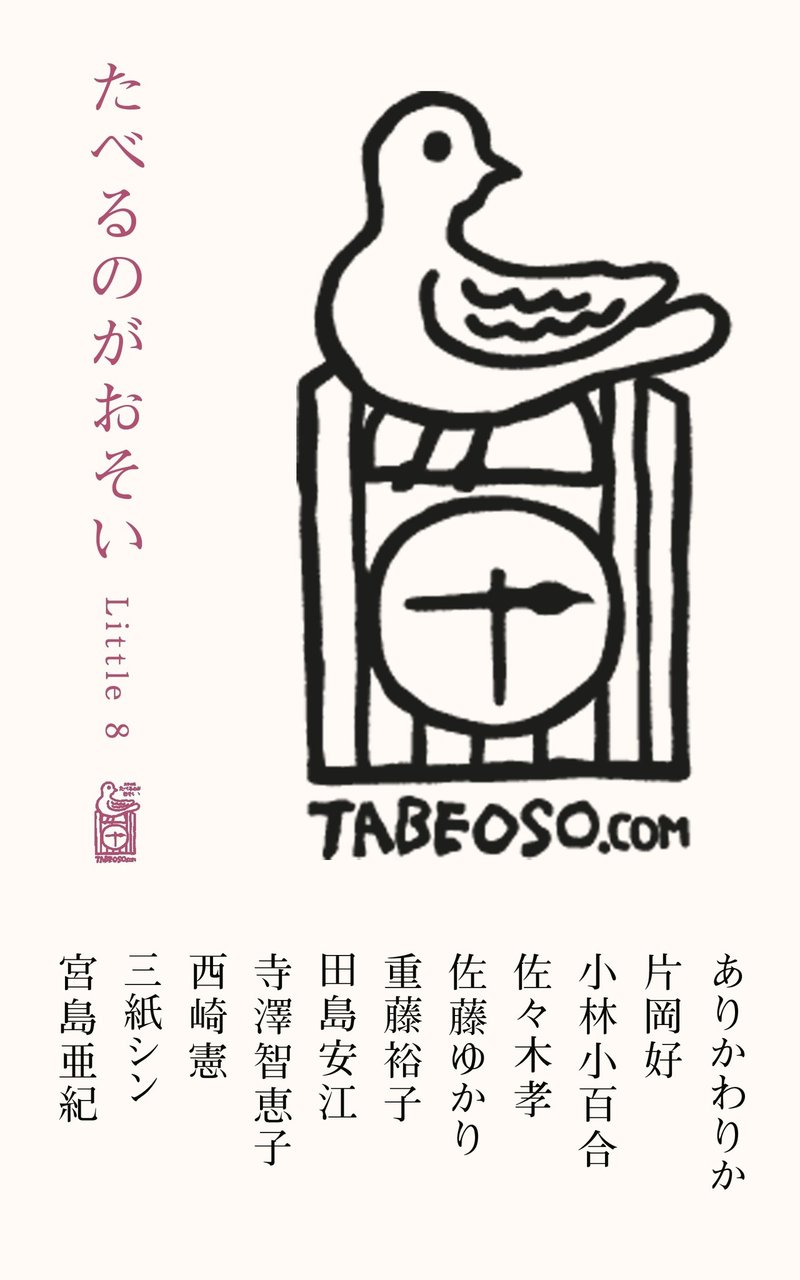
【内容】
『たべるのがおそい』全作ガイド 西崎憲
「並行世界の『たべるのがおそい』ギャラリー」片岡好
挿画部作品&挨拶
ありかわ りか、片岡好、小林小百合、佐藤ゆかり
重藤裕子、寺澤智恵子、三紙シン、宮島亜紀
連載エッセイ〈眠れない夜のために1〉
「昨日あったもの明日あるもの」西崎憲
翻訳「恋する男」レオノーラ・カリントン、西崎憲訳
片岡好デザイン事務所ウェブサイト連載写小説「モジャ!」
「始まりも終わりも突然に」田島安江
——————————————————————————
『たべるのがおそい』全作ガイド
『文学ムック たべるのがおそい』は2019年の春刊行の vol. 7 で終刊になりました。同誌はもしかしたら全巻でひとつの巨大なアンソロジーだったのかもしれません。以下はそのガイドです。『たべるのがおそい』を散歩するときに参照していただければ幸いです。 ーー 西崎憲
†
『たべるのがおそい』刊行のきっかけになったのは、福岡の出版社書肆侃侃房の代表である田島安江氏との打ち合わせだった。二〇一五年の春だったように思う。『たべるのがおそい』は、その打ち合わせの席からはじまった。
どうして打ち合わせをしていたかと言うと、そのとき、わたしは同版元で歌集を刊行することになっていたのだ。作業はすでに終盤に差しかかり、装幀について相談していた。場所は都内のどこかの喫茶店だった。
装幀の話が終わり、緊張がゆるんだところで、田島氏が歌集を出した後、なにか面白いことをやりたいですね、といった意味のことを口にした。
そして「面白い」ものとは何かについてふたりで話し、その場で文芸誌を創刊することに決めた。
わたしが編集長を務めることになり、その後、アートディレクターの片岡好氏、挿画とりまとめの宮島亜紀氏、編集の佐々木孝氏が加わって、編集体制が固まった。特色として挿画を多くすることも決めた。挿画はスタート時が七人、その後ひとり増えて 八人になった。
創刊号が出たのは、最初の打ち合わせの半年後くらいだったと思う。
これまで、少なくない数の翻訳書や小説を刊行していたので、出版の事情にはある程度通じていたが、いきなり編集の仕事をしたわけで、慣れないための失敗もそれなりにあった。
実務的な作業ではそこまで大きな失敗はなかったが、依頼の時期が遅くなったり、連絡が不完全だったなど、基本的なところで冷や汗をかいたこともある。編集スタッフのあいだで方針に関して議論になったこともあった。
結局七冊目で終刊になったのだが、わたしとしては三号雑誌にならなかったことを喜ぶ気持ちのほうが強い。
終刊の理由をよく訊かれるのだが、わたしが時間を工面できなくなったことが一番大きい。とにかく自分の作品は書けないし、訳せないし、仕事が停滞する一方だったのである。
予想外だったのは、二度芥川賞の候補作が出たことである。どうしてこのような小さな文芸誌にまで目を配ってくれたのか、いまでも狐につままれたような気分である。たぶん今村夏子さんの存在があったからだとは思うが。
候補作になったのは、一冊目の今村夏子さんの「あひる」と、四冊目の宮内悠介さんの「ディレイ・エフェクト」で、とくに最初の今村さんのときは、候補になったことを御本人からメールで教えていただいたのだが、生涯最高レベルの驚きだった。そして嬉しさも筆舌に尽くしがたいものだった。
私事にわたるが、その年の夏は、今村さんの芥川賞の待ち会と同じ週に、フジロックフェスティバルでトランペットを吹いた。スコットランド出身のバンド「トラッシュキャン・シナトラズ」のバックを務めたのである。その週がおそらくわたしの生涯でもっとも華やかな夏の一週間ということになるだろう。さすがにあれ以上の夏は今後はないように思う。もちろん、あってくれたら嬉しいわけであるが。
短歌にこれだけ力を入れた文芸誌はなかっただろう。それは特色と言えたかもしれない。
自分が実作者なのでそうなったのかもしれないが、短歌(そして短詩型全体)に、わたしは大きな希望をいだいている。短詩型は小説では掬えないものを掬う形式であり、きわめて現代的なジャンルであると考えている。
『たべるのがおそい』が成功したかどうか、自分ではよくわからない。しかし参考にしています、と言われたこともあったし、『たべるのがおそい』の存在が、独立の理由のひとつだった、と有能な編集者に言われたこともある。それはもちろん嬉しいことだった。
しばしば訊かれたのが、どうして「たべるのがおそい」という名前にしたかということだった。わたしはその度にすこしずつ違う答えを返した覚えがあるのだが、決定的な理由はない。ただ、文の形の名前がそのときはいいような気がしたし、「個人」の事情に関するものがいいようにも思ったし、珍しく商業的なことも考えた。つまり一度耳にしたら忘れないような語列がいいだろうと考えたのだ。
さて、全作ガイドと銘打つほど立派なものではないのだが、七冊に収録された全作品について簡単に記してみる。
1 vol. 1
「文と場所 夢の中の町」
巻頭エッセイをどなたにお願いするかはほとんど悩まなかった。歌人の穂村弘さんは優れたエッセイストでもあって、エッセイストとしてはとにかく外さないという印象がある。予想に違わず、送られてきたものは舌を巻くうまさだった。
家族を題材にするエッセイには独特の静けさがある。
のちに文学関係の場でお会いして、創刊号の執筆者リストを見て、これはいいものを書かなければ、と思ったということをうかがった。
「あひる」 今村夏子
三枚から六十枚というめちゃくちゃな枚数でお願いした。とにかく書くのが苦しいのだろうと想像されたので、軽い気持ちで引き受けられるような依頼の仕方を考えた。「こちらあみ子」のような作品の作者が絶筆するなどということはあってはならないのだ。
届いたときに、すぐには書肆侃侃房に送らず、結局一日自分のところに止めておいた。一日だけ世界中で自分だけがその作品を知っているという状況を楽しみたかったのだ。たべおそにはそうしたくなる作品がいくつかあった。
芥川賞候補になったが、すでに記したようにその報せは生涯最大の驚きだった。まさか自分の人生にそういうことが起きるとは思ってもいなかったのだ。
ご存知のように、今村夏子さんは二〇一九年に『紫のスカートの女』で、芥川賞を受賞している。「あひる」のときはひじょうに悔しい思いをしたので、溜飲が下がったことといったら。
「バベル・タワー」 円城塔
『たべるのがおそい』を刊行することが決まって最初に依頼した書き手が円城塔さんだった。面識がなかったので、どきどきしながらメールを差しあげた、そしてすぐに快諾のメールをいただいた。編集をはじめてから、引き受けてもらうことがいかに嬉しいことなのか、骨身にしみている。
意外なことに、円城塔さんの二通目のメールには、テーマがあったほうが書きやすいということが書かれていた。
そこでわたしは、『たべるのがおそい』創刊の意味や自身の役割のことを念頭において「インターミディエイト intermediate (中間物、媒介者、仲介者、媒介、手段)」あるいは「インターコース intercourse (交通、交際)」ではどうかと返事をした。
それが名作「バベル・タワー」になって返ってきた。
「バベル・タワー」はおそろしい傑作である。一読して、わたしは自分が小説を書く意味はあまりないなとさえ思った。この作品は円城塔さんの作品のなかで一番好きである。大傑作。この文語のうまさはあまりといえばあまりである。
「静かな夜」 藤野可織
藤野可織さんもまた創刊号にぜったいあって欲しい名前だった。わたしにとっては特別な作家で、それは藤野さんが海外のスーパーナチュラルフィクションに直結する魅力を備えた作品を書ける作家だからである。そんな作家は日本にはほとんどいない。そして文章の切れ味。
「静かな夜」もまた、すぐには編集部には送らなかった。
藤野可織さんの作品にはつねにアトモスフィアが濃厚に立ちこめている。
「日本のランチあるいは田舎の魔女」 西崎憲
自分の作品である。ウェルメイドなファンタジーへの希求はかなり強くあるのだが、これまで書いたことはなかった。これが最初の作品である。同じようなテイストの中篇をもう一作書くことを予定している。
「再開」 ケリー・ルース、岸本佐知子訳
岸本佐知子さんの名前がない文芸誌創刊号というのはわたしは考えることができなかった。そして編集者だったら、ひとり残らず岸本さんの原稿を受けとりたいと望むのではないだろうか。
訳出する作品は岸本さん自身に選んでいただいた。 ケリー・ルースはまだ一冊しか短篇集がないらしいが、気になる作家である。
「コーリング・ユー」 イ・シンジョ、和田景子訳
このときは、韓国文学のこれほどのブームがくるとは想像もしていなかった。わたし自身も、日本翻訳大賞の『カステラ』でその面白さに目を見開かされたばかりだった。
デリケートな形の影といった作品。評判もとてもよかった。
短歌は五人。現代短歌の若手を代表する方々である。掲載歌を一首ずつあげよう。
「はばたく、まばたく」 大森静佳
大森静佳さんはひじょうに端正な作風である。
そのひとの靴はすこぶる深かった 記憶を補強する冬の楡
「桃カルピスと砂肝」木下龍也
木下龍也さんさんはトリックスターのような存在である。
スカートのなかを見飽きるほどながいながい梯子を少女とのぼる
「ひきのばされた時間の将棋」堂園昌彦
堂園昌彦さんは独自の美学のようなものをそなえていると言えるか。
することがなくて見ている爪の上でひかりが村祭りを開くのを
「ルカ」服部真里子
服部真里子さんの歌にはどこか聖性があるように思う。
アランセーターひかり細かに編み込まれ君に真白き歳月しずむ
「東京に素直」平岡直子
平岡直子さんは才気の横溢する方で、アティテュードにも特徴がある。
あなたはあなたの脳と生きつつ地下鉄ですこし他人の肩にもたれた
創刊号の特集を決めるにあたっては多少悩んだ。
しかし、本にかかわるものであることだけは、最初から決めていた。この文芸誌が考えるべきは、まず本であるというような意識が、もしかしたらあったかもしれない。
結局〈本がなければ生きていけない〉と剽軽さにすこし傾いたものになった。
「虚構こそ、わが人生」日下三蔵
その特集の最初に来るべきかたはやはりこの人以外にはないだろう。本が取りだせない本棚の説得力。
日下さんは原稿料はいらないとおっしゃった。そのかわりたべるのがおそいを二冊くれと。
「Dead or alive?」佐藤弓生
佐藤さんは歌人、詩人であるが、個人的には書物の人というイメージをずっと抱いてきた。
校閲という仕事はユーモアと結びつきやすいのかもしれない。
「楽園」 瀧井朝世
書評家という存在がなければずいぶん世のなかはつまらなくなるだろう。たべおそでは書評家に敬意を払うことをしたかった。
気持ちよく本の読める場所・環境は読書家が好む話題のひとつだろう。写真の猫氏は刊行後、登仙された。
「ただ本がない生活は想像のむこう側にも思い浮かばず」米光一成
米光一成さんの本は本棚のなかで横になったり縦になったり床に横積みされていたりする。計十六人の本棚が紹介されたわけであるが、自分の本棚と一番似ているのが、米光さんのものだった。
2016/4/15
2 vol. 2
創刊号が思ったより好評で、芥川賞候補作品が出たりしたのだが、自分はそこまでは喜ばなかったような気がする。とにかく読書家が読んで面白いものをとひたすら考えていた。
「立つべき場所、失った場所」金原瑞人
金原瑞人さんは英語圏の文学の翻訳者であるが、詩歌のよき理解者でもある。それは詩歌にとって僥倖であったと言えるだろう。
しかし塚本邦雄が出てきたのはかなり意外だった。
特集は〈地図—共作の実験〉で、これは後になって、一番難解な特集だと言われることになった。小説の実験には大変興味があるので、一番自分がわがままを通した号ということになるかもしれない。
「リャン—エルハフト」石川美南×宮内悠介
これは自分を含めた三人でメールで相談しながら進め、かつADの片岡さんからもどんどんアイディアがきて、大変面白く進められた。そうやって進めているうちに新しい設定や土地が産まれてきて、あまり経験したことのないスリルを覚えた。
「星間通信」円城塔×やくしまるえつこ
こういうテキストはここでしか生まれなかったと思う。有機的にふたつのテキストが絡みあうようなレイアウトにすることになったのだが、かなり難渋した。最終的に円城さんのアイディアで完成させることができた。
宇宙の文通。宇宙の孤独。すごいテキストである。
「三人の悪人」西崎憲×穂村弘
こちらはシンプルなリレー形式で進めた。書き手のほうにまわって、共作には難しさと面白さの両方があるように感じられた。
「共作」についてはまたどこかでなにかやりたい気持ちもある。
小説はこちらからの依頼が三名。
「私たちの数字の内訳」津村記久子
津村記久子さんには畏敬のような気持ちをいだいていたので、引き受けてくださったときはほんとうに嬉しかった(好きな作家にしかお願いしなかったので、嬉しかったのは全員なのだが)。
「私たちの数字の内訳」は見事な作品である。『たべるのがおそい』には完璧に近いという印象をいだいた作品がいくつか掲載されているが、そのひとつである。この巧みさには舌を巻くしかない。
「チーズかまぼこの妖精」森見登美彦
森見登美彦さんに似た作家はひとりもいない。日本だけでなく世界を探してもひとりもいないだろう。そのことの凄さはもっと知られるべきかもしれない。小さく愛らしい作品。
「ミハエリの泉」四元康祐
四元康祐さんは現代詩に独自のものを加えたように思う。そしてわたしは氏のなかに大きな可能性を見る。「ミハエリの泉」はすくおうとすると水のように逃げる不可思議な作品であるが、今後も氏が散文を書いてくださることを強く望んでいる。
「回転草」大前粟生
最初は公募はあまり重要には考えてはいなかった。たぶん大前粟生さんが原稿を送ってくださったおかげで『たべるのがおそい』のなかで公募というものの位置が定まったかもしれない。
最初に送ってくださった作品はまだ現代の人間が理解できないような作品だった。掲載不可のメールを送って、一週間後に送られてきたのがこの「回転草」だった。『たべるのがおそい』の前にすでに『早稲田文学』のほうでデビューしているが、『たべるのがおそい』が躍進のきっかけを作ったと強弁して、自己満足を味わいたい。
短歌はこの号から四名に固定されることになった。
「せかいのへいわ」今橋愛
今橋愛さんはとにかくエネルギーの初期値が高い歌人である。たいていの歌人ははじめてから一、二年ほどで作ったものが最高傑作になるのだが、今橋さんの持続力は驚異的である。
どうぶつに
ゆるくゆるく つなをつけてな
かいたかったし かわれたかった
さようなら
せいめいりょくがすきでした。
ホープ吸いおりせかいのへいわ
「公共へはもう何度も行きましたね」岡野大嗣
岡野大嗣さんは書肆侃侃房の新鋭短歌シリーズが生んだスターのひとりであるのだが、一風変わった感覚を具えている。平易で親しみやすいが、どことなく虚無感が感じられるのだ。
市役所のボールペンをつなぐ紐が長い みんなへ首をふる扇風機
「二度と殺されなかったあなたのために」瀬戸夏子
瀬戸夏子さんは短歌の地図を広げたと思う。瀬戸夏子さんのおかげで発見された半島や丘陵が存在するのだ。最近はあまり歌作をされていないように見えるのだがとても残念である。
朝からくるしげに喘ぐ本の音あがいても雪にしかならないや
卑弥呼の結び目をほどいていくならあなたは妹と知れるだろう
「忘れてしまう」吉野裕之
静かな感情、静かな風景を歌う歌人。吉野裕之さんの歌は風景画のように読める。とても好きな歌人である。
嬲られて水あることや桐の花
美しいこと考えている人のかたわらにいて靴箱になる
「すこし・ふくざつ」倉本さおり
〈本がなければ生きていけない〉は単純に人の本棚を眺める楽しみがあるのだが、倉本さおりさんの回から写真の撮り方などにも目が行くようになった。
「無限本棚」中野善夫
蔵書という語からわたしが連想する人物はまず日下三蔵さんであるのだが、二番目が中野善夫さんである。中野さんの書庫はとにかく整理されている。エッセイも物語仕立てになっていて、今後このような方向に行かれるのかもしれない。
「遅れる鏡」ヤン・ヴァイス、阿部賢一訳
怪奇幻想文学ファンはこのヤン・ヴァイスの翻訳にだいぶ驚かれただろうと思う。創元推理文庫から以前刊行された『迷宮1000』はとてつもない傑作だったのだ。この作品のアイディアも秀逸である。 阿部賢一さんの青春はおそらく怪奇幻想とともにあったはずだ。
「カウントダウンの五日間」アンナ・カヴァン、西崎憲訳
翻訳がヴァイスとアンナ・カヴァンという組合せなので、この号は翻訳にかんしては幻想文学の風味が強かったのではないだろうか。カヴァンは特別な作家である。この作家にかんしては自分は短い言葉で語ることができない。
2016/4/17)
3 vol. 3
「Mさんの隠れた特技」小川洋子
編集者としては新米なので、大きなお名前のかたにお願いするのはかなり恐かった。しかし小川洋子さんは快く引き受けてくださった。
作中のMさんは、柴田元幸さんであるという説がある。
「特集〈Retold 漱石・鏡花・白秋〉」
この特集もまた自分のわがままだったかもしれない。たしかにいま考えてみると、こういう特集で売れるわけはない。どう考えても。特集は「カフェ」とか「旅」とか、せめて「写真」とかにしないとだめなのだ。しかし個人的にはもちろん満足の号だった、
「あかるかれエレクトロ」倉田タカシ
泉鏡花ときわめて先鋭的なSF作家の組合せはなにより自分が読みたかったものだった。結果、かなりこわいものが誕生したように思う。倉田タカシさんの違う側面が現れているようで興味深い。
「小詩集 漱石さん」最果タヒ
現代の優れた詩人と漱石の組合せも個人的にほんとうに興味があってお願いした。四つの魅力的な詩。こちらも最果タヒさんの異なる面を感じる。そして同時に地力のようなものも。朗読でききたい詩である。
「ほぼすべての人の人生に題名をつけるとするなら」高原英理
高原英理さんと北原白秋の組合せはそれほど意外ではないだろう。そう思っていた。しかし送られてきたものはかなり想像と違っていた。とても不思議で理知的なテキスト。思索的用語の戯れ。
「白いセーター」今村夏子
夜中に届いて、ひじょうにざわざわした気持ちになった。これもまた完璧な作品である。今村夏子さんがこの時代にいてくれたことを読者として喜びたい。気持ちがざわざわするのだが、わたしはこの作品が大好きで、今村さんの代表作のひとつだと考えている。
「乗り換え」星野智幸
現代日本の屈指の書き手である。骨太さというものは技術で補うのがかなり難しい種類の特性で、骨太の作家と言われる作家の書くものは単に目が粗いだけのことも多い。骨太の作家というのはつまり星野智幸さんのような作家のことである。
「親水性について」山尾悠子
芥川賞候補の作品が出ることも予想を越えたことであったけれど、まさか自分が山尾悠子さんの作品に編集者として関係するとは夢にも思わなかった。すでに幻想系の伝説的な作家という範疇を越えて、日本を代表する作家である。しかも進歩しているというおそろしさ。書けば幻が現実へと変じる魔術的筆力。
「エスケイプ」相川英輔
たべおそはあとで優秀な新人を数人世に送った功績を讃えられるかもしれない。これはとても印象的な作品だった。相川英輔さんはジャンルの狭間にいるが、いずれ広く受け容れられる作家になるだろう。
「虫歯になった女」ノリ・ケンゾウ
ノリ・ケンゾウさんも公募からであるが、相川英輔さんとはまったく違う個性の持ち主である。この文体はほかにはいないだろう。ノリ・ケンゾウさんもまた日本の小説界で今後興味深い仕事をしていくことを確信している。
「一生に二度」西崎憲
語れないことについて語ろうと思って書いた作品であるが、褒めてくれたかたは、残念ながら三人くらいだった。単行本で雪辱したいと思っている。
「すべてのひかりのために」井上法子
わたしは井上法子さんを読むとロマン主義の詩を思いだす。エクスタティックなイギリスの詩人たち。稀な歌人である。
対岸のとおいともしびそこまでがわたしでここからがわたしたち
「黙読」竹中優子
竹中優子さんの歌は仮借ない。見た目より独創が深いし、愛着をわかせる歌人であり、もちろん自分の愛着も深い。
素顔で生きてきたからシミも勲章と笑う女の顔醜くて
「隣り駅のヤマダ電機」永井祐
永井祐さんは短歌のために、スペクタクルなものを作ったり、見つけだしたりはしない。とにかく独自の見識を持った歌人。
「ヤギ ばか」で検索すると崖にいるヤギの画像がたくさん出てくる
「二〇一七年、冬の一月」花山周子
花山周子さんの歌は近代短歌のように重い。それがフィルターのようなものではなく根底からのものであることは容易にみてとれる。
冬の夜の黒い水たまりに箸入れて電球餅を食べる道の辺(べ)
「『本がなければ生きてこれません』でした。」杉本一文
心地よい軽みと渋さをもった文である。文はやはり人なのだ。良き先達に深い尊敬の念を。
「本棚をつくる」藤原義也
自作の本棚の写真に目を惹かれる。たゆみなく本を読み、たゆみなく本を作ってきたかたの静かで充実した書棚と文章。
「ピカソ」セサル・アイラ、柳原孝敦訳
セサル・アイラ、この魅力的な饒舌。セサル・アイラを掲載できたことはほんとうに誇らしかった。世界の現代文学を紹介したいという思いも強かったのだが、版権取得にはかなり予算が必要で大変難しかった。
「カピバラを盗む」黄崇凱、天野健太郎訳
天野健太郎さんを知ったのは『歩道橋の上の魔術師』においてだった。同書は台湾文学の魅力が凝縮されて詰めこまれたような作品で、台湾文学の面白さに多くの読者の目を向けさせた。
天野健太郎さんは二〇一八年に逝去された。
『たべるのがおそい』をはじめてわたしはふたつの死に遭遇した。ひとつは天野さんの死で、もうひとつは赤染晶子さんである。依頼を考えていたときに訃報を耳にした。
天野健太郎さんは俳人でもあった。俳句のコレクションを現在電子書籍で準備中である。
2017/4/15
4 vol. 4
「主さん 強おして」皆川博子
作家の文というものはおそろしいもので、ディスプレイのなかでも、あまつさえ横組み表示であっても、「声」のようなものをこちらに放ってくる。皆川博子さんの文章にはとくにそういう印象が強い。現代日本の怪物的な散文家。
「特集〈わたしのガイドブック〉」
二号、三号ほどではないが、この号の特集もどうもフォーカスを結びにくいものであるように思う。反省しても遅いが反省している。
しかし、寄せられた文章の密度は高い。
「駅」澤田瞳子
駅や空港というものは何と魅力的なものだろう。一日いても飽きないのでないだろうか。そういった駅愛好家の気持ちを代弁してくれる文章である。澤田瞳子さんの大活躍はほんとうに嬉しい。
「ガイドブックのための(または出発できなかった旅のために)」谷崎由依
テーマのある文章を依頼したとき、それがどういう形で処理されるかは、頼む側にとってはとにかく興味深い。谷崎由依さんから返ってきたものはスマートこのうえないものだった。
「1985年の初夏に完璧な女の子になる方法」山崎まどか
自分が山崎まどかに原稿を依頼する! さまざまな種類の感慨におそわれた文章。「私のような語り手があなたにも不可欠だ」は卓越したフレーズである。無限の切なさ。
「ストリート書道に逢いたくて」山田航
山田航さんは歌人なので、エッセイを依頼するときに何となく申しわけない気持ちになった。しかし山田さんはエッセイがとてもうまいのである。
「人には住めぬ地球になるまで」木下古栗
木下古栗さんのような書き手がある程度認められていることは(十分ではないのだが)健全ではないかと思う。『たべるのがおそい』が木下さんに依頼しないでいることはとうていできることではなかった。
「橙子」古谷田奈月
現在注目すべき作家のひとりであって、わたしは古谷田奈月さんがどこに進んでいくのかをつねに注視している。これまでにいなかった書き手だろう。
「狭虫と芳信」町田康
町田康さんの文はどんなに砕けたものであっても、わたしはそこに殺気のようなものを感じ取ってしまう。だからリラックスしては読めないのだが、そこで起こることは、緊張しながら笑うという奇妙な事態である。
「ディレイ・エフェクト」宮内悠介
この作品もまた芥川賞候補になった。『たべるのがおそい』からは驚くことにオールタイムベストに入るような短篇がいくつか産まれているが、この作品は作者の集中力、題材の魅力などの点で絶妙のバランスが現出していて、これも完璧に近い短篇であると思う。宮内悠介さんの作品のなかで一番すきなものである。しかし傑作あまたの作家なので、これは我田引水だろう。
「IN IN in」伊舎堂仁
伊舎堂仁さんのスタイルはアートスクールっぽいと思う。短歌にとって貴重な存在である。
いてください 伊舎堂くんがそっちまで向かいますので、 くん は好きだな
「ポーラスコンクリートの眠り」國森晴野
國森晴野さんの作る歌には現代短歌の抒情の側面がとても自然に現れている。
北方でちいさな島が消えましたすこし速度をます駆動音
「挽歌」染野太朗
染野太朗さんは近代短歌からの流れに棹さして個人というものを追っているように見える。
出会ひなほすといふことのない日々にゐてことばばかりがこころのやうで
「皐月」野口あや子
野口あや子さんの主題の設定はグラディエーションの状態で広範囲にわたる。主題を絞りがちな短歌の世界では異色かもしれない。
綴じ紐のような言葉だ信号が変わるあわいに綴じられていく
「本屋の蔵書」辻山良雄
辻山良雄さんは西荻窪の名書店 Title の店長である。つぎの言葉はなるほどと思った。
「本当に必要な本なら一回手放したとしても、また何かの形で手元に戻ってくるように思っているので、特に惜しいということはない」
「読んでいて涙が出る本」都甲幸治
綺麗な本棚である。『写真論』があるのが嬉しい。人の本棚に自分が好きな本を見つけるとなぜ嬉しいのだろうか。
「マルレーン・ハウスホーファー集」マルレーン・ハウスホーファー、松永美穂訳
ただただ素晴らしい作品であり、素晴らしい翻訳。この翻訳が『たべるのがおそい』の頂点のひとつだったように思う。
「フランス古典小説集」アルフォンス・アレー、マルセル・シュオッブ、マルセル・ベアリュ、西崎憲訳
これはほんとうに個人的なことになるのだが、翻訳作品を掲載するにあたって簡便化を図るために自分でフランスの小説、スペイン語の小説を訳せたのはほんとうに自分にとってはいい経験になった。この三人の作家はフランス語の小説の世界の宝石のような作家たちである。
2017/10/11
5 vol.5
「おさまりのよい場所」酉島伝法
単純に川辺で書くということにびっくりする。エッセイだがなんとなく不穏な感じがするのは、書き手が酉島伝法さんだというこちらの先入見ゆえか。イタチとの遭遇の描写がスリリング。
「特集〈ないものへのメール〉」
特集は号を重ねるにしたがって、自分の好みを抑え、売れゆきを考えたものにしていった——ような気がしていたが、あらためてみるとそういう感じはまったくしない。
「拷問の夢を見ている」大前粟生
エッセイと小説の中間か、あるいは小説よりの文ということになるか。奇妙なものの出現にわくわくする。
「昆虫図鑑にないキミヘ」黒史郎
怪談を書く作者はたいてい文章がたくみである。黒史郎さんの子供時代にかんするエッセイ。コウガイビルを検索し、なるほどと思う。
「ジェネリック」柴田元幸
安定感を感じさせるエッセイである。
内容からはそれるが面白いやりとりがあった。
アートディレクターの片岡さんから、特集の英語タイトルを考えて欲しいと言われて、苦しんで自分が捻りだしたのはたしか A mail to not existing thing といった感じの表現だったと思う。しかしその後、ゲラの段階で柴田元幸さんから、違う表現のほうがいいのではないかと指摘があって、結局柴田元幸さんに考えてもらった。
このタイトルの英訳はかなり難しいと思う。最初から存在しないものへのメールなのか、いまは存在しないものへのメールなのか。
「こんにちは、鴨長明さん」蜂飼耳
蜂飼耳さんがこういう切り口で来るとはほんとに予想していなかった。『無名抄』にかんする随想。
蜂飼耳さんにはどうしてもお願いしたくて二号のときにメールを書いたのだが、そのときは締切が重なっているということで断念した。二度目の依頼で引き受けていただき、ほんとうに嬉しかった記憶がある。
「ある夜の思い出」今村夏子
人が這う小説というのはジャンルとは言わないまでも相当数のものがある。そしてその系譜につらなる作品の傑作がまたひとつ誕生した。這うことにかんしての小説はいくらでも書けるだろうが、このテイストと組みあわせるのは非凡である。
「天井の虹」岸本佐知子
こちらもまた非凡な感覚の持ち主である。岸本佐知子さんにどうしても小説を書いていただきたくて、自腹で銀座のワインの店でお願いした。
雲や気象が学ぶ高校の話。雲たちも進路を考えるころである。
憧れのセキ先輩。
不良のタツマキ。
屋上のなんという特別な時間。
「雨とカラス」澤西祐典
芥川龍之介を研究されている澤西祐典さんの直球のような小説。その真っ直ぐさにうたれる。
「千年紀の窓」米澤穂信
素晴らしい変化球小説。その曲がり具合にうたれる。米澤穂信さんにもとにかく書いていただきたかった。
「地下鉄クエスト」大田陵史
公募からきた二作はこの号でも素晴らしかった。
終電の終わった地下鉄のレールを歩く人々、レールの横の壁で、ぼーっと明るいラーメン屋、語られていないことは多く、読みどころの多い作品である。大田陵史さんの作品は読み巧者でないと愉しめないだろうが、明らかに今後の文芸の星のひとつ。
「馬」齋藤優
寓話。寓話の命運はすでに尽きたようにも思っていたのだが、この作品を読んですこし考えを変えた。寓話は死んではいない。まったく死んでなどいない。
「杏仁豆腐」内山晶太
静かで私的な風景。派手ではないがほかにない歌風。貴重である。
春われはちいさくなりて仰ぐなり薺[なずな]を日々の尖塔として
「星ふるふ」小原奈実
小原奈実さんは旧仮名表記を遵守するスタイル。それがコスプレのようになっていないのは単におそるべき集中力のせいだろう。
木犀の呼吸のうちをゆく夜を苦しめる木は濃くにほひたり
よろこびは群れて来たりぬみづからを焚きてふくらむ冬の小鳥よ
「四月」仲田有里
作為と無作為の中間にあるようなテキストをつむぐ。とても微妙な歌人だと思う。深い読者が最後にそっと出すような歌人である。この微妙さはもっと多くの人に理解されてほしいのだが。
クリームがお皿について指でぬぐう 魚が水に合わずに死んだ
「これはテストだとあいつは言っておれは水にはいる」フラワーしげる
小学生の作る俳句や短歌と勝負したいと思うことがたまにある。いや頻繁にある。
まず性器からかくんだよ裸をかくときは 小学生 永遠に生きろ
「窓のない部屋から」石井千湖
本と部屋にかんする夢想が楽しい。読書家同士だったらこの話題で二時間は話せるだろう。整然とした書棚である。猫もいる。
「ドロナワ古本コレクター」北原尚彦
本、本、本の人生を送っていらっしゃる北原尚彦さんの魔境のような本棚。いや古本、古本、古本の人生か。なんという素晴らしい人生。
「ごみ」ツェワン・ナムジャ、星泉訳
『たべるのがおそい』で各国の文学を紹介できたらいいな、珍しい国の小説を紹介できたらいいなとずっと思っていた。ここに実現した。小説って面白いぞ。ごみの山の赤ん坊、不可思議なラスト。
「ジャングル」エリザベス・ボウエン、西崎憲訳
以前筆者はボウエンはイギリスの作家のなかで文章のうまさでは五指に入るだろうと思っていた。いまあらためて考えると、小説というもの自体がここ十年くらいで変わってきているので「文章のうまさ」が意味するところもまた違ってきていて、以前ほど単純には言い切れないのだが、とにかく切れ味がいい文を書く作家であり、暗示の手法に未曾有の手腕を発揮する。
2018/4/10
6 vol.6
「雰囲気で書いているのかも」前田司郎
わたしは前田司郎さんの『探偵宇宙船』という小説が大好きである。
五反田の喫茶店で十五年くらい書いたという記述になんとはなしに頭を下げたくなる。
「特集〈ミステリー狩り〉」
ミステリーの特集は創刊号のころからいつかやろうと考えていた。多くの読書人と同様、わたしもクリスティーやクイーンを読んで育ったのだ。
「ボイルド・オクトパス」佐藤究
『Ank: a mirroring ape』はほんとうに面白かった。そしてわたしは筆力や熱量に気おされた。この作品にもまたそれを感じる。ほとんど物理的な想像力だと思う。この世界の匂い、この埃っぽさ。
「メロン畑」深緑野分
この作品に横溢する無国籍の感覚にわたしは児童文学に入り浸っていたころを思いだした。深緑野分さんは物語の申し子、生粋のストーリーテラー。
「飴の中の林檎の話」北野勇作
北野勇作さんはたしかにSFからスタートしたと思うのだが、近年書いているものは、たぶん「文学」だと思う。その語はなにを表すか、わたしにも判然とはしないのだが。成長する作家。
「野戦病院」谷崎由依
谷崎由依さんの文章の明晰さは驚くべきものである。そして明晰な文章でしか描けない曖昧なものが世界にはあって、これがそれである。生々しさ、谷崎由依さんの龍のリアリズム。傑作。
「彼」酉島伝法
倉田タカシさんとお会いしたときに、この作品にたいする感想を述べていて、それは「酉島さんはアンプラグドでもすごい」というものだった。円城塔さんは以前「酉島伝法は人類にはまだ早い」と述べられていたように思う。オールタイムベスト級の達成振り。
「誘い笑い」大滝瓶太
この号の公募は大滝瓶太さんであった。日常的なことを扱っているのにどこかひんやりとした感覚があり、こういうテイストははじめてだと思った。公募からの作者はみな膨大な伸びしろの存在を感じさせるが、大滝さんもまたそうである。独自の書き手になるはずである。
「どちらも蜘蛛の巣の瞳」我妻俊樹
我妻俊樹さんは短歌と小説の両方で活躍されている。どちらでも驚くべき独創性を発揮している。真四角の球体といった手触り。
ああ海と足がぶつかる衝撃も入り組んだ路地の選挙ポスター
「鳥の家」石川美南
短歌と物語を結びつけることがいいことなのか、わたしは時折考える。物語性を強く感じさせる短歌がそれゆえに面白くないと思うことも少なくないからだ。結論は出ていないが、物語性に執した歌人のなかで、石川美南さんはまぎれもなく最上級のひとり。
一族の夕雲として 飛行機に乗って帰らなかった長兄
「星を食べない」斎藤見咲子
斎藤見咲子さんの短歌は大きなものによりかからずただただ個人というものに依拠して作っているように見える。そこが大変潔癖な印象を与える。得がたい歌人であり、注視している。
許せない気持ちのままでいることで保たれている海の輝き
「夢を釣る」中山俊一
短歌は自己愛や甘さを許す形式であって、それはおそらく多くの人間の救いとなるだろう。救いは必要なのだ。
ブーツ履くまでを扉に凭れれば背筋に迫りくるクリスマス
「本の絵を描く人になりたい」林由紀子
わたしはこの文を読み、しんとした気持ちになった。幻想的な美術や文学に決定的に魅入られた者には家はない。それらの人々には現世の家はないのだ。それに似たものがあるとすればたぶんそれは書物だろう。
「頭を殴られ気絶する」吉野仁
わたしはずいぶん以前から吉野さんの穏やかな文のファンであって、多くのミステリーを教えていただいた。だからここは吉野仁でなければいけなかった。
「三つの銅貨」メアリー・エリザベス・カウンセルマン 、狩野一郎訳
海外のミステリー、怪奇、幻想、SFのリファレンスを読んでいると、「ストロング」という語がしばしば使われることに気づく。この作品はまごうかたなくストロングな作品である。カウンセルマンは伝説のパルプマガジン『ウィアードテールズ』の寄稿者だった。
「あまたの叉路の庭」ホルへ・ルイス・ボルヘス 、西崎憲訳
ミステリー特集ということでボルヘスのミステリー作品を訳出した。現代文学の原点のひとつになっている作品ではないかと思う。ここでは贅言は不要だろう。
2018/10/13
7 vol. 7
終刊号である。じつは八号までと思っていたのだが、この号の準備と翻訳の賞の準備が完全に重なるため、ほとんど自分の仕事ができず、深刻な危機感を感じての決断だった
「文とふん」斎藤真理子
ほんとうにこの三年ほどの斎藤真理子さんの活躍はすごいものである。アトラスのごとき力で韓国文学隆盛を独力で引き寄せた感さえある。もちろんひとりの力でそれがなったわけではないだろうが。そして言うまでもなく斎藤真理子はひじょうに優れた文章家なのである。
「特集〈ジュヴナイルー秘密の子供たち〉」
ジュヴナイルはもちろん大好きなのだが、二号あたりから特集の候補にあげていたにもかかわらず、なかなか踏み切れなかった。七号で実現できたのは、編集スタッフの佐々木さんの強い希望があったからかもしれない。結果としてはかなり成功したのではないかと思う。ここでしか見られないようなものになっていると思う。
「作文という卵から小説という鳥は生まれない」岩井俊二
かなり以前、岩井俊二さんと、NHKの少年ドラマの話をして、そのことはずっと頭に残っていた。岩井さんは文章家としてもなにかを成し遂げるのではないかと思う。注目して待ちたい。
「上水線83号鉄塔」銀林みのる
銀林みのるさんの名前はある人々にとっては魔法の名前である。『鉄塔武蔵野線』の読者にとっては。
面白いとか楽しいとか興味深いといった言葉で語られる本は多いが、同書はそういう語では語られない。『鉄塔武蔵野線』に決定的に魅了された人たちがそうなった理由は、文が持つ態度、振るまいであったような気がする。そして魔法はまだ生きていた。
「米と苺」櫻木みわ
櫻木みわさんはSF方面から現れた書き手であるが、今後はそれ以外の分野でも評価されていくはずである。テイストというのは文学ではあまり重視されないのだが、テイストこそもしかしたら最重要事なのかもしれない。
「ジュヴナイル」飛浩隆
当代切っての文章家のひとりであろう。おそろしいほどの筆力であり、読み手に身長が二十メートルある感覚、百メートルを六秒で走るような感覚を体験させることも可能である。特集「ジュヴナイル」で、タイトルがジュヴナイルの作品を送ってくださったことにはだいぶ虚をつかれた。惑星ソラリスの海みたいな作家である。
「おまえ知ってるか、東京の紀伊國屋を大きい順に結ぶと北斗七星になるって」西崎憲
銀林さん、飛さんの作品を見て、たまらず自分も書きたくなって書いたものである。人の作品に影響を受けることはとてもいいこと。
「物置」松永美穂
この号の裏特集は翻訳者に初の小説を書かせることだったのかもしれない。この号ではドイツ小説の翻訳者である松永美穂さんとスペイン語小説の翻訳者の柳原孝敦さんが初の小説を発表している。おふたりとも滋味のある文を書くことのできる文章家なので予想に違わず素晴らしいものを寄稿いただいた。
小さくて穏やかで静かなもの。
「ラピード・レチェ」高山羽根子
高山羽根子さんの活躍には心から賛辞を送りたい。高山さんがいなければなかったテイストがこの世に存在するようになったのだ。中篇集『オブジェクタム』は読者や小説の書き手を震撼させる出来だった。本作も独特の足さばき、手さばきの作品である。ついに最後までスポーツの名前は出てこない。
「けば」小山田浩子
小山田浩子さんはデビューのときから、底知れない書き手といった印象を抱いていた。それは題材の面でも文章の面でも。そしてダイレクトに世界文学的なものに繋がっているようにわたしには思われる。小説を書くときに特別な装置や構えや小説語といったものを必要としない。とてもすごいことだと思う。
「儀志直始末記」柳原孝敦
スペイン語文学の屈指の翻訳者、紹介者である。小説のことを長く考えてきたことが隅々に表れていて、圧巻の出来映えになっている。そしてボルヘスへの返答でもある。それぞれ個人的にはボルヘスには返答しなくてはならないのだ。
「三日月の濃度」熊谷純
作者や作品を紹介するときに個人的な情報を書くのを避けたいという気持ちはもちろんあるのだが、書かずにいられないものもなかにはある。それを書くことによって詩性が高まるように思うからだ。熊谷純さんはコンビニで働いていて、メールは使わず、原稿もすべて郵送でのやりとりである。『真夏のシアン』という素晴らしい歌集がある。
三日月とわたしの距離は縮まらず給与明細を確かむ
「手をつないだままじゃ拍手ができない」佐伯紺
「寝た者から順に明日を配るから各自わくわくしておくように」という歌を作る歌人に原稿依頼をせずにいられるものだろうか。
派手な襟 強い風 夜 でかい川 この雲のむこうは流れ星
「天国と地獄」錦見映理子
錦見映理子さんの作品は物語的な素養が下敷きになっているように見える。安定した力を見せる家人。太宰賞を受賞されている作家でもある。
偉人伝ひたすら読みし幼年の記憶のなかに髭あまたあり
「インフルエンザに過ぎる」 虫武一俊
虫武一俊さんは二十代の十年ほどをひきこもりで過ごしたということである。第一歌集の『羽虫群』にはそのあたりの苦しみが実感をもって、かつ見事に作品化されている。その後、職を得、結婚もしたようだ。
病臥している間きみが居間にきた小さな蜘蛛を逃がしていたこと
「心にプロなんてない」梅﨑実奈
梅﨑実奈さんは新宿紀伊國屋書店の輝かしい短歌の棚を構成している。文中でコラムのタイトルを難じていらっしゃって、それはあまり見たことのない景色だったのだが、それ『たべるのがおそい』的だったのかもしれない。
「安住の書庫を求めて」東雅夫
東雅夫さんは伝説の季刊誌『幻想文学』を編集していたころから、つねに輝かしい先達であった。同誌では自分は書くほうだった。終刊号に逆に原稿をお願いすることになった巡りあわせには個人的に深く感慨を覚えた。
被災した書物の写真に胸が痛む。
「退社」チョン・ミョングァン、吉良佳奈江訳
公募からのはじめての翻訳だった。吉良佳奈江さんは二度目の改稿で一回目の訳文から飛躍的に進歩を遂げていた。
「ヨハン・ペーター・へーベル(1760ー1826)の主題による七つの変奏」ハイミート・フォン・ドーデラー、垂野創一郎訳
垂野創一郎さんはとにかく目利きであって、垂野さんの紹介の本であれば全幅の信頼をおいて構わない。現代では少なくなった文学における「驚異博士」である。この作品は驚くほど現代文学的である。ゴーストストーリーと現代文学のファン、必見である。レイモン・クノーの『文体練習』も連想させる。
2019/4/17
以上、駆け足だったが、一応全作について記してみた。
あらためて、関係した方々、お読みになってくださったすべてのかたのよい読書生活を祈りたいと思う。
そして『たべるのがおそい』は終刊になるが、作者にも読者にも終わりはない。柏書房から十月に短文とデザインをテーマにした描き下ろしアンソロジーのシリーズ kaze no tanbun の一冊目が刊行された。電子書籍レーベル惑星と口笛ブックスでは、芥川賞作家の町屋良平さんの書き下ろし短篇が刊行を待っている。現在最注目とも言える作家の書き下ろし短篇が電子書籍レーベルから刊行されるのだ。これは新しい時代ではないか。いつのまにか我々はもう新しい時代に突入しているのではないだろうか。
書肆侃侃房からも春に、新しい文芸誌『ことばと』が刊行される。そちらのほうには自分はかかわらないが、その文芸誌もまた新しい道を造っていくだろう。
自分がこれから文芸誌をやるかはわからない。『たべるのがおそい』のように自由にやらせてくれるならばまたやってもいいのかもしれない。未来のことは誰にもわからない。
しばらく新しい文芸、オルタナ的な文芸を追っていこうと思う。
そういうものは単に文章を書くことだけから発生するわけではないだろう。
思い返すと『たべるのがおそい』はたしかに新しかったし、オルタナティヴでもあったようにも見えるが、かといってこれまでの文学や出版を否定したわけではなかった。否定というものはあまり面白いものではないのだ。
たべるのがおそいことは、実生活ではあまりよいことのように思われないことのほうが多いだろう。いや、おそいこと、ということ全体が現代ではあまりいいことのように思われないはずだ。しかしおそい者が一番遠くまでいけることがあるのは、歴史が証しているようでもある。
※現在7冊買ってくださった方には、このガイド、さらにレオノーラ・カリントンの翻訳、エッセイなどを収録した PDF、ePub、mobi を進呈する計画を進めています。お楽しみにお待ちください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
