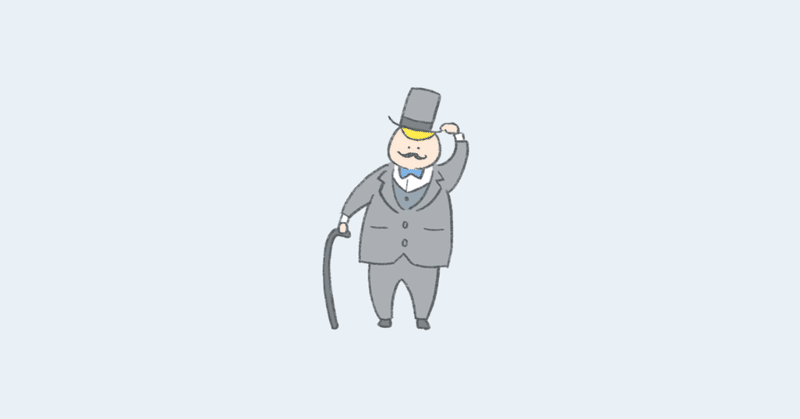
コネティカットのひょこひょこおじさん
座右の銘
世の中、一度見聞きしたら忘れられない言葉というものがある。私にとっては「コネティカットのひょこひょこおじさん」がそれに該当する。なぜコネティカットなのか、何がひょこひょこなのか、どういうおじさんなのか。全く意味が分からない。3つの単語の連なりからなるこの言葉は、中身のない大きな衝撃を私に与え、無駄に胸の奥に深く刻み込まれた。もう少し格言めいたものとこのような出会いを果たせば、座右の銘に据えるなどしただろう。しかし残念ながら私はこのように素っ頓狂な言葉を自身の座右に据える程の胆力がなかった。
出会ったものは理解不能だが、出会い自体は悪いものではなかった。ゆえにここではそれについて述べる。何事も、結果よりも過程が重要なのだ。
『九つの、物語』
この言葉を知ったのは橋本紡『九つの、物語』からである。主人公の女性がこれについて語るシーンがある。この本の題名はサリンジャー『ナインストーリーズ』からきており、「コネティカットのひょこひょこおじさん」も『ナインストーリーズ』の中の章の名前である。
『ナインストーリーズ』は夏目漱石『夢十夜』のように独立した9つの小話で成り立っている。そして難解さは『夢十夜』を凌ぐ。私は『九つの、物語』を読んでから『ナインストーリーズ』を手にとってみたが、よく分からなかった。読後に残ったのはやはり、「コネティカットのひょこひょこおじさん」という使い道のない単語のみであった。
『九つの、物語』はそれと思えばわかりやすい本である。粗筋は至ってシンプルである。
「死んだ兄の幽霊と日常を過ごし、兄を失ったことを受け入れていく」
ところで、創作物を理解するのには2つの方法があると思う。1つは物語の枠内で考えること、もう1つはその枠を超えて、作者の思想や過去の作品を織り交ぜて理解することである。無論、他人に話して疎まれるタイプは圧倒的に後者である。私は以前、全く興味のない奥さんにガンダムのストーリーを原作者の考えの変遷に沿って滔々と語り、辟易させたことがあるので間違いない。
しかしここでは敢えてそのやり方で話を進める。
2000年代初頭の潮流
作者の橋本紡氏の作品にはいくつかのモチーフがある。本、心の病、大切な人の死などである。「九つの、物語」にもそれらが余すところなく登場する。その中でも特に重要なのが大切な人の死である。
橋本氏が本格的に作品を発表する少し前の2000年代初頭、世の中にはある潮流があった。それは「世界の中心で愛を叫ぶ」という作品によりセンセーショナルに広まった。セカイ系と純愛の潮流である。当時学生だった私は、次のような書評を頻繁に目にした。
「社会性を喪失した男女2人の閉じた世界の中で、恋人の死による自己憐憫を極大化させた主人公のモノローグ」、「感動を与えることは簡単である。登場人物の誰かを殺せばいい」、「最近の人は感動するためとか、泣くために本を読むと言うが、読書の本質は人生の糧を得ることで、感動などは副次的な産物に過ぎない」
恐らく、誰かの死とは普遍的なテーマの1つであり、何かを伝える上で作劇場効果的な手段だと思うが、当時はそれを目的化し、徹底的に純化することで死別の喪失感を最大化し、読者にとてつもない共感と衝撃を与える作品が多かった。
その時代を経た橋本氏の作品にも、重要なモチーフに大切な人の死がある。しかし橋本氏の場合、取り扱ったのは死そのものではなく、その後であった。
物語の終わりとその後
物語には終わりがある。最高の結末で終わればグッドエンド、最悪の状況で終わればバッドエンドである。しかし物語が終わっても人生は終わらない。
例えば最愛の人を失っても、同時に自分が死ぬわけではない。その時はどれほど辛くても、残された側は寝て目が覚めれば次の日がやってきてしまう。そこにもう失った人はいないが、それを受け入れて生きていかなければならない。
私は幼い頃、家族のようにかわいがっていた子犬を病気で失ったことがある。その悲しみたるや、私は泣き疲れて意識を失うように眠るまで悲しみに暮れた。この世の終わりの日に自分が悲劇の主人公になったかと思うばかりであった。しかし当たり前のことだが、目が覚めれば日は昇って何でもない翌日が既に始まっており、私以外の世界は昨日までと何も変わらず動いていた。
私自身、その日の昼を過ぎる頃にいつものように空腹を覚えた。お腹を空かせて何かを食べるという行為が愛犬の死を冒涜するようであり、またここで何かを食べてしまうと今日が来てしまったことを肯定するようでもあって、空腹を覚えた自分に自己嫌悪を覚えた。しかし食べなければ死んでしまう。そして残酷なことに、これだけのことで死ぬほど我々は弱くない。私はやがて食事を摂り、日常に戻り、愛犬のことは忘れないが、思い出す頻度は少なくなっていった。私と愛犬の物語があるとすれば、確かにその日に終わりを迎えたが、私の人生はそこで終わりではなかった。
橋本氏の描く物語はこういった、大切なものを失った後の人生である。そこには大きな感動もなく、心揺さぶられる事件もない。それは既に過ぎ去って、今は日常が残っている。その中でいかに様々な現実に折り合いをつけて、人は立ち直っていくか。
この作品の主人公は、その過程を失った対象と経ることができる点で、現実を生きる我々と異なる。また、この点だけはファンタジー色を排した他の作品とは異なり、違和感を覚える。しかしその点についても、氏の重要なモチーフが織り込まれている。
何があっても、我々はひょこひょこと生きていくのだ。読み終わってそういう感想を抱くことは多分ないと思うが、いずれにせよ私はこの本から忘れられない言葉と、それよりも重要なエッセンスを得たように思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
