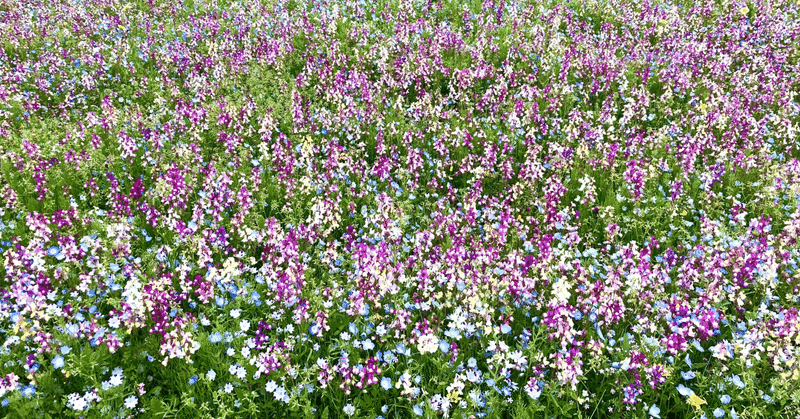
雇用の流動化について
雇用の流動化(の中での企業と労働者の信頼関係喪失による労働者育成の軽視)についてどう思う?と書いてあったので、このテーマを踏まえて整理してみようと思う。
雇用の流動化とは
流動化とは、ようは簡単に他のものに置き換えられること、変換できることを指す。つまり、
雇用の流動化とは、雇用(労働)について、臨機応変にいろんな形で、自由に雇えること(自由に働けること)を指す。これまでの正規社員onlyの状態への、アンチ的表現である。
会社は正規社員という枠にとらわれずに自由に採用活動を行えて、一方、働く側も、自分の好きな働き方で、労働市場へ参入できるようになる!! 例えるなら、会社はこれまでの定型の椅子だけではなくて、自由に色んな椅子を用意することができるし、働く側も自由に色んな自分に合う椅子に座れるようになる。と、なんとも耳障り良い言葉に聞こえるが、その実態は絵に描いた餅でしかない。
流動化という絵にかいた餅
企業や雇う側の原理原則は、利益の最大化である。つまり、営業時間内に最大限に働き、商機を逃さず、利益生産を最大限にすることを労働者に求めている。
なので結局は、具体的な以下3通りのイスしか作られない。
・土日休みで、月~金はがっつり働く労働者
・365日営業させるべく、シフト制で商機を逃すべく回す労働者、
・繁忙期閑散期、生産はじめから安定期、労働需要変動に対応できる労働者
現行法では2人雇うよりも1人のほうが、健康保険やら社会保険関連で圧倒的にコストが安くなる。また、2人に仕事を割るよりも、勝手知る1人が営業時間中は全て対応してくれる方が伝達連携不足等も起きずに、トラブルもない。つまり、企業は、月~金みっちり働いてくれ、必要な時には”残業”で労働者一人が調整してくれる状態が、企業コストは最安のため、選ばれて用意される月金がっつりイスだ。
BtoC系のビジネスで多いが、営業を回すのに最低限必要な人員を用意して、シフト制で回して商機を逃さんとする365日年中無休イスも用意される。
最後は、年単位や季節単位等で業績や市場が変動していくので、1,2年単位や売り上げの動向を見て微調整(年更新やシーズンだけ雇用)を入れられる調整イスが用意される。労働者の調整弁がお手軽にできるイスのことであり、期間工や派遣、パート、アルバイトがまさにそうだ。
というわけで、利益の最大化を考えれば、企業は様々な椅子を用意する必要性はなく、結局は上の3つの椅子を用意するばかりで、流動性とは名ばかりの、企業にとっての都合良さを求めるばかりだ。
労働者から見ても絵空事
色んな椅子ができて、労働者からすれば自由に好きな椅子に座れるhappyというのも絵空事である。自分らしいはたらき方とは幻想だ。
例えば、育児や介護や、大学スクールに通うとか、やりたいことややるべきことがあるから、週休3・4・5日で働きたい!!時短勤務で働きたい!!そういうはたらき方をしたい人もいるかもしれない。
しかし、その選択をすれば、労働時間が減り生産性生産高が減るので、当然給与も減る。給与が減ってもその選択をできる人はいるのだろうか。少数はいるだろうが、大多数はそうではないはずである。ほとんどの人は、給与が減るのを良しとはしない。(20代の預貯金額の統計データとか。結婚、出産育児、家、老後にかかる費用等々の先行き不安等々、要は、現在はほとんどの人が、みっちり働いていても、生活や将来が苦しい見通しなのだ。そんな選択はできない。)
つまり、労働者からみて雇用の流動性を求める成立する人というのは、余裕があり生活基盤が安定している人が、多少収入は減っても、自分のやるべきことやりたいことの時間が欲しい!!という場合にしか成立しない。言い換えるならば、労働者における雇用の流動性とは、生活基盤が安定しているんだから、もっと労働時間を減らしたい!という労働者の根源的願望でしかない。
具体的に言えば、一部の高給取りの人が休みを増やしたくなる場合とか、パラサイトシングル(親のすねかじり)、旦那や世帯所得で見れば、収入がへっも問題ないの層でしか、労働時間を減らすというのは成立しない話だ。とはいえ、そもそも上述の通り、そんな椅子を企業は、基本用意しないので、結局そういう人材は、パート、アルバイト的な形で雇用されることになる。
つまり、雇用の流動性とは、企業はそんな椅子を用意することはない非現実のものであるし。労働者の側でも、その夢を実現できるのは、裕福な人が、収入が減ってもいいから労働時間を減らしたーーい!という場合の極一部の話でしかない。雇用の流動性という言葉のなんと茶番のことだろうと思う。
相反する立場をどうまとめるか。労働、安定、生産成果競争力の最適解とは
本当の意味で、雇用の流動化という言葉を考えるには、もっと掘り下げた視点が必要になる。
結論を書けば、社会全体や企業の利益生産高がある程度以上に高くなる点と、労働者にとっても、生産性生産高成長革新と満足度が高くなる、労働者の労働環境や安心成長の点はどこで調和されるのか、という問いだ。
社会企業は、利益を最大化したい。労働者は、安定(生活基盤)を確保しつつ、労働以外の何かの時間を十二分に欲しい。言い換えれば、この2つ反する立場の最大公約数を探す作業ともいえる。
例えば、エクセルを何百件手打ちする。それを毎日やらされて、こきつかわれているような状況を想像して欲しい。目の前のことに追われている状況だ。企業は利益を最大化する為、さぁ何件も打て!休まず打て!とせっつく。手打ちするという生産高は最大になるかもしれない。しかし、もし、労働者に安心や時間や教育費をあげれば、一旦立ち止まったり勉強する機会があれば、コピペとか数式とかマクロとかの生産性向上がおきて、手打ちの手間を減らし、一日の件数は劇的に改善するかもしれない。
最適解を探す要素は、以下の3点だ。
1、労働時間と余暇や休暇
2、安定のライン、安定の担保、
3、成長生産性向上への動機づけ、成長、生産性向上の機会や費用の提供、リターン。
昭和の時代は、終身雇用と年功序列が維持できたし機能したので、労働者は安心安全を手に入れて、その奉公忠誠として、がむしゃらに会社の為に働いたことだろう。休日出勤もあったろうし。休みに会社仕事関連の勉強や何かをする人も今以上にいただろう。労働者に安心を担保すればそれだけでうまくいくと思う人もいるかもしれない。
あるいは、アメリカの成果型社会スタイルもある。人を簡単に首にできる。安心なんかない。そして、もし凄いのを生み出せば、その分成果報酬でどかんと報いるぜと、労働者に常に危機的状況において、無理に叩いて走らせまくることで、労働者の成長生産性向上を促す方法だ。
あるいは、ドイツみたいに残業は恥、絶対しないものみたいな文化スタイルもある。労働時間を最初からがっつり規定することで、限られた時間しかないのだから優先順位をつけたり効率よく立ち回らないといけないので、必然的に生産性があがるという方法もある。その分しゃかしゃかしたり、優先順位が低いものがおざなりになるリスクもある。
労働環境の在り方、と生産性の最大化と労働者の満足はどう折り合いがつくのか。難しい問いである。
終わりに
私は、安定と安心がある中で、たっぷりの時間を与えてもらい、自分のやりたいことをするのが理想的だと思う。労働関連でもいいし、労働以外の自分の道(趣味や副業やその他)を進んだっていいと思う。そこで得た成長生産的な何かは、直接企業会社に還元されることもあるだろうし。間接的に企業会社に還元されたり、あるいは、仕事関係なくても社会全体の誰かに還元される。結果として、企業社会全体の生産高が高まる。
しかし、夏休みの子供のようなものだとも思う。色んな人がいる。
安定と安心を担保して、時間を与えられても、ただ遊ぶ消費ばかりの人もいる。これでは生産性は向上しないで、ただ働く時間が減っただけだ。本人は嬉しいかもしれないが、社会企業全体は+ではないし、ひいては自分にもマイナスに還ってくる。ただ飯ぐらいはできないので、皆の総量が減れば、食べられる量も当然その分へる。
時間が与えられても締め切り間近にならないと本調子になれない人もいる。締め切りやらなにやら誰かがせっつかないと、尻を叩かないとできない人もいる。お金やそれをしたら手に入るものを明確に提示されないとやれない人もいる。
色々考えられるが、とりあえずの今、皆が目の前のことに追われすぎていて、どういうタイプの誰しもが、労働ではない生産的活動を行う時間が少なすぎると思う。個々人や日本人に合ったカスタマイズ微調整は、その時間を与えた後の様子を見て考えればいいと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
