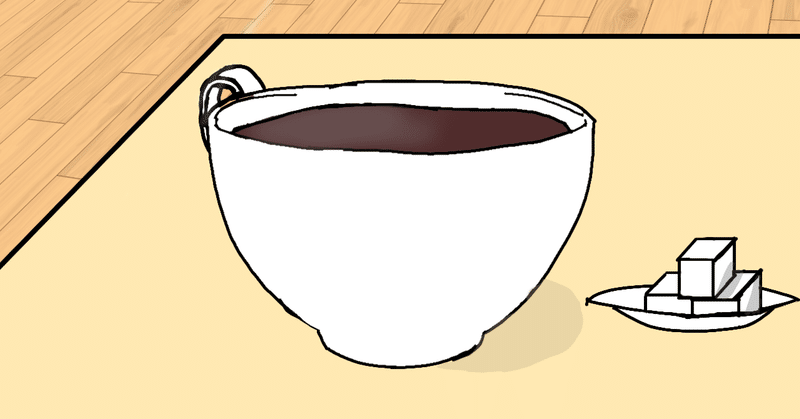
【連載小説】3話 トイは口ほどにものを言う
バイト一年目、始めたばかりの頃は美弥子にも彼氏がいた。その時の相手はもう顔も覚えていない。イマイチ趣味が合わなくて、二年目に入る前に別れたんだったか。
そもそも美弥子のトイもあんまり彼のトイといて楽しそうにしてなかったし、解り切った結末というやつだろう。
それ以来、ずっと恋人の座は空いたままだ。
恋人が欲しいと思わない訳じゃなかった。いい人がいれば気になるものだし、あ、あのお客さんイケメン、なんて思った事も二度や三度じゃ足りやしない。
それでも、店の中でずっと顔を突き合わせてる人が平均よりもうんと整った顔をしていれば、目も肥えてしまうというものだろう。
いつの間にか視線が追いかけて。
声がすれば聞き逃すまいと耳を傾けて。
トイでバレないように、近くに寄っちゃだめよってようく言い聞かせたのは大分初期の頃。
押し切った形になってしまったけれど、慣れた職場での継続雇用を勝ち取って、正社員一年目は浮かれていた、のだろう。
やっぱり私が必要なんじゃない、と驕った部分もあった。
今にしてみればとてもじゃないけど恥ずかしい思い出ばかりだ。
店長の目に映る自分が少しでも魅力的に見えるようにと、派手めな化粧をしたり、髪を飾り立てたり。店内にお客様がいるにもかかわらず、店長へ色々な話題を振っては静かな空間をぶち壊してしまったりしていて、どうして解雇されなかったのか不思議な位だなと今にして思う。
まぁ、そんな色々は勿論、彼には逆効果だった。
そりゃそうだろう。仮にも飲食店の店長をやってる人なんだから、店の状態が良いか悪いかは重要事項。なんたって自分の生活に直結する案件なのだから。
接客せずに店長とばかり話す店員や、自分が目立ってしまって店の装いや雰囲気を邪魔するヤツなんて迷惑でしかない。
ほんと、よく解雇されなかったわね。
過去の自分を振り返る度、頭の悪い子供だったなと反省しかない。けれど、今だってその頃から多少成長したと思っているけれど、子供には変わりないだろう。
なんたって店長とは13も歳の差があるのだから。
彼から見れば、自分はお子様というか、恋愛の相手とは見られないのかもしれない。二十歳そこそこの小娘なんて受け入れる枠に入れてもらえないのかも。
それだけが理由ではないと思うけれど、いくら話しかけても視線を送っても、どこ吹く風。まったく相手にはしてもらえず、袖にされ続けた。
バイト二年目に入る頃に、それまでの行動の愚かさに気付いた。自分の目の前にあるガラスがいかに曇っていたか、大事なものを遠ざけ見えなくしていたのは自分なのだと解ってからは、職務中の自分の間違いを一つ一つ正していった。
喫茶ひといきはあまり広い客席を持つ店ではない。そして店内の雰囲気は木目を活かした落ち着く色でまとめられている。
そんな店に合う店員とはどんな服装で、どんな所作だろう、と考えるようになった。そして、まずはできる事からと服装や髪型と化粧を一気に方向転換させたのだ。地味さと清潔感、そして丁寧さを心掛けるようになった。
美弥子自身、元々愛想がよかったからこそ客商売のバイトを選んだので、お客様との会話に困ることは無かった。けれどそれまでは友人に話しかけるような気安い態度が多かったのを、お客様と店員という、一線を引いた、より丁寧な接客を目指し始めた。
さらに休日には積極的に評判の良い他店へ赴くことで、その店ごとの店員の所作をメモし、自身のスキルアップを目指したのだ。
ひといきに合う店員になり、スキルアップすると決めた間は、店長へのアプローチは一切しないように気を付けた。普通の、オーナーと雇われ店員として接するに留めるように。
けれど、トイは正直だ。
美弥子がひといきでバイトを始めてから正社員一年目までは、彼女のトイは店内をふらふらと見まわったりお客のトイと話し込んだりして、一つ所にはいなかった。
店長のトイはというと、出会った時、美弥子がバイトをしたいとひといきの入口ドアをくぐった日からずっと、いつもカウンター上、入口近い辺りに座って、店内を見ている。時折例外はあれど、ほぼ90パーセント、同じ場所だ。
たまに、店内をめぐる美弥子のトイと目が合うと、ニコ、と笑ってくれる。それを見る限りは、まったく脈が無い訳じゃないのかもしれない。でも、他のお客たちのトイにも同じように微笑んでいるから、単純に愛想笑いなのか、ああやって笑顔を返すのが彼のトイの常なのかもしれない。
その店長のトイの隣、に座るのはさすがに美弥子のトイと言えど難しそうにしていた。どうやら、すぐ隣に並ぶ、というのは、トイにとってかなり大事な場所であり、とても親しいか親しくなりたい相手でないと許されないらしい。それこそ家族や夫婦、恋人同士くらいの。
ということで隣には座れないのだしと、美弥子のトイはカウンターの反対の端に座るようになった。
この方が確かに店内を俯瞰で見る事ができて、何かあればすぐ美弥子へ教えてくれるようになったのだ。そして、店内が見渡せるという事は、店長のトイの姿を視界に入れる事も可能という事。
正確には、店内を見るふりをしているのだ。いや、この言い方でも正しくないだろう。美弥子のトイの視線の先は、7割位は店内を見ている。お客の雰囲気やトイ達の様子を。残りの3割程は、店長のトイを見ているのだ。
彼に見つからぬよう、気付かれないように、と気を付けながら、美弥子のトイはちらちらと店長のトイを見ては、ひといきの店内に、同じ空間にいられるという喜びを噛みしめていたのだった。
「それじゃ、今日はこれで」
「あら、もう良いの。ああ、そっか、この後はデート?食事にでも行くのかしら?」
カウンターでブレンドとウインナーコーヒーを飲んでいた優斗と彩矢は、美弥子が物思いにふけってしまっていた間に、それぞれ飲み終えて、ある程度店長とも話をして、頃合いになったようだった。
「ああ、いえ、特には……それよりもお二人に報告できてホッとしました」
「別にわざわざ改まって来てくれなくても良かったのよ?明後日になれば、二人とも店にいるでしょうに」
「でも、バイト中にこういう話をするのは違うと思うので」
彩矢のこんなところがとても好ましいと思う。真面目で、一生懸命。自分が彼女と同じくらいの頃は、前述の通りとてもじゃないが比較にならないダメさだったので。
「偉いなぁ、彩矢ちゃんは。よし、それじゃ今日の二人の分は私が出してあげるわ。お祝いってことで、ねっ。その代わりすぐに別れるなんてことにならないでよ?末永く仲良くしてくれることが条件!」
ちょうどいい、とばかりに言うと、二人は驚いた顔をして口を開こうとする。けれど美弥子が先に二の句を継ぐことで何も言えなくさせてしまう。それでいい、お祝いの気持ちも、ずっと続いてほしい気持ちも本当なのだから、受け取ってもらいたかった。
「ありがとう、ございます」
「しっかり胸に刻みます。皆さんに言われたからじゃないですけど、本当に、彩矢ちゃんが大切なので」
しっかりと頷いた優斗は、ぎゅ、と再び彩矢の手を取って握りしめ、見つめ合う。
うん、それでいい。
それじゃあね、と送る美弥子に頭を何度も下げながら、彩矢と優斗は店をあとにした。
月曜のランチ時にくる優斗は普通だろうけど、きっと火曜の顔は緩みっぱなしになるんだろう。そして彩矢も、照れくさそうにはにかみながら、それでも真面目に仕事をこなすんだろうな、と想像できた。
初々しい、誕生したばかりの恋人たちがうまく行くだろう事を確信して、美弥子は満足そうな笑みを浮かべて、ほっと息をついた。
ひといきでの正社員も三年目になって、それなりに接客スキルも板についてきたように思える。咄嗟の受け答えは勿論のこと、珈琲の知識も少しずつ勉強したり店長に聞いたりして、誰に聞かれても一人で答えられるように、なってきているはず。
うん、と頷いた美弥子の顔は自然と満たされた笑顔が浮かんでいた。それは彼女が努力してきた時間と技術に裏打ちされた、見惚れるような綺麗な顔だった。
そして一息いれたあと、ぐるりと見まわした店内はシンと静かな空間が広がっていた。
ふとあいた、隙間の時間。お客は誰もおらず、夕飯時にはまだ少し早い。
美弥子はいまのうちにおしぼりの補充やカップの片付けをしようとレジ前からカウンターへ入った。す、と向けた視線の先には店長がいたのだけれど、彼の手の中には何故かトイが抱えられている。
さっきまで座っていたのに、どうしたのだろう。
「店長、その子どうかしたんですか?」
「ん?ああ、いやいや、別にどうってことないよ。少し疲れてるみたいだから休ませようかと思ってね」
「え、でもすごいニコニコですよ?」
店長の手の中にいる彼のトイは、とてもいい笑顔で美弥子を見ている。彼の言うように疲れている風には見えなかった。
「ハイになってるんだよ、昨日ゲームやってたらハマっちゃって少し夜更かししてさ。寝不足なんだ」
「そんなものですか」
「そそ、ちょっと裏いってくるね」
バックへ連れていく、ということはトイ専用の箱、トックスの中へ入れてくるということなのだろう。あの箱にはトイ達が安心する術がかけられているらしく、普段は離れたがらないトイもトックスの中には大人しく入ってくれる。
通常はトイ達に見られたくない、仕事上の機密事項を扱うタイミングであったり、取引先との契約時であったり、はたまた恋人同士の時間であったり。他には、一人になりたい時とかだろうか。とにかく、トイに邪魔されたくないタイミングで入れる事が多い。
トイは基本的に本人と同じような体調であることがほとんどのため、もしトイが不調そうだというなら、店長もそうだろう。
「店長は大丈夫なんですか?寝不足なんだったら、少し休んできてもらっても大丈夫ですよ」
「だいじょーぶだいじょーぶ、俺は慣れてるから。コイツだけ休ませてくるよ」
「はぁ……わかりました」
大丈夫という彼の顔は確かに普通そう、というか不調のふの字も見えない通常通りで、ならばトイが疲れているというのもわからないのだけれど、まぁ平気というならそうなのだろう。
美弥子は腑に落ちない何かを喉の奥へ押し込んで、バックへ下がっていく店長の後姿を見つめていた。
ここ最近、店長は少し、挙動がおかしい……ような気がする。
美弥子が気付かないうちに彼のトイが居なくなっていて、トックスにしまわれていたという事がちょくちょくあるのだ。
基本的にはいつもと同じ、カウンターの上に座ってニコニコしてるし、店長もカウンターの中で笑顔で接客している。
けれど、たまに客足の途絶えた時間とか、あまり居ないタイミングでふとカウンターの上を見ると、そこにいたはずのトイが消えている。
もしや体調不良なのかもしれないし、病気にかかっているけれど平静を装っていたりするのかもしれない。とどのつまりは、どうしたのだろう、と心配になるのだけれど、でも本人の問題でもあるからあまり突っ込んで聞くのも憚られる。
結局、美弥子は今日もあまり深く理由を聞くことはできずに、店長のトイが彼の手の中で運ばれていく様子を見ているしか出来ないのだった。
美弥子は、およそ4か月前の4月に、店長へ今までよりも解りやすくアプローチした事があった。
けれど、目を見て言った、私なんてどうですか?の一言は、怖くなってすぐに視線を逸らし、冗談ですよと茶化して、うやむやにしてしまおうとした。
けれど、店長はそんな美弥子の背に向けて、こんなおっさんはやめておいたほうがいい、と真面目に答えを返してくれてしまった。
美弥子の言い方も悪かったのだろう、好きだとも傍に居たいとも言い出せなかったのだから。だとしても、だ。好きとも嫌いとも言わない店長の言い方は、美弥子に応える気はまるでないと言われたようで、つい口をついて言ってしまっただけだった美弥子は、その事をひどく後悔した。
後悔したけれど、時間は待ってくれやしない。
日常は巡るし、朝はいつも通りにやってきて、ひといきは営業を始めて、お客様がやってくる。
何も気にしていない、何も気まずくなんかない、というように普通の顔をして、トイにも今まで通り、普通にしてなさいねと言い聞かせて出勤した翌朝は、あまりにもいつも通りで、あっけないよりも悲しかった。
ほんの少しくらい、意識してくれたって。
一瞬で悲しい顔なんてなかったようにして、おはようございますと言った美弥子には見えなかった。
彼女がドアに手をかける前まで、店長がどんな表情でいたか。
カランと鳴るドアベルと、すりガラス越しに人影が見えるのはこういう時に便利だと内心で思われていたとは露ほども気付かずに、美弥子は毎朝の支度を始めたのだった。
そんな、少しだけ気まずい、けれど大人なのだからといつも通りの仮面を被った二人がいるひといきへ、彩矢がやってきた。そして彼女の明るさと真面目さに向き合っているうちに、店長と美弥子の間の空気は大分緩和されたのだった。
小説を書く力になります、ありがとうございます!トイ達を気に入ってくださると嬉しいです✨
