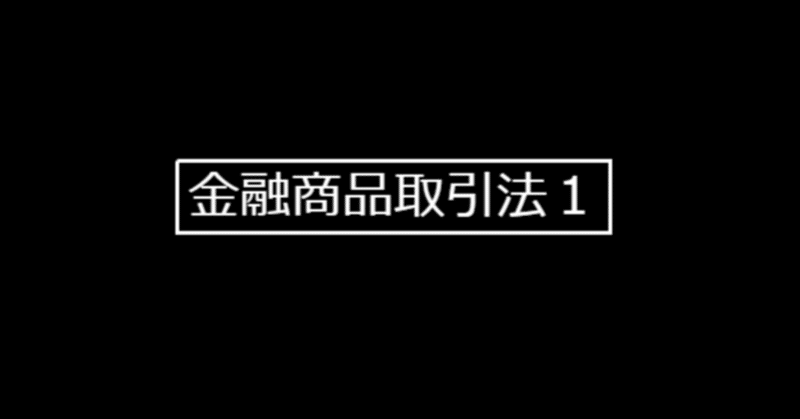
金融商品取引法1
おはようございます。
キツネの目と申します。
本日は「金融商品取引法」について記載していきます。
よかったら参考にしてください
数年前の話になりますが僕に金融商品取引法を教えてくれたのは某金融庁の許認可を得て営業している会社でした。
そこで教わった金融商品取引法は間違いが多かったです。
バカな僕は「金融庁の許認可を得ている会社の代表理事が言うことだから正しいんだろう!」
と大して調べもせずに鵜呑みにして恥をかいたものです。
皆さんはそうはならず自分で調べる癖をつけてくださいね。
・金融商品取引法概要

・目的
金融商品取引所の適切な運営を確保する等により、有価証券の発行及び金融商品の取引を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もって国民経済の健全な発展及び投資家保護を資することを目的としています。
金融商品取引法が適用される範囲は、有価証券とデリバティブ取引に分かれます。

・有価証券とは
金融商品取引法での有価証券とは以下の通りです。
第一項有価証券
国債証券
地方債証券
特別の法律により法人の発行する債券
資産流動化法に規定する特定社債
社債券
特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
優先出資法に規定する優先出資証券
資産流動化法に規定する優先出資証券、新優先出資引受権証券
株券、新株予約権証券
投資信託・外国投資信託の受益証券
(いわゆる会社型投資信託の)投資証券、投資法人債券、外国投資証券
貸付信託の受益証券
資産流動化法に規定する特定目的信託の受益証券
信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券
法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち内閣府令で定めるもの(CP:コマーシャルペーパー)
抵当証券法に規定する抵当証券
外国又は外国の者が発行する1~9、12~16の性質を有する証券・証書
外国の者の発行する証券・証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付け等を業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
(金融商品市場、外国金融商品市場、店頭デリバティブ取引における)オプションを表示する証券・証書(カバード・ワラント)
預託証券・証書(原証券・証書の発行国以外で発行されるもの)
流通性その他の事情を勘案して、公益又は投資者保護を確保することが必要なものとして政令で定める証券・証書
第二項有価証券
(みなし有価証券)証券又は証書に表示される権利以外の権利ですが、金融商品取引法の規制を及ぼすべきことから、有価証券とみなされているもの。
信託の受益権及び外国の者に対する権利で信託受益権の性質を有するもの
合名会社、合資会社の社員権、合同会社の社員権、及び外国法人に対する社員権でこれらの性質を有するもの
組合契約、匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約上の権利、及び社団法人の社員権その他の権利、並びに外国の法令に基づく権利であってこれらの権利に類するもの(集団投資スキーム持分)
特定電子記録債権及び政令で定める権利
※金融商品取引法上の有価証券でないもの(小切手、国内CD(譲渡性預金)など)
「一般的な有価証券」と「金融商品取引法上の有価証券」はその範囲が異なるので注意してください。
・デリバティブ取引

金融商品取引法の適用対象には、有価証券の他にデリバティブ取引も含まれます。
金融商品取引法の適用対象となるデリバティブ取引は次の通りです。
・市場デリバティブ取引
金融商品取引市場の取引基準に従って行われる取引
金融商品、金融指標の先物取引、オプション取引、スワップ取引、クレジット・デリバティブ取引など
・店頭デリバティブ取引
市場デリバティブ取引と同様の取引で、金融商品市場外で行う取引
・外国市場デリバティブ取引
外国金融商品市場において行う取引で、市場デリバティブ取引と類似の取引
・金融商品取引業者

金融商品取引業者とは、内閣総理大臣の登録を受け、金融商品取引業を営む者をいいます。
金融商品取引業者は次の行為を業として行います。
・自己売買
自分自身の勘定で有価証券(債券、株式他)等の売買を行うこと。
有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引。
・媒介
他人同士の取引が成立するよう尽力すること。
売買契約の当事者にはなりません。
・取次ぎ
自己の名(金融商品取引業者)でもって、委託者の計算(顧客の資金)で売買を引き受けること。
通常の個人投資家が株を売買する場合は、この取次ぎにあたる。
・代理
委託者の名(顧客)でもって、委託者の計算(顧客の資金)で売買を引き受けること。
・有価証券等清算取次ぎ
債務を金融商品取引清算機関に負担させる条件で、顧客の委託で、その顧客の代理で取引を成立させること。
・有価証券の引受け
有価証券の発行体、売出人のために販売を引き受けること。
全部または一部を取得(買取引受け)
売れ残りを取得する(残額引受け)
発行体から直接引き受け(元引受け)
・有価証券の売出し
すでに発行された有価証券の売付け、買付けの申込みの勧誘のうち、以下の人数以上の者を相手として行う方式。
第一項有価証券=50名以上を相手に行うもの
第二項有価証券=500名以上が所有することとなるのもの
・有価証券の募集
新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘のうち、以下の人数以上の者を相手として行う方式。
第一項有価証券=50名以上を相手に行うもので、勧誘対象者が適格機関投資家等に限定されていないもの
第二項有価証券=500名以上が所有することとなるのもの
・私設取引システム(PTS)運営業務
証券会社が金融商品取引所(証券取引所)を通さず、株式等の売買を成立させる取引。
金融商品取引業者間でコンピューター・ネットワーク上の市場で行う取引の総称。
・金融商品取引業の分類

金融商品取引業者は、業務の内容によって以下の4つに分類されています。
・第一種金融商品取引業
証券業、金融先物取引業
・第二種金融商品取引業
信託受益権販売業、商品投資販売業
・投資助言・代理業
投資顧問業(投資助言業務)など
・投資運用業
投資信託委託業、投資法人資産運用業、投資一任契約に係る業務
・金融商品取引業を行うためには
金融商品取引業を行うには、以下のように登録や認可が必要になります。
金融商品取引業 => 内閣総理大臣に登録
私設取引システム(PTS)運営業務 => 内閣総理大臣の認可
・営業保証金制度

登録や認可を受けるには、以下の最低資本金(法人)及び営業保証金(個人)の額が決められています。
・第一種金融商品取引業者
5,000万円
・投資運用業
5,000万円
・第二種金融商品取引業者
1,000万円
・投資 助言代理業
500万円
・私設取引システム(PTS)運営業務
3億円
僕は某会社に300万円の入社金を要求されました。
この時の投資助言代理業の登録するための金だ。と説明されたことに納得したからなんですよね。
今から考えれば本当にバカでした。
・財務体質要件
金融商品取引業者は、その財務体質が健全であることが求められています。そのため以下のような規定がありあます。
経理(健全性の確保)
自己資本規制比率120%以上を維持する。
事業年度ごとに、業務や財産に関する説明書類を作成し、全ての営業所等に備え公衆の縦覧に供する必要がある。
金融商品取引責任準備金の積立て
金融商品取引の事故に備え、金融商品取引責任準備金の積立てが義務付けられている。
報告・資料の提出義務など
事業年度ごとに、事業報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
・金融商品取引業者の行為規制

金融商品取引法は、金融商品取引業者の地位に鑑みて、その行為規制を幅広く規定しています。
・誠実・公正義務
金融商品取引業者は顧客に対して、誠実かつ公正に業務を行わなければなりません。
・広告規制
金融商品取引業者等が広告等を行う場合には、以下の内容を表示することが義務付けられています。
金融商品取引業者の商号、名称又は氏名
金融商品取引業者等である旨と登録番号
手数料や損失が生じる恐れがあるなど、顧客の判断に影響を及ぼす重要な事項
(リスク情報は最も大きな文字・数字と著しく異ならない大きさで表示)
この広告等には、パンフレット、電子メール、ファックス、郵便などが含まれます。
・契約締結前書類交付義務

金融商品取引業者等は、取引の前にあらかじめ顧客に対して契約締結前交付書面を交付して重要事項の説明をする義務があります。
このとき、クーリング・オフの有無について記載する場合は、12ポイント以上の大きさの文字・数字で記載する必要があります。
なお、契約が成立した時は、基本的に書面を作成し顧客に交付しなければなりません。
ただし、書面を交付しなくても公益または投資者保護のため支障を生じることがないと認められるもの(内閣府令で定めるもの)はこの限りではありません。
・取引態様の事前明示義務

金融商品取引業者等は、顧客から有価証券の売買又は店頭デリバティブ取引に関する注文を受けたときは、あらかじめ、その顧客に対し、自己がその相手方となって当該売買を成立させる仕切り注文なのか、又は媒介し、取次ぎし、もしくは代理して取引を成立させる委託注文なのかを明らかにしなければなりません。


・業務義務規定
ここでは特に重要な3つの義務について見ていきます。
・適合性の原則の遵守義務

適合性の原則とは、顧客の知識、投資経験、財産の状況および取引の目的に照らして、不適当な勧誘を行ってはならないということです。
さらに踏み込むと、金融商品取引業者等は、顧客が投資を望んだとしても、不適当な場合は否定される場合もありうるということを含んでいます。
つまり、金融商品取引業者等は、市場の担い手としての義務を負っているということを意味します。
・最良執行義務
最良執行義務とは、顧客からの注文について、最も条件の良い方法で執行しなければならいというものです。
金融商品取引業者等は、そのための方針及び方法を定めなければなりません。
さらにその最良執行方針等を公表し、それに従って注文を執行しなければなりません。
上場有価証券及び店頭売買有価証券の売買等に関する注文を受ける場合には、あらかじめ顧客に対して、最良執行方針等を記載した書面を交付しなければなりません。
なお、これらの書面の交付は電子交付によることができます。
・分別管理義務

分別管理とは、顧客から預託されている財産と、自己(金融商品取引業者)の固有財産を分けて保管しなければならいというものです。
万一、金融商品取引業者が破たんした場合にも、顧客の財産が損なわれないようにするための措置です。
さらに、分別管理された顧客の財産の保管は、信託会社等に信託しなければならず、定期的に公認会計士又は監査法人の監査を受けなければなりません。
また、分別管理監査報告書(及び経営者報告書)の写しを公表しなければなりません。
・損失補てん等の禁止

顧客に対して損失の補てんを行うこと、約束することは法律で禁じられています。
これは、金融商品取引業者自身が行うことはもちろん、第三者をして行わせてもいけません。
損失保証・利回保証
顧客に損失が生じたり、予定の利益が生じなかった場合に、それを補てんするための財産上の利益を提供することを、顧客に申し込んだり約束したりする行為は禁止。
損失補てんの申込み・約束
すでに生じた損失を補てんしたり利益を追加するための、財産上の利益を提供すること顧客に申し込んだり約束する行為は禁止。
損失補てんの実行
実際に損失を補てんしたり利益を追加するために、財産上の利益を提供することは禁止。
・業態・業務状況に係る行為規制
金融商品取引業者等は、以下の禁止行為等を守って業務を行わなければなりません。
・名義貸しの禁止

自己の名義(金融商品取引業者の名義)で、他人に金融商品取引業を営ませることは禁じられています。
・社債管理者になること等の禁止

有価証券関連業務を行う金融商品取引業者は、社債管理者や担保付社債信託契約の受託会社になることはできません。
・過当な引受競争の禁止
金融商品取引業者等が、引き受けに関する自己の取引上の地位を維持し又は有利にさせるために、著しく不適当と認められる数量、価格その他の条件により有価証券の引受けを行うことは禁止されています。
・回転転売等の禁止
あらかじめ顧客の意思を確認することなく、頻繁に売買等を行うことは禁止されています。
・金融機関との誤認防止
金融商品取引業者が、金融機関と同一の建物で業務を行う場合は、顧客が金融機関と誤認しないように適切な措置を講じなければなりません。
・引受人の信用供与の制限
有価証券の引受人となった金融商品取引業者は、引き受けた有価証券を投資家に販売する場合、引受人となった日から6ヵ月を経過するまでは、その投資家に対して買付代金を貸し付けてはなりません。
これは、本来金融商品取引業者が負うべき引受証券の売れ残りリスクを、顧客に転嫁できないようにするための規則です。
・一括受注の制限
不特定多数の投資者から委任を受けて一括して売買を行う投資グループ等からの注文では、あらかじめ当該投資者の意思を確認しなければなりません。
・断定的判断の提供による勧誘の禁止

株価等は将来の動きを正確に予測することが不可能ですが、金融商品取引業者等が「このあと必ず値上がりします」などと、将来の断定的な判断を提供して勧誘することは禁止されています。
仮に、提供した予測が結果的に的中して、顧客の利益になったとしても違反行為になります。
また、断定的な判断を提供したり、虚偽の事実を告げると、金融商品販売法において、顧客が被った損害の賠償責任を負います。
・虚偽の表示の禁止

有価証券の売買その他の取引に関し、虚偽の表示をし、又は投資者の投資判断に重大な影響を及ぼすような重大な事項について誤解を生じさせるような表示をすることは禁止されています。
この規定は、実際に勧誘行為がなくても適用され、故意・過失の有無は問いません。
虚偽の表示には、表示すべきことを表示しないという不作為も含まれます。
・特別の利益の提供等の禁止
取引の際、公開株を優先的に割り当てるとか、不当に安い価格で有価証券を売るなど、特別な利益を提供することは禁止されています。
なお、社会通念上一般的なサービスとされるものは含まれません。
・大量推奨販売の禁止
相場操縦防止や投資者保護の観点から、金融商品取引業者等は、特定かつ少数の銘柄を不特定多数の顧客に対して過度に勧誘することは禁止されています。
・インサイダー取引注文の受託禁止

インサイダー取引と知りながら、あるいはそのおそれがあることを知りながら、当該売買取引の相手方となったり、当該取引の受託をしてはいけません。
この規定に違反すると、インサイダー取引の幇助犯として刑事責任を問われる可能性もあります。
・法人関係情報の提供による勧誘の禁止
有価証券の発行者の会社の未公表情報を顧客に提供して勧誘することは禁止されています。
これは、特別の利益提供による勧誘やインサイダー取引の幇助に繋がる可能性もあるので、特に注意する必要があることから設けられている規定です。
・自己または他の顧客の利益を図るための過度の勧誘の禁止
自己または他の顧客の利益を図るために、有価証券の買付けや売付け、もしくはデリバティブ取引などを一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘してはいけません。
・市場価格歪曲に係る市場疎外行為
・フロントランニングの禁止
顧客から有価証券の売買の委託を受けて、その売買を成立する前に、自己の計算でその有価証券の売買を成立させることは禁止
顧客より先に金融商品取引業者が同じ取引をしてはいけないということ
・無断売買の禁止
あらかじめ顧客の同意を得ることなく、顧客の計算において売買することは禁止
・自己計算取引及び過当数量取引の制限
取引一任契約等において、過当と認められる数量の売買で、取引所金融商品市場秩序を害する行為は禁止
・作為的相場形成等の禁止
主観的な目的の有無を問わず、特定の銘柄の価格を作為的に形成するおそれがあることを知りながら受託する行為は禁止
・信用取引の自己向かいの禁止
顧客の信用取引を市場で執行した金融商品取引業者は、その決済に必要な現金又は株券を自己の責任で調達しなければならない
・役職員の地位利用
役職員等の立場で知りえた特別な情報をもとに売買を行ったり、専ら投機的利益の追求を目的として売買等を行うことは禁止
・引受金融商品取引業者による安定操作期間中の自己買付等の禁止
安定操作ができる金融商品取引業者は、安定操作期間中に自己の計算による買付けや、他の金融商品取引業者に自己の計算による買付け委託等は行ってなならない
※「自己の計算」とは、金融商品取引業者の財産で取引すること。損益の結果は金融商品取引業者に帰属する。
「顧客の計算」とは、顧客の財産で取引すること。損益の結果は顧客に帰属する。
信用取引の自己向かいの禁止
顧客が信用取引を申し込んだとき、金融商品取引業者自身がその信用取引を受けることも理論的に可能で、金融商品取引業者は資金等を調達する必要がなくなります。
ただしその場合、顧客側に利益が生じる時は金融商品取引業者が損をし、逆に顧客側が損をすると金融商品取引業者が得をします。
この状態は顧客と金融商品取引業者の利益が真っ向から対立するため、顧客に対する誠実義務違反となり、公正な価格形成を阻害するものとして禁じられています。
長くなりましたが本日は以上です。
また明日も「金融商品取引法」について記載していきます。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
