
入れ替わっている 平野啓一郎の『三島由紀夫論』を読む36
蓼科を仲介者として結ばれた聡子と清顕は、また蓼科を仲介者として結ばれたみねと飯沼と対になる。聡子と清顕の子供は殺され、みねと飯沼の子は生まれてやがて本多に見いだされる。この子も対になる。みねと飯沼の子は清顕の尽力によって齎されたという意味合いもあるからだ。確かにある意味、みねと飯沼の子は聡子と清顕の子の身代わりなのだ。
最初に禁を犯して女中に手を付けたのは飯沼だった。清顕はまた勅許のお達しが出た後の聡子を抱くという禁を犯した。この反復は着々と準備されていたものだった。この関係性に関しても平野啓一郎の『三島由紀夫論』には具体的な指摘がない。
これは書かれている対なので読めばわかるとでも言いたいのであろうか。
しかし仮にそうであれば平野啓一郎は何故しばしば「創作ノート」をガイドブックのように用いてしまうのだろうか。
「実はね、きのうあなたに手紙を出したんです。そのことでお願ひがあるんだけど、手紙が着いても、絶対に開封しないでください。すぐ火中すると約束してください」
聡子と清顕の関係はこの手紙から捩じれた。その正直ではない嘘の手紙で。この手紙を焼くという振る舞いは矢張り何度か反復された。では何故三島由紀夫は「創作ノート」を焼かなかったのであろうか、と問わないのであろうか。それが焼かずに残されている以上、それも一つの創作に過ぎないと理解できないものであろうか。三島由紀夫のたくらみ通り平野啓一郎は「創作ノート」をガイドブックのように用いて前置きをたくさん拵え、作品そのものからは気を逸らしてしまう。
例えば平野は「18 『浜松中納言物語』」において、清顕には「圧倒的な才能が欠けている」と指摘する。しかし本多に
貴様は偉人でもなければ天才でもないだらう。でもすごい特色がある。貴様には意志といふものが、まるっきり欠けてゐるんだ。
こう言われて自分と対比される意味に届いていない。
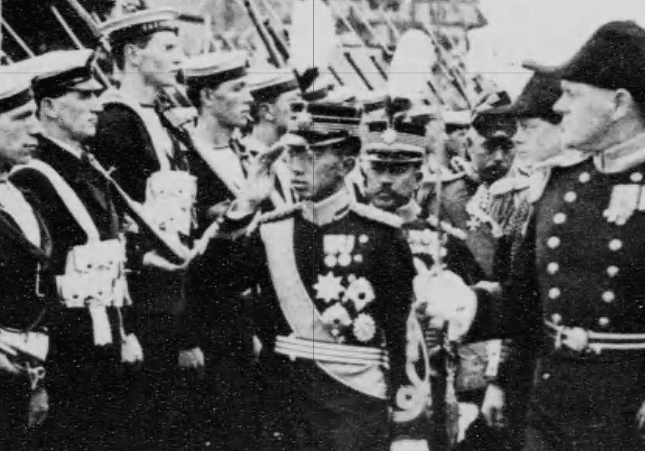
結果、彼を形容する「美しい」、「美しさ」という直接的な言葉の執拗な連呼は空疎化し、ほとんど逆効果にさえなっている。その点に、作者の力みの空回りや、焦燥、或いは、表現力の衰耗を見る批判は、必ずしも不当とは言えないだろう。
不当だ。
唯一の友人が「でもすごい特色がある。貴様は外見だけは美しいだらう」とでも言っていたらその通りだが、清顕は松枝侯爵から見れば謎であり、本多にとってみると意志を欠いた珍しい人間なのだ。彼の美しさだけにとらわれているのは女中や芸者だけの話だ。聡子にしてみればそのホワイトアスパラガスのような擬宝珠が魅力なのだ。
とりあえずこの「意志を欠いた珍しい人間」という清顕が見えていないことは、清顕の行動がありきたりの意味の「恋」に見えてしまう読み誤りにつながる。
確かに二十五章で三島は、
『僕は聡子に恋をしている』
こう書いてみる。しかしその感情は二十四章でこう説明されていたものだ。
自分にとつてただ一つの真実だと思はれるもの、方向もなければ帰結もない「感情」のためだけに生きること、……そのやうな生き方が、つひに彼をこの歓喜の暗い渦巻く淵の前へ導いたのであれば、あとは淵へ身を投げることしか残されてゐない筈だ。
これを悲恋などと呼ばれてはたまらない。
脳科学を巡って自由意志や感情という概念の再定義がかまびすしく言われている。ここで三島が捉えようとしている「感情」が一般的には「衝動」と呼ばれているものであることは後の行動から客観的に判断できることであろう。そこには聡子を勝ち取るという「目的」があるようでない。何故なら聡子を勝ち取ることが「目的」であれば、行動は一度だけで済んだはずである。
平野啓一郎は「52 三島と「悪」」において本多が透に「雲一つない虚空へ向かって放たれるような、その機構の完全な目的の欠如」を見出す出会いを確認している。しかしこの目的の欠如の向かう方向性の対を見ない。
これは『金閣寺』論から始まる「美」の問題でもあるが、三島が「死・エロティシズム・美」と言い出すのは平野の区分による第四期以降の後半のことで『午後の曳航』においてさえまだその美学は完成していない(猫の死に少しのエロスも絡めていない)三島は「美しい二十歳の夭折者」というものを必要としていて、その美しさというものは結果としての美ではなくただの外見である。外見の美しさはもともと空疎なものだ。それを改めて空疎と言ってみて、清顕が「感情」のためだけに生きる、と言いながら衝動に振り回されているだけ、ということが見えていないのではないか。
そもそもはったりの手紙なんて書かなければよかったのだし、聡子に復讐しようとしたことが間違いのもとで、感情が抑えきれていない。それを本多は「貴様には意志といふものが、まるっきり欠けてゐるんだ」と言ってみる。
そこで改めて清顕の年齢と得利寺とが問題になってくる。何故清顕の感情は勅許に逆らう方に向かい、本多は「貴様には意志といふものが、まるっきり欠けてゐるんだ」と言ったのかと言えば、本多には清顕が何者かの、つまり『豊饒の海』のロジックに当てはめれば美しい二十歳の夭折者の反復であるとは意識されないまでも、何かそういう不思議な感じ、ありきたりの「自分」というものに閉ざされた人間ではないという感じがしていたんじゃなかろうか。
それに対して本多は自分の意志で歴史に関与したいようなことを言ってみる。
つまりは非転生者、当たり前の存在として意志を止められないと言っている。この本多はこじつけと断って、日露戦役の写真と清顕を結び付ける理由をこんな風に説明してみる。
明治と共に、あの花々しい戦争の時代は終はつてしまつた。戦争の昔話は、監武課の生き残りの功名話や、田舎の炉端の自慢話に堕してしまつた。もう若い者が戦場へ行つて戦死することはたんとあるまい。
しかし行為の戦争がをはつてから、その代わりに、今、感情の戦争が始まつたんだ。この見えない戦争は、鈍感な奴には感じられないし、そんなものがあることさへ信じられないだらうと思ふ。だが、たしかに、この戦争ははじまつてをり、この戦争のために特に選ばれた若者たちが、戦ひはじめてゐるにちがひない。貴様はたしかにその一人だ。
行為の戦場と同じやうに、やはり若い者が、その感情の戦場で戦死してゆくのだと思ふ。それがおそらく、貴様をその代表とする、われわれの時代の運命なんだ。……それで、貴様は、その新しい戦争で戦死する覚悟を固めたわけだ。さうだらう?
この話の分からなさに関しても平野啓一郎の『三島由紀夫論』は触れていない。「22 「文化意志」としての清顕」の中で「感情の戦争」を「恋愛」にすり替えようとするだけだ。
何故三島は戦争がもう起こらないといういかにも無理な前提を置いたのであろうか。大正二年の時点で本多はまだ知らなかったかもしれないが、大正三年には第一次世界大戦は始まり、休む間もなく大東亜戦争が始まる。「もう若い者が戦場へ行つて戦死することはたんとあるまい」などという見立ては「日米開戦論」などを鑑みてもあまりに楽観的で、事実としてこの後若者が大量に戦死するのだから、この「感情の戦争論」そのものが無意味で空疎なものに思える。
しかし無駄に持ち出した話とも思えず、本多は返事をしない清顕に対して、こう受け止めまでする。
本多は清顕がさうして答へなかつたのは、答へるまでもなく自明なことであつたからか、それとも、かう言はれたことがたしかに心に叶ひながら、それがあんまり晴れがましく語られたので、まともに答へことができなかつたか、どちらかだと思はれた。
かなり強引ながら、実際に清顕が、
僕は感情の血を流すやうに生まれついてゐる、決して肉体の血は流さないだらう。
既にこのように考えていることから、本多の推測自体は三島由紀夫の中では正しいのである。
しかしこの「感情の戦争論」がそのまま理解できるという人は存在しないだろう。
これは正直解らない。
戦争というのは国家間の争いで、端的には殺し合いである。「受験戦争」とか「経済戦争」と比喩的に使われる戦争という言葉も厳密には激しい競争という程度の意味合いで、戦争の定義を満たしていない。感情の戦争と言ってみて、清顕は誰を殺すのか。
そもそも「感情の戦争」を「行為の戦争」と対比させることに無理があるのではないか。
とりあえずはそう考えてみる。
考えてみてあまりにも杜撰なこじつけを、間もなく意味がなくなると知りつつ、三島が大真面目に持ち出してきた意味になお困惑する。この「感情の戦争論」に類似した屁理屈はないかと考えてみる。
そんなものは見当たらない。
時代としては「もう若い者が戦場へ行つて戦死することはたんとあるまい」という感覚そのものは1970年代に近い。大正二年ではいかにも早い。
清顕の行為が「感情の戦争」ならば、「感情の戦争」とはセックスのことともいえよう。許されざるセックス。感情のままの目的のないセックス。しかし何が争われているのか明確ではないしそれを「われわれの時代の運命」とまで高められる根拠が解らない。
そこまで言っておきながら次章、第二十八章で本多はこう言われてしまうのだ。
この若さで、彼はただ眺めてゐた! まるで眺めることが、生まれながらの使命のやうに。
これは清顕の行動を知らされた後の変化である。ここに「意志することを止められない」と言っていた本多の捩じれが始まっている。仮にそれが何なのかまるで解らないものだとして、本多は清顕の「感情の戦争」のとばっちりを受けたのである。三島はそれを「不可解な顛倒」と書いてしまう。
いや、あんたが不可解と書いてどうする。
とりあえず本多には「内省」が与えられる。
ただ本当に「内省」すべきは行為の戦争がもう終わったという前提に立つ「感情の戦争論」を説明しない三島由紀夫論を決定版と呼ぶ人だろう。
まだ少し書きたいことがあるのでこの話はもう少し続く。
[余談]
98円の本が二冊売れた。60円の儲け。結局君ら、金がないのか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
